夢を想い描く子供たちとエンターテインメント、スポーツは、人々の情熱と太陽の力で革新的で持続ある、より良い世界や未来を創れる可能性が存在する。
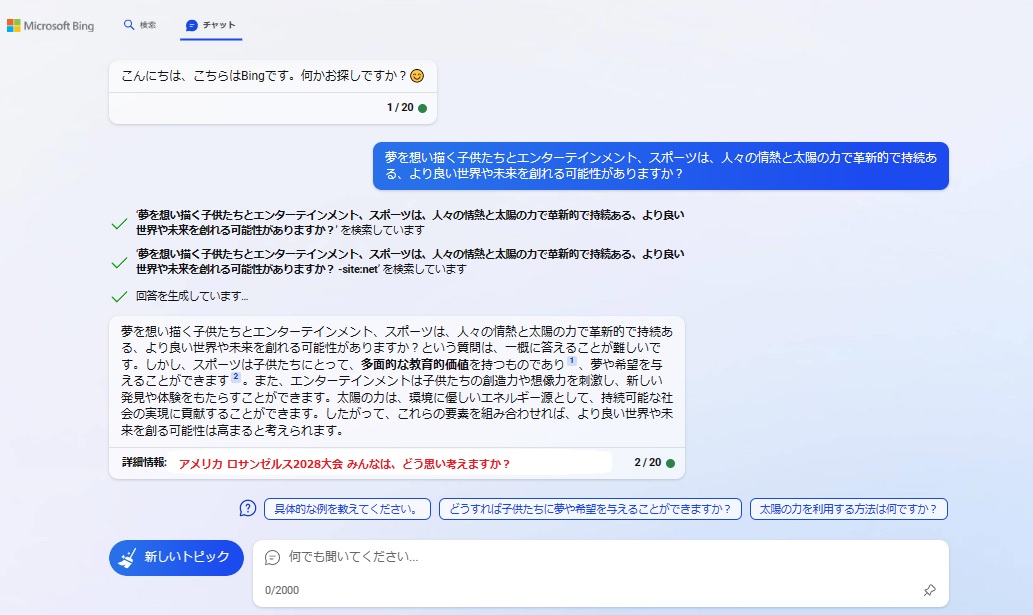
次回、アメリカ ロサンゼルス2028 大会仕様予告♪ ついにアメリカ サザンカリフォルニアに上陸かぁ! 乞うご期待♪ 我々の培ったレガシーをついにアメリカで実証実験ならびに検証、ガハガハぁ This is American Dream !?
追伸、ついに念願の巨大かつ分厚い鉄壁が開いた♪、世界中の球児「ベースボール(野球)やソフトボール」がアメリカ ロサンゼルスで復活開催!オ~マイガット、聖火の灯る中、太陽の力を全身に浴びながら、青春の若き汗を流し合う?これぞ、アメリカンドリーム!ヘイ~ボーイ ここは観光地、ロサンゼルスだぜぇ~♪想定3,000万人以上(推定1億人のシステムを組み込んで)の観光客をお・で・む・か・え?
7月14日から7月30日 17日間 XXXX日後に開催予定
オリンピック開催競技の参考内容を製作中です。(パリ2024大会まで)
- 陸上競技 Ver. 開催期間:
- バスケットボール Ver. 開催期間:
- バスケットボール3×3 Ver. 開催期間:
- ロードサイクリング Ver. 開催期間:
- タイムトライアル
- ロードレース
- サイクリングトラック Ver. 開催期間:
- チームスプリント(女子/男子)
- スプリント(女子/男子)
- ケイリン(女子/男子)
- チームパシュート(女子/男子)
- オムニアム(女子/男子)
- アディソン(女子/男子)
- マウンテンバイク Ver. 開催期間:2024年7月28日~7月29日
- クロスカントリー(女子/男子)
- BMXフリースタイル Ver. 開催期間:
- BMXレース Ver. 開催期間:
- アーチェリー
- バレーボール Ver. 開催期間:
- ビーチバレー Ver. 開催期間:
- サッカー Ver. 開催期間:
- ゴルフ Ver. 開催期間:
- ハンドボール Ver. 開催期間:
- ホッケー Ver. 開催期間:
- ラグビー Ver. 開催期間:
- バトミントン Ver. 開催期間:
- 卓球 Ver. 開催期間:
- テニス Ver. 開催期間:
- トライアスロン Ver. 開催期間:
- 乗馬 Ver. 開催期間:
- 馬場馬術
- 総合馬術
- 障害馬術
- 体操競技 Ver. 開催期間:
- 新体操 Ver. 開催期間:
- トランポリン Ver. 開催期間:
- カヌー Ver. 開催期間:
- ボート Ver. 開催期間:
- セーリング Ver. 開催期間:
- サーフィンVer. 開催期間:
- 空手(パフォーマンス) Ver.
- 柔道
- フェンシング
- レスリング
- ウエイトリフティング Ver. 開催期間:
- テコンドー
- 野球 Ver.
- ソフトボール Ver.
- 射撃 Ver. 開催期間:
- 現代五種競技 Ver. 開催期間:
- フェンシングランキングラウンド(エベ)
- 水泳(200メートル自由形)
- フェンシングボーナスラウンド(エベ)
- 馬術(障害飛越)
- レーザーラン(射撃5的+800メートル走を4回)
- 競泳 Ver. 開催期間:
- ダイビング Ver. 開催期間:
- マラソン水泳 Ver. 開催期間:
- アーティスティックスイミング Ver. 開催期間:
- 水球 Ver. 開催期間:
- スポーツクライミング Ver. 開催期間:
- スケートボード Ver. 開催期間:
- 水上競技
- トライアル
- フラッグフットボール
- スカッシュ
- 帆走
- クリケット
- ラクロス ボクシング ブレーキン
トラック
トラックは己の限界を超える激烈な闘い、人類に与えし新記録への挑戦

トラックは人間が「いかに速く走れるか」を争う競技です。 試合は距離、男女別に合計25種目が行われ、人類最速を決める戦いで、鍛練を重ねた選手の身体能力や体力、技術、作戦、駆引き、世界新記録に注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
陸上競技 トラックの主な強豪国と地域:
「 男子100メートル イタリア、アメリカ、カナダ etc.」
「 男子200メートル カナダ、アメリカ etc.」
「 男子400メートル バハマ、コロンビア、グレナダ etc.」
「 男子800メートル ケニア、ポーランド etc.」
「 男子1,500メートル ノルウェー、ケニア、イギリス etc.」
「 男子5,000メートル ウガンダ、カナダ、アメリカ etc.」
「 男子10,000メートル エチオピア、ウガンダ etc.」
「 男子3,000メートル障害 モロッコ、エチオピア、ケニア etc.」
「 男子110メートルハードル ジャマイカ、アメリカ etc.」
「 男子400メートルハードル ノルウェー、アメリカ、ブラジル etc.」
「 男子4×100メートルリレー イタリア、カナダ、中国 etc.」
「 男子4×400メートルリレー アメリカ、オランダ、ボツワナ etc.」
「 女子100メートル ジャマイカ etc.」
「 女子200メートル ジャマイカ、ナミビア、アメリカ etc.」
「 女子400メートル バハマ、ドミニカ共和国、アメリカ etc.」
「 女子800メートル アメリカ、イギリス etc.」
「 女子1,500メートル ケニア、イギリス、オランダ etc.」
「 女子5,000メートル オランダ、ケニア、エチオピア etc.」
「 女子10,000メートル オランダ、バーレーン、エチオピア etc.」
「 女子3,000メートル障害 ウガンダ、アメリカ、ケニア etc.」
「 女子100メートルハードル プエルトリコ、アメリカ、ジャマイカ etc.」
「 女子400メートルハードル アメリカ、オランダ etc.」
「 女子4×100メートルリレー ジャマイカ、アメリカ、イギリス etc.」
「 女子4×400メートルリレー アメリカ、ポーランド、ジャマイカ etc.」
「 混合4×400メートルリレー ポーランド、ドミニカ共和国、アメリカ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会 陸上競技 トラックでメダル獲得した国と地域です。
ロサンゼルス2028大会は欧米やアフリカ、アジア諸国勢との熾烈な順位争いに熱風が吹き荒れる。
精神力と肉体の限界に挑みながらスタミナとエネルギー効率を最後の最後まで維持できる持久力と耐久力を備えた陸上競技 トラックの王冠を掴み取れる国はどこだぁ!
【トラック種目の特徴】
陸上競技 トラックは競技場内1周400メートルの走路「トラック」を使って実施される競技です。 オリンピックでは短距離走、中 長距離走、障害走、ハードル、リレーが行われ、距離、男女別に合計25種目が行われます。 生身の人間が「いかに速く走れるか」に挑戦するシンプルな競技だけに体力が全てと考えがちですが、実は、スタートを始め多くの技術も身につけないと世界の上位に食い込むことはできない競技です。 0.1 秒、0.01 秒速く走るため、トラックでは鍛え抜かれた選手たちが肉体の限界に挑む激烈な戦いが繰り広げられます。 すべての種目に共通するのは「走って競う」ということのみです。
古代オリンピックから行われている陸上競技は、記録に残る最も古い競技で、紀元前776年からの勝者の名前が文書化され残存しています。
近代における最初の競技大会では、1840年にイギリス、シュロップシャーで開催され、今日知られる陸上競技の様式に近い大会です。 その他の選手権大会は1880年代に始まり、当初はイギリス、アメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国で繁栄し広がった競技になります。 1912年には、国際陸上競技連盟(IAAF/現ワールドアスレチックス)が設立され、国際大会を統括するようになった競技です。
【オリンピックにおける歴史】
古代オリンピックから行われてきた陸上競技は、1896年にアテネで開催された第1回近代オリンピックで行われます。 今日まで夏季競技大会の花形として非常に人気が高い競技です。
男子種目は、ロサンゼルス1932大会以来ほとんど変わっていないが、メルボルン1956大会では20キロメートル競歩が新たに追加されます。 女子種目は、アムステルダム1928大会で、初めて登場し、バルセロナ1992大会まで17種目のみが行われてきた競技です。 現在では、北京2008大会で女子3,000メートル障害が導入されて以来、男子と同じ種目数が競い合われている競技です。
1960年代は、発展途上国で陸上競技が人気となり、その後、世界全体に人気が広がり、北京2008では、62か国の選手が決勝に出場しています。
【種目別の特徴】
短距離走は100メートル、200メートル、400メートルの3種目が行われます。 男女6種目とハードル男女4種目だけはスターティングブロックを使用したクラウチングスタートです。 「人類最速」を決める100メートルは直線路のみでレースになります。 100メートル走はスタートが重要で、200メートル走はスプリント力とコーナーリングのテクニックが求められ、400メートル走は、さらにスタミナも要求される厳しいレースです。
中 長距離走は800メートル、1,500メートル、5,000メートル、10,000メートルが行われます。 男女4種目はスタンディングスタートです。 800メートルはスタートから100メートルまでセパレートレーンを走り、その後オープンレーンになります。 1,500メートル以上は弧状のスタートラインに立ち、始めからオープンレーンで行われる種目です。 800メートル、1,500メートル走は最後までのスタミナを維持する持久力とラストスパートに求められる短距離選手に匹敵するスピードも要求されます。 5,000メートル、10,000メートル走は持久力に加え、エネルギー効率を考慮した限りなく無駄を省いた走りが重要です。 中 長距離走はトップ集団を始め中盤、後方など自分のポジションの戦略や他の選手との駆け引きも重要になります。
障害は中 長距離走に跳躍の要素が加わった種目が3,000メートル障害でトラック1周に5か所設置された障害物を超えながら記録と順位を競い合います。 障害物の高さは男女別で男子91.4センチメートル、女子76.2センチメートルです。 障害物5か所のうち1か所には障害物の直後に水豪が用意され、距離の長さだけでなく、障害物を超えながら走る過酷な種目になります。
ハードル走は女子100メートル、男子110メートル、男女400メートルの4種目が行われます。 ハードル男女4種目はスターティングブロックを使用したクラウチングスタートです。 コース上に10台のハードルが置かれ、跳び越えながら走りタイムを競い合います。 全種目、故意でハードルを倒さなければ失格にはなりません。
リレーは4人の選手がバトンをつなぎながら走る種目で、自己ベストが速い選手を集めれば勝てるわけではありません。 東京2020大会から新種目として加わった男女混合4×400メートルリレーは男女各2名の選手を何番目に配置するかが、各国の重要な戦略になり大逆転が起こりうる注目すべき新種目です。 全てのトラック種目に共通するのは、いかに速く走るかということであり、それは相手との戦いであると同時に、自己の記録との闘いでもあります。
【ロサンゼルス2028大会へ向けた展望】
短距離界では、リオデジャネイロ2016大会まで、ジャマイカやアメリカが力を見せつけてきたが、近年台頭してきているのはジャマイカ、南アフリカ、バハマです。
しかし東京2020大会では、男子100メートル イタリア、アメリカ、カナダ、男子200メートル、カナダ、アメリカ、男子400メートル、バハマ、コロンビア、グレナダが力を発揮し、女子100メートルでは、ジャマイカ、女子200メートル、ジャマイカ、ナミビア、アメリカ、女子400メートル、バハマ、ドミニカ共和国、アメリカが台頭しています。
女子100メートルハードル、男子110メートルハードル、男女400メートルハードルではアメリカやジャマイカの選手が常に世界ランキングの上位を占めてきた勢力図です。 しかし、東京2020大会では、男子110メートルハードル、ジャマイカ、アメリカ、男子400メートルハードル、ノルウェー、アメリカ、ブラジル、女子100メートルハードル、プエルトリコ、アメリカ、ジャマイカ、女子400メートルハードル、アメリカ、オランダと新たな勢力図が歴史に刻まれています。
リレージャマイカ、アメリカが強いが、リオデジャネイロ2016大会の日本のようにチームワークとテクニックがあれば、他のチームが上位に食い込んでくることもある種目です。 東京2020大会では、男子4×100メートルリレー、イタリア、カナダ、中国、男子4×400メートルリレー、アメリカ、オランダ、ボツワナ、女子4×100メートルリレー、ジャマイカ、アメリカ、イギリス、女子4×400メートルリレー、アメリカ、ポーランド、ジャマイカになります。 リレーはバトンパスの失敗で失格になることが多いだけに、予想外の結果もあり得る種目です。
長距離では、驚異的な世界新記録でリオデジャネイロ2016大会の金メダルを獲得した女子10,000メートルのエチオピアに注目が集まります。 東京2020大会では、男子10,000メートル、エチオピア、ウガンダ、女子10,000メートル、オランダ、バーレーン、エチオピアが勝利を掴んでいる近状です。 長距離のトラック種目は、今後もアフリカ出身選手を中心に展開されるか、100年目を迎えるパリ2024大会でのさらなる勢力図に世界中の注目が集まります。
短距離は北中米が他を圧倒する勢い、中 長距離はアフリカ出身選手がせめぎ合うレース展開になるだろう。
日本はアムステルダム1928大会での女子800メートル銀メダル以来、長い間、トラック種目でのメダル獲得がなく、北京2008大会の男子4×100メートルで、80年ぶりの銅メダルを獲得しています。 リオデジャネイロ2016大会の男子4×100メートルでは銀メダルを獲得した経験があるチームです。 若手の短距離選手の躍進が目立つようになり、選手個々の自己ベストはジャマイカ、アメリカには差をつけられているが、持ち前のチームワークを発揮し、ロサンゼルス2028大会での活躍に期待が集まります。
【開催会場】
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
フィールド
フィールドは己の磨き上げた技で、一瞬に懸ける世界新記録への挑戦!

フィールドはトラック内外で行う競技です。 試合は華麗な跳躍、力強い投てきに分けられ、好記録を勝ち取る選手は力強いだけでなく、動作や流れるようなフォームの美しさ、迫力あるアクション、戦略に注目!日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
陸上競技 フィールドの主な強豪国と地域:
「男子走高跳 カタール、イタリア、ベラルーシ etc.」
「男子棒高跳 スウェーデン、アメリカ、ブラジル etc.」
「男子走幅跳 ギリシャ、キューバ etc.」
「男子三段跳 ポルトガル、中国、ブルキナファソ etc.」
「男子砲丸投 アメリカ、ニュージーランド etc.」
「男子円盤投 スウェーデン、オーストリア etc.」
「男子ハンマー投 ポーランド、ノルウェー etc.」
「男子やり投 インド、チェコ etc.」
「女子走高跳 ROC、オーストラリア、ウクライナ etc.」
「女子棒高跳 アメリカ、ROC、イギリス etc.」
「女子走幅跳 ドイツ、アメリカ、ナイジェリア etc.」
「女子三段跳 ベネズエラ、ポルトガル、スペイン etc.」
「女子砲丸投 中国、アメリカ、ニュージーランド etc.」
「女子円盤投 アメリカ、ドイツ、キューバ etc.」
「女子ハンマー投 ポーランド、中国 etc.」
「女子やり投 中国、ポーランド、オーストラリア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会 陸上競技 フィールドでメダルを獲得した国と地域です。
ロサンゼルス2028大会は欧米やアフリカ、アジア諸国勢との緊迫感漂う順位争いに手に汗を握る。
助走スピードや踏み切るタイミング、ジャンプ力、きれいな空中でのフォーム、モチベーションを盛り上げ集中し調整力など競技テクニックを備えた
陸上競技 フィールドで己に勝つ国と地域はどこだぁ!
【フィールド種目の特徴】
フィールド競技は陸上競技のトラック内側、外側で行われます。 フィールド競技は、「跳躍」と「投てき」の2つに分けられ、「跳躍」は、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳の4種目で、跳ぶ高さや距離を競い合う種目です。 「投てき」も、砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投の4種目で、こちらは手で投てき用具を遠くへ投げ、その距離を競い合います。 フィールド競技はトラック競技のように何人もの選手が同時に競うことはなく、1人ずつ試技を行い、その記録で順位が決まる形式です。 フィールド競技は、記録への挑戦であり、自分との勝負になります。
古代オリンピックから行われている陸上競技は、記録に残る最も古い競技であり、紀元前776年からの勝者の名前が文書化され残存している競技です。
近代における最初の競技大会は、1840年にイギリス、シュロップシャーで開催され、今日知られる陸上競技の様式に近い構成になります。 その他の選手権大会は1880年代に始まり、当初はイギリス、アメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国で繁栄し広がった競技です。 1912年には、国際陸上競技連盟(IAAF/現ワールドアスレチックス)が設立され、国際大会を統括するようになります。
【種目別の特徴】
【跳躍】
走高跳は跳び越えるバーの高さを競い合う競技です。 フォームは“はさみ跳び”や“ベリーロール”など様々なスタイルが存在し行われてきましたが、現在は背面跳びが支流で行われています。 男子は約2メートル40台、女子は2メートル前後の戦いが繰り広げられ、身長を超える高さを舞う美しいフォームに圧巻です。 試合はパスを除いて3回続けて失敗すると敗退となり、助走スピードや踏み切るタイミング、きれいな空中でのフォームが好記録を叩き出すポイントになります。
棒高跳はポールを使用してバーを跳び越えた高さを争う競技です。 ポールは木製や竹製、グラスファイバー製が使用されてきましたが、現在は、さらにより大きくしなり復元力が強いガラス繊維や炭素繊維が用いられた強化プラスチック製のポールが使われるようになり大幅に記録が飛躍しています。 試合は選手により、ある程度の高さになるまでパスが行え、体力を温存させながら、さらにより高いバーにチャレンジすることも可能です。 しかし、最初の高さで3回続けて失敗すると記録が残りません。 選手はリスクを取りながらチャレンジするか、もしくは体力の消耗を考えながらも確実に好記録を残し、メダル獲得に挑む2つの戦略に注目です。
走幅跳は前方へ跳ぶ距離を競い合います。 試合は主に空中で脚を回転させる“はさみ跳び”もしくは体を大きくそらせてから前へかがむ“そり跳び”が多く見られる種目です。 足が踏み切り板を超えるとファウルになり、3回ファウルすると記録なし、可能な限り前方で踏み切ると記録が伸びますが、ファウルを気にしすぎると大きなジャンプができず記録が伸びません。 選手たちの葛藤や自分のモチベーションを盛り上げ、集中できるように助走の際に、観客に手拍手を求める選手たちのパフォーマンスにも注目です。 助走スピードが跳躍距離に影響するため、短距離のトップ選手が走幅跳びでも活躍するケースがあります。
三段跳(トリプルジャンプ)はホップ、ステップ、ジャンプと3回跳び、飛距離を争う競技です。 試合は1歩目と2歩目を同じ側の足で踏み切り、最後のジャンプを反対側の足で踏み切って跳びます。 助走スピードやジャンプ力、3回目のジャンプをスムーズに跳ぶ調整力など競技テクニックが必要になる種目です。 そのため、選手たちは経験豊富なベテラン勢が多く活躍しています。 この三段跳と走幅跳は、決勝で6回の跳躍チャンスが与えられますが、4回目以降に進めるのは上位8人のみです。
【投てき】
砲丸投(ショットパット)は片手で押すように投げ、男子7.26キログラム、女子4キログラムの金属の球を投げて飛距離を競い合います。 試合は重い金属球をダイナミックに20メートル以上飛ばす選手たちの巨体から繰り出される迫力に注目です。
円盤投は直径2.5メートルのサークル内で選手が回転し、遠心力を働かせて円盤を投げ飛距離を競い合います。 試合は円盤の重さ、男子2キログラム、女子1キログラム、飛距離を伸ばすために筋力だけでなく、回転エネルギーを円盤が前方に飛び出すための力に変えるテクニック求められる種目です。 風の影響を強く受けやすいため、選手自身が風を掴むタイミングなどもポイントです。
ハンマー投げ(ハンマースロー)はワイヤーの先に砲丸を付け、遠心力を働かせて飛ばし距離を競い合います。 試合は直径2.135メートルのサークル内で選手たちが3~4回転し、グリップとワイヤー、砲丸を合わせたハンマー全体の重さ、男子7.26キログラム、女子4キログラムを回転エネルギーの力を利用して投げる種目です。 雄叫びと共に繰り出される選手たちの気迫に満ちた戦いは凄みがあります。
やり投げ(ジャベリンスロー)は投てきの中で唯一、助走をつけて投げ合う競技です。 試合は回転投法は認められておらず、助走スピードでやりの重さ、男子800グラム、女子600グラム、長さ男子2.6~2.7メートル、女子2.2~2.3メートルのやりを男子90メートル、女子70メートル台で勝負し合います。 やり投げは、まっすぐ走り、まっすぐ投げるシンプルな競技で直線的なスピード感が魅力です。
なお、投てき種目は全て予選通過標準記録に達した選手のみが決勝に進みます。 決勝は3回の試技で上位8番目までの記録の選手が残り、さらに3回の試技を行い合計6回の試技の中での最高記録で順位が決まる種目です。 跳躍、投てきともに、上位にくる選手は力強いだけでなく動作も美しく、流れるようなフォーム、迫力あるアクションもフィールド競技の見どころになります。
【ロサンゼルス2028大会へ向けた展望】
跳躍
アメリカとヨーロッパ勢が強い種目です。
高い身長がジャンプの高さにある程度影響するため、体格に勝る欧米選手が上位を占める傾向は今後も続くと考えられます。
棒高跳の男子は、アメリカとヨーロッパ勢が入り乱れる展開です。
女子の棒高跳はシドニー2000大会からと歴史が浅く、過去5大会でロシアが金メダル2個と銅メダル1個を獲得しています。
女子も欧米選手の戦いが予想される展開です。
走幅跳は伝統的にアメリカの活躍が際立っており、男子ではロサンゼルス1984大会からアトランタ1996大会まで4連覇したヒーローを輩出してきた種目になります。 女子もアメリカに勢いがある種目です。
三段跳の男子はアメリカが強いが、女子はアメリカが上位に顔を出さず、ヨーロッパ、アフリカ、南米などさまざま国と地域の選手が入り乱れています。 パリ2024大会の跳躍も、欧米選手が中心となるだろう。
投てき
砲丸投はかつて、男子はアメリカ、女子はロシア(旧ソ連)が圧倒的に得意としてきた種目です。
近年はヨーロッパやニュージーランド選手の活躍が目立つが、リオデジャネイロ2016大会ではアメリカが復活し、男女とも優勝しています。
円盤投の男子は、かつてはアメリカのパワーが群を抜いていたが、最近はヨーロッパ勢が強さをみせ、また女子もヨーロッパが強いです。
ハンマー投男子は、ロシア、ハンガリー、ベラルーシ、ポーランド、スロベニアなど東欧の活躍が目立っています。 女子はシドニー2000大会から正式種目として採用されているが、東欧に加えてキューバや中国が活躍している種目です。 やり投は男女ともにヨーロッパ勢がメダリストの大半を占めてきたが、近年はアジア勢も力をつけてきています。 フィールドは全体にヨーロッパの選手が強いです。 だが、投てきでは、近年、中国が台頭してきており、今後はアジアの選手が活躍する可能性が出てきています。
欧米勢が強いフィールド、アジアがどこまで食い込めるか、ロサンゼルス2028大会に注目が集まるだろう。
日本はアムステルダム1928大会の三段跳で日本初のオリンピック金メダルを獲得し、次のロサンゼルス1932大会、さらにベルリン1936大会で金メダルを獲得し、日本の三段跳3連覇を果たした実績があります。 棒高跳でもロサンゼルス1932大会とベルリン1936大会で銀メダルを手にするなど、かつての日本は跳躍が強かった種目です。 投てきはもともと日本が強い種目ではなかったが、アテネ2004大会のハンマー投げで金メダル、ロンドン2012大会で銅メダルを獲得しています。 だが、それ以降は続いていないのが実情です。 今後の若手の活躍に期待が集まります。
【開催会場】
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
マラソン
マラソンは過酷な自然環境に応じた心理的な駆引き、己の限界との勝負

マラソンは真夏の猛暑の中で行われ、最も人気が高いロードレースです。 試合は一般公道で実施され、距離42.195キロメートルを代表選手たちが熾烈な戦いを繰り広げ、仕掛けや追い抜くタイミング、走り方に注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
陸上競技 マラソンの主な強豪国と地域:
「男子マラソン ケニア、オランダ、ベルギー etc.」
「女子マラソン ケニア、アメリカ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会 陸上競技 マラソンでメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会はアフリカや欧米、アジア諸国勢との仕掛ける順位争いに驚異の自然界も驚く。
最も過酷な自然環境に打ち勝つ陸上競技 マラソンを走り切れる国と地域はどこだぁ!
【マラソン種目の特徴】
ロード(一般道路)で実施されるマラソンは、要求が厳しく、戦術的であり、時にはアスリートが協力してライバルを倒すことさえある競技です。 パリ2024大会のマラソンは、真夏の屋外で行われため、路面温度や外気温が高い最中、己のスタミナと精神力の限界に挑むほど過酷なレースになります。
マラソンの起源は紀元前5世紀、戦いの勝利の知らせをアテナイに伝えるため、若い兵士がマラトンからアテネの約40キロメートルを走り、「われ勝てり!」と伝えて息絶えたという、言い伝えからその名が付いたマラソンです。 アテネ1896大会以来、オリンピックでは欠かさずに行われており、数あるオリンピック競技の中で最も人気が高い種目の1つになります。
マラソンは距離が長いだけでなく、路面の状況や道の勾配、気象条件などの影響を大きく受ける種目です。 選手同士や選手自身、そして自然との過酷な戦いに注目して観戦すると醍醐味が分かち合えるでしょう。
オリンピック男子のマラソンの歴史はアテネ1896大会から、女子はロサンゼルス1984大会から行われ、距離42.195キロメートルの長い一般道路で繰り広げられ、選手たちは持久力の限界と闘いながら競い合っています。
【解説】
一般公道で行われているマラソンは、坂道のアップダウンや路面の状況などロードコンディションが選手に大きな影響を与える種目です。 そのため、代表選手とコーチは予めコースを下見し、勝負を仕掛けるポイントや走り方についての作戦を練っています。
天候の影響を受けやすいマラソンだが、実際にマラソンが行われるパリの8月の気温は30度を超える恐れや乾燥、湿度など様々な影響するため、十分な対策が必要です。
そのため、水分補給が重要となるが給水ポイントは選手同士の接触が多く、転倒事故が起きやすい場所でもあるので注意しておくことが求められます。
なお、オリンピックのマラソンはペースメーカーが不在のため、選手は自分でペースを作って走らなければなりません。 選手同士の熾烈な駆け引きも同時に行われ、仕掛けるタイミングや仕掛けられた時についていく、それとも自分のペースを維持するか、追い抜くタイミングなど注目すべきポイントが多い種目になります。
マラソン種目の1キロメートル平均タイムは、男子で3分~3分10秒、女子は3分20秒~30秒です。 これを上回れば上位に食い込むことができる可能性が高くなり、選手たちのラップタイムに注目が集まります。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは】
男子のマラソンは、アテネ1896大会から実施され、これまでにオリンピックで連覇を果たした選手は2人しかいない過酷なレースです。 ローマ1960大会と東京1964大会のエチオピア、モントリオール1976大会とモスクワ1980大会の東ドイツになります。 一方、ロサンゼルス1984大会から始まった女子マラソンでの連覇はゼロです。 それほど、上位であり続けることが困難な種目になります。 マラソンの長距離ならではの心理戦と駆け引きに注目しよう。
直近のオリンピック選手男子の記録は2時間10分前後、しかし世界記録は2時間2分台でオリンピックの記録はかなり遅く思われますが、アテネ2004大会以降、オリンピックは8月に行われるため、選手は猛暑と戦いながら走ることになり、自然環境の影響を受けタイムが遅くなります。
近年のオリンピックのマラソンでは男女ともに、暑さに強いケニアやエチオピアなどアフリカの選手勢がメダルを獲得している勢力図です。 そのため、暑さに強い国や地域の選手たちにとってはメダル獲得のチャンスになります。
オリンピックのマラソンは記録ではなく順位を狙う競技です。
そのために参加する全ての選手は他の選手より、いかに速くフィニッシュするかを考え、激しい戦いを繰り広げています。 マラソンはいかに速く走るかというシンプルな競争だけでなく、相手を弱気にさせたり混乱させたりするための心理戦が展開されるレースです。
例えば、向かい風が吹けば他の選手の後ろを走り、後半のきつい上り坂でスピードアップさせたり、表情を読み取られないようにサングラスを掛けたり、あえて苦しくない表情を作って併走する場面や自分の影が相手に見えないようにして近くを走るなど、あの手この手で相手を動揺させる戦略を作ります。
同じチームの選手が集まってトップ集団を形成し、スピードを上げ下げして後続を揺さぶることもある戦いぶりです。
マラソン選手のシビアな心理戦にも注目して応援すると臨場感が伝わります。 観客は正規ルートに並び、選手を温かく応援しましょう。
日本はかつてマラソンで多くのメダルを獲得している強豪国です。 特に女子マラソンでは、シドニー2000大会、アテネ2004大会で、日本のマラソン連覇を達成しています。 ロンドン2012大会、リオデジャネイロ2016大会では、エチオピア、ケニアの選手が金メダルを獲得しており、アフリカ勢が強い印象だが、ロンドン2012大会の優勝タイム2時間23分07秒、リオデジャネイロ2016大会は2時間24分04秒、日本選手が叩き出した、シドニー2000大会 2時間23分14秒は、最近の記録と変わらないか速いほどのタイムです。 ロサンゼルス2028大会以降、新たな選手の再登場に期待が集まります。
【開催会場】
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
競歩
競歩は過酷な自然環境の中で厳しいルールや駆引き、己の限界との勝負

競歩は常に左右どちらかの足が地面に接し「歩く」速さを競い合うシンプルな種目です。 試合はひたすら前を向き、懸命に歩き続け、路面状況や勾配、気象条件だけでなく戦略的かつシビアな心理戦などに注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
陸上競技 競歩の主な強豪国と地域:
「男子20キロメートル競歩 イタリア、日本 etc.」
「男子50キロメートル競歩 ポーランド、ドイツ、カナダ etc.」
「女子20キロメートル競歩 イタリア、コロンビア、中国 etc.」
上記の強豪国は東京2020大会 陸上競技 競歩でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会は欧米や南米、アジア諸国勢とのシビアな心理的順位争いに厳しいルールも歯が立たない。
最も過酷な自然環境に打ち勝つ陸上競技 競歩を歩き切れる国はどこだぁ!
【競歩種目の特徴】
パリ2024大会の競歩は一般公道で開催され、要求が厳しく、戦術的であり、 時にはアスリートが協力してライバルを倒すことさえある競技です。
競歩は「歩く」速さを競う種目で、常に左右どちらかの足が地面に接していなくてはならなく、前に振り出した脚が接地してから腰の真下に来るまで膝が曲がってはいけないなど様々な厳しいルールが設けられています。
オリンピックではロンドン2012大会で、トラック種目として3,500メートル競歩が行われているが、ロードで行われるようになったのはロサンゼルス1932大会からです。
【ルール】
20キロメートル競歩(男子、女子)
男女混合競歩
競歩は距離が長いだけでなく、路面の状況や道の勾配、気象条件などの影響を大きく受ける種目になります。 選手同士、選手自身、そして自然との過酷な闘いに注目して観戦すると醍醐味が分かち合えるでしょう。
最初に歩くタイムを競う競歩は、走る行為は認められず、両足が同時に地面から離れないかなどを審判員が厳しくチェックし、明らかな反則に対しては「レッドカード」が示される競技です。
同一の選手に対して3人以上の審判員からレッドカードが出されると、その選手は失格になります。 競歩は相手選手や自分の記録、路面の状況や道の勾配、気象条件だけでなく、厳しいルールとの戦いでもある種目です。
パリ2024大会では、20キロメートル競歩(男子、女子)、新たに35キロメートル チーム競歩(混合競歩)が加わります。 歩く種目であることから、それほどスピードは出ていないと思われがちだが、ひたすら前を向き懸命に「歩く」競歩選手のストイックさに心打たれる観客も多い種目です。 競歩は一般道路の長い距離で繰り広げられる戦いで、真夏の過酷なレースになり己の持久力と精神力の限界に挑むレース展開になります。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは】
競歩は伝統的にヨーロッパ勢が強かったが、男子20キロメートルではロンドン2012大会で中国が金と銀、リオデジャネイロ2016大会で同じく中国が金と銀メダルを獲得し、男子50キロメートルでは日本が銅メダルを手にしている種目です。
女子でもリオデジャネイロ2016大会で中国が金と銅メダルを獲得するなど、近年ではアジア勢の活躍が目立っています。
パリ2024大会ではアジア勢を中心としてメダル争いが展開される可能性がある種目です。
オリンピックの競歩は記録ではなく順位を狙う競技で、参加する全ての選手は他の選手より、いかに速くフィニッシュするかを考え、激しい戦いを繰り広げています。
競歩はいかに速く歩けるかというシンプルな競争だけでなく、相手を弱気にさせたり混乱させたりするための心理戦が展開されている種目です。
例えば、向かい風が吹けば他の選手の後ろを歩き、後半のきつい上り坂でスピードアップさせたり、表情を読み取られないようにサングラスを掛けたり、 あえて苦しくない表情を作って併走する場面や自分の影が相手に見えないようにして近くを走るなど、あの手この手で相手を動揺させる戦略を作ります。
同じチームの選手が集まってトップ集団を形成し、スピードを上げ下げして後続を揺さぶることもあるレースです。
競歩の長距離ならではのシビアな心理戦と駆け引きにも注目して応援すると臨場感が伝わります。
観客は正規ルートに並び、選手を温かく応援しましょう。
日本は、競歩で2015年3月に男子20キロメートルで当時の世界新記録を樹立し、同年、世界選手権の男子50キロメートルで銅メダルを獲得しています。 リオデジャネイロ2016大会の男子50キロメートルで銅メダル、東京2020大会の男子20キロメートルで銀、銅メダルを獲得するなど日本選手の活躍が続いている種目です。 選手層の厚みを増し、ロサンゼルス2028に向けてさらに注目が集まります。
【開催会場】
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
混成
混成は過酷な自然環境の中で身体能力と効果的戦略、己の限界との勝負

混成は陸上競技の全ての要素を組合せた男子十種、女子七種目を2日間で行う競技です。 試合は実力を持った世界各国のスーパー選手同士が集い、究極のアスリートたちが繰広げる最高のパフォーマンスに注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
陸上競技 混成の主な強豪国と地域:
「 男子十種競技 カナダ、フランス、オーストラリア etc.」
「 女子七種競技 ベルギー、オランダ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会 陸上競技 混成でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会は欧米諸国勢との究極の順位争いに各キング&クイーン達からも健闘を讃え合う大きな拍手と歓声が沸き起こる。
最も過酷な自然環境に打ち勝つ陸上競技 混成の王冠を掴み取れる国はどこだぁ!
【混成種目の特徴】
混成は男子10種と女子7種目の2つの種目が2日間にわたって行われる競技です。 歴史は紀元前708年、古代オリンピックで行われ、あらゆる競技能力に秀でた競技者を決めるため、「五種競技」が考えられたのが起源になります。
この競技にちなんで近代オリンピックで行われ始めたのが、男子の10種競技と女子の7種競技です。 お互いに短、中、長距離、跳躍、投てきと陸上競技の全ての要素を組み合わせたトップクラスの実力を持った選手同士が集い戦い、究極のオールラウンダーを決めます。 混成の勝者は「キング オブ アスリート」、「クイーン オブ アスリート」の称号が与えられる種目です。
10種競技(男子)
・1日目:100メートル、走幅跳、砲丸投、走高跳、400メートル
・2日目:110メートルハードル、円盤投、棒高跳、やり投、1,500メートル
7種競技(女子)
・1日目:100メートル、走高跳、砲丸投、200メートル
・2日目:走幅跳、やり投、800メートル
【解説】
男子十種競技、女子七種競技
混成は短、中、長距離、跳躍、投てきと陸上競技の全ての要素が必要になり、それぞれに使う筋肉やメンタル、トレーニング方法が異なります。 競技種目によっては相反する身体能力が必要となるため、全てにおいてトップの成績を収めるのは至難の技です。 そのため、2日間にわたって最高のパフォーマンスを維持することは難しいとも言われています。
出場選手たちは自分が得意不得意に応じて、試技の回数を少なめにして次の種目に集中したり、不得意な種目で力を抑えて体力を温存させたりなど、戦略的に競技を進めていくことが重要です。
最も注目すべき見どころは最後に行われる中、長距離である10種競技の1,500メートルと7種競技の800メートルになります。 最終順位が決まるというだけでなく、2日間にわたる長く過酷なレースのフィナーレを飾る種目になるからです。 2日間、厳しい戦いを繰り広げた選手たちの間には、いつのまにかライバル同士が生み出す勝敗を越えた連帯感が生まれます。
最終レースのフィニッシュでは、選手同士で手をつないだり、笑顔で抱き合ったり、肩を組んでウイニングランをしたりと、感動的なシーンが見られる種目です。 スタジアムでは勝者も敗者もなくお互いに健闘を讃え合う選手たち、観客からは大きな拍手と歓声が沸き起こり、競技場全体が感動に包まれるのが、混成10種競技、7種競技のフィナーレの特徴になります。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは】
10種競技は欧米選手が強さを誇り、最近ではアメリがロンドン2012大会とリオデジャネイロ2016大会の2連覇を果たしている強豪国です。 リオデジャネイロ2016大会で銅メダル、東京2020大会で銀メダルを獲得したフランス、 東京2020大会で金メダルを獲得したカナダが、しばらくは10種競技を引っ張る存在になると考えられます。
7種競技はかつてアメリカが圧倒的な強さを発揮し、ロサンゼルス1984大会で銀メダル、続くソウル1988大会とバルセロナ1992大会で連覇を果たした強豪国です。 だが、それ以降はイギリスを中心にヨーロッパ勢が上位を占めています。
近年の注目選手はベルギーで、リオデジャネイロ2016大会で金メダルに輝き、2017年5月、オーストラリアで行われた混成競技の大会で優勝、東京2020大会でも金メダルを獲得し、ロサンゼルス2028大会での活躍も期待される有望な選手輩出国です。
日本はリオデジャネイロ2016大会で日本チームの旗手を務めた日本記録保持者が盤石の強さを誇っていたが、2017年の世界陸上選手権代表選考会では若い選手が優勝しています。 リオデジャネイロ2016大会代表になり、日本の10種競技をけん引きする存在です。 7種競技では、世界の壁は厚く急成長ととげる有望選手に期待が集まります。
【開催会場】
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
バスケットボールは己たちの妙技と戦術、迅速な展開やルールとの勝負

バスケットボールは5人制で、相手コートのリングにボールを投入れる競技です。 試合はチームワークや俊敏性、戦術に加え、全員攻撃・守備と目まぐるしく攻守が入れ替るスピーディーな試合展開に注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
バスケットボールの主な強豪国と地域:
「女子:アメリカ、日本、フランス etc.」
「男子:アメリカ、フランス、オーストラリア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では、欧米、アジア勢との順位争いに瞬きを忘れる。
己の妙技で、数多くのポイントを獲得し、新たな勢力図を築き上げられる国と地域はどこだぁ!
【バスケットボール競技の特徴】
バスケットボールは、全員攻撃、全員守備、めまぐるしく攻守が入れ替わる、スピーディーな試合展開です。 1チーム5人ずつで、パス、ドリブルなどでボールをつなぎ、相手コートのリングに投げ入れる競技になります。 男子では平均身長が2メートルに迫る選手たちが10人、屋内28メートル×15メートルのコートの中で、まるで花火が散るようにスピーディーな接近戦を繰り広げ、また不可能とも思える体勢から、ここしかないと思うポイントに撃つ針の穴を通すようなショットは圧巻です。 相手を翻弄するようなトリックプレーがゴールに結びつくシーンは痛快そのもの、観客から大歓声があります。 バスケットボールは、チーム戦術と個人技、瞬間的なスピードが魅力の、極上のエンターテイメントです。
【バスケットボール競技の歴史】
バスケットボールは、カナダ出身のジェームス ネイスミス博士が冬の間、生徒に健康を維持するために考案し、体育の授業に取り入れたことから広がります。 1891年12月に、アメリカ、マサチューセッツ州のスプリングフィールドにある国際YMCAインターナショナル トレーニング スクールに在籍していた体育教師は、適切な屋内スポーツを探し求めていたスポーツです。
【オリンピック競技としての歴史】
オリンピックでは、セントルイス1904大会でデモンストレーション競技として実施されます。 初めてオリンピックに登場し、この大会はアメリカのバスケットボール選手権のイベントとしてカウントされ、アメリカのチームのみが参加したゲームです。 1920年代には初の国際大会が開催され、その数年後のベルリン1936大会よりバスケットボールがオリンピック正式競技となります。 1950年代には男女初の世界選手権が開催された歴史です。 なお、女子バスケットボールは、40年後のモントリオール1976大会で初めてオリンピック種目として採用されます。 競技人口は4億5千万人といわれ、国際競技連盟(FIBA)加盟国はサッカー(FIFA)を上回る213ヵ国にのぼる人気スポーツです。
歴史的に見ると、米国は1972年、1988年、2004年を除くすべての大会で男子チームがオリンピック金メダルを獲得し、1984年以降、1992年のオリンピックを除くすべての大会で女子チームが優勝するなど、自らが発明したスポーツで特に優位に立っています。
アマチュア規定撤廃後のバルセロナ1992大会では、NBAのスター選手たちが集結した「ドリームチーム」と呼ばれるアメリカ代表が格の違いを見せつけ、各試合で平均40点以上の差をつけて金メダルを獲得し、大会に大きな華を添えたチームです。 以来、アメリカ代表チームは歴代NBAの花形選手を集め、世界中のスポーツファンの注目の的になっています。
【ルール】
実施種目
バスケットボール大会(女子/男子)
バスケットボールは、長方形の屋内コートで5人のプレーヤーからなる2つのチームが対戦する競技です。 5人制バスケットボールの攻防は全員攻撃、全員守備、プロスポーツとして発展してきただけあって、観客を楽しませるためのルールが多く存在します。
プレーヤーは手を使ってボールをコントロールし、ゲームの目的は、床から3.05メートルの高さに吊り下げられたフープにボールを投げ、フープからどれだけ離れているいかに応じて、2ポイントと3ポイントを獲得することで、できるだけ多くのポイント獲得することです。
ボールの扱いや接触プレーには細かく反則が設けられており、反則を避けながらオフェンス(攻撃)側はいかに相手のディフェンス(守備)をかいくくって相手のゴールにシュートを決めるか、またディフェンス側はいかに相手の攻撃にプレッシャーをかけてオフェンスからボールを奪い取ったり、シュートミスを誘って自分たちの攻撃に転じるか、という攻防が展開されます。
オフェンスになったチームは一定時間内にシュートを放たなければならないというルールも試合をスピーディーで魅力的なものとしている試合形式です。
ポイント数は、ショットが放たれた位置によって異なります。 3ポイントラインよりも外側からショットすれば3ポイント、それよりも内側からショットすれば2ポイント、反則などで一度プレーが切られ、ディフェンスのない状態で決められた場所からショットする「フリースロー」は1投1ポイントです。
オリンピックのバスケットボールの試合は、10分間のクォーターを4回に分けて行われます。 4ピリオド、合計40分間で2桁、3桁まで得点が争われるが、接戦の終盤にはショットの一本一本が、強力なプレッシャーのかかるものとなる試合展開です。
プレーヤーはオフェンスとディフェンスを切り替え、持久力、柔軟性、そしてもちろん、コートを駆け巡り、ボールを撃つ際に多くのスキルが要求されます。
特にプレッシャーがかかるのはフリースローの場面です。 ショットが得意とされている選手がプレッシャーから外す場面が多く、逆に1つのショットをきっかけにゾーンに入った選手が神がかったように連続ポイントをしたりと、アスリートのメンタルの状態が手に取るように伝わってきます。
攻撃のカギを握るポジションの一つは、技術と俊敏性と戦術眼を高レベルで必要とされる「ポイントガード」です。 チームの強さはポイントガードの質によって左右されるといっても過言ではありません。 このポイントガードの選手に注目してみると、いかに広い視野で戦況を見極め、コートの至るところに顔を出し、指示を飛ばし、攻守の切り替えや鋭いアシストなどでゲームメイクしているかがわかるはずです。
ドリームチームアメリカを、どこのチームが倒せるか注目が集まります。 アトランタ1996大会以降、男女ともにアメリカが強さを誇り、アテネ2004大会での男子を除いて金メダル独占中です。 リオデジャネイロ2016大会は男女とも予選から全勝で金メダルに輝いており、「1強」時代は今後もしばらく続くだろう。 パリ2024大会ではNBAスーパースターの選手たちが、オリンピックの舞台に踏むかどうか注目が集まります。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
男子の銀メダル争いはスペイン、フランス、セルビアなどヨーロッパ勢が中心だが、南米のアルゼンチン、北米カナダも実力をつけている競技です。 また、女子ではオーストラリアがシドニー2000大会から3大会連続で銀メダルを獲得するなど、アメリカに迫る活躍を見せています。 NBAのインターナショナルプレーヤーはますます増加し、NBAチーム主力で活躍する選手は自国代表として国旗を背負い、国の名誉のために戦うだろう。 普段のNBAでの戦いとは全く違う迫力ある40分間が繰り広げられます。
日本の代表チーム(5人制)の愛称は男女ともに「AKATSUKI FIVE(アカツキファイブ)」です。 男子は初めて正式種目となったベルリン1936大会から出場し、モントリオール1976大会を最後にオリンピックから遠ざかっているが、2016年にBリーグ(ジャパン プロフェッショナル バスケットボールリーグ)が開幕したことで、日本のバスケットボールは盛り上がり、東京2020大会を経てロサンゼルス2028大会ではどのようなプレーを魅せてくれるのか期待が高まります。
女子はモントリオール1976大会で5位入賞、アトランタ1996大会で7位入賞、3大会ぶりに出場となったリオデジャネイロ2016大会では準々決勝で女王アメリカに敗れたものの、アトランタ1996大会以来のベスト8進出を果たす実力です。 アジアでは2017年までアジアアップ3大会連続優勝を遂げるなどの頭抜けた実力を誇っています。 東京2020大会では銀メダルを獲得し、脂がのってきたチームです。
バスケットボール開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
3×3バスケットボールは独特の雰囲気の中で、迅速な攻防との勝負!

3×3バスケットボールは3人制で、コイントスで攻撃側、守備側を決めて行う競技です。 試合はアーバン・ストリート・スタイルで、チームワークや俊敏性、柔軟性、予測力が要求される戦術と技に注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
3×3バスケットボールの主な強豪国と地域:
「女子:アメリカ、ROC、中国 etc.」
「男子:ラトビア、ROC、セルビア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。
ロサンゼルス2028大会では、欧米、アジア勢との順位争いにストリート系が注目する。
己の技とチーム力で、メダル獲得できる国と地域はどこだぁ!
【3×3バスケットボール競技の特徴】
世界一のアーバン(都会環境)スポーツとされる3×3バスケットボールは、バスケットボールのクリエイティブなバリエーションとして、フォーマルではない構造のストリートバスケットボールから発展したスポーツです。
屋外コートからオリンピックへと進化した3×3バスケットボールは、5×5バスケットボールの開発を担当する統括団体である国際バスケットボール連盟(FIBA)によって長年にわたって構成されてきた競技になります。
2021年、東京2020大会でオリンピック正式種目に採用され、実施された1チーム3人同士で得点を競う「3×3 バスケットボール(スリー エックス スリー)」 新種目は、よりハードでスピーディーな試合展開です。
フランスでの3×3ワールドツアーや3×3スーパーリーグなどのイベントの導入は、DJと音楽が刺激的な雰囲気の中でプレイされるこの若いアーバンスポーツの人気の高まりを反映しています。
東京2020大会からの新種目3×3バスケットボールは主にストリートシーンで発展してきたスポーツです。 バスケットボールの歴史の中では新しい形式だが、全世界での競技人口はすでに40万人を超え、ワールドカップには180以上の国と地域が参加する人気スポーツに成長しています。
【オリンピック競技としての歴史】
2010年シンガポールユースオリンピックのプログラムに3×3バスケットボールが新たに加わり、また、2014年南京ユースオリンピック、2018ブエノスアイレスユースオリンピックにも出場した競技です。
この若いスポーツの目覚ましい成功を背景に、IOCは2017年に東京2020オリンピックの種目に3×3バスケットボールを含めることを決定したと発表し、この新しいダイナミックでスペクタクルな都会的なバスケットボールのバリエーションは、オリンピックの観客を魅了しています。
【ルール】
実施種目
3×3バスケットボール大会(女子/男子)
3×3バスケットボールは、通常のバスケットボールコート(縦28メートル×横15メートル)の約半分(縦11メートル×横15メートル)を使用した、ハーフコートで行われ、3人のプレーヤーからなる2つのチームが競い合う競技です。 コイントスで攻撃側、守備側を決め、ゲームを開始し3人で試合に臨みます。
どちらのチームも、誰がボールを持っているかに応じて、同じフープを攻撃および防御する試合展開です。
10分一本勝負で、通常のバスケットボールの3ポイントラインが2ポイントラインとなり、その外側からであれば2点、内側が1点(フリースローも1点)となります。
勝者は、どちらかのチームが10分間の終了時に最高得点を獲得したチーム、または21点先取した場合はその時点でゲームが終了です。
2021年の東京大会では、3人の選手と1人の補欠選手からなる8チームが、3×3バスケットボール史上初の男女オリンピックタイトルを目指して激突しています。
5人制よりもさらにスピーディーな攻防が繰り広げられるため、スリリングで目の離せない観戦体験になる試合展開です。 また、試合中でもMCや音楽など、エンターテイメントでゲームを盛り上げるのが大きな特徴でもあります。 3×3のゲームは短いですが、3×3のプレーヤーは5×5のプレーヤーと同じくらいの柔軟性、スキル、予測力を発揮することが必要です。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
3×3バスケットボールの世界ランキング上位国は、男子ではセルビア、ロシア、女子では中国、ウクライナと以外にもアメリカの順位は低い傾向があります。 ただしこの種目は世界ランキングの順位変動が激しく、メダル獲得は出場チームすべてに可能性があり、猛暑のパリでどう戦うか各国ともに準備に余念がないだろう。
日本は新種目「3×3バスケットボール」の世界ランキング2018年11月時点で男子4位、女子は8位につけています。 ロサンゼルス2028大会での日本バスケットボールチームの活躍に期待が集まりそうです。
3×3バスケットボール開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
ロードは一貫性と集中力で完璧なポジションを取り、己の脚力の勝負!

ロードは一般公道コースで実施され鍛え上げた脚力や体力、テクニック、各国のチームワークが光る競技です。 試合はスピードと耐久力、戦略に加え、限りなく空気抵抗を減らす走りや各チームの駆引きに注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
サイクリング ロードの主な強豪国と地域:
「エクアドル、ベルギー、スロベニア、オーストリア、オランダ、イタリア etc.」
タイムトライアル
「スロベニア、オランダ、オーストラリア、スイス etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では西欧、東欧、オセアニア勢との順位争いに向かい風が吹き荒れる。
己のエンジンを全開(kgf.m(N.m)/RPM)にスパークさせて、公道をうならせる国と地域はどこだぁ!
【自転車競技の特徴】
自転車は18世紀末にドイツで発祥されたのちフランスで改良され、ほどなく貴族階級の間でスポーツとして楽しまれるようになります。 その後、ヨーロッパからアメリカにわたり、アメリカでも普及したスポーツです。 自転車は、過去と現代の展望の両方を反映して、さまざまな分野で構成されています。 ロードサイクリングはスポーツの最も初期の形態です。
【オリンピックとしての歴史】
19世紀には、自転車の発明によりレジャーの娯楽となり、サイクリングの人気が急上昇します。 最初のレースは数年後に開催され、記録は1868年にパリのサンクルー公園で開催されたのが始まりです。
その後、まもなく、国内連盟が設立され始め、オリンピック第1回大会のアテネ1896大会から正式競技として採用され、 以来途切れることなく実施されている最も長い歴史を持つ数少ない競技の一つになります。 1900年から1908年までの3回の大会のうち、ロードサイクリングが欠場したのは1回だけです。 1900年には国際自転車競技連合として知られる国際連盟が設立され、さまざまな競技の組織を監督するようになります。
自転車レースはプロの世界を中心として発展してきたため、オリンピックの舞台では比較的地味な存在であったが、 バルセロナ1992大会からプロ選手の参加が可能になり、オリンピックでの注目度がアップしている競技です。
女子種目はロサンゼルス1984大会で、初めて個人ロードレースが採用された後、種目を増やし、 ロンドン2012大会以降男女種目同時実施が実現しています。
【自転車競技の歴史】
アトランタ1996大会からは、ロード タイムトライアル、マウンテンバイクが、シドニー2000大会はトラック種目に日本で発祥したケイリンが、 北京2008大会からはBMXレースがそれぞれ種目に加わり、東京2020大会ではトラック種目のマディソンとBMXフリースタイルの追加が決定された競技です。 このように、自転車レースのバリエーションは近年ますます広がりを魅せています。
今や世界最高のサイクリストたちによって論争されているオリンピック種目にさらなる名声をもたらしている競技です。
競技は使用する機材の違いで、すり鉢状の傾斜がついた競技場(オリンピックでは1周250メートル)で実施されるトラック、 一般公道で実施されるロード、起伏に富んだコースで実施されるマウンテンバイクとBMXレーシング、BMXフリースタイルの5つに大別されます。
繰り広げられるポジション争い、駆け引き、フィニッシュまで気が抜けない、手に汗握る戦いは圧巻です。
【ロードとは】
自転車ロードは屋外で行われ、オリンピックでは個人ロードレースと個人タイムトライアルの2種類の種目に分かれています。 個人ロードレースは一般公道を使い、男子は250キロメートル超、女子は130キロメートル超のコースを一斉スタートして着順を競う種目です。 全選手が一斉にスタートするロードレースは、持久力が試され、同じ国の選手のチームワークが光る種目でもあります。 多くの場合、レース(女性は120キロメートル以上、男性は200キロメートル以上)は、数百メートル以上のスプリントフィニッシュで勝つため、選手はレースの前半で完璧なポジションを取り、エネルギーを節約することが必要です。
個人タイムトライアルは一定の時間間隔を空けて1名ずつスタートし、男子は50キロメートル前後、女子は30キロメートル前後の距離の走行時間を競う種目です。 タイムトライアルが50キロメートルを超えることはめったにないため、ロードレースよりもはるかに短い距離をカバーします。 一貫性と集中力、そして効果的な空力ポジショニングとパワーによる保存が求められる種目です。
ロード種目 開催地:
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
トラックは空気抵抗を限りなく低減させた走り、己の脚力と駆引き勝負
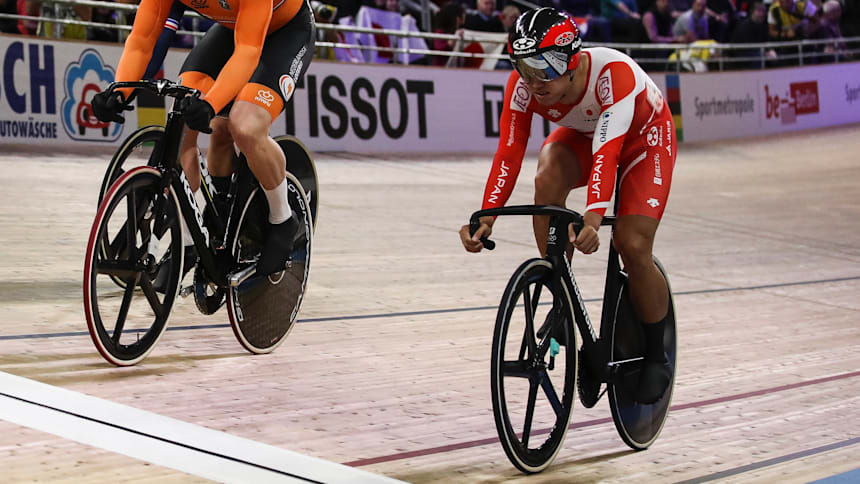
トラックは新種目も追加され、男女6種目ずつ行われる最も数多い種目競技です。 試合はすり鉢状の傾斜がついた競技場(1周250m)で実施され、如何に空気抵抗を抑え、チーム力を最大限に発揮できるかが見所! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
サイクリング トラックの主な強豪国と地域:
「オムニアム:イギリス、ニュージーランド、イタリア、アメリカ、オランダ etc.」
「ケイリン:イギリス、マラウイ、オランダ、ニュージーランド、カナダ etc.」
「スプリント:オランダ、イギリス、カナダ、ウクライナ、ホンコン・チャイナ、 チーム:オランダ、イギリス、フランス、中国、ドイツ、ROC etc.」
「パーシュート:イタリア デンマーク、オーストラリア、ドイツ、イギリス、アメリカ etc.」
「マデイソン:イギリス、デンマーク、フランス、ROC etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。
ロサンゼルス2028大会では、欧米、オセアニア、アジア勢との順位争いに空気摩擦で火花が飛び散る。
己のエンジンが叩き出す、100年目の新記録を打ち出す国と地域はどこだぁ!
【トラック競技の歴史】
長年オリンピック競技として君臨してきた自転車トラック競技は、近代最初のオリンピックで採用されたが、1912年のストックホルム大会では実施されなかった種目です。 120年以上の歴史を持つこのスポーツでは、ヨーロッパ諸国、特にイギリス、フランス、オランダ、イタリアがメダル獲得数の大部分を占めています。 しかし、他の国々は大会ごとに力をつけ、改善している種目です。 例えば、2019年の世界選手権で金メダル6個を含む10個のメダルを獲得したオーストラリアなどが存在します。
【トラックとは】
最初の自転車は1850年代に、特にフランスで発明され、今日私たちが知っている自転車とはかけ離れたものです。 しかし、1870年代になってようやくイギリスは木製の屋内トラックでサイクリングの競技会を発展させ、1878年にロンドンで最初の6日間のレースが開催されます。 トラックサイクリングは急速に人気が高まり、国際サイクリング協会の創設とともに発展を続け、これにより、1893年にシカゴで最初の世界選手権が開催された種目です。
トラックは、最も種目数が多く、男女それぞれ6種目ずつ実施される種目になります。
スプリントは、個人で着順を競う種目で、力を最大限に発揮するためには空気抵抗をいかに和らげるかが重要になり、レース中は最も風圧を受ける先頭を避けるためにさまざまな駆け引きが行われる種目です。 そして最終周付近からは、それまでとは打って変わって爆発的な先頭争いが繰り広げられ、一気に勝負がつく種目になります。 「いつ仕掛けるか」の判断もまた勝負のカギとなり、手に汗握る戦いです。
男子が1チーム3人。女子が1チーム2人で行うチームスプリントは、1周ごとにそれまで先頭走り、風よけとなっていた選手がコースから外れていき、 最後の選手がフィニッシュラインに達したタイム記録となります。 チームの力が問われる種目です。
チームパシュートは、4人1組の2チームが対面でスタートし、4キロメートルで競われ、相手を追い抜く、またはタイムで勝つことで勝者となります。 見どころは、空気抵抗から仲間を守り合うチームワークです。
ケイリンは7人までの選手によってトラック8周で競われる種目で、レース途中までは先頭誘導車が選手たちへの風よけをしながら段階的に速度を上げ、選手たちはその後ろで激しいポジション争いを繰り広げます。 先頭誘導車が速度を時速50キロメートルまで上げ、残り3周で離脱すると、レースは一気にヒートアップし、そこからの激しい流れが見どころです。
オムニアムは、トラックレースの複合種目で1日に4つのレースを行い、各レースの合計得点で順位を競い合います。 4レースの内訳は、多数の選手が一斉にスタートして順位を争うスクラッチ、周回ごとに先頭の選手にポイントが入るテンポレース(オリンピックでは東京2020大会で初の実施)、2周回ごとに最下位の選手が脱落するエリミネーション、中間ポイントを獲得しながら30キロメートル前後を走破し、ポイントを競うポイントレースです。
新種目マディソンは、2人1組のペアで、レース中に選手が交代しながら男子は50キロメートル、女子は30キロメートルを走って競い合います。 選手交代は、待機している選手と行うが、その際、選手の体に触れなくてはいけなく、高速走行中の選手が交代時に、待機中だった選手を加速するために手を引いて放つ「ハンドスリング」が大きな見どころです。 ハンドスリングではなく、腰を押しても良いことになっています。
トラック競技 開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
マウンテンバイクは己の持久力と技術で、コースを征服できるかの勝負

マウンテンバイクは山道を走り抜けるクロスカントリー競技です。 試合は起状に富んだコースで実施され、様々な表情があり、選手の鍛え上げた脚力や体力、テクニックで、如何にコースを制覇できるかが見所! 日本勢の活躍に期待する。フランス勢は100年目に挑む。
世界状況
マウンテンバイクの主な強豪国と地域:
「スイス、イギリス、スペイン etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では、西欧勢との順位争いに野生動物も加わる。
己の戦略を駆使したコース取りができる国と地域はどこだぁ!
【マウンテンバイク競技の歴史】
マウンテンバイクは、トラックサイクリングとロードサイクリングから100年後のアトランタ1996大会で、男女の個人レースでオリンピックデビューを果たした種目です。 オリンピックの短い歴史の中で、フランスとスイスの選手は、この種目で定期的に表彰台に上がり、この種目で授与された42個のメダルのうち16個を合わせて獲得しています。
【マウンテンバイクとは】
マウンテンバイクは、1970年代に登場した比較的新しいスポーツで、一部のサイクリストがバイクをオフロードに持ち出して、新しいトレイルを探索したいと考えついたのが始まりです。 1990年代には、ライディング中に受ける衝撃に耐えることができる最初のマウンテンバイクが作成されます。 その後、マウンテンバイクが普及し、それ自体がスポーツとなり、形になり始めた種目です。 最初の非公式大会は1980年代に開催され、1990年代に最初の公式世界選手権が開催されます。
【ルール】
クロスカントリーマウンテンバイクには、男女2種目が実施されます。 1周4キロメートル~6キロメートルの未舗装の山道を走るマウンテンバイク種目(クロスカントリー)は、同じスタートラインから出発し、山岳地帯の起伏の多い地形を周回し、さまざまな表情があるコースをテクニック、持久力、スタミナでいかに征服するかが見どころです。 レースはマススタートを特徴とし、一般的には複数のラップで行われます。 選手は1時間20分から1時間40分かけて、競技中に数十キロメートルをカバーする紆余曲折に満ちた激しいコースを完走する試合展開です。
マウンテンバイク競技 開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
BMXフリースタイルは己の技の難易度や独創性など、様々な採点との勝負

BMXフリースタイルは新種目として追加された競技です。 試合は曲面やスロープが複雑に組み合わせた施設で行われ、1分間にトリックを数多く行い、技の難易度や独創性、流れ、コントロール、着地などに注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
BMXフリースタイルの主な強豪国と地域:
「イギリス、アメリカ、スイス、オーストラリア、ベネズエラ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。
ロサンゼルス2028大会では、欧米、オセアニア勢との順位争いに大道芸人(パフォーマー)も興味が沸く。
己のパフォーマンスを発揮できる国と地域はどこだぁ!
【BMXフリースタイル競技の歴史】
BMXフリースタイルは、2018年にブエノスアイレスで開催されたユースオリンピックで初めてオリンピックの舞台に登場します。 満員の観衆の前で、スリリングな光景を披露し、IOCにこの究極のアーバンスポーツの可能性を確信させた種目です。 BMXフリースタイルは、2021年に東京で開催されたオリンピック種目で初登場させます。 この新しいスポーツは、新鮮な感覚をもたらし、すでにエキサイティングで包括的なサイクリングプログラムにアドレナリンを注入する種目です。
【BMXフリースタイルとは】
1970年代にカルフォルニアのレース文化から生まれたBMXフリースタイルは、ヒーローを模倣することに熱心な、この地域の子供やティーンエイジャーの想像力から生まれます。
このスポーツは、その後、数十年にわたって人気が高まり、2000年代のX GamesやFISE国際エクストリームスポーツフェスティバルなどのエクストリームスポーツ大会のプログラムを統合させた種目です。 第1回BMXフリースタイルワールドカップは、2016年に自転車競技の世界統合団体であるUCIによって、その年のFISEの一部として開催されます。
【ルール】
BMXフリースタイルは、都市の公園や曲面やスロープを複雑に組み合わせた施設で行われる種目です。 選手は60秒間にできるだけ多くのトリックを披露することが求められます。
1分間にトリック(ジャンプ、空中動作、回転などの技、テクニック)をいくつも行い、点数を競う採点競技です。 スコアは、技の難易度やジャンプの高さ、独創性(創造性)、流れ、コントロール、着地、スタイルなどが採点の対象となります。
これまで速さを競うことに主眼が置かれていた自転車競技に、新たな風が吹く種目です。
BMXフリースタイル(女子/男子)
BMXフリースタイル開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
BMXレーシングは己の素早い反応とエネルギーの爆発力、持久力との勝負

BMXレーシングは起状あるコースで高々とジャンプを繰返し、幾つかの傾斜の付いたコーナーを抜けフィニッシュを目指し、順位が決まる競技です。 試合は高所からの落下や接触など危険がつきまとう熱戦に注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカは。
世界状況
BMXレースの主な強豪国と地域:
「イギリス、コロンビア、オランダ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では、西欧勢との順位争いにエキサイティングな危険がつきまとう。
己の走りを素早く決められる国と地域はどこだぁ!
【BMXレーシング競技の歴史】
BMXは2003年に国際オリンピック委員会(IOC)の決定で、2008年北京オリンピックの正式種目として採用され、オリンピックの舞台で活躍した歴史は比較的浅いが、すでにオリンピックで存在感を示している選手もいます。 オリンピックで2度の金メダルを獲得したコロンビアと、東京2020で優勝し、2021年の世界チャンピオンであるオランダは、パリ2024で表彰台の頂点に立つ有力候補の2人です。
【BMXレースとは】
BMXはバイシクル モトクロスのことで、オートバイのモトクロスの影響を受けて1960年代にアメリカ カリフォルニアで誕生した競技になります。 子供たちは、自転車でアイドルの真似をして楽しみ、BMXは、1980年代初頭に最初のBMX連盟が設立され、本格的なスポーツに発展し始めた種目です。 1982年に第1回BMX世界選手権が開催され、1993年にはBMXが国際自転車競技連合を正式に統合し、オリンピック競技への最初のハードルを突破します。
【ルール】
BMXレーシングは、8メートルの高所にあるスタートヒル ゲートから最大8人が一斉に坂を駆け下り、400メートルのトラックに飛び込み、最高時速60キロメートルに達する種目です。
BMXレーシングは、大きく起伏のあるコースで高々とジャンプを繰り返し、幾つかの傾斜の付いたコーナー(バーム)を抜けてフィニッシュを目指し、着順で順位が決まります。 この種目は、最も反応が速く、ペースが速い選手が勝てる戦いです。
高いジャンプからの落下や接触などの危険がつきまとうため、フルフェイスヘルメットやゴーグルなど5種別中で最も多くの装備が必要だが、それだけにレースは迫力満点な試合展開になります。
BMXレーシングは、数分間の持久力が評価される傾向があり、わずか数秒の短時間で激しいエネルギーの爆発が必要です。 素早い反応と爆発力は、集団の先頭でゲートから飛び出し、フィニッシュラインまでリードを維持するために不可欠になります。 決勝レースは、観客が息を殺して見守るスリリングな光景です。
レース(女子/男子)
BMXレーシング競技 開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
歴代メダル獲得数ベスト3は、自転車文化の本場である西欧の国々、フランス、イタリア、イギリスで、西欧に次いでアメリカ、オーストラリア、東欧と続きます。 ただ、トラック種目においては近年ニュージーランドやオーストラリアといったオセアニアの選手たちが力を上げてきており、ロサンゼルス2028大会の表彰台では、これまでとは少し違った顔ぶれが見られるかもしれません。
BMXでは、アメリカやオーストラリア、コロンビアなど西欧以外からメダリストが出ており、今後が注目される種目です。 アジア地域からは近年、中国の選手が力を伸ばしています。
また、自転車競技の特徴として選手寿命が長く3大会にわたってメダルを獲得し続けている選手が珍しくありません。 スピード、テクニック、チームワーク、鍛え上げられた脚力が躍動する自転車競技は、種目ごとに異なる勢力図、複数のオリンピックを制し、記憶に刻まれる次の英雄に注目が集まります。
日本はケイリン発祥の地で、これまでにトラック種目でいくつかのメダルを獲得し、近年ではロード種目でも有望選手が育っており、ロサンゼルス2028大会へ向けて期待が持てそうです。 また、新種目BMXフリースタイルのパークでは、ジュニア世代が注目されていて、自転車の複数種目で日本選手が活躍する可能性は広がりつつあります。
アーチェリーは驚異の集中力と強靭なメンタル、己の平常心との闘い!

アーチェリーは標的を狙って弓で矢を放ち、得点を競い合う競技です。試合は張詰めた緊張感が漂う空気の中、体力や精神力の強さ、平常心を保って70メートル先の的を正確に射抜く高度な技に注目!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
アーチェリーの主な強豪国と地域:
「男子:韓国、チャイニーズタイペイ、トルコ、イタリア、女子:韓国、ROC、ドイツ、イタリア、混合団体:韓国、オランダ、メキシコ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。ロサンゼルス2028大会ではアジアや欧米、南米勢との極限の緊張感が痺れる順位争いに呼吸が乱れる。自然状況を読み取り、味方に付け、正念場で僅かな雑念を払い、矢を放てる国と地域はどこだぁ!
【アーチェリーの特徴】
アーチェリーは、70メートル先から標的を射抜く驚異の集中力、極限の緊張感に観る者すべてが息を呑む競技です。 選手と一体になって、張り詰めた緊張感と心地よい屋外の爽快感をともに味わうことができます。 アーチェリーは、現在も行われている最古のスポーツの1つで、かつては狩猟や戦いのために人類が文明とともに発展した道具です。 アーチェリーは、標的を狙って弓で矢を放ち、得点を狙う競技になります。
体力や技術はもちろん必須だが、わずかな雑念がミスにつながる競技で、メンタルの強さが勝敗の決め手となります。 一流選手たちが重要な場面で、どれだけ平常心を保って正確に矢が放てるかが見どころです。 アーチェリーには、屋外の地面の平坦な射場で行うターゲットアーチェリー、森や山などで行われるフィールドアーチェリー、屋内で行われるインドアアーチェリーなど競技の種類はさまざまだが、オリンピックではターゲットアーチェリーが実施されています。
【アーチェリーの歴史】
紀元前1200年、ヒッタイト人とアッシリア人が戦場で弓矢を使ったのが始まりです。 記録に残る最初のアーチェリー大会は、周王朝(紀元前1027-256年)に中国で行われています。 1931年に、このスポーツは世界中で発展し、国際アーチェリー連盟が設立され、現在はワールドアーチェリーとして知られている競技です。
【オリンピックとしての歴史】
アーチェリーは早くからオリンピックに登場し、パリ1900大会でアーチェリーが開催され、1920大会まで続けて実施されてきましたが、パリ1924大会からしばらく外された競技です。 その後、ミュンヘン1972大会まで50年以上にわたってオリンピックから遠ざかり、再び正式競技として復活した競技になります。 アーチェリーはミュンヘン1972大会で再導入され、それ以来、オリンピック種目として採用されている競技です。 韓国は1972年のオリンピック復帰以来、金メダルの半分以上(45個中、27個)を獲得し、圧倒的な強さを見せています。
【ルール】
オリンピックでは、標的は直径122センチメートルの円で、射手から70メートル離れた位置で競技を行い、中心に当たれば10点、以下、得点となる円の帯が並んでいて、9点、8点、1点と外側に向かって点数が小さくなる配点です。 1点の外側は0点となります。 射手から70メートル離れた位置というのは、オリンピック競泳の50メートルプールより、さらに長い距離です。 そんなに遠くからCDと同じ大きさの中心の10点をめがけて矢を放ちます。 まずはその壮大さ、高度な技に圧倒される競技です。
【アーチェリー競技方法】
オリンピックのアーチェリーは、男女2種目、団体2種目(男女別)、そして東京2020大会で初めて行われた混合種目の5種目で実施されます。 アーチェリーは大きな集中力と器用さが必要です。 アーチェリーは、特に決勝戦や個人種目では、たった一度のミスが致命的になる可能性があるため、神経がすり減ります。
予選は64人の選手で行われるランキング ラウンドで、ランキングに応じて決勝までノックアウト方式で競い合い、トーナメントのランキングを決めるために行われる試合です。
1人が72射放ち、合計得点で1位から64位までの順位を決め、1位対64位、2位対63位とトーナメントでの対戦相手が決まります。 1対1で行われるトーナメントでは、1射ずつ交互に射つ(1射の制限時間は20秒)試合方式です。 1マッチ6ポイント先取で勝利になり、1セット3射30点得点で得点の高いほうの選手に2ポイント、引き分けの場合はそれぞれに1ポイントが付与されます。 最大5セットまで行い、両者5ポイントの引き分けのときはシュートオフ(タイブレーク)を行い勝者を決定する競技です。
予選と異なり1対1で対戦するので、勝つか負けるかの戦いになります。 アーチェリーは自分との闘いというが、相手が高い点を出せば、どうしても気持ちに影響するもので、相手の得点によって、さらに良い得点を出すこともあれば、プレッシャーでミスしてしまうこともある試合展開です。 どれだけ相手に影響されず、自分のパフォーマンスができるかが、一番の見どころになります。 シーソーゲームになることも多く、1射、1射、最後まで安心はできません。
矢をつがえ、引き、狙いを定め、引いた矢を離すまでの一連の動作を、選手は心を乱さず、集中力を高めて行いますが、その時の心身の緊張は観る者にもはっきりと伝わってくるものです。 観戦する時は、この緊張感をともに味わい、また競技場で観戦する場合は、矢が的に向かって飛んでいくスピード感や、矢が的に吸い込まれていく時の爽快感も、 選手とともに感じることができます。
団体戦では、1チーム3人構成で予選の合計点数順に、12ヵ国のトーナメント組み合わせが決まる試合方式です。 1セットは3選手が各2射の計6射、これを4セット行い、総得点の高いチームが勝ちとなります。 1マッチ5ポイント先取で勝利し、1セットは、選手が各2本射ち計6射60点満点で得点の高いほうのチームに2ポイント、引き分けの場合はそれぞれに1ポイントが付与される仕組みです。 最大4セットまで行い、両チーム4ポイントのときはシュートオフ(タイブレーク)を行い勝者を決定します。 いい緊張感がつくられてパフォーマンスが上がる選手もいれば、失敗が許されないというプレッシャーで、ミスをしてしまう選手もいる試合展開です。 国を背負って一流選手たちが見せてくれる人間らしいドラマが楽しめます。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
オリンピック アーチェリー 8連覇を誇る韓国勢の牙城を、切り崩すことができる国と地域はどこだ。
アーチェリーの強豪国といえば、なんといっても韓国です。 男女、団体とも圧倒的な強さを誇ります。 韓国の層が、いかに厚いかを知るには、韓国代表に選ばれるほうが難しいと言われており、その通りになる出来事もあるぐらいです。 アーチェリーは体力だけでなく、精神力の強さも問われるので、トップ選手の年齢の幅が広いのが特徴になります。 30歳代はもちろん、40歳代のトップ選手もいる競技です。 メンタルの強さは経験を積むことで磨かれるという面もあり得るからだろう。 東京2020大会を経てロサンゼルス2028大会で、誰が代表になって活躍するか、熟練の選手か、若手か、技術的に均衡の中、予測するのは難しくなりつつあります。
男子は韓国の次に強豪国と言われるのがアメリカです。 他にチャイニーズタイペイ、トルコ、イタリア、オーストラリア、フランス、日本などがメダルを狙ってくるだろう。 女子は中国、ROC、チャイニーズタイペイ、ドイツ、イタリア、メキシコ、日本などがメダル候補です。 層の厚い韓国の牙城をこれらの国々が崩すことができるか、注目が集まります。
日本ではアーチェリーへの興味を持つ人が、増えつつありベテラン勢や若手も自分の力が発揮できるように期待したい。
アーチェリー開催会場
※東京2020大会関連資料より、参考元:
バレーボール 女子 Ver.
女子バレーは磨上げた己の戦術と戦略で、粘り強いラリーを制する勝負

女子バレーは高い技能や作戦、チームワークと協調性が求められる球技です。 試合は監督の采配やセッターやアタッカー、ブロッカー、オポジット、リベロの大胆なスーパープレーが魅力! 日本女子の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
バレーボール 女子の主な強豪国と地域:
「アメリカ、ブラジル、セルビア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会は欧米や南米、アジア勢との粘り強い順位争いに執念の火花を散らす。
各国の選手たちの高い技能や身体能力、戦術、チームワーク、協調性を備えたバレーボールの名誉を掴み取れる国はどこだぁ!
バレーボール 男子 Ver.
男子バレーは磨き上げた己の戦術と戦略で、力強いラリーを制する勝負

男子バレーは高い技能や作戦、複雑性を持合せた球技です。 試合は渾身の力で仕掛ける強烈なサーブやスパイク、低いトスを速く上げて打つ速攻などパワーみなぎるダイナミックなスーパープレーが魅力! 日本男子の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
バレーボール 男子の主な強豪国と地域:
「フランス、ROC、アルゼンチン etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会は欧米や南米、アジア勢のパワーみなぎる順位争いに目が追いつかない。
各国の選手たちの高い技能や身体能力、戦術、チームワーク、複雑性を備えたバレーボールの名誉を掴み取れる国はどこだぁ!
【バレーボールの特徴】
バレーボールは、バスケットボール発祥の地である米マサチューセッツ州のスプリングフィールド大学を卒業後、同州ホルヨーク市のYMCA体育指導者を務めていたウィリアム G モーガンによって1895年に考案された競技です。 ウィリアム G モーガンは、高齢者がプレーできるスポーツを作りたいと考え、当初は「ミノネット」と呼ばれ、誰もが楽しめる室内の娯楽スポーツとして、テニスやハンドボールなどの他のスポーツの特徴を取り入れて発展したスポーツになります。
バレーボールは瞬く間に人気を博し、20世紀初頭には、カナダをはじめ、キューバや日本など、世界中で急速に普及していった競技です。 最初のルールブックは1900年代初めに作成され、1947年には国際バレーボール連盟(FIVB)が創設されます。 その2年後に男子の第1回世界選手権がチェコスロバキアで開催され、1952年には女子の世界選手権がソビエトで開催された歴史です。
バレーボールは、ネットによって分けられた18メートル×9メートルのコートで、2つのチームがネット越しにボールを打ち合い、ボールを落とさずに、3回以内のタッチで相手コートに返球します。 相手チームのサーブをレシーブし、トスを上げ、スパイクを打ちこむのが基本的な流れで、攻撃と防御を交互に行うプレースタイルです。 選手の高い技能や身体能力に加え、高い戦術を理解し合える最良のメンバーのチームワークや協調性が求められます。
どちらかのチームがコート内に落球したり、大きくはじいてアウトになったり、また反則によってボールを繋げなくなるまで、ボールを打ち合うラリーが続く試合展開です。
バレーボールのポジションはセッターとスパイカー(アタッカー)、ブロッカー、オポジット、リベロとそれぞれの役割があります。 スパイカーやオポジットの強烈かつのダイナミックなスーパープレーや、粘りのレシーブ、目の前に立ちはだかる高い壁を打ち破る強烈なアタック、諦めずにボールを追う姿から目が離せません。
【オリンピック競技としての歴史】
バレーボールは、東京1964大会において、新競技として男女種目ともにオリンピックデビューを果たした競技です。 当時は、1リーグ総当たり制(ラウンドロビン方式)で行われ、全てのチームがお互いに対戦する選手権が行われています。 8年後、この方式は1972年ミュンヘンオリンピックで変更され、予選ラウンドと、上位8チームによる決勝ラウンドで構成される標準的なトーナメントに取って代わられ、メダル獲得チームを決定する形式です。
1960年代から70年代にかけては、男女ともに日本とソビエト連邦が表彰台の常連だったが、1980年代以降、アメリカ合衆国、中華人民共和国、ブラジル、キューバが強豪国に名を連ねるようになります。 1990年代から今日にかけては、これらの国に加えイタリア、中国も力をつけてきている勢力図です。
男子はロシア(旧ソ連)、ブラジル、アメリカ合衆国、女子はロシア、中華人民共和国、キューバがそれぞれ、オリンピックでの金メダル獲得数トップ3を占めています。 オリンピックでは、これまでに男女それぞれ15個の金メダルが授与されたが、その10個をこれらの国が獲得している強豪国です。
【ルール】
種目
バレーボール大会(女子/男子)
バレーボールの主な大会や国際試合は、長さ18メートル、幅9メートルの室内コートをネットで2つに分けて行います。 1チーム6人制で、前衛 後衛それぞれ3人の計6人がボールを素手で打ち合って対戦するチームスポーツです。
守備を専門とするリベロは、どの後衛の選手とも交代することができるポジションで、レシーブのスペシャリストとして、1人だけ異なる色のユニフォームを着用するので判別しやすくなっています。
試合は、ラリーに勝ったチームが1点と同時に次のサーブ権を得るラリーポイント制で、25点先取の5セットマッチで行われるルールです。 ただし24-24の同点になった場合はデュースとなり、相手チームより2点リードするまで試合は続けられます。 特に実力が拮抗したチーム同士の対決では1点の取り合いが長く続き、手に汗握る試合展開です。 3セットを先に獲得したチームが勝者となりますが、セットカウントが2-2となった場合、最終第5セットは最小限2点差をつけて15点を先取したほうが勝利します。
男子のプレーは、速さと高さ、そしてパワーが魅力です。 バレーボールの試合では、特に華麗かつ強烈なジャンプサーブは、時速130キロメートルにも到達します。 低いトスを速く上げて素早くスパイクを打つ速攻(クイック攻撃)は、目が追いつかないほどの速さです。 また、2メートルを超える長身の選手がスパイクを打つ高さは、3.5メートルにも達し、その打点から、渾身の力でボールを相手コートに叩きつける迫力は観客を魅了させます。 選手には、高い筋力や瞬発力、そのスパイクをレシーブするための電光石火の反射神経が要求される試合展開です。
女子は、男子に比べてラリーが続きやすく、1回のプレーが長いのが特徴になります。 コートに落ちる寸前のボールを拾い、最後まで諦めずに追いかける粘り強いプレーに、心からの声援を送りたいところです。
速さと高さ、パワーみなぎる男子のプレー、粘り強い女子のプレーに刮目せよ!
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
現在、世界バレーボール ランキングで上位を占めているのは、男子はフランス、アルゼンチン、ブラジル、アメリカ、イタリア、ポーランド、ロシアなど、女子はセルビア、中国、アメリカ、ブラジル、ロシアなどです。
オリンピックの金メダル獲得数は、男女ともロシアが4個とトップだが、うち男子は3個、女子はすべてソビエト連邦時代のものになります。 高さとパワーを誇ったソビエト連邦に対抗すべく、速攻やフェイントといった戦術が他国で次々と編み出され、競技に複雑性が加味されていった競技です。 近年では、ヨーロッパの伝統国に加えて、男女ともブラジル、アメリカの活躍が顕著となっています。
観戦中は、得点を量産するエーススパイカーに目が行きがちだが、実際に試合を組み立てているのはセッターです。 多くの場合、指示を出す司令塔役を務め、サインによってチームメイトに戦術を伝達します。
プラン通りに攻撃を実行して成功させるには、レシーブしたボールをうまくセッターに返すことがカギです。 名セッターは処理の難しいボールも自在に扱います。 またセッターが繰り出す正確かつ精度高いトスやブロッカーの度胸、守備を専門とするリベロは、レシーブのスペシャリストとして大変重要なポジションです。
確かにスパイクやブロックでは身長が高く腕のリーチが長いほうが有利であるが、単純に体格差だけで勝敗が決まるわけではありません。 各国のチームで要となるセッターに注目すると、よりゲームの奥深さが感じられるはずです。 また、監督の采配にも注目し、対戦相手の特徴を踏まえつつ、誰を先発で起用するか、さまざまな状況に応じて、どのような選手交代をするのか、また悪い流れを断ち切るタイムアウトのタイミングなども、勝利への重要なポイントとなります。
日本女子は東京1964大会において、回転レシーブという新しい技術を導入して金メダルを獲得し、東洋の魔女と呼ばれ、その後、モントリオール1976大会で金メダル、他大会で銀メダルと銅メダルを各2個獲得した強豪チームの一つです。 女子は情報端末によって戦況を分析、活用するITバレーでサーブやディフェンスを強化し、世界と互角に戦えるチームとなっています。
日本男子はミュンヘン1972大会で、時間差攻撃を生み出し金メダルに輝き、その後の大会でも銀と銅を1個ずつ獲得している強豪チームです。 ロサンゼルス2028大会へ向けて、新たな技や戦術を身に付け、どこまで躍進できるのか期待が高まります。
【開催地】
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
ビーチバレーボールは己たちの戦術と柔軟な対応力、連携プレーの勝負

ビーチバレーボールは砂の上で2人1組のチームが対戦する競技です。 試合は自然環境に対応する能力や戦況に素早く適応し臨機応変にプレーする能力、チームワーク、コミュニケーションなどに注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
ビーチバレーボールの主な強豪国と地域:
男子「ノルウェー、ROC、カタール etc.」
女子「アメリカ、オーストラリア、スイス etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会は欧米、オセアニア、アラブ、アジア勢との順位争いに素足がヤケドする。
己たちの反射神経で、臨機応変にプレーできる国と地域はどこだぁ!
【ビーチバレーボールの特徴】
バレーボール競技の一つとして、砂の上で実施されるビーチバレーボールは、1920年カリフォルニア州サンタモニカの海岸で誕生したスポーツです。 屋内のバレーボールから派生したビーチバレーボールは、2人1組のチームが対戦します。
最初の公式ビーチバレーボールトーナメントは1947年に開催され、1950年にカリフォルニア州のビーチを数百人の選手が転戦するサーキットも開催された競技です。 1983年に最初のプロ選手組合(バレーボールプロフェッショナル協会 AVP)が創設され、1987年には国際バレーボール連盟(FIVB)公認の初の国際大会がブラジルで開催されます。 ビーチバレーボールは、男女とも1996年アトランタ大会から、正式オリンピック種目となった競技です。
【オリンピック競技としての歴史】
ビーチバレーボールは、1992年のバルセロナ夏季オリンピックでデモンストレーション競技として初めて登場し、アトランタ1996大会でオリンピックの正式種目としてデビューを果たします。
ブラジルとアメリカは、この競技で大きな成功を収めており、42個のメダルのうち、合計24個のメダル(金メダル10個を含む)を獲得している強豪国です。 金メダルで表彰台に上がった他の国内オリンピック委員会は、男子(ロンドン2012)と女子(リオデジャネイロ2016)のドイツ、女子(シドニー2000)のオーストラリア、男子(東京2020)のノルウェーになります。
【ルール】
種目:ビーチバレーボール(女子・男子)
ビーチバレーボールでは、2人制の2チームが、長さ16メートル、幅8メートルの砂場で、ネットで仕切られたコート上で対戦します。 コートのサイズは、インドアよりひと回りほど狭めですが、コートの中央に張られるネットは、室内バレーボールと同じ高さ(女子では2.24メートル、男子2.43メートル)のものが用いられる競技です。
試合は、3セットマッチで行われ、2セット先取したチームが勝者となります。 最初の2セットは、それぞれ21点まで行われるが、3セット目まで実施される場合は15点までとなるルールです。 各チーム選手2人でコート内を全てカバーしなければならないため、電光石火の反射能力が要求され、かなりハードな競技だと言えます。
ビーチバレーボールの試合は屋外で行われるため、風、太陽、雨がプレー条件に影響を与える可能性があり、したがって、試合に勝つために、選手はさまざま状況に素早く適応し、臨機応変にプレーする能力も求められる競技です。 チームメイトの、息の合った連携プレーが見どころで、相手チームには見えないように、腰の後ろで、両手の指を使ったサインを送ってコンタクトをとっています。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
ビーチバレーボールは、インドアのバレーボールから転向したプレーヤーが多く、2人制であることから近年参加国も増えている競技です。 アメリカとブラジルが強豪国として知られており、過去6回のオリンピックでは、男女ともアメリカが3回金メダルを獲得しています。 他にもノルウェー、ラトビア、ポーランド、ドイツ、カナダが頭角を現してきている勢力図です。
日本ビーチバレーボールは、女子はアトランタ1996大会で5位、シドニー2000大会で4位に入賞を果たし、競技の人気も次第に高まっており、今大会での躍進が楽しみです。 かつて日本バレーボール界は、新たな戦術や技術を披露して、メダルを獲得してきています。 果たして、ロサンゼルス2028大会へ向けて新たな取り組みや技の開発が発揮できるかが活躍のカギです。
ビーチバレー競技会場
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
サッカー 男子 Ver.
サッカーは若手が活躍し過酷な困難や課題、逆境を乗越える己との勝負

サッカーは若手スター選手が集い華麗なスーパープレーやダイナミック、ドラマティックさがある球技です。 試合は強豪チームが多く、神童的な技能や高い戦術、パフォーマンスを発揮できるかに注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
サッカー 男子の主な強豪国と地域:
「ブラジル、スペイン、メキシコ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では欧米や南米、オセアニア、アフリカ、アジア諸国勢との過酷な試練の順位争いにホイッスルが鳴り響く。
過酷な課題や困難、逆境を乗越えられたサッカーの勲章である優勝トロフィーを掴み取れる国と地域はどこだぁ!
サッカー 女子 Ver.
サッカーは若手が活躍し過酷な困難や課題、逆境を乗越える己との勝負

サッカー女子はチームワークや協調性が求められ、華麗なプレーやダイナミック、ドラマティックな球技です。 試合は強豪チームが多く神童的な技能や高い戦術、パフォーマンスを発揮できるかに注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
サッカー 女子の主な強豪国と地域:
「カナダ、スウェーデン、アメリカ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では欧米や南米、オセアニア、アフリカ、アジア諸国勢との過酷な試練の順位争いにホイッスルが鳴り響く。
過酷な困難や課題、逆境を乗越えられたサッカーの勲章である優勝トロフィーを掴み取れる国と地域はどこだぁ!
【サッカー競技の特徴】
サッカーの起源は古代中国にまでさかのぼり、近代的なサッカーは中世イギリスで生まれとされています。
1863年に設立されたフットボール・アソシエーション(イングランドサッカー協会)によってルールが整備され、1930年から4年ごとに開催されるFIFAワールドカップは世界中で高いテレビ視聴率を誇る大イベントとなった大会です。
サッカーは世界で最も人気の高いスポーツに成長を遂げています。
サッカーは1チーム11人でボールを相手のゴールに入れて点数を競う球技です。 ボール1つあればプレー(遊べる)できるので、ヨーロッパ、南米、アジア、アフリカなど大陸を問わず、世界各地の子供達など幅広く親しまれています。
試合は他の球技に比べ点数を得ることが難しく、それだけに1得点の重みが異なり、得点シーンでは観客の目をくぎ付けにし、人々を熱狂させるドラマティックさと魅力があるスポーツです。
【オリンピックにおける歴史】
オリンピックの男子サッカーは、FIFAワールドカップよりも歴史が長く、ロサンゼルス1932大会を除いて(1930年からFIFAワールドカップが開催されたため)第2回近代オリンピック パリ1900大会から毎大会で実施されています。
モスクワ1980大会まではオリンピック憲章のアマチュア規定のためプロ選手が出場できず、注目度は高くありませんでしたが、現在は世界の若手スター選手のお披露目、活躍の場となっており、毎回大きな盛り上がりを見せている競技です。
1992年バルセロナ大会からは出場資格が23歳以下となり、1996年アトランタ大会からは23歳以下のチームに3名のオーバーエイジ選手を加えることができるようになり、FIFAワールドカップでは実現しない若い顔ぶれの活躍が見られます。
男子サッカーはバルセロナ1992大会まではヨーロッパ諸国が圧倒的な強さを誇る強豪国です。 しかし、スペインが同大会で金メダルを獲得したのを最後に、アトランタ1996大会以降、アフリカとラテンアメリカ勢が金メダルを独占しています。
女子サッカーはアトランタ1996大会でオリンピックデビューを果たし、アメリカ合衆国女子チームは、表彰台の常連の強豪国です。
アメリカはアトランタ1996大会以来、アテネ2004大会、北京2008大会、ロンドン2012大会で4度の金メダルに輝いています。
ドイツ女子チームは、リオデジャネイロ2016大会で優勝し、カナダは東京2020大会で金メダルを獲得した国々です。
女子サッカーは年齢制限がなく、金メダルはワールドカップと同等のステータスを持っています。 オリンピックの女子サッカーは男子と比べて歴史は浅いですが、世界における女子サッカーの普及、発展に大きく寄与している種目です。
【ルール】
種目
男子、女子
オリンピックでのサッカー競技は男女ともFIFAのトーナメントと全く同じルールで実施されます。
ただし、男子サッカーはチーム構成が少し異なっており、各チームは、2001年1月1日以降に生まれた選手(パリ2024大会の時は23歳以下となる)で主に構成されなければならないルールです。
しかし、3名だけならその日以前に生まれた選手をチームリスト(合計18名)に加えることができます。
1チーム11名の選手からなる2チームが、90分間(45分ハーフ)にわたって芝生のピッチ上で対戦する競技です。
サッカーは、非常に多くの試合があるため、開会式の前に競技が始まる唯一のスポーツになります。
そのため、シドニー2000大会以来、大会が正式に開かれる2日前にトーナメントが始まる競技です。
【ポジション】
サッカーのポジションは大きく分けて、ゴールキーパーやディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードになります。
ゴールキーパーはゴールエリア内でプレー時間を過ごしながら、シュートを防ぐ役割で、最後方から全体を見渡しながら、大声でチームメンバーに指示を与え、自陣をまとめる重要なポジションです。
ディフェンダーはプレーエリアが自陣ゴールに近いため、一つのミスが失点につながることもあり、冷静沈着な判断と勇気あるプレーで相手チームの攻撃を食い止め、仲間と連携しながら動く常に重要なポジションになります。
また戦術によりディフェンダーがピッチをダイナミックに駆け上がって攻撃に参加し、得点につながるプレーをすることもあり、豊富なスタミナと俊足とを兼ね備えた選手が役割を務めるポジションです。
ミッドフィルダーは主にピッチのハーフウェイライン付近にポジションを取りながら、守備と攻撃の両方を行ってゲームメイクを担います。
なお、守備的な動きが多く、攻撃の芽を事前につぶすボランチ(守備的ミッドフィルダー)の働きは一見目立たないですが、非常に重要です。
より相手ゴールに近いエリアでプレーする攻撃的ミッドフィルダーは、前方のスペースを見つけ一発で通すスルーパスなど、華やかなプレーで観客を魅了させる力があります。
フォワードは仲間たちが運んで来たボールを相手ゴールに入れる「得点」を至上命題としているポジションです。 ゴール前での攻防は視聴者の目を集めるだけに点が入れば大スターになるとともに、またシュートミスも観る者に悪い印象を与えやすく、良くも悪くも目立つポジションになります。
競技は1グループ4チーム総当たりのグループリーグを経て上位2チームが決勝トーナメントに進み、メダルを争う構成です。
サッカーは日中の屋外でハーフタイムを挟んで90分間走りっぱなしの過酷さや交代選手の起用など、いかにチームのコンディションを持続させながら連戦を戦い抜けるか、メダル獲得を目指すには大きな課題が山積みです。
サッカーは手でボールに触ることができなく、ボールを操る足技、相手ディフェンスを交わし相手ゴールへとボールを運ぶチームワーク、相手チームの攻めを防ぐ戦術などファンたちを魅了し続ける力があります。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
男子サッカーで強豪国は、ブラジル、アルゼンチンなどの南米の国々と、イングランド、ドイツなどの西欧諸国です。
だが、オリンピックは近年までアマチュア規定でプロ選手の出場がなく、旧ソ連やハンガリーなどの東欧諸国やカナダ、アフリカ諸国など、ワールドカップとは違う顔ぶれの国々が金メダルを手にしています。
ワールドカップ最多優勝を誇るブラジルも、オリンピックではリオデジャネイロ2016大会で優勝したのが唯一の金メダルです。 近年は、アテネ2004大会、北京2008大会でアルゼンチンが2連覇を成し遂げています。
ロンドン2012大会ではメキシコが金メダルを獲得し、ヨーロッパ諸国の栄冠はバルセロナ1992大会のスペインを最後に遠ざかっている状況です。 ただし、アジアからの金メダルは全大会を通しても、獲得できていません。
女子サッカーでは、スウェーデン、ドイツ、ノルウェーといった中欧、北欧諸国と北米、そして日本が強さを見せています。 だが、今後多くの国、地域で女子サッカーが普及していくにつれ、この勢力図もより複雑化していくことが予想される状況です。
持久力、瞬発力、視野の広さとさまざまな能力が必要とされるサッカー競技は、どのような環境においてもより高いパフォーマンスを維持できるかが金メダル獲得のカギになります。
若さが発揮されるオリンピックのサッカー、ロサンゼルス2028大会で新な勢力図に刻まれる国と地域に注目です。
日本男子はオリンピックのサッカー初出場となったベルリン1936大会の初戦で優勝候補スウェーデンに勝利した「ベルリンの奇跡」や、メキシコ1968大会での銀メダル、アトランタ1996大会でブラジルを破った「マイアミの奇跡」などの華々しい実績など、古くから多くの国民の注目を浴びてきています。
メキシコ1968大会以来のメダルを望まれて久しいが、最近ではロンドン2012大会のベスト4が最高順位となっている強豪国の一カ国です。
女子サッカーはロンドン2012大会で銀メダルを獲得し、ワールドカップでは優勝の経験をもち、強豪国として毎大会優勝候補に挙げられるが、他の国が力を伸ばしてきています。 今後もメダル圏内にとどまり続けるかどうかは、日本女子サッカーの今後の普及、強化次第になりそうです。
【開催会場】
※東京2020大会関連資料より
ゴルフは自然状況や地形に応じた戦術と攻略法を駆使した己との勝負!

ゴルフは、広大なフィールドでクラブを使い、いかに少ない打数で回れるか競う球技です。 試合は適応性やテクニック、豪快なショット、繊細なタッチ、精強なメンタルが勝敗を分け重圧に打ち勝てるかに注目。 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
ゴルフの主な強豪国と地域:
「男子個人ストロークプレー:アメリカ、スロバキア、チャイニーズタイペイ etc.」
「女子個人ストロークプレー:アメリカ、日本、ニュージーランド etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。
ロサンゼルス2028大会は欧米勢やオセアニア勢、アジア諸国勢との1打の順位争いに手に汗握る。
雄大な自然環境と己に打ち勝つ国と地域はどこだぁ!
【ゴルフ競技の特徴】
ゴルフは、広大なフィールド上でクラブといわれる道具を使い静止したボールを打ち、直径108ミリメートルの小さな穴(カップ)まで、いかに少ない打数で入れられるかを争う競技です。
ゴルフは、体系的なルールを有した最初の近代スポーツのひとつで、1744年、スコットランドのエディンバラで成文化された競技になります。
試合は1ラウンド18ホールで構成され、選手は4日間で4ラウンド72ホールをプレーし合計の打数が少ない順に上位となる競技です。
19世紀の終わりには、最初の女子トーナメントが開催され、今日、世界中で6,000万人以上のゴルファーが、30,000か所を超えるゴルフコースでプレーしています。
なお、オリンピックでは、国際ゴルフ連盟(IGF)が発表した世界ランキングをベースに、男女それぞれ60名が出場する予定です。
【オリンピックにおける歴史】
ゴルフが実施されたオリンピックは、リオデジャネイロ2016大会以前ではパリ1900大会、セントルイス1904大会の2大会のみで、リオデジャネイロ2016大会で112年ぶりに復活し、東京2020大会でも続けて実施され、100年目を迎えるパリ2024大会でも実施されます。
【コースの特徴】
ゴルフは競技場となる各ホール(コース)により異なった地形や距離が特徴です。
各ホールはティーインググラウンドと呼ばれるスタート地点からパッティンググリーンまで、芝が短く刈られた「フェアウェイ」エリアや芝が長く伸びた「タフ」エリア、池やバンカー(砂地のくぼみ)などの障害物エリア、その他に地形のアップダウンや曲がりなど各ホールにより異なった難易度が設けられています。
特に、「パッティンググリーン」エリアは最も神経を使う場所で、エリア表面の芝は最も短く刈られ、ポテトチップスのような、うねりや傾斜になっており各ホールごとに異なった構造です。
ゴルフは天候に左右されやすい競技で、それゆえにゴルフの面白さや醍醐味、奥深いスポーツだと言われています。 特に雨では地表面や芝の状態が変わりやすく、風の強さや方向など二度と同じコンディションでのプレーができない楽しさが味わえる競技です。 世界中の老若男女が面白さから生涯スポーツとして多くの愛好者から親しまれています。
豪快なドライバー、繊細なパッティング、メンタルの強さが勝敗を決する一打を生むスポーツです。
【ルール】
種目
男子個人ストロークプレー
女子個人ストロークプレー
ゴルフは、状況に応じた攻略法とメンタルの勝負が見どころになります。 なお、ゴルフは原則としてシンプルなスポーツです。
実際、最初の公式ルールでは次のように説明されています。 「ゴルフは、ルールに従って、ボールをクラブで打ちながら、ティーグランドからホールまで運ぶ競技である」
選手は、ホールまでの距離、コース面など、状況に応じて異なるクラブを使い分けて競い合うことが可能です。
ゴルフ道具のクラブは最大14本まで持ち歩くことができます。 ボールを打つ道具には遠くまで飛ばせるドライバーなどのウッド類や正確性を重視するアイアン類、ターゲットとなるパッティンググリーンで使うパターなど、それぞれの用途に合わせ選んで使う競技です。
広大な大自然の中で打つドライバーショットの迫力は見応えがあります。
また各クラブであるウッド類やアイアン類は、ボールを打つ打面の角度が異なり、プレーヤーが状況に応じて選択するクラブや攻め方など、1打1打の判断力とテクニックが競技の見どころです。
また、メンタル面の強さが勝敗を大きく左右するスポーツであり、各選手が重要な場面で重圧に打ち勝てるかどうかも注目ポイントになります。
なお、審判員が立ち会わないということもゴルフの大きな特徴です。 これは、ゴルフがフェアプレーを重んじ、「ゴルファーはみな誠実であり、故意に不正をおかす者はいない」という基本的な考え方に基づいています。
また、ゴルフ規則書に規定されている罰則は、ゴルフの規則を知らなかったり、過失によってその処置を誤ったりしたプレーヤーに対して、競技全体の公平さを図る観点から決められているルールです。
【ゴルフの基本的な用語】
ゴルフの各ホールは3打、4打、5打などの規定の打数が設定されています。 この打数と等しい打数でカップにボールを入れることを「パー」といい、1打少ないことを「バーディー」、2打少ないことを「イーグル」、逆に1打多いことを「ボギー」、2打多いことを「ダブルボギー」という表現が良く放送で聴くゴルフ用語です。
18ホールのゴルフコースのパーは72が一般的で、72より1打少ない71で終わると「1アンダー」、2打多い74で終わると「2オーバー」といいます。
オリンピックでのゴルフ競技は、ストロークプレー形式で行われ、1ラウンド18ホールで構成され、選手は4日間で4ラウンド72ホールをプレーして、合計の打数が少ない順に上位に君臨する競技です。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
112年ぶりにゴルフ競技が行われたリオデジャネイロ2016大会では、男子は世界ランキング11位、オリンピック参加者の中では5位の選手が優勝しています。
ゴルフのランキング上位の顔ぶれは、毎年少しずつ変わるが、男子はアメリカが上位者の数で他国を圧倒し、他はスペイン、スウェーデン、イギリス、オーストラリア勢などの選手層が厚い勢力図です。
女子は韓国勢が圧倒的に強く、リオデジャネイロ2016大会では、世界ランキング15位までは1か国につき4人出場できたが、韓国は8位までに4人ランクインしていたことから、世界ランキング9位、10位だった韓国の選手が出場できなかったほどの強豪国になります。
実際、世界ランキング2位だった選手が金メダルを獲得している状況です。 韓国以外はアメリカの層が厚く、アジア勢の若手の活躍が著しく眩しさを増しています。
フランス パリ1900大会から100年の時(ゴルフ競技実施)を超えて開催するパリ2024大会は世界各地から「我こそは」と出場枠を手にして挑んでくるだろう。
男子は強豪国アメリカ勢、女子は韓国勢に他国が食い込めるか注目です。
そんな中、日本勢は世界ランキング上位選手を中心に、勝負強さと度胸を盾に己の打点のインパクトが地響きを立て弾道ボールとなりぶっ飛んでいくことに期待が集まります。
【開催会場】
※東京2020大会関連資料より
ハンドボールは多彩な技や戦術と戦略、己たちのチームワークとの勝負

ハンドボールは7人制で走る、飛ぶ、投げる、スポーツの3大要素を必要とする競技です。 試合は頭脳的かつ華麗な連携プレーやダイナミックさ、フィールド展開の速さ、大迫力のシュートなどに注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
ハンドボールの主な強豪国と地域:
「女子:フランス、ROC、マケドニア etc.」
「男子:フランス、デンマーク、スペイン etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。
ロサンゼルス2028大会では、欧米、アフリカ勢、中東、南米、アジア勢との順位争いに子供たちも“ドッチボール”を始める。
己のジャンピングシュートで新たな勢力図を築き上げられる国と地域はどこだぁ!
【ハンドボールの特徴】
ハンドボールは、走る、飛ぶ、投げるというスポーツの3大要素をすべて必要とするフィールドの格闘です。 1チーム7人ずつで、ボールを手で扱って相手コートのゴールへ投げ入れ、得点を競うのがハンドボールになります。 全身のバネを使って放たれる大迫力のショットは見どころです。
【ハンドボールの歴史】
ハンドボールは、19世紀末にスカンジナビアとドイツで初めてプレーされ、フィールドハンドボールもスポーツとして認知されつつ起源があります。 G.Wallstromは、1910年にスウェーデンに、このスポーツを紹介し、この2つのバージョンは、1966年に屋内ハンドボールがフィールドハンドボールに取って代わるまでプレーされてきたスポーツです。 ハンドボールは、19~20世紀初頭のヨーロッパに起源をもち、世界へと広がったスポーツになります。 1946年創設の国際ハンドボール連盟には2017年時点で200を超える国と地域が加盟しており、アジア、アフリカ、南米などでも普及が進んでいる競技です。 古くはドイツ発祥の11人制が主流であったが、スカンジナビアを中心に広がった7人制が次第に支持を得て現在に至っています。
【オリンピック競技としての歴史】
フィールドハンドボールは、ベルリン1936大会でオリンピックデビューを果たしたが、その後は正式競技から外れ、ヘルシンキ1952大会ではデモンストレーション競技として採用された競技です。
屋内バージョンは、20年後のミュンヘン1972大会から採用され、初めてオリンピック種目として登場した競技です。 ベルリン1936大会以降、ハンドボールは屋内で行われています。
女子初の大会は、その4年後のモントリオール1976大会で初めて採用され、実施された種目です。
韓国がソウル1988大会で2個、バルセロナ1992大会で女子の1個のメダルを獲得したことを除けば、ハンドボールのオリンピックメダルはすべてヨーロッパの国が獲得しています。 ハンドボールは、ヨーロッパ諸国が支配している競技です。
東京2020大会では男女各12チームがメダル争いが繰り広げられ、パリ2024大会でも、再び男女各12チームが出場し対戦が行われる予定になります。
【ルール】
実施種目
ハンドボール大会(女子/男子)
ハンドボールは、7人のプレーヤーのうち1人はゴールキーパーとして自陣ゴールを守り、6人がドリブルとパスでボールをつないで相手ゴールを攻略するという点はサッカーと共通性がある競技です。
プレーヤーはボールを足で扱ってはならない、ドリブルなしで最大3歩進むことができ、最大3秒間ボールを保持することができます。 ハンドボールは、1人の選手がボールを扱える時間には制限があり、交代は無制限、といったルールはバスケットボールに近い要素がある競技です。
ハンドボールならではの要素は、ゴールから6メートルのゾーンにはゴールキーパーしか入ることができず、シュートはこのゾーンの外側から、またはゾーンの外側から内側に向かってジャンプしている状態で打たなければならないルールや、体の正面からの接触プレーには反則がとられないため、格闘技に近いボディコンタクトが見られることがあります。
選手にとって非常にフィジカルで要求の厳しいスポーツです。
消極的なプレーは違法であるため、攻撃的な戦略も奨励されている競技になります。 したがって、持久力と強さはプレーヤーにとって重要な資質です。
ハンドボールには戦術、チームワーク、柔軟性も含まれており、すべてのプレーヤーが攻撃と防御を交互に行うスポーツになります。
これら、複数の競技に共通するチームスポーツの楽しさと独自のダイナミックさ、双方合わさったものがハンドボール競技の魅力です。 特に6メートル以上離れたゴールにボールを投げ込むために必要とされる力と勢いは並大抵ではなく、選手がジャンプをしながら全身バネを使ってシュートを放つ場面は迫力満点で見逃せません。 ダイナミックさと華麗な連携プレー、展開の速さに注目しましょう。
時にはゴールキーパーが自陣から相手ゴールをめがけ超ロングパスやシュートを放ち、プレー開始から数秒で得点が決まってしまうこともある試合展開です。 そんなシーンもあるので、一瞬たりとも試合から目が離すことができなくなるだろう。 他にも多彩な個人技や頭脳的な連携など、ぜひ試合を見てその魅力を体感してもらいたいです。
現代版は、コートの広さ40メートル×20メートル、フットサルコートと同じ、前後半各30分を戦い、決着がつかなければ延長前後半各5分の延長戦が行われます。 前後半各30分の2試合終了時に最も多くのゴールを決めたチームが勝利です。 オリンピックでは、女子と男子の両大会に12チームが出場します。
ここ最近のハンドボールは、よりスピード展開を重視しており、両チームとも攻撃回数が60回、70回を数えるため、得点は20点以上になる試合がほとんどです。 オリンピックでは12チームによるグループリーグから決勝トーナメント戦を経てメダルが争われます。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
ヨーロッパ勢がトップに君臨するハンドボール界、新風を巻き起こすチームの出現に注目です。 メダル争いは公式競技採用当時からヨーロッパによって繰り広げられており、ヨーロッパ以外のチームによるメダル獲得は男子ではソウル1988大会の韓国の銀メダルのみになります。 女子ではこれまで6回メダルを獲得している韓国が強豪国の一角を成している状況です。
なお、リオデジャネイロ2016大会では男子はデンマークが金、フランスが銀、ドイツが銅メダルで、女子はロシアが金、フランスが銀、ノルウェーが銅メダルを獲得しています。 2017年の男子世界選手権ではフランス、ノルウェー、スロベニア、クロアチアがベスト4です。
男子世界ランキングでは常にドイツ、デンマーク、スウェーデン、ロシア、フランスなどヨーロッパ勢が10位以内を占めています。 中堅どころになるとエジプト、チュニジア、といったアフリカ勢や中東、韓国が名を連ね、日本も中堅といえる位置に近づきつつある激戦地帯です。 また、南米では、アルゼンチンやブラジルが成長株だろう。
女子にもほぼ同様の傾向がみられるが、韓国がメダル常連であること以外にアンゴラが国際大会などで存在感を見せています。 女子の勢力図は男子に比べ若干、地域的に広がりが見られる状況です。 これらの国がオリンピックでも結果を出していくことで、世界のハンドボール人気は、さらに広がっていくだろう。
日本は2017年に世界的な名将の監督を迎え、急ピッチで東京2020大会に向けた強化を進め、女子は海外に代表主力選手を移籍させ、国内外同時に普及強化を進めています。 ロサンゼルス2028大会では男女ともに、どのような試合展開を見せてくれるのが楽しみです。
ハンドボールの開催地
※東京2020大会関連資料より
ホッケーは攻守プレー、己のスティックワークとチームワークとの勝負

ホッケーは11人制でボールを相手チームのゴールに入れて得点を争う競技です。 試合は選手同士の鬩ぎ合いや駆引き、スピード、持久力、精神力、優れた協調性、技術力、華麗な剛速球シュートに注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
ホッケーの主な強豪国と地域:
「女子:オランダ、アルゼンチン、イギリス etc.」
「男子:ベルギー、オーストラリア、インド etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では、欧米、オセアニア、中東、アフリカ、アジア勢との順位争いに熱気が立ち上がる。
己の妙技で、巧妙にボールを操り、新たな名誉を刻む国と地域はどこだぁ!
【ホッケー競技の特徴】
ホッケーは、縦91.4メートル、横55メートルのフィールド上で、ゴールキーパー1名を含む1チーム11名の選手からなる2チームが対戦し、 直径7.5センチメートルのボールを相手チームが守るゴールへ入れて得点を競う球技です。
各15分の4クォーター制(計60分)で実施され、より多くの得点したチームが勝者となります。 同点の場合は相手ゴールキーパーと攻撃選手の1対1の8秒間の攻防を行うシュートアウト戦により勝者を決定する競技です。 ゴールキーパー以外は、手足でボールに触れることができず、スティックの片面のみでボールをコントロールします。 冴えわたるスティックワークで高速のシュートがゴールをつらぬく試合展開です。 スティックはカーボン製で長さは約90センチメートル、ボールは野球の軟球とほぼ同じ大きさ、重さのプラスチック製を使用します。
【ホッケーの歴史】
ホッケーの名前は、フランス語のhocquet(ホッケースティックの湾曲した形にちなんで羊飼いの曲がり角を意味する) に由来し、そのルーツは古代にまでさかのぼる起源を持つスポーツです。
歴史によると、このスポーツの初期の形態は4,000年前にエジプトで行われ、エチオピア(紀元前1,000年) とイラン(紀元前2,000年)でバリエーションがプレーされています。 さまざまな博物館が、クリストファー・コロンブスが新世界に到着する数世紀前に、 ローマ人やギリシャ人、アステカ人によってゲームの形式がプレイされていたと報告されているスポーツです。
近代ホッケーは19世紀半ばにイギリスで登場し、イートン校などの私立学校の成長に大きく起因しています。 最初のホッケー連盟は1876年に英国で設立され、ゲームの最初のルールセットを確立させます。
ジェンダーバランスはホッケーのコアバリューです。 世界の3,000万人のプレーヤーのうち、51%が女性で、49%が男性になります。
【オリンピックとしての歴史】
ホッケーはオリンピックではロンドン1908大会に初登場し、正式種目となり、アムステルダム1928大会で最後の種目となった競技です。 女子はモスクワ1980大会で採用され、導入されます。
現代のアングロサクソンのルーツを考えると、現代のホッケーは、インド、パキスタン、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、そしてもちろんイギリスなど、イギリス連邦の現在および元メンバーによって支配されてきたスポーツです。 オリンピックの100年の歴史の中で、最も圧倒的な強さを誇ってきたのはインドになります。 1928年から1956年の間に8つの金メダルと6連覇を達成したインドの男子チームは、オリンピックで最も圧倒的な強さを発揮し、この期間を通じて、チームは30勝、197得点、わずか8失点という素晴らしい成績を収めた強豪国です。 しかし、アルゼンチン、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、フランスなど、他の国も国際ランキングのトップにランクインし、このスポーツを真にグローバルなものにしています。
前回の東京オリンピックでは、男子の部でベルギー、女子の部でオランダが金メダルを獲得した競技です。
【ルール】
実施種目
ホッケー(女子/男子)
ホッケーは、スピード、技術力、楽しさはホッケーの主な特徴であり、持久力と優れた協調性を必要とするエキサイティングでダイナミックなスポーツになります。
ピッチ上には、フォワード、ミッドフィールダー、ディフェンダー、ゴールキーパーを含む各チームに11人のプレーヤーで構成され、各プレーヤーは、いつでも何度でも交換することが可能です。 チームはゴールキーパーなしでプレーすることを選択できます。(原則として一時的に) 最も多くのゴールを決めたチームが勝利し、ノックアウトマッチでは、シュートアウトセッションが両チームを分ける形式です。
ホッケーは、ステックワークの妙技、一瞬で入れ替わる攻守、スピーディーでスリリングなゲーム展開を楽しもう。
ホッケーの最大の特徴は、サークル(シューティングサークル)と呼ばれるゴール前の半径のシュートゾーンの中から打ったシュートのみが得点とみなされることにあります。 したがって、サークル内のせめぎ合いや駆け引きが大きな見どころです。 攻撃側は、ドリブルやパスを使って相手ディフェンスの網をいかにくぐり抜けてサークル内にボールを持ち込み、シュートを打って得点につなげるかに注目が集まります。
守備側は、それをどう防ぎ、失点を最小限に食い止めるかが勝敗のカギを握る試合展開です。 各プレーヤーのスティックワークの妙技、また守備から一瞬にして攻撃に入れ替わる展開とチームプレーが、ホッケー最大の魅力といえるでしょう。
そして、サッカーのようなオフサイドがないことも特徴の一つです。 1996年のルール改正によってオフサイドが廃止されたことで、得点の入る確率が高まり、よりスピーディーでスリリングなゲーム展開が楽しめるようになります。 ホッケーでは選手の交代は何度でも自由に行えるため、交代のタイミングが試合の行方を左右する展開です。 試合の流れや、どの選手の運動量が落ちているかなどを読みながら観戦すると、試合への理解が一層深まり、楽しさも増すだろう。
なお、モントリオール1976大会から、オリンピックの試合は人工芝のフィールドで行われるようになります。 転倒した際、摩擦によるやけどを防ぐため、人工芝に散水してプレーをする仕様です。 人工芝フィールドでの試合実施によって、球速が速くなり、プレーヤーのスピードや体力、技術などが、より高いレベルで要求されるようになります。
エキサイティングなスポーツへと劇的な進化を遂げたホッケーは、観戦する側も熱狂に包まれる試合展開です。 なお、シュート時のボールのスピードは、世界のトッププレーヤーともなると時速200キロメートル以上に達することもあります。 高速鉄道並みの速さなので、見逃さないよう気をつけて観戦することが重要です。
アスリートはフック状の棒を使い、それを使って硬いボールを打ち込み、コントロールして打ちます。 スティックの平らな面のみ使用でき、凸面の使用は許可されていません。 ゴールキーパーを除き、プレーヤーは手や足でボールに触れることはできないルールです。
フォルトを犯した場合、レフリーは当該プレーヤーにグリーンカード(2分間の出場停止)、イエローカード(5分間の出場停止)、レッドカード(退場)を科すことができます。 ホッケー場の長さは91.40メートル、幅は55メートルで、両端にあるゴールは、D字型の射撃エリアに囲まれている試合フィールドです。 ゴールは、相手のシュートエリア内からのみ得点できます。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
安定した強さを誇るオランダ、ドイツ、オーストラリア 目立つアルゼンチンに注目です。 近代ホッケーは19世紀半ば、イギリスのクリケット選手たちが、試合のできない冬場に始めたのが起源とされています。 したがって発祥の地であるイギリスをはじめ、主にインド、パキスタン、アフリカ諸国、オーストラリアなどで広まり盛んなスポーツです。 またヨーロッパ各国でも人気があり、オランダやドイツも強豪国として知られています。
初めてオリンピックに採用されたロンドン1908大会では、イングランド、アイルランド、スコットランド、ウェールズ、ドイツ、フランスの6つの国、地域が参加し、イングランドが初代金メダルを獲得した競技です。 過去のオリンピックで最も多くの金メダルを獲得したのはインドで8個、次いで5個のオランダ、4個のオーストラリア、イギリス、ドイツと続いています。 近年ではオランダやドイツの活躍が目立っており、オランダ男子チームはアトランタ1996大会とシドニー2000大会、ドイツ男子チームは北京2008大会とロンドン2012大会を、それぞれ連覇している強豪国です。
リオデジャネイロ2016大会では、アルゼンチン男子チームが、オリンピック初のメダルにして金メダルを獲得するという、新しい風が吹いています。 アルゼンチンは女子も、ロンドン2012大会で銀メダルを獲得するなど、台頭著しいです。 FIH(国際ホッケー連盟)の過去のランキングで、男子のトップ3はオーストラリア、アルゼンチン、ベルギーで、女子のトップ3はオランダ、イングランド、アルゼンチンとなっています。 アジアの国々は苦戦を強いられているのが実情です。
日本は豊富な運動量と攻守にわたる組織力を武器にロサンゼルス2028大会に向けて強化に励んでいます。
ホッケー開催地
※東京2020大会関連資料より
ラグビーは己の身体能力と強靭な戦術を駆使したダイナミックな挑戦!

ラグビーは広大なフィールドで繰り広げられる7人制のボール競技です。 試合はスピーディーかつダイナミックな展開で、強靭的なフィジカルが要求され、一瞬で攻守が入れ替わる攻防戦が魅力。 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
ラグビーの主な強豪国と地域:
「 男子:フィジー、ニュージーランド、アルゼンチン etc.」
「 女子:ニュージーランド、フランス、フィジー etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。
ロサンゼルス2028大会は欧米やアフリカ、アジア諸国勢との激動的な順位争いにホイッスルが鳴り響く。
広いフィールドで素早くトライできる国と地域はどこだぁ!
【ラグビー(セブンズ)の特徴】
ラグビーの起源は、中世ヨーロッパまでさかのぼり、1823年にイギリスのパブリックスクールであるラグビー校で開催されていたフットボールがきっかけで「ラグビースクールフットボール」が人気となった競技です。 現在のルールは、1845年から1848年の間に、イギリスのラグビーという町にある学校とケンブリッジ大学出身の生徒によって考案されます。
1871年には、ラグビーフットボールユニオン「RFU:現在のイングランドラグビー協会(国内連盟)」が設立され、初の国際試合がイングランドとスコットランドで行われている競技です。 1886年には「IRFB:国際ラグビーフットボール評議会(国際ラグビー委員会)」(現在のワールドラグビー)が発足し、イングランドでは沢山のラグビークラブが創られ、ラグビーは世界に普及します。
ラグビーは15人制(ラグビーユニオン)、13人制(ラグビーリーグ)、7人制(ラグビーセブンズ)など、様々なラグビーが世界各地でプレーされ、各種大会が開催されている競技です。
【オリンピックにおける歴史】
オリンピックにおけるラグビーの歴史は、いくつかの時代に分けられます。 最初、ラグビーは15人制種目としてパリ1900大会で実施され、ロンドン1908大会、アントワープ1920大会、パリ1924大会で実施され、それぞれフランス、オーストララシア(オーストラリアとニュージーランドの選手の組み合わせ)、そしてアメリカ合衆国が2度優勝している競技です。
しかし、その後オリンピックではラグビーがしばらく実施されず、長いブランク期間を経て2009年の国際オリンピック委員会(IOC)の決定により、リオデジャネイロ2016大会より7人制(セブンズ形式)ラグビーとしてオリンピックの舞台に大きく復活を果たします。 女子ラグビーもリオデジャネイロ2016大会で初めて開催され、その後、東京2020大会でも実施された競技です。
東京2020大会では女子種目でニュージーランドが金メダル、男子種目でフィジーが2大会連続の金メダルを獲得しています。
一瞬にして相手を抜き去るスピード、変幻自在なパス、強力なフィジカル、7人が広大なフィールドで目まぐるしい攻防を繰り広げる戦いから目が離せない。
【ルール】
種目:男子、女子
ラグビーは、長い年月の中で多くの様式を生み出してきた競技です。 ラグビーリーグ、ビーチラグビー、タグラグビーなどが行われています。
主なゲームは大きく分けて2つの形式で構成され、15人制のラグビーユニオンと7人制のラグビーセブンです。 ラグビーのルールはタックルやバックワードパス、スクラムに関して基本ルールを共有し、ピッチ上のプレーヤーの数によって異なります。
7人制のラグビーセブンズは、広いフィールドを使ってスピード感のあるダイナミックな試合が14分間(7分ハーフ)にわたり展開され、とてもペースが速くて激しい戦いです。 選手は、15人制ラグビーよりもさらに多くのスプリントやスピードが求められ、また多くのトライを決めるためダイナミックで見応えのあるプレーが特徴と言えます。
【ラグビーの得点】
得点は15人制のラグビーユニオンと同じ方法でトライで5ポイント、コンバージョンで2ポイント、ドロップゴールまたはペナルティで3ポイントを獲得できるルールです。
得点方法は4種類あり、相手のゴール領域内でボールを接地させる(グランディング)「トライ」が5点、トライ後ゴールポスト間にボールを蹴り入れる「コンバージョンゴール」が2点、試合の流れの中でゴールポスト間にボールをワンバウンドさせて蹴り入れる「ドロップゴール」は3点、相手反則時に与えられるペナルティキックでのゴールが3点獲得できます。
試合時間が短いのでトライを先行しているチームが有利になり、トライ後のコンバージョンによる2点の加点は勝敗や戦術に大きく影響する流れです。
【チーム構成】
チームはフォワード3人、バックス4人で構成され、1試合につき1チーム5回まで交代することができます。 ポジションとしての呼び名はあるものの、15人制(ラグビーユニオン)ほどポジションによっての役割が決まっていなく、一人一人の瞬時の判断で攻守が入れ替わり、どこからでもトライを狙ってくるので非常にエキサイティングな試合展開です。 時には100メートル近く走りトライを決める、スピード自慢の選手が多いのも7人制の特徴になります。 7人制(ラグビーセブン)はとてもコンパクトなスクラムとなるため決着がつきやすく、これもスピーディな試合展開の要因の一つです。
相手を抜き去るステップ、駆け上がるスピード、パス、キックなど、後ろにしかパスが出来ないこと以外は自由度が高い競技で、様々な戦術を駆使して相手陣のゴールラインにボールを運ぶことで得点になります。
フィールドは、7人制でも15人制と同じ幅70メートル、長さ100メートル、広いフィールドを少ない人数でプレーするため、一人一人のスピードやタックルの強さが一層求められる競技です。
また長いパスを多用してボールを大きく動かすためダイナミックな試合展開となるのも魅力で、試合時間は14分間と短くハーフタイム2分間を挟んで全員が一瞬たりとも気を抜けないスピーディかつ強烈なタックルが繰り広げるため、観客側も決して目が離せません。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
ラグビーと言えばなんといっても強豪国ニュージーランド、15人制のラグビーワールドカップ、ザ・ラグビーチャンピオンシップでは圧倒的な勝率を誇っています。
一方で、7人制においての王国はフィジーであり、HSBCワールドセブンシリーズや過去の各種大会での優勝回数は突出しており、そのプレースタイルは世界中のセブンズファンを魅了している強豪国です。
リオデジャネイロ2016大会では、男子フィジー、イギリス、南アフリカが、女子はオーストラリア、ニュージーランド、カナダがそれぞれ金、銀、銅メダルを獲得しており、男子のニュージーランドはメダル獲得成らず、5位に終わています。
東京2020大会では、男子フィジー、ニュージーランド、アルゼンチン、女子はニュージーランド、フランス、フィジーがそれぞれ金、銀、銅メダルを獲得しており、ロサンゼルス2028大会での新たな勢力図が楽しみになるだろう。
だが、7人制ラグビーはパリ2024大会で3回目となる新しい競技です。
ラグビー王国ニュージーランドがリベンジするのか、セブンズでは圧倒的な強さを持つフィジーが連続の金メダルに輝くのか、あるいは他の国が台頭してくるのか、多くのチームにメダルへの可能性が開けていると言えます。
ラグビー王国ニュージーランドの雪辱なるか、それともフィジー、オリンピックのラグビーは波乱の可能性大です。
日本は、リオデジャネイロ2016大会でラグビー王国ニュージーランドを下した最初のチームは、なんと我らが日本で、男子チームは近年急激に実力を伸ばしており、ランキング上位国とも接戦を演じている強豪国です。
過去のラグビーワールドカップ2015イングランド大会では、強豪優勝候補の南アフリカに勝利し、過去1勝しかしていなかったワールドカップで3勝を挙げた実績を持ちます。
リオデジャネイロ2016大会ではニュージーランド以外にも格上とされる相手に勝利を重ね、メダルまであと一歩と迫る4位に入賞し、世界に大きなインパクトを残したチームです。
「サクラセブンズ」の愛称で親しまれている女子7人制日本代表は、強化を加速しており、サクラ満開となるのが楽しみになるチームになります。
【開催会場】
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
バドミントンは球技最速を誇り、己のショットで戦略の裏を狙う勝負!

バドミントンはラケットを使ってネット越しにシャトルを打ち合い、得点を争う競技です。 試合はラリーが続く中での選手同士の駆引き、多彩なショット、ストロークの種類、ゲーム展開の変化に注目! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
バトミントンの主な強豪国と地域:
「女子シングルス:中国、チャイニーズタイペイ、インド etc.」
「女子ダブルス:インドネシア、中国、韓国 etc.」
「男子シングルス:デンマーク、中国、インドネシア etc.」
「男子ダブルス:チャイニーズタイペイ、中国、マラウイ etc.」
「混合ダブルス:中国、日本 etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。
ロサンゼルス2028大会では、欧米、アフリカ、アジア勢との順位争いに反射神経が研ぎ澄まされる。
己のショットで新たな勢力図を築き上げられる国と地域はどこだぁ!
【バトミントン競技の特徴】
バトミントンのショット初速は球技最速で、多彩なショットで相手の裏を鋭く狙い撃つ競技です。 バトミントンは、1人対1人、または2人対2人で、ラケットを使ってネット越しにシャトルを打ち合い、得点を競うゲームになります。
バトミントンが他のネットスポーツと決定的に違うのは、丸いボールではなくシャトルというまったく形の違うものを使うからになります。
シャトルとは、半球状のコルクに水鳥などの羽根を接着剤などで固定したものです。 ラケットで打った瞬間の初速は、あらゆる球技の中で最も速いが、空気抵抗を大きく受けるため、初速と相手コートに届くときの終速は著しく異なります。 そのシャトルの特性により、バトミントンはストロークの種類が多く、ラリーがスピードや変化に富んでいることが特徴です。
【バトミントン競技の歴史】
バトミントンはラケットスポーツであり、その正確な起源は今でも謎に包まれています。 これは、ヨーロッパ、特に裕福な階級の間で人気のある娯楽であったバトルドールとシャトルコックの古いゲームから進化した競技です。 しかし、バトルドールとシャトルコックがいつバトミントンの競技スポーツに変身したかは正確にはわかっていません。
1860年初頭にグロスターシャーのボーフォート公爵の邸宅で初めてバトミントンがプレーされたため、バトミントンハウスと呼ばれた彼の邸宅にちなんで名付けられたという説もあります。
このゲームはインドに伝わり、軍の収容所で人気のあるスポーツになり、徐々にイギリスの植民地に広がり、その後ヨーロッパや東アジアに広がりをみせた競技です。 今日のバトミントンは、あらゆる年齢や能力の人々に広くアピールする世界的なスポーツになっています。
【オリンピックとしての歴史】
バトミントンは、1972年のミュンヘンオリンピックでデモンストレーション競技としてデビューした競技です。 1988年にはソウルでエキシビションスポーツが開催されます。 1992年のバルセロナ大会では、男女シングルス、男女ダブルスの4つのメダル種目で正式にオリンピック種目に加わた競技です。 混合ダブルスは1996年のアトランタオリンピックで追加された種目になります。 アジア諸国はメダル獲得国を独占しており、オリンピック史上のバトミントンメダル121個のうち106個をアジア大陸の選手が占めるスポーツです。
【ルール】
実施種目
シングルス(女子/男子)
ダブルス(女子/男子)
パリ2024には172名の選手が出場します。 男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの5種目が10日間にわたって行われ、金、銀、銅の5つのメダルが授与される競技です。
バトミントンの試合はすべて2ゲーム先取の3ゲームマッチで、各ゲーム21点を先取したほうが勝ち、20点オールになったときは2点差つくまで続きます。 ただし29点オールになった場合には30点目を獲得したほうがそのゲームの勝者となる形式です。
シングルスではそれぞれ3~4人の16のグループに分かれて総当たりのリーグ戦が行われ、各グループで1位になった選手が決勝トーナメントに進みます。
ダブルスでは4人ずつの4つのグループに分かれリーグ戦が行われ、それぞれの上位2人が決勝トーナメントに進む形式です。
バトミントンの試合で強打されるスマッシュは、手元に届いた時にかなりのスピードが残っているが、ヘアピンとよばれるネットプレーやドロップショットでは一瞬にして速度が落ちます。 ラケットの握り方や力の入れ方、角度のつけ方などにより、緩急の差に加え、さまざまな変化が生まれ、多彩なショットの打ち分けにつながるスポーツです。
一流選手は、ここに打ったらここに返ってくる、と2手、3手先を読んでプレーします。 相手の動きを予測しあい、逆をつくプレーをしあう駆け引きもバトミントン観戦の面白さのひとつです。 シングルスでは特に、相手を動かしてオープンスペースを作り、そこに狙うと得点につながりやすくなります。 いかにオープンスペースをつくるかが見ものです。
ダブルスではシングルス以上にスピーディーな展開が見もので、また一人一人の実力に加え、二人のコンビネーションが大きく影響してきます。 ローテーションといわれるが、攻撃、守備、再び攻撃と二人の陣形は状況に応じてめまぐるしく変化していく展開です。 どんな球がきた時にどんなフォーメーションになっているのか、それがどう変化していくかを見るだけでも面白いだろう。
混合ダブルスでは、女子が集中攻撃を受けるのがパターンです。 女子が男子の強打をどれだけレシーブできるか、男子はパートナーの女子をどれだけフォローできるかが勝利のカギを握ります。 バトミントンのショットは多彩、スピードと変化を楽しみたいものです。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
前大会のメダリストを各国の多くの選手たちが追うだろう。 古くからバトミントンの選手層が厚いのは中国です。 他には韓国、バトミントンを国技とするマレーシア、インドネシア、ヨーロッパではデンマークなどが圧倒的に強く、しかし近年は、その勢力図が大きく変わり、日本台頭、さらに台湾、香港、タイ、インドなどにランキング上位の選手が多い傾向があります。
男子ダブルスは、中国、デンマーク、インドネシア、日本などのペアがランキング上位に名を連ねており、さながら戦国時代です。 世界のランキングの構成が大きく変化しています。 女子ダブルスでは日本、デンマークなど、中国、韓国、日本のペアが追っている状況です。 混合ダブルスでは、中国、インドネシア勢の層が厚く、パリ2024大会での新たな勢力図に注目が集まります。
日本は近年バトミントンの選手強化に力を入れており、日本を抜きにバトミントン強豪国を誇ることはできません。 圧倒的な強さで世界を席巻しています。 東京2020大会でも活躍を魅せた日本、ロサンゼルス2028大会ではどのような展開が繰り広げられるか期待したいです。
バトミントン開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
卓球はスピーディーな戦型の妙技、緻密な戦術と戦略、己の執念の勝負

卓球は男女シングルスや団体、混合ダブルスの5種目で実施される球技です。 試合は3つの戦型を使い分けた、百戦錬磨の技が光るダイナミックなラリーの応酬、一瞬の判断で繰り出される攻撃の攻防戦に注目。 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
卓球の主な強豪国と地域:
「男子シングルス:中国、ドイツ etc.」
「男子チーム:中国、ドイツ、日本 etc.」
「女子シングルス:中国、日本 etc.」
「女子チーム:中国、日本、ホンコン チャイナ etc.」
「混合ダブルス:日本、中国、チャイニーズタイペイ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。
ロサンゼルス2028大会は中国を始め中欧、アジア諸国勢との群雄割拠の順位争いに火花を散らす。
一瞬のまばたき、息もつかぬ卓上のラインぎりぎりのコースを狙う死闘を制する国と地域はどこだぁ!
【卓球競技の特徴】
卓球の起源は19世紀終わりのイギリスで、当時上流階級の間ではテニスが流行していたが、雨天時に食堂のテーブルをコートに見立て、テニスの真似ごとや夕食後の家族の間での娯楽としてプレーされています。
卓球はローンテニスに由来しているとも言われていますが、プレー様式をそのまま取り「テーブルテニス」もしくは卓上にボールが落ちる音から「ピンポン」という呼び名がついた競技です。
当時の用具は本をネットとしてテーブルに置き、ラケットに葉巻入れの蓋とボールにはシャンパンのコルクを丸めたものという実に上級階級らしいものを使用しています。 その後、卓球専用の道具が考案され進化した競技です。
現在は木製の版に特殊ゴム(ラバー)が貼られたラケット、プラスチック製の球が使われています。
【オリンピック競技としての歴史】
国際卓球連盟は1926年設立され、ベルリンとロンドンで競技会が開催され、同じ年にロンドンで最初の世界選手権が開催されます。 2017年時点で約226という国際スポーツ統括組織としては有数の加盟国数を誇っている競技です。
卓球はソウル1988大会で初めて男子 女子ともに正式競技として登場し、当初は男女それぞれシングルス、ダブルスの4種目であったが、北京2008大会より男女シングルス、ダブルスが団体戦に変わり男女団体の4種目が実施されます。 東京2020大会では混合ダブルスに拡大され、種目数は計5種目となり、男女とも同数の参加が可能です。
アジア、特に中国で絶大な人気を誇る卓球は、世界中で4,000万人以上がプレーし、世界で最も多くの参加者を抱えるスポーツに成長しています。
【ルール】
種目:
シングルス(女子、男子)
団体(女子、男子)
混合ダブルス(混合)
卓球は非常に軽量なボールと、両側にゴムまたはカーボンファイバーでコーティングされた木製の版(ブレード)で構成される洗練されたラケットを使用し、卓上の中央のネットによって2つに分割されたテーブルでプレーが行われる競技です。
シングルスの試合形式は1ゲーム11ポイントの7ゲームマッチ(2つのクリアポイントの差)で、4ゲーム先取した選手が優勝します。 団体戦はシングルス4試合とダブルス1試合で構成され、それぞれ5試合で3試合を先取したチームが勝者となる戦いです。 各チームは3人のプレーヤーで構成され、チームが3つの個別のゲームに勝ったときに試合が終了します。 混合ダブルスの試合ではプレーヤーは交代でボールを打ち合う形式です。
トップレベルの競技者同士の戦いは眼にもとまらぬ火花のような攻防を繰り広げる展開になります。
【卓球の戦術】
卓球の試合は選手が採用する「戦型」によって、全く違う様相を魅せる展開です。
「ドライブ主戦型」とは
現在、世界のトップ選手の主戦型は卓球台から少し距離をとったポジションから前後左右のフットワークを使い、腕を大きく使ってボールに強いドライブをかけ、常に攻撃的な戦い方です。 この戦型は体の大きな選手が得意とするスタイルになります。
「前陣速攻型」とは
卓球台に身を寄せたポジショニングから、相手の打球の種類やコースを素早く把握して速いタイミングで球を打ち返し、相手の反応を遅らせてポイントをとる戦い方です。 この戦型は小柄な選手が強みを発揮しやすいスタイルになります。
「カット主戦型」とは
卓球台から距離をとり、相手の強打に対して強い下回転をかけたボール(カットボール)を返球し、回転の変化でミスを誘い、そしてチャンスと見るや一気に前に出て強烈な球を放ち、ポイントを奪う戦い方です。 現在、カット主戦型をとる選手の数は減っているが、緩急に富んだこの戦い方は他の戦型にないドラマティックさがあり、ファンが多いスタイルになります。
各国の選手たちが、どの戦型を採用するか、異なる戦型や同じ戦型同士の戦いなど、“戦型”という視点で観戦してみると各国の選手ごとの特徴がよりはっきり見えて面白いです。
サーブ(サービス)に注目
相手を惑わす下回転のサーブ、ワンバウンドしてからの勢いがある上回転のサーブ、横に曲がる横回転のサーブなど、様々なサーブがあります。
レシーブの種類に注目
下回転のカット(ツッツキ)に加え、最近多くの選手が使うのは、バックハンドから手首をグルッと回して横回転させるチキータです。 球が曲がっていく軌道がバナナのようであるとされ、この名が付いたレシーブ方法になります。
各国の出場選手たちの細かなテクニックに注目しよう。 ほんの一瞬の間に選手たちが繰り出す、様々なテクニックを知ると、新鮮な驚きが味わえる競技です。 トップアスリートが打つボールの速度は時速100キロ以上にもなり、幅152.5センチメートル、長さ274センチメートルという狭い台の上で繰り広げられるスピード感に観る者は引き込まれます。 これだけの速度をもって、ラインぎりぎりのコースを狙ってやりとりされる大胆な攻撃の応酬は、競技スペースの狭さとは裏腹にダイナミックです。
卓球は息もつかせぬ卓上の死闘!1ミリのコースの違いと一瞬の判断が勝負を決めます。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
20世紀半ばまで、卓球はハンガリー、チェコ、オーストリア、ドイツなどの中央ヨーロッパ諸国に席巻されてきた競技です。 しかし、ソウル1988大会の正式競技として採用されて以来、主に中国の選手が圧倒し始め、東京2020大会までに授与された全115個のメダルのうち60個(32個の金メダルを含む)を獲得しています。
直近の大会をみるとドイツが連続でメダルを獲得しヨーロッパでは存在感をみせているが、中国の厚い壁を突破することは困難です。 最近、特に力をつけてきたのは日本で中国を脅かす存在となりつつあります。
卓球の歴史は変わるのか!絶対王者中国を追う各国の今後の成長に注目です。 郡雄割拠の時代来るか?ロサンゼルス2028大会では中国や日本、ドイツ、アジア勢の強豪入り乱れるメダル争いに注目が集まります。
日本は女子団体のロンドン2012大会銀メダル、リオデジャネイロ2016大会銅メダル、東京2020大会銀メダル、シングルス銅メダル、男子団体のリオデジャネイロ2016大会銀メダル、シングルス銅メダル、東京2020大会銅メダル、混合ダブルス金メダルとオリンピックにおける卓球のメダルラッシュは記憶に新しいです。
近年になって突如力をつけています。
敏捷さ、あきらめない精神力など、日本選手の多くに共通する資質は卓球競技にマッチしており、そう遠くない将来、絶対王者である中国からトップの座を奪うポテンシャルは現時点で他のどの国よりも高いです。
男女ともにロサンゼルス2028大会では金メダル、そんなフレーズも、現在の日本チームの勢いを見れば決して夢ではなく、大いに期待が集まります。
【開催会場】
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
テニスは己のメンタルとの闘い、全力で駆引きし意地と根性で挑む勝負
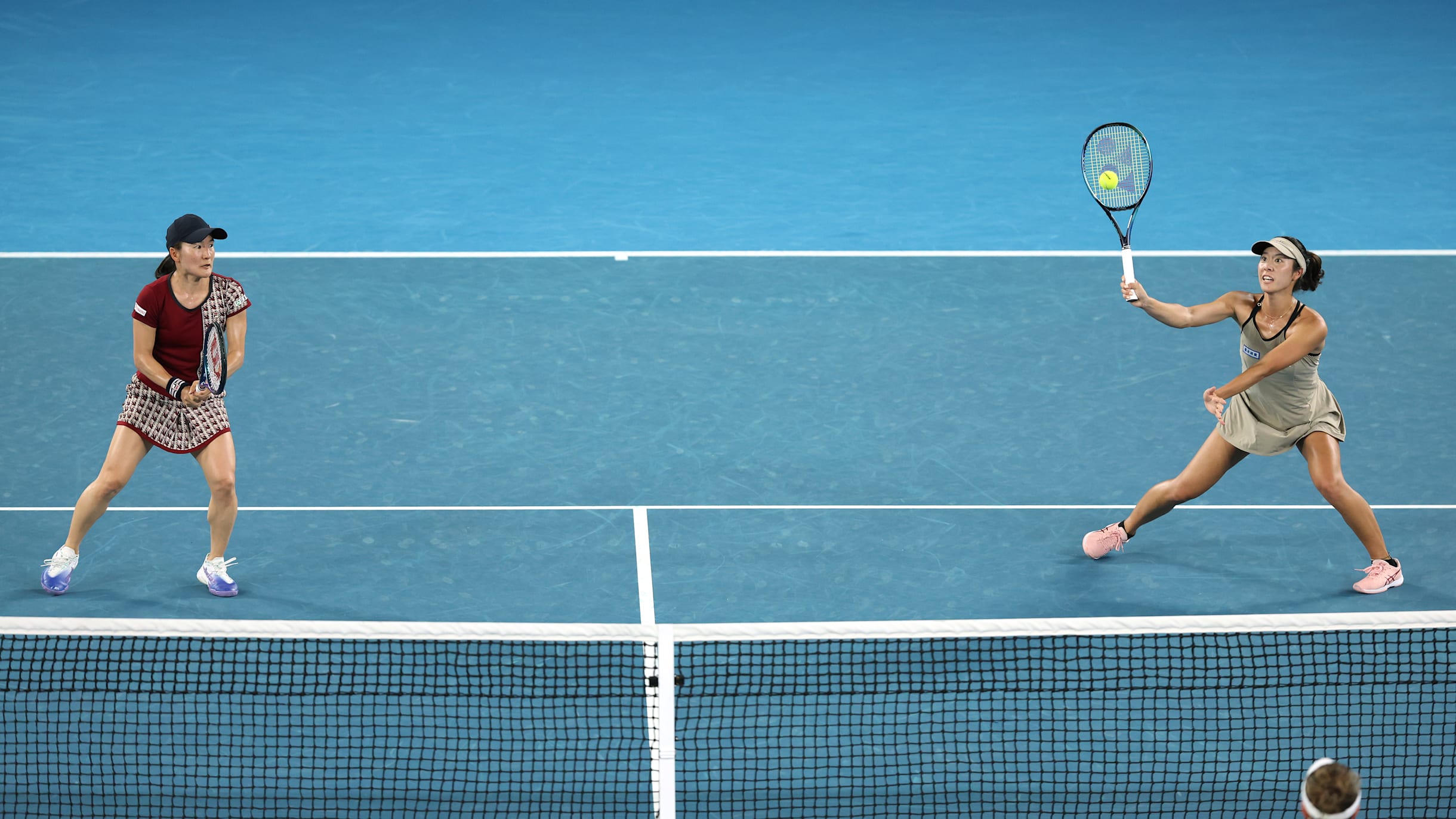
テニスはラケットを使いネット越しにボールを打ち合い、得点を争う競技です。 試合はラリーが続く中で、どちらが先に攻撃を仕掛けるか、戦術や熟練の技、チームワーク、選手の個性やコートとの相性に注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
テニスの主な強豪国と地域:
「女子シングル:スイス、チェコ共和国、ウクライナ etc.」
「女子ダブルス:チェコ共和国、スイス、ブラジル etc.」
「男子シングルス:ドイツ、ROC、スペイン etc.」
「男子ダブルス:クロアチア、ニュージーランド etc.」
「混合ダブルス:ROC、オーストラリア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。
ロサンゼルス2028大会では、欧米、南米、オセアニア勢との順位争いに首筋が鍛えられる。
己の意地と根性、情熱を燃やし尽くし、メダル獲得できる国と地域はどこだぁ!
【テニス競技の特徴】
テニスは1人対1人、または2人対2人で、ラケットを使ってネット越しにボールを打ち合い、得点を競うスポーツです。 時速200キロ以上のサーブから、はじめる駆け引き、メンタルコントロールもカギを握ります。
【テニス競技の歴史】
テニスの前身は、11世紀にフランスで生まれた「ジュ・ド・ポーム」です。 修道院の中庭で行われ、手のひらを使って壁や傾斜した屋根にボールを打ち付けて行っています。 今日、私たちが知っているテニスは、19世紀のイギリスで開発されたスポーツです。 クロケットの人気が急上昇したため、オールイングランド・クロケット・クラブは芝生をテニスに使わせることを決めます。 19世紀を通じて世界中でいくつかの国内連盟が設立され、1913年に国際ローンテニス連盟(ILTF)が誕生した競技です。
【オリンピック競技としての歴史】
テニスは、歴史上、断続的にオリンピックで争われています。 1896年にアテネで開催された第1回近代オリンピックで実施された正式競技のスポーツの1つでしたが、テニス界では、その後プロが参加するトーナメントが台頭したため、1924年のオリンピック後、アマチュアリズムを重視していたオリンピックから長い間外されていた競技です。
1968年のメキシコ大会ではデモンストレーションとして復活したものの、1988年、再びオリンピックにプロ選手の参加が認められるようになり、ソウル1988大会から復活します。 それ以来、世界最高峰の選手たちが大会のたびに世界を驚かせてきた競技です。
近年では、2008年のシングルスと2016年のダブルスで優勝したラファエル・ナダル、2008年のオリンピックダブルスで優勝したスタン・ワウリンカとロジャー・フェデラー、そしてオリンピックで8つのタイトルを獲得したセリーナとビーナス・ウィリアムなど、多くのスーパースターが金メダルを獲得しています。
オリンピックにおけるテニス競技には、男子、女子それぞれシングル(1人対1人)と、ダブルス(2人対2人)があり、さらにロンドン2012大会からは男女ペアで行うミックスダブルスが加わる試合です。
負けたら敗退する「トーナメント方式」で行われ、一発勝負になり、準決勝敗退者だけは、あとに3位決定戦を行います。
シングルスの出場枠は「64」で、原則として世界ランキングの上位から順に、かつ国別対抗戦で十分な代表経験がある選手に出場権が与えられる構成です。 また、1国から出場上限数は6人(シングルスは4人)となっています。
【ルール】
実施種目
シングルス(女子/男子)
ダブルス(女子/男子)
オリンピックテニスは、男子シングルスと女子シングルス、男子、女子、混合ダブルスで実施される競技です。
試合の開始前のトスで決まった一方のプレイヤーがサーバー、他方がレシーバーとなり、ゲームごとに交替します。 スコアは、0ポイントがラブ(love,0)、1ポイントがフィフティン(15)、2ポイントがサーティー(30)、3ポイントがフォーティー(40)、と数えていく形式です。 4ポイント先取すると、1ゲーム獲得でき、3ポイントで並んだ場合はデュースとなり、以降2ポイント差がつくまでゲームは続きます。 先に6ゲームを先取した方が1セットを獲得する試合構成です。 シングルスの試合は、3セット先取で行われます。 ゲームカウントが5対5になったときは、先に7ゲームを先取した方が1セットを獲得し、6対6になったときは、最終セットを除きタイブレークが採用されるルールです。
テニスは、裏をかくなど「駆け引き」が見もの、メンタルがゲームの流れを変えることもあるスポーツです。
テニスではサーブを打つ側が有利とされているため、サーブ権持つゲーム(サービスゲーム)を獲得することを「キープ」といいます。 一方、相手がサーブを打つゲームを自分には不利なため、このゲームを獲得することを「ブレーク」と言うテニス用語です。
自分のサービスゲームを確実にキープしながら、相手のサービスゲームをどれだけブレークできるかが勝利の鍵で、競っている試合では、ゲームは1つでもブレークすると、大きなアドバンテージとなります。
サーブやボレーを得意とする選手、ストロークのうまい選手など選手の個性を知って観戦すると楽しみが増え、ラリーが続いた時、どちらが先に攻撃を仕掛けるかも見ものです。
ライン際を狙ったショットやネット近くのドロップショット、左右の揺さぶり、回転やスピードを変えるなど仕掛ける技に注目が集まります。 テニスはメンタルが重要なスポーツ、とろわけ孤独な闘いであるシングルスでは、緊張や焦り、ネガティブな気持ちをどうコントロールするかが大切です。 相手の裏をかくプレーが決まったときは大歓声が起こり、選手のメンタルが影響し、試合の流れが大きく変わることもあります。 負けている試合でもうまく流れをつかんで逆転へと結びつけていける選手もいれば、プレッシャーやミスが原因で自分らしいプレーができなくなり自滅してしまう選手もいる試合展開です。 メンタルの戦いという視点は、テニス観戦の醍醐味の一つです。
テニスのコートには土でできたクレーコート、天然芝のグラスコート、アスファルトを基礎としたハードコートなどがあります。 バウンドが低いグラスコートを得意とする選手もいれば、バウンド後の球速が遅いクレーコートを得意とする選手もいる、各選手のコートとの相性を知っておくと、より面白く見られるゲームです。 オリンピックで使用するのはハードコートになります。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
ロサンゼルス2028大会では、レジェンドが意地を見せるか、若手が台頭するか、楽しみです。 オリンピックではダブルスや男女ミックスダブルスに注目が集まります。 普段シングルスしか出場しない大物選手が、同じ国同士でペアを組んでメダルを取りに挑んでくるからです。 サーブや強打で勝るシングルス選手のペアが押し込むか、ダブルス専門の熟練ペアが戦術やチームワークでものにするか、オリンピックならではの見どころになります。
テニスは日本人がオリンピックで初めてメダルを取った競技です。 有力選手が出場するか注目が集まります。
テニス開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
トライアスロンは己の経験と戦略、トランジション作戦との効率勝負!

トライアスロンは1人のアスリートが異なる3種目を連続して行う耐久競技です。 試合は種目の能力の高さやバランス、ペース配分などが問われ、選手同士の駆引きや戦術、トランジションの素早さなどに注目。 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
トライアスロンの主な強豪国と地域:
「男子個人:ノルウェー、イギリス、ニュージーランド etc.」
「女子個人:バミューダ、イギリス、アメリカ etc.」
「混合リレー:イギリス、アメリカ、フランス etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。
ロサンゼルス2028大会では欧米やオセアニア勢との順位争いに各業界の鉄人たちがシビレを切らす。
己のアスリート魂が再び燃え上がる国と地域はどこだぁ!
【トライアスロンの特徴】
トライアスロンは、スイム(水泳)、バイク(自転車ロードレース)、ラン(長距離走)の3種目を、この順番で1人のアスリートが連続して行う耐久競技です。 ラテン語の3を表すトライと、競技を意味するアスロンを組み合わせて名付けられています。
トライアスロンは3つの長い歴史を持つ種目で構成されていますが、国際的なスポーツシーンに登場したのはごく最近のことです。 1970年代にサンディエゴトラッククラブによって、従来のトラックトレーニングに代わるワークアウトとして発明されます。 クラブは1974年に最初の公式トライアスロンイベントを開催し、8.5キロメートル未満のランニング、8キロメートルのサイクリング、550メートルのスイムを特徴とした大会です。 このスポーツは1980年代を通じて人気が高まり、1989年、フランスのアヴィニョンで国際トライアスロン連合(ITU)が設立され、第1回トライアスロン世界選手権が開催された歴史を持つ競技です。
【オリンピック競技としての歴史】
オリンピックでは、スイム1.5キロメートル、バイク40キロメートル、ラン10キロメートルの、合計51.5キロメートルで着順を競い合います。 この設定距離は、オリンピック ディスタンス、またはスタンダード ディスタンスと呼ばれる構成です。
ワールドカップシリーズは1991年に始まり、8ヵ国で11レースが行われています。 トライアスロンは、1974年に初めてアメリカで競技大会が開催された比較的新しいスポーツです。 このイベントをきっかけに、トライアスロンはより身近なものとなり、シドニー2000大会から正式競技となり、男女とも実施されています。
トライアスロンは比較的新しいスポーツであるため、真に支配的な国はありません。 男子のメダリストは1時間45分ほど、女子のトップは2時間を切るスピードで駆け抜けてゆく競技です。 6大会で授与された39個のメダルは16カ国に分かれているが、3個以上の金メダルを獲得できた国と地域はありません。 東京2020大会では、新種目として男女による混合リレーが行われ、パリ2024大会でも引き続き、混合リレー種目が実施される予定です。
スイム、バイク、ラン、異なる3つの競技を制する真の鉄人は、どこの国や地域のアスリートが手にするか注目が集まります。
【ルール】
種目
個人(男子/女子)
混合リレー
トライアスロンは、経験と戦略のスポーツとも言われ、3つの種目それぞれの能力の高さはもちろん、バランスやペース配分が大切だからです。 スイムから先行してランで逃げ切ったり、速いランニングタイムで後方から追い上げたりと、各選手が得意とする種目で、いかに他の選手と差をつけられるかが見ものになります。
オリンピックのトライアスロンは、男女ともに、水泳1500メートル、自転車40キロメートル、ラン10キロメートルで構成されている競技です。 ヒートはなく、最初にフィニッシュラインを通過した選手が勝者となるシングルレースで、汎用性とスキルが求められます。
東京2020大会では、男女の個人種目に加え、初めて混合リレーが実施され、男性2人、女性2人のチームがショートコースのトライアスロンで競い合う種目です。 この混合レースはペースが速く、予測不可能な試合展開が楽しめます。
競技中スイムからバイク、バイクからランへと種目を転換するトランジションも、注目すべきポイントの一つです。 トランジションエリアで、次の種目に合わせたウエアに着替え、シューズを履き替えるが、この時間もタイムに含まれています。 そこで選手は素早くスムーズに着替え、ウエアやシューズ、ヘルメット、サングラスなど用具の配置にも各自工夫を施して、無駄な動きを省くことが重要です。
例えば、少しでもタイムを縮めるために、バイクシューズをあらかじめペダルに付けておき、走りながらシューズを履くなど各自で戦略を考えて大会へ挑んでいます。 トランジションは、トライアスロンの第4種目と言われることもあるほど、重要なポイントです。
さらにドラフティングと呼ばれる戦術にも注目が集まります。 空気抵抗の軽減を図るため、バイクで先行する選手の直後を走って風よけとし競技を有利に展開する戦術です。 どちらが先に出るか、お互いの駆け引きに、観ている者の緊張感も高まります。
そしてランでは、選手はフィニッシュが近づくにつれて徐々に加速し、スパートし、長距離での勝負ではあるが、最後は僅差となることもあり、フィニッシュラインを超えるまで目が離せない競技展開です。
選手同士の駆け引きやトランジションにも注目しょう。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
トライアスロンは、競技として成立してから40年余り、オリンピックでもまだ6回しか行われていない歴史の浅いスポーツだが、競技人口は世界中で着実に増加しており、世界選手権から各地域で催される小規模な大会まで、年間を通じて数多く実施されています。
各国の状況をみると、イギリスをはじめとしたヨーロッパ勢の強さが目立っている競技です。 また、競技発祥の地であるアメリカや、オーストラリア、カナダなども各種大会への出場者が多く、好成績を記録しています。
オリンピックでの参加枠は、国際トライアスロン連合(ITU)が指定する競技会での成績に対して、選手の所属する国別にポイントが与えられ、ポイントが上位の国から順に3枠、2枠、1枠と割り振られる配分です。 したがって、成績が上位の国ほどより多くの選手が参加でき、メダル獲得のチャンスも広がります。
これまでの6大会で金メダルを獲得したのは、男子はイギリスが2個、ドイツ、ニュージーランド、カナダが各1個です。 なお、女子は、スイスが2個、アメリカ、オーストラリア、オーストリアが各1個となっています。 メダルの男女総数では、イギリス、スイス、オーストラリアが計5個と肩を並べており、選手層の厚さからも強豪国と呼べるだろう。 東京2020大会でも、これら強豪国の選手が活躍する公算が高いと思われていたが、男子ではノルウェー、イギリス、ニュージーランド、女子はバミューダ、イギリス、アメリカ、混合リレーでもイギリス、アメリカ、フランスと新鋭が現れ、パリ2024大会でも新たな国や地域の活躍の可能性にも期待が高まる競技です。
イギリスなどヨーロッパ、アメリカ、オセアニア勢の強さが目立つ強豪国の選手の活躍に注目が集まります。
日本は、シドニー2000大会から、男女とも出場を続け、北京2008大会では、5位入賞を果たし、世界のトップクラスとは、まだ差があるものの、女子は毎回3名が出場しており、実績を挙げつつある状況です。 東京2020大会の経験を活かし、ロサンゼルス2028大会でも活躍できることに期待が高まります。
開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
馬場馬術、総合馬術、障害馬術
馬術は選手と馬の信頼関係、指示の妙技、己たちの華麗な演技の勝負!

馬術は愛馬と共に駆け、性別関係なく人馬ペアで行う競技です。 試合は3種目、選手と騎乗馬の資質が問われ、優雅さ漂う独特の雰囲気の中、人馬一体の迫力ある走りやジャンプ、ダイナミックな演技が魅力! 日本は出場選手に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
馬術の主な強豪国と地域:
「ドイツ、イギリス、オーストラリア、フランス、スウェーデン、オランダ、アメリカ、ベルギー etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では気品漂う順位争いに豪華な食事が待ってるぜぇ。
ヴェルサイユ宮殿での競技ダンスを華麗かつ大胆に決める国と地域はどこだぁ!
【馬術の特徴】
馬術は、動物を扱い、男女の区別なく同じ条件で実施されることが特徴の競技です。 人馬ペアで競技を行うため、選手と同様に騎乗馬の資質も問われます。
オリンピックでは、コース上に設置された大きな障害物を飛び越える際のミスの少なさと走行時間で競う「障害馬術」、ステップなどの演技の正確さと美しさを採点する「馬場馬術」、障害と乗馬の2つにダイナミックなクロスカントリー走行を加えた「総合馬術」の3種目が行われる競技です。
各種目において個々の人馬のパフォーマンスが個人成績としてカウントされる個人競技および各国チーム3人馬の成績を合計して団体成績とする団体競技が行われます。
馬術の起源は古代ギリシャで、騎手と馬が戦いで生き残るためには完璧なパートナーシップが必要だと考えられ、馬を訓練する方法として馬場馬術が開発された競技です。
古代オリンピックでは、馬術競技が戦車競走という形で登場し、大胆でエキサイティングな光景で、乗馬の芸術は、ルネッサンス期に復活するまで実施されていません。
【オリンピック競技の歴史】
馬術競技はパリ1900大会で初めて採用、実施され、1912年のストックホルム大会で正式デビューした競技です。 ヘルシンキ1952大会で軍人以外の男子および女子の参加が認められるまでは、男子の軍人のみが参加できる競技になります。 1964年には、すべての馬術競技に女性が参加できるようになり、オリンピックで唯一の混合種目です。 選手は規定によって燕尾服や乗馬服、シルクハットなどの帽子を着用し、優雅さが漂う独特の雰囲気のもと競技が行われます。
【ルール】
馬術は3つの種目からなり、男女が対等に競い合う競技です。
種目:イベンティング チーム個人 馬術 チーム 個人 ジャンプ チーム 個人
選手と馬のコンビネーションが見どころで、飛越の迫力や華麗な演技に注目しましょう。
馬場、総合、障害3つの種目に共通する見どころは、拳(手綱)、脚、体重の移動などにより馬へ細かい指示を出す選手の技術と、それに応える馬の能力です。 選手と馬の信頼関係によるコンビネーションが見事な飛越や演技を生み、迫力と華麗さに目を見張ります。
馬場馬術は、20メートル×60メートルの長方形のアリーナ内で、馬の演技の正確さや美しさを競う規定演技と、必須の要素で構成し、音楽をつけて行う自由競技です。 なんといっても、よく調教された馬の、まるで自ら楽しみながらダンスを踊っているかのような躍動感が見どころになります。 選手の指示に従って、リズムよくしなやかにステップを踏んだり、図形を描いたりする見事な演技と芸術性に目を見張る種目です。 選手はなるべく小さく馬に合図を送り、馬はそれに応じて正確かつ華麗な動きをします。 文字とおり人馬一体の妙技に注目しよう。 審査員は、コース内を動き回る容易さと流動性を評価する種目です。
総合馬術は、馬場馬術と障害馬術にクロスカントリーを加えた3種目を同じ人馬のコンビで行い、馬術のトライアスロンに似ており、合計減点の少なさを競う複合競技になります。 総合馬術は、馬場馬術、クロスカントリー、障害馬術の順に行われる種目です。 人馬ともに総合的な能力やテクニックが求められ、さらに選手は持久力や精神力、経験が必要になります。 3日間かけて行われるため、馬のコンディションを良い状態に保つようケアすることが重要です。
メインとなるクロスカントリーでは、竹柵、生垣、水濠など自然障害物を組み合わせた40を超える障害物が起伏に富んだ長いコースで構成されています。 その6キロメートル近いハードなコースを10分ほど駆抜ける迫力はダイナミックです。 スピードは時速30キロメートル以上になり、迫力満点のスリリングさが醍醐味になります。 最短距離を攻めればタイムは早くなるが失敗するリスクが高く、安全策をとればその分タイムがかかるため、選手がどのようなコース取りをするのかも見どころです。 最も汎用性の高いスキルを持つ馬と騎手が3つの種目で優勝します。
障害馬術では、競技アリーナに設置されたさまざまな形状の障害物を、決められた順番どおりに飛越し、走行する競技です。 障害物の落下や、馬が止まったり横に逃げたりする不従順などのミスなく、規定タイム内にゴールすることが求められます。 障害物を倒すたびにペナルティが課せられ、敏捷性、テクニック、馬と騎手の調和が不可欠です。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
馬術の発展には、自然環境と設備が重要となるため、古くから馬術が親しまれてきた歴史のある国で盛んに行われていて、競技人口も多くなります。 ドイツなどは、多くの人が子どもの頃から馬に親しみ、競技に出場して技術を磨いている強豪国です。 選手と競技馬の層が厚く、また馬術用馬の生産も国家的に行われており、馬術が1つの文化として国全体に根づいています。
オリンピックで行われる3種目について世界の情勢を見ると、馬場馬術では長年ドイツが圧倒的な強さを誇り、特に団体で金メダルをほぼ独占してきたが、近年ではオランダも力をつけてきており、ドイツを脅す存在になっている強豪国の一つです。 この2ヵ国に加えて、イギリスも好成績を出しています。
総合馬術は、ドイツ、イギリスなどのヨーロッパ勢に加えて、オーストラリア、ニュージーランドも強さを発揮している種目です。 障害馬術では特に突出して秀でた国はなく、ドイツ、オランダ、アメリカ、カナダ、スウェーデンなどが常に上位を争っています。 世界全体を見ると、やはり馬術大国ドイツが強く、オリンピックの総合馬術個人では、ドイツ、スウェーデン、フランス、イギリスと続く勢力図です。
東京2020大会に続く、フランス2024大会、ロサンゼルス2028大会でもこの勢力図は簡単に崩れないと思われるが、どんな人馬が優れたパフォーマンスを見せてくれるのか楽しみになるだろう。
日本は、近年、欧米からトレーナーを招いて人馬の技術向上に努め、また多くの日本人選手がヨーロッパを拠点に活動し、国際大会に参加するようになったことで技術レベルは着実に向上してきています。
馬術会場
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
体操は己の精神力の強さと高難度、完成度の高い技が試される勝負戦!

体操は器機を用い身体で演技を行う競技です。 試合は熟練の技や美しさ、安定した演技が求められ、男子は力強さと豪快さ、女子は優雅さと華やかさなど、非日常的かつ洗練された動きや選手たちの技量に注目。日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
体操競技の主な強豪国と地域:
「男子あん馬:イギリス、チャイニーズタイペイ etc.」
「男子つり輪:中国、ギリシャ etc.」
「男子ゆか:イスラエル、スペイン、中国 etc.」
「男子チーム:ROC、中国 etc.」
「男子個人総合:中国、ROC etc.」
「男子平行棒:中国、ドイツ、トルコ etc.」
「男子跳馬:韓国、ROC、アルメニア etc.」
「男子鉄棒:クロアチア、ROC etc.」
「女子ゆか:アメリカ、イタリア、ROC etc.」
「女子チーム:ROC、アメリカ、イギリス etc.」
「女子個人総合:アメリカ、ブラジル、ROC etc.」
「女子平均台:中国、アメリカ etc.」
「女子段違い平行棒:ベルギー、ROC、アメリカ etc.」
「女子跳馬:ブラジル、アメリカ、韓国 etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国や地域です。
ロサンゼルス2028大会では欧米や南米、アジア勢との順位争いの各種スコアに目頭が熱くなる。
己の身体一つで、伝説のパーフェクトスコアを超える国と地域はどこだぁ!
【体操競技の特徴】
体操競技は器械を用いて身体で演技を行い、技の難度や美しさ、安定性などを基準に審判員が判定を行い、得点を競う採点競技です。 男子は「ゆか、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒」の6種目、女子は「跳馬、段違い平行棒、平均台、ゆか」の4種目が行われ、それぞれの器具の特性を活かした演技で構成されています。 なお、女子のゆかは音楽に合わせて演技が行われるのが特徴です。
体操は非常に古いスポーツであり、そのルーツは古代にまで、さかのぼります。 1881年には国際体操連盟が設立され、世界最古の国際スポーツ連盟です。 当時、体操は身体運動と知的活動を組み合わせる方法として哲学者によって推奨されています。 体操は19世紀に人気が高まり、競技の数が増え、1896年にアテネでオリンピックが復活したときに最高潮に達した競技です。
【オリンピック競技としての歴史】
体操競技の歴史は、第1回のアテネ1896大会のオリンピックから始まります。 当初は男子のみだったが、アムステルダム1928大会からは女子体操競技も行われている競技です。
かつては規定演技と自由演技の総合得点で競われていたが、アトランタ1996大会を最後に規定演技は廃止され、現在は自由演技のみで競技されています。 体操は20世紀前半から大きく発展し、アスリートが芸術的な動きの限界を押し広げるにつれて進化し続けている競技です。
1960年代から70年代にかけて、日本はオリンピックの表彰台を独占し、その後、ソ連と東ドイツに追い抜かれ、現在、体操競技の主役は、日本、アメリカ、ロシア、中国が中心となっています。
体操競技は回転、跳躍、着地などの難易度や完成度も求められるシビアな闘いです。
【ルール】
体操競技は、さまざまな器具を使った個人競技と、すべての器具を使った団体競技で構成されています。 体操競技は、器具ごとに異なるスキルが必要です。 男子は床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒、女子は跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動などを競い合います。 さまざまな要素があり、それぞれが前回よりも壮観で、ダイナミックなシークエンスと構図には、強さ、敏捷性、協調性、正確さが求められる競技です。 体操は大会ごとに進む技の高難度化 熟練の技術と精神力の強さが試される競技になります。
採点方法は長年にわたって10点満点制が採用され、モントリオール1976大会において「白い妖精」と呼ばれたメディア コマネチ(ルーマニア)が、史上初めて10点満点を出した選手として有名です。 だが、選手の得点が極めてわずかな範囲に集まってしまい明確な差がつけられず、些細な誤審でメダルの色が変わる事件が起きたことを八端に10点満点廃止が議論されるようになります。 そして2006年から技がどれだけ難しいのかを得点化したDスコア(技の内容など運動の難易度、演技価値点)と、演技の完成度を得点化したEスコア(演技の美しさや出来栄え点)の合計得点を争う上限のない採点方式となって、現在に至っている競技です。
体操競技の各種目には多くの技があり、それぞれの技の運動の難しさの程度は難度で表され、配点は難度により異なります。 どの高難度の技を取り入れるか、様々な難度の技をどう組み合わせて構成し、安定した演技をするかに選手の技量やメンタルの強さが試され、得点に反映される競技です。 最大の見どころは、なんといっても体操競技ならではの非日常的なアクロバティックな技や、洗練された美しい動きではないでしょうか。 体操競技は動きそのものが勝敗につながるため、演技時間は短いが、気を抜ける動きは一つもありません。 その中で、男子はそれぞれ特徴的な動きを示す6種目において力強さと豪快さを、女子は4種目で優雅さと華やかさを楽しめます。
競技は、最初に予選が行われ、団体総合、個人総合、種目別のそれぞれの決勝進出をかけて予選で演技することになるが、各選手、各種目で行った1演技の得点によって予選を通過するかどうかが決められる形式です。 (ただし、跳馬種目別の権利を得ようとする選手のみ跳馬を予選で2演技行う)
団体総合は、各国1チームで演技を行い、合計得点でメダル獲得を目指します。 個人総合は、すべての種目(男子は6種目、女子は4種目)を1人の選手が演技して、合計得点を競い合う形式です。 種目別では、各種目の得点上位の選手が決勝で激突します。
すべて予選の得点は加味されず、決勝での得点により順位が決めら、また、体操競技では、技の名前に、その技を最初に成功させた選手の名前が付くことも特徴です。
国際体操連盟(FIG)の定める国際大会で、過去に実施されたことがない新技を事前に申請したうえで発表し成功すると、その技の通称として実施した選手の名前が会議を経て技名として認定されます。 ロサンゼルス1984大会で森末が発表した平行棒の「モリスエ」など日本人選手の名が付く技も多いです。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
アメリカ、ロシア、中国、日本が中心か、選手が繰り出す完成度の高い高難度の技に注目が集まります。 かつて圧倒的な強さを誇ったのは日本の男子です。 現在では男子は日本、中国、ロシアなど、女子はアメリカ、ロシア、中国などが強豪国として知られています。 演技の難しさのみが上限を撤廃されている関係で、多くの高難度の技に挑戦する選手は多いが、ミスのあった選手が上位になってしまう矛盾も起こり、現在ではその完成度も非常に厳しく見られるようになった競技です。 トップを目指す選手たちは、完成度の高い高難度の技を発表するため、日夜努力をしています。
日本は、まさに「体操ニッポン」、「お家芸」と謳われ、ロサンゼルス2028大会でも円熟のベテラン勢と若手の活躍が期待され、「体操強豪国ニッポン」と大歓声が響き渡ることでしょう。
【開催地】
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
新体操はリズミカルかつ躍動感あふれる己の華麗な演技と芸術性の勝負

新体操は手具と一体化するような、しなやかで洗練された動きと曲の雰囲気に溶け込むような演技を求める競技です。 試合は体操の要素を組合せた高度な技や力強さ、柔軟性、スピード感ある巧みな演技に注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
新体操の主な強豪国と地域:
「個人総合:イスラエル、ROC、ベラルーシetc.」
「団体総合:ブルガリア、ROC、イタリア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では欧州勢との順位争いに芸術家たちも目に力が入る。
己の演技で世界中を魅了させる美しい舞を繰り広げられる国と地域はどこだぁ!
【新体操の特徴】
新体操は、手具を使いながら音楽に合わせてリズミカルな演技を行い、芸術性を競う採点競技です。 身体と手具が一体化するような、しなやかで洗練された美しい動きと、曲の雰囲気に溶け込むような演技が魅力で、躍動感あふれるダイナミックな動きの中に、頭からつま先まで全神経を集中させてバランスを保つ繊細さ兼ね備えています。
体操は、古代文明にまでさかのぼる起源を持つ、今日でも実践されている最古のスポーツの1つです。 実際、1881年に設立された国際体操連盟(FIG)は、世界最古の国際スポーツ連盟になります。 しかし、新体操は、19世紀後半から20世紀初頭にかけてヨーロッパで流行した集団体操から発展したため、はるかに新しい競技です。 国際体操連盟(FIG)は1961年に新体操を種目として認め、その2年後、ブダペストで第1回世界選手権が開催されています。
1963年に第1回新体操世界選手権がハンガリーで開催された後、女子のみのオリンピック正式種目になったことで、多くの国々に新体操が広まった競技です。 個人総合はロサンゼルス1984大会から、団体総合はアトランタ1996大会から実施されています。
新体操はアスリートでありアーティスト、息のあった華麗な舞で美を競い合う競技です。
【オリンピック競技としての歴史】
新体操は、これまで女性だけの種目だったが、個人競技でオリンピックデビューを果たし12年後の1996年、アトランタで団体競技が導入されています。 東ヨーロッパ諸国、特にロシアは、このスポーツで大きく支配している強豪国です。 例えば、ロシアは、新体操がオリンピック種目として採用されて以来、17タイトルのうち10タイトルを獲得しています。 スペイン、カナダ、イスラエルだけが覇権を握り、金メダルを獲得している国です。
【ルール】
種目
個人総合(女子)
団体戦(女子)
演技は13メートル四方のフロアマットで行われ、個人競技と団体競技の2つに大きく分けられます。 個人は「ロープ(個人はジュニアのみ)フープ ボール クラブ リボン」の5つのうち、オリンピックではロープ以外の4種目を1人の選手が行う形式です。
個人競技では、体操選手は各器具を1回ずつ使用し、4回演技を行い、団体競技は、1チーム5人の選手によって2種目が行われます。 なお、演技時間は、個人競技は1種目につき1分15秒~1分30秒、団体競技は各種目2分15秒~2分30秒と決められており、長すぎても短すぎでも1秒につき0.05点の減点となる採点形式です。
新体操は動きによる表現で、伝統舞踊と体操の要素を組み合わせ、リボン、フープ、ボール、クラブの4つの器具を使用します。 体操選手の演技中に演奏される音楽も重要な役割を果たし、ボーカル付の音楽が許可されている女性だけの種目です。
このイベントでは、1回目の公演には1組の装置が含まれ、2回目の公演には2つの異なる装置が含まれます。 ルーチンは、Dスコア(エクササイズの難易度/内容)、Aスコア(芸術性)、Eスコア(実行)の組み合わせを使用して評価される採点形式です。
各種目に求められる高度なテクニック、手具と連動した動きや柔軟性が見どころになります。 競技の一番の見どころは、スピード感あふれる巧みな手具さばきだろう。 6メートルの長さのリボンを流れるように大きな弧を描くなど自在に操るためには、常に手首を動かし、しかも、リボンが床についたり、絡まって結び目ができたりすると減点対象となってしまう種目です。 笑顔で華麗に舞いながら、いとも簡単にリボンをクルクル回しているように見えるが、実際は見た目以上に筋力が必要になります。
空中に投げてキャッチしたり、身体に巻きつけたりするロープの演技は、持ち方や投げ方のテクニックはもちろん、軽やかなステップやジャンプにも注目です。 フープの演技では、高く投げたフープを体を通して受け止めるといった高度なテクニックと、ダイナミックな動きが見せ場になります。
ボールの演技では、手具であるボールが小さい分、特に体や動きの柔軟性が重要で、胸や背中などで転がすボールが、身体に吸いつくように流れる動きが見どころです。
長さ40~50センチメートルのクラブの演技では、必ず2本をセットで使い、左手で回しながら右手で投げるなど左右で異なった動きをすることもあり、常に双方を意識しなくてはならず、より集中力が必要とされる分、落下も起こりやすくなります。 選手は、より完璧な演技を目指すが、一瞬のミスによる減点が大きく順位を左右する種目です。
なお団体では、単一の手具、または2種類に手具を組み合わせて演技を行います。 投げによる手具の交換といった、曲芸のような大胆な技を含め、スピーディーかつ息の合った一糸乱れぬ動きに注目です。 そして、着用する衣装も見どころの一つになります。 デザインや色づかい、装飾が凝っており、ラメやスパンコールがふんだんに施されてきらびやかに輝く、色鮮やかな衣装でも楽しませてくれる競技です。 選手は力強さやスピード、そして柔軟性が求められるアスリートであると同時に、美しさを表するアーティストでもあります。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
圧倒的な強さを誇り、連覇を続けるロシア、演技を引き立てる音楽にも注目です。 新体操のルーツは、バレエをもとにした芸術体操と考えられています。 そのため、バレエの歴史が古く、伝統のあるヨーロッパ勢が上位をほぼ独占する状態が続いており、特に芸術性のあるスポーツに圧倒的な強さを誇るロシアの存在が際立っており、世界をリードしている強豪国です。
各国、地域もロシアに倣い、また独自の技やスタイルに磨きをかけているが、選手層の厚さや環境から鑑みて、この傾向は長く続くと思われます。 そのほか、ベラルーシやウクライナがメダルの常連です。
なお、卓越した技術と同時に、凛とした美しさや芸術性を競い合う新体操では、女性らしい身体のラインを強調するしなやかな演技が大きな魅力なので、身長が高く、長い手足が目を引く選手が多いのが特徴になります。 また、優美な演技の魅力を引き出す音楽の役割も大きいです。 各国の選手が、どのような曲を用いて自身の演技の世界観を表現するのかにも、ぜひ注目してみましょう。 ちなみに声は楽器の一つと考えられるため、ボーカル入りの曲は団体競技1演技まで、個人競技2演技まで許容されている競技です。
日本は1968年の全日本学生選手権で初めて個人競技が行われ、この大会をきっかけに「新体操」という名称が使われるようになります。 日本代表は日本体操協会によって編成される日本ナショナル選抜チームで、愛称は「フェアリージャパン」です。 全国からオーディションで選んだ若手選手を集中合宿で鍛えていく強化策を取っています。 東京2020大会での活躍をばねに、ロサンゼルス2028大会では更なる活躍に期待しよう。
開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
トランポリンは己の卓絶したバランス感覚と運動能力が要求される闘い

トランポリンは体力と集中力、強い精神力、美しい姿勢での正確さ、より高く、力強い演技が求められる競技です。 試合は、空中遊泳をするようなアクロバティックな演技と華麗な跳躍、ダイナミックさに注目。 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
新ルールに変更される予定なので注意
世界状況
トランポリンの主な強豪国と地域:
「男子:ベラルーシ、中国、ニュージーランド etc.」
「女子:中国、イギリス etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では欧州、オセアニア、アジア勢との順位争いにポップコーンの弾き音が聞こえてくる。
己の磨き上げた跳躍で、世界を魅了させる国と地域はどこだぁ!
【トランポリンの特徴】
トランポリンは、地上8メートルの跳躍でみせるアクロバティックな演技、卓越したバランス感覚で宙を舞う競技です。 縦4.28メートル(プラスマイナス6センチメートル)、横2.14メートル(プラスマイナス5センチメートル)の、テープ状のナイロンなどを編んだベッドと呼ばれる弾力性の強いシートを、スプリングでフレームに固定し、反動によって高く跳躍します。
男子選手のジャンプの高さは地上8メートルにも達するほどダイナミックだが、空中でわずかでも傾いたり姿勢を崩すと中央のゾーンに着床できないという繊細な一面を持っている競技です。 選手には卓抜したバランス感覚と運動能力が求められ、観客はその迫力に息を呑むダイナミックさ魅了されます。
トランポリンは、1934年にアメリカの体操選手ジョージ・ニッセンが、サーカスのアクロバットがセーフティネットで跳ねるのを観察して発明し、彼らはアクロバットを再現するために、最初にプロトタイプトランポリンを作ったのが始まりです。
トランポリンは当初、宇宙飛行士やアスリートが他のアクロバットスポーツのトレーニングをするための機器として使用されていましたが、すぐにそれ自体がスポーツとして非常に人気を博した競技になります。 最初のトランポリン世界選手権は1964年にロンドンで開催され、34年後の1998年に国際体操連盟を統合した競技です。
【オリンピック競技としての歴史】
トランポリンは2000年のシドニー大会でオリンピック種目となり、男子と女子のトランポリンの個人競技が体操競技の他の種目に加わります。 オリンピック種目になって以来、中国は12個のタイトルのうち4個を含む36個のメダルのうち14個を獲得し、トランポリンのメダル獲得数でも大きくリードしている強豪国です。 しかし、中国がメダル獲得数を圧倒する一方で、カナダのロージー・アクレナン選手は、男女を問わず、オリンピックタイトルの防衛に成功した最初で唯一のトランポリン選手が存在します。(2012年と2016年)
【ルール】
種目
個人(女子/男子)
トランポリンは、空中でのアクロバティックな演技で、美しさ、難しさ、高さを競う採点競技です。 トランポリンは、技の出来栄えを見る演技点と、回転とひねりの数で算出する難度点、滞空時間を計測する跳躍時間点、さらにどれだけトランポリンの中心で演技を行うかを評価する移動点を加算して、それらの合計得点で順位を競い合います。
トランポリン個人種目(男子と女子)は、合成繊維でできた長方形のキャンバスであるトランポリン上で、8メートル以上の高さで跳ね回り、ひねり、跳ね返り、宙返りを繰り返す試合展開です。
ベッドはスチールスプリング付きのフレームに取り付けられており、その反動動作によりアスリートは空中に高く舞い上がります。 競技中、アスリートは10の要素で構成されるエクササイズを行い、難易度、実行力、空中で過ごした時間に応じて採点される形式です。 このスポーツは非常に技術的で、絶対的な精度が要求されます。
10種目連続して行われる高難度の跳躍や宙返り、決勝ではドラマチックな大逆転の可能性もあり、まるで空中遊泳をするような浮遊感を伴って、連続して行われる跳躍や宙返りダイナミックさ、姿勢の美しさが注目ポイントです。
選手はジャンピングゾーンと呼ばれる赤い枠内で、高さのある安定した演技を目指します。 もっとも重要な点は、それぞれの跳躍でより高く垂直方向に飛ぶことです。 高さと滞空時間を稼ぐために、トランポリンの中央に着地するように意識し、次の跳躍の高さへと繋げていきます。 だが足元が不安定なうえ、空中で少しでも体勢が崩れただけで着地位置が大きくずれてしまうという危うさがある競技です。 演技中、目印として中心部に描かれた7センチメートル(プラスマイナス3センチメートル)の赤い十字マーク付近にきちんと降りられるか、また外れてしまった場合には次の跳躍でうまく体勢を持ち直すことができるかが見どころとなります。 ちなみに、跳躍や宙返りの空中姿勢には、タック(抱え型)、バイク(屈身型)、レイアウトあるいはストレート(伸身型)の基本的な3種類があり、さらに回転数やひねりを加えることで技の難易度が上がり難度点が計算される採点形式です。
オリンピックの予選では、第1自由演技および第2自由演技の合計で予選が行われます。 第1自由演技は、ルールで定められた特別要求(特定の技や演技構成により加点される)を含む、異なる10種目の技を構成し演技を行う構成です。 そのため、第1自由演技より、さらに高難度の技の連続を見ることができます。 また、演技の美しさ(Eスコア)、技の難しさ(Dスコア)に併せ、高さ(滞空時間)の跳躍時間点(Tスコア)、およびどれだけ平行に移動しないかを評価する移動点(Hスコア)すべてを合計し、上位8名が決勝に進出する構成です。 連続で10種目、しかも1種目ずつ高難度の技を実施しなければならないため、体力と集中力、さらには強い精神力が要求されるシビアな競技といえます。 世界の男子選手のトップクラスだと、10種目のDスコアは17.0点を超え、メダル争いに絡むには、このラインが目安となるだろう。
なお、決勝での自由演技は、予選の得点は加算されず0点スタートとなり、決勝の得点のみ順位が決定します。 しかも、やり直しがきかないため、たとえ8位通過の選手でも一発逆転優勝の可能性がある試合展開です。 そのため、上位通過者といえども油断できず、予選とはまったく順位が入れ替わるようなスリリングな勝負が繰り広げられることになります。 約20秒と短い競技時間は一発勝負の緊張感に満ちており、一瞬も目を離さずに、1本1本の跳躍を見守ろう。 メダルの行方は、最後の選手の演技が終了するまでわからないからです。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
オリンピックではシドニー2000大会から個人競技のみが新種目として正式採用され、男女12名が参加したのが始まりになります。 オリンピックの出場枠は、男女それぞれ各国最大2名です。 前年に行われる世界選手権で決勝に進出した選手の所属国が出場権を獲得し、それ以外の出場権はワールドカップシリーズの上位成績などで決定します。 オリンピック競技として歴史は浅いものの、男女とも特に中国勢の活躍が目立っており、表彰台の常連です。 中国のほか、ロシア、ベラルーシなども強豪国と見なされています。 女子はカナダ勢の堅実さがあるが、男子同様に中国、ロシア、ベラルーシが上位を占める勢力図です。
足や腕を伸ばした美しい姿勢で正確に、より高く、そして力強い演技が求められます。 ロサンゼルス2028大会では、どんな選手がオリンピックのプレッシャーに飲まれることなく華麗な跳躍を冷静に決めることができるか、そして決勝ではどのような逆転ドラマが展開されるかに注目です。
日本は、近年、競技人口が増えており、世界で活躍する選手も育っています。 予選の壁を突破して、決勝の舞台で高く舞う日本選手の活躍に期待しよう。
開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
カヌーは己の艇を操る技術とパドル捌き、敏捷性や判断力、攻略の勝負

カヌーは2つの異なるボート、種目で行われる水上の熱いレースです。 試合は短距離を全速力で漕ぎ着順を競うスプリントと激流を制する技とタイムを競うスラロームがあり、大自然と一体となる爽快感が魅力。 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
カヌーの主な強豪国と地域:
・カヌースプリント:
「女子カナディアンシングル200メートル:アメリカ、カナダ、ウクライナ etc.」
「女子カナディアンペア500メートル:中国、ウクライナ、カナダ etc.」
「女子カヤックシングル200メートル:ニュージーランド、スペイン、デンマーク etc.」
「女子カヤックシングル500メートル:ニュージーランド、ハンガリー、デンマーク etc.」
「女子カヤックフォア500メートル:ハンガリー、ベラルーシ、ポーランド etc.」
「女子カヤックペア500メートル:ニュージーランド、ポーランド、ハンガリー etc.」
「男子カナディアンシングル1000メートル:ブラジル、中国、モルドバ共和国 etc.」
「男子カナディアンペア1000メートル:キューバ、中国、ドイツ etc.」
「男子カヤックシングル1000メートル:ハンガリー、ポルトガル etc.」
「男子カヤックシングル200メートル:ハンガリー、イタリア、イギリス etc.」
「男子カヤックフォア500メートル:ドイツ、スペイン、スロバキア etc.」
「男子カヤックペア1000メートル:オーストラリア、ドイツ、チェコ共和国 etc.」
・カヌースラローム:
「女子カヌー:オーストラリア、イギリス、ドイツ etc.」
「女子カヤック:ドイツ、スペイン、オーストラリア etc.」
「男子カヌー:スロベニア、チェコ共和国、ドイツ etc.」
「男子カヤック:チェコ共和国、スロバキア、ドイツ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では欧米、オセアニア、南米、アジア勢との順位争いに魚たちも響めき始める。
己のパドル捌きで、100年目のコースを攻略できる国と地域はどこだぁ!
【カヌーの特徴】
カヌーはスピード勝負のスプリント、激流を制するスラローム、2つの水上の熱いレースが繰り広げられる競技です。
数千年の昔から、カヌーは北アメリカ、シベリア、グリーンランドで日常的に水上の移動手段として使用され 輸送や貿易のために世界各地で人々に親しまれています。
カヌースラロームはスキースラロームをモデルに、1932年スイスで始まり、最初の競技は平らな水域で行われましたが、後に急流に切り替えられた種目です。 主に狩猟や漁業(釣り)の道具でしたが、カヌーとカヤックのスポーツ競技は、19世紀半ばにイギリスで初めてスポーツになります。
1866年に設立されたロンドン ロイヤル カヌー クラブは、このスポーツの発展に重点を置いた最初の組織です。 1890年代には、ヨーロッパ全土でカヌーとカヤックが人気を博したスポーツになります。 記録に残る最初のカヌースプリント競技レースは、1896年に英国ロイヤルカヌークラブで開催された大会です。
カヌーには、流れのない直線コースで一斉にスタートし、着順を競うスプリントと、激流を下りながら吊るされたゲートを順に通過してタイムと技術を競うスラロームがあります。
川や湖、またそれに似た屋外の人工のコースで行われるので、大自然と一体となる爽快感が最大の魅力です。 風を感じながら水上を疾走する気持ち良さを、観客者もともに味わうことができる競技になります。 競技で使われるカヌーのタイプは2種類です。
ブレード(水かき)が片端だけについているパドルで行うカナディアンと、両端についているパドルで行うカヤックになります。
さらにスプリントはシングル(1人乗り)、ペア(2人乗り)、フォア(4人乗り)の区別があり、距離も200メートル、500メートル、1,000メートルの3種類です。 これらを組み合わせて男女でスプリントが計10種目、スラロームが3種目行われます。 リオデジャネイロ2016大会までは、女子はカヤックのみで、男子より種目数が少なかったが、東京2020大会では女子にカナディアンが加わり、種目数も男女同数になった競技です。
【オリンピック競技としての歴史】
カヌースプリントは、1924年のパリ大会で、既にデモンストレーション競技として採用され、1936年のベルリン大会でオリンピックの正式種目となります。 ロンドン1948大会からは女性がカヤックのみで競技に参加できるするようになった競技です。
一方、カヌースラロームは1972年のミュンヘンオリンピックでデビューし、1992年のバルセロナ大会でオリンピックの常設種目となります。 ヨーロッパ諸国の選手は、オリンピック史上、カヌースラロームのメダルの約90%獲得し、大きな成功を収めている競技です。
パリ2024大会では、カヤッククロス種目(男女)で新しいスラローム競技形式が導入されます。 スキークロスやスノーボードクロスと同様に、4人の選手がスタートラインから一斉に出発し、カヤックレールなどの操作が必要な10個のゲートや障害物でマークされたコースを駆け下る種目です。 ゲートを逃さずにフィニッシュラインを通過した最初の2人の選手が次のラウンドに進みます。
【ルール】
スラローム種目
カヤックシングル(女性/男性)
カヌーシングル(女性/男性)
カヤッククロス(女性/男性)
スプリント種目
男子カヤックシングル(K-1)1000メートル
男子カヤックペア(K-M-2)500メートル
男子カヤックフォア500メートル
男子カナディアンシングル(K-1)1000メートル
男子カナディアンペア(K-2)500メートル
女子カヤックシングル(K-1)500メートル
女子カヤックペア(K-2)500メートル
女子カヤックフォア500メートル
女子カナディアンシングル(K-1)200メートル
女子カナディアンペア(K-2)500メートル
カヌーカヤックの種目には、カヌーカヤックスプリトとカヌーカヤックスラロームという、オリンピックのプログラム一部である2つの非常に異なる種目があります。 それぞれに独自のルールがあります。 各種目は、カヤックとカヌーの2種類のボートを指します。 カヤックは座ってダブルブレードのパドルを使用しますが、カヌーヤーはボートにひざまずいてシングルブレードのパドルを使用します。
カヌーとカヤックのスラローム競技は、新しいホワイトウォータースタジアムの人工急流コースで開催されます。 スラローム競技は、最大25のゲートを通過するコースでの時間制限のあるレースで、可能な限り最速でボートをコントロールし、ゲートを見逃したり触れたりしてペナルティを受けないように注意することが必要です。 ゲートに触れるとレースタイムに2秒のペナルティが加算され、ゲートを外すと50秒のペナルティが科せられ、選手は良い結果を出すことができません。 これらのレースでは、アスリートの集中力、反応、技術が試されます。 パリ2024大会では、カヌーの急流種目が組み合わさったカヤッククロスがオリンピックデビューを果たし、4人の選手が同時に競い合う種目です。
カヌースプリントレースはフラットウォーターで行われ、さまざまな距離(女子は200メートルまたは500メートル、男子は500メートルまたは1000メートル)のスプリントが行われ、1艇につき1人、2人、または4人の選手が出場し競い合います。
爽快なスプリント、スリリングなスラローム 大きく異なる2つの見どころを取り上げてご紹介しましょう。
スプリントは、少し前までフラットウォーターレーシングと呼ばれていた種目です。 まさに平らで静かな水面で、8つのレーンが張られ、一斉にスタートしてゴールまで、まっすぐ進んでいくレースになります。 ボート競技に似ているが、漕ぎ手の向きがカヌーは前向きで、後ろ向きのボートとは逆です。 またボートの漕ぐ道具であるオールと異なり、カヌーの道具のパドルは艇に固定されていないので、細かな操作ができるのも特徴の一つになります。 距離もボートが2,000メートルであるのに対し、カヌーのスプリントは200メートルから1,000メートル、200メートルは30秒から50秒で終わってしまう。 スプリントの名の通り、短距離を全速力で漕ぎ抜ける競技で、スタートでの素早い飛び出しがポイントです。 スタートダッシュの後、水しぶきを上げながら猛スピードで水上を滑るように突き進んでいく様は迫力があり、見ていても爽快さが伝わってきます。 選手たちのリズミカルで無駄のない動きも格好がいい種目です。 とくにペア、フォーの息の合った動きは美しく、見る者を魅了します。 最後はスパート力も重要です。 白熱した戦いは、最後まで目を離せません。
カナディアンとカヤックでも注目点は異なります。 カナディアンは片側しか漕がないので、ふつうに右で漕いでいると左方向に傾いてしまうため、方向をコントロールする漕ぎ方の技術が必要です。 膝を立てた独特のスタイルとともにカナディアンの見どころになります。
カヤックは両側で漕げるため、カナディアンより速く進む種目です。 よりダイナミックなスピード感が醍醐味になります。
一方、スラロームは変化に富んだ流れのある川に、2本のポールをぶら下げたゲートを20前後設け、これに触れないように通過しながら上流から下流へと下るワイルドなタイムレースです。 ゲートに触れたり、ゲートを通過しなかったりするとペナルティの点がタイムに加算されていきます。 人が立っていられないような急流で自由自在に艇を操るテクニックが見どころです。 とくにゲートを通過するときはスリリングで、横に流されてゲートを通過できないと50秒もタイムが加算されてしまうので、可能な場合は漕ぎ戻って通過することもあります。 ゲートのうち6から7個は、上流に向かって通過しなくてはならないアップストリームゲートです。 流れに逆らって漕ぐ選手のパワーに注目してみましょう。 全体に注意深さとスピードが求められるので、見ていてもドキドキしてくるレース展開です。 選手のパワーやバランス感覚、敏捷性に加え、刻々と変化する川の流れや波の状況を見極める判断力も注目ポイントになります。 スラロームにもカナディアンとカヤックの2種類があり、カナディアンは、より細かな技術が見どころで、カヤックは、豪快さやスピードが魅力です。 競技はタイムとペナルティの加点の合計ポイントが少ない選手が上位となります。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
カヌーが盛んなのはヨーロッパです。 中でも伝統的に強いのはドイツで、これまでに金メダル21個を含む59個を獲得しています。 しかもこれは東西ドイツが1つになってからの数字です。 東ドイツ、西ドイツ時代のメダルを加えると90個になります。 ドイツのほかに、スプリントではハンガリー、ウクライナ、ベラルーシ、スペイン、ロシア、ノルウェー、スロバキア、チェコ、イギリス、ニュージーランド、スラロームでは、フランス、スペイン、スロバキア、イギリス、チェコ、オーストラリアなどの選手層が厚く、強豪です。
男子スプリント、カナディアンでは、シングル1,000メートル、ペア1,000メートルでドイツがロンドン2012大会とリオデジャネイロ2016大会で金メダルに輝き2連覇の快挙を成し遂げています。 カヤックでは、ペア1,000メートル、カヤックフォア1,000メートルでもドイツ勢が優勝している強豪国です。
女子では、スプリントカヤックシングル500メートルで2連覇中のハンガリーとニュージーランドの対決が注目されます。 ペアでもハンガリーと組んで金メダル、フォアでも2連覇を果たし、リオデジャネイロ2016大会では3冠に輝いた女王です。 女子スラロームではロンドン2012大会銅メダル、リオデジャネイロ2016大会金メダルに輝いたスペイン、東京2020大会ではドイツ、イギリス、オーストラリアなど強豪国が力を発揮しています。
スラロームは、人工のコースで行われ、流れが強くパワーが必要になるコースもあれば、比較的ゆるやかで変化に富み、細かな技術が必要になるコースもある種目です。 選手によって得意なコースのタイプが異なり、ロサンゼルス2028大会のコースが仕上がり次第、どんなコースなのか特徴を知っておくとレースの見方も変わってくるだろう。
ドイツをはじめとしたヨーロッパ勢がロサンゼルス2028大会でも力を発揮できるか注目が集まります。
カヌーは日本ではあまり関心が高い競技とはいえなかったが、リオデジャネイロ2016大会でスラローム男子カナディアンシングルで日本人初となる銅メダルを獲得し、一躍注目されるようになった競技です。 ロサンゼルス2028大会では、東京2020大会の経験を活かし、若手や熟練の技を発揮してくれる選手に期待したい。
スラローム種目 開催地
スプリント種目 開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
ボートは己の無駄ないリズムと駆引き、一糸乱れぬチームワークの勝負

ボートは進行方向に背を向け、水上の直線コースでボートを漕ぎ順位を争う競技です。 試合は水面を滑るように進むスピード感や自然の中で競技する心地良さ、解放感、全員が完全にシンクロした統一感は圧巻。 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
ボートの主な強豪国と地域:
「男子エイト:ニュージーランド、ドイツ、イギリス etc.」
「男子クオドルプルスカル:オランダ、イギリス、オーストラリア etc.」
「男子シングルスカル:ギリシャ、ノルウェー、クロアチア etc.」
「男子ダブルスカル:フランス、オランダ、中国 etc.」
「男子フォア:オーストラリア、ルーマニア、イタリア etc.」
「男子ペア:クロアチア、ルーマニア、デンマーク etc.」
「男子軽量級ダブルスカル:アイルランド、ドイツ、イタリア etc.」
「女子エイト:カナダ、ニュージーランド、中国 etc.」
「女子クオドルプルスカル:中国、ポーランド、オーストラリア etc.」
「女子シングルスカル:ニュージーランド、ROC、オーストリア etc.」
「女子ダブルスカル:ルーマニア、ニュージーランド、オランダ etc.」
「女子フォア:オーストラリア、オランダ、アイルランド etc.」
「女子ペア:ニュージーランド、ROC、カナダ etc.」
「女子軽量級ダブルスカル:イタリア、フランス、オランダ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では欧米、オセアニア、アジア勢との順位争いに野鳥たちが空を飛び、魚たちが泳ぎ始める。
己のオール捌きで、世界最高速度でのゴールを決める国と地域はどこだぁ!
【ボートの特徴】
ボート競技は、水上の直線コースでオールを使ってボートを漕ぎ、順位を争う競技です。 カヌーと逆で、進行方向に背中を向けて漕ぐスタイルで、ボートに足を固定し、レール上に設置されたシートが前後に動き、主に脚力を使って進みます。 オリンピックでは2,000メートルで行われる競技です。
シングルスカルを除き、2人以上のチームで行うため1人1人の能力も必要だが、何よりチームワークが求められます。 全員の息がぴったりと合ったときの美しさは、まさにボート観戦の醍醐味といえる瞬間です。
ボートはもともと古代エジプト、ギリシャ、ローマで輸送手段として機能していましたが、スポーツになったのは17世紀末から18世紀初頭にかけてのイギリスになります。 最初の主要なボート競技は、1829年に始まった、現在でも毎年開催されているオックスフォード アンド ケンブリッジ ボートレースです。
【オリンピック競技としての歴史】
ボート競技は、歴史が古く、1896年にアテネで開催された第1回近代オリンピック(男子)以来、すべての大会で開催されています。 しかし、この大会は海上で行われる予定だったため、その年は悪天候のため、中止になった競技です。 その後、第2回パリ1900大会から実施されており、女子種目が正式にオリンピック種目として採用されたのは、ずっと後のモントリオール1976大会になります。 オリンピックのボート競技は当初アメリカが独占していたが、その後はソビエト連邦とドイツが台頭してきた競技です。
水面に描かれる美しい航跡、究極のチームワークで一直線にゴールを目指す。
【ルール】
種目
ペア(男子/女子)
ダブルスカル(男子/女子)
フォア(男子/女子)
シングルスカル(男子/女子)
軽量級ダブルスカル(男子/女子)
ボート競技の種目は、大きく分けてダブルスカルとスイープローイングの2つの種類があり、スカルはオールを右手と左手に1本ずつ、合わせて2本持って漕ぐ競技です。 一方、スイープローイングはオールを1本ずつ持って漕ぐ競技になります。
漕ぎ手の人数で分けると、スカルにはシングル(1人)、ダブル(2人)、クオドルブル(4人)の3種類があり、スイープローイングにはペア(2人)、フォア(4人)、エイト(8人)の3種類です。
漕ぎ手漕ぎは、船に固定されたオールを使ってボートを推進させます。 他の種目とは異なり、漕ぎ手は移動方向に背を向けて座っているため、フィニッシュラインを後ろ向きに横切りるスタイルです。
漕ぎ手は2,000メートルの距離を、単独で、または2人、4人、8人のチームで競い合います。
また、種目により体重制限の設けられた「軽量級」があり、軽量級は、男子の漕手各人が72.5キログラム以下で、平均体重が70.0キログラム以下、女子は漕手各人が59.0キログラム以下で平均体重が57.0キログラム以下となっている構成です。 パリ2024大会からは男女の種目数が同じ5種目ずつになる予定をしています。
静かに、そして強いリズムで真っすぐに進むボート、スタートからフィニッシュまで目が離せないレース展開です。 ボート競技は、スタートからフィニッシュまで、艇がいかに速くたどり着くかを競うシンプルな競技になります。 しかし、実は奥が深く、魅力、見どころは多く、まずは鏡のように静かで穏やかな水面を滑るように進むスピード感、人間の力だけでこんなに速く進むのかと驚かされる速さです。
また、自然の中で競技する心地よさや解放感は見ている人にも伝わってきます。 そして、2人以上の種目では、一糸乱れぬチームワークが魅力です。 全員が完全にシンクロした統一感は圧巻、順に観戦ポイントを見ていこう。
まず、スタート、固定されたスタートポンツーン(桟橋)に船尾をつけ、合図とともに一斉に飛び出します。 序盤では各艇とも高いピッチで力を爆発させ、一気にトップスピードまでもっていき、ここではボートが加速する迫力や選手の熱気が伝わってくるレース展開です。
中盤では各艇の特徴や戦略が見えてきます。 序盤のスピードを維持すると体力が続かなくなるので、体力を温存しながら最大のスピードを出すための無駄のないリズミカルな動きが重要です。
勝負所でスパートを仕掛けることもあります。 各艇の駆け引きが見ものです。 終盤になると、一気にスピードが上がり、気力、体力を振り絞ってのデッドヒートが繰り広げられるラストスパートになります。
そして固唾を飲んで皆が見守るゴールでは、100分の1秒の差が勝敗を分けるレース展開です。 白熱したレースは最後まで一瞬も目が離せません。 チーム種目が多い中、1人で漕ぐシングルスカルにも注目です。 バランスを保ち、まっすぐに進むのが難しいといわれる種目なので選手のテクニックをよく見よう。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
ボートは欧米で人気があり競技人口も多く、アメリカ、イギリスも強いが、強豪国の筆頭はドイツです。
過去に獲得したメダル数では、東ドイツ、西ドイツ時代を加えるとドイツが100個を超えてトップになります。 リオデジャネイロ2016大会でも男女ともにクオドルブルスカルで優勝し、ほかに男子エイトでも銀メダルを獲得、男子クオドルブルスカルは2連覇です。
男子は国によって得意種目があります。 イギリスは舵手なしフォアでは、シドニー2000大会から5連覇という偉業を成し遂げ、2位につくオーストラリアは3回連続銀メダルを獲得している常連国です。
舵手なしペアとなるとオーストラリアの2連覇後、ニュージーランドが2連覇しています。 ボートの花形エイトは毎大会熾烈な戦いを繰り広げ、アテネ2004大会から、アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリスの順に勝っており、連覇は難しい状況です。
女子は近年、ドイツ以上にイギリスが強く、リオデジャネイロ2016大会では舵手なしペアで金、エイトとダブルスカルで銀メダルを獲得しています。 ロンドン2012大会でも3人の金メダルを輩出している強豪国です。 アメリカも強豪国で、エイトでは3連覇を果たしています。 東京2020大会では3連続2位のオーストラリアが金メダルを獲得し、男子舵手なしフォアが注目種目です。
女子の新種目、舵手なしフォアはオーストラリアが初の金メダルを獲得し、欧米勢以外では、近年力をつけてきた中国や南アフリカなどにも期待が集まります。
欧米勢の牙城を崩せるか?連覇を賭けた試合に注目しよう。
日本ではローイング、漕艇、端艇、競艇などと呼ばれるボート競技の人口は、欧米に比べると少ないです。 残念ながらオリンピックのボート競技でメダルを獲ったことはなく、最高で6位になります。 ただ、大学でのボート競技は盛んで、多くの大学にボート部があり、伝統的な対校戦も少なくないため、観戦スポーツとして根強いファンがいることも確かです。 また、高校においても、全国47都道府県の高校にボート部があり、国体予選には全都道府県から参加しています。
これまでのオリンピックでの日本の出場種目の多くは軽量級ダブルスカルです。 アテネ2004大会以降、それ以外で出場したのはロンドン2012大会女子シングルスカルのみになります。 前年度の世界選手権で各国の種目ごとの出場枠が決まるが、他の種目はなかなか出場枠を得られない状況です。
日本ボート協会では新人育成に力を入れていて、高校生、中学生も強化合宿に参加しています。 ロサンゼルス2028大会までに力をつけてくれることを期待したい。
開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
セーリングは己の頭脳と実行力や自然環境の変化、海面攻略との勝負!

セーリングは海面で実施される競技です。 試合は刻々と変る条件を計算し、臨機応変に戦略を組立て自然を味方に付けるセッティングや戦術、強靭な肉体と精神力でコースを攻略するダイナミックな戦いに注目。日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
セーリングの主な強豪国と地域:
「男子470級:オーストラリア、スウェーデン、スペイン etc.」
「男子49er級:イギリス、ニュージーランド、ドイツ etc.」
「男子RS:X級:オランダ、フランス、中国 etc.」
「男子フィン級:イギリス、ハンガリー、スペイン etc.」
「男子レーザー級:オーストラリア、クロアチア、ノルウェー etc.」
「女子470級:イギリス、ポーランド、フランス etc.」
「女子49er FX級:ブラジル、ドイツ、オランダ etc.」
「女子RS:X級:中国、フランス、イギリス etc.」
「女子レーザーラジアル級:デンマーク、スウェーデン、オランダ etc.」
「混合ナクラ17級:イタリア、イギリス、ドイツ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では欧米、オセアニア、アジア勢との順位争いに波風が立つ。
己の判断力で、100年目の自然環境を攻略できる国と地域はどこだぁ!
【セーリングの特徴】
ヨットはオランダで発祥し、輸送や連絡などの実用目的で活用されていたが、1660年にイギリス国王とヨーク公が初めてヨットレースを行ったのがスポーツとしてのヨットの起源と言われています。 その後、ヨット競技はおもに上流階級のレジャーとしてヨーロッパ諸国に広まり、大陸を渡ってアメリカなどにも伝わったスポーツです。
国際的なセーリングレースは、1851年にニューヨークヨットクラブのメンバーがイギリスでの競技会に参加することを決めたときに始まります。 競うために、彼らはアメリカと名付けられた101フィートのスクーナー船を建造し、イギリスに航海し、ハンドレッドギニーカップと呼ばれるトロフィーを獲得したのが始まりです。 トロフィーは、その後、この最初の国際セーリング大会を記念してアメリカズカップと改名されます。
20世紀半ばになるとアメリカでウィンドサーフィンが盛んになり、ロサンゼルス1984大会からヨット競技の一つとしてウィンドサーフィンがカテゴリーに加えられた種目です。
【オリンピック競技としての歴史】
セーリングは、近代オリンピックのあらゆる大会で種目として採用されてきたスポーツになります。 しかし、1896年4月1日にアテネで開催され、悪天候のため主催者は中止を余儀なくされた競技です。 その後、第2回パリ1900大会から実施された最初の大会になります。
それ以来、競技に含まれるカテゴリーは常に進化し、さまざまなイベントで、モノタイプクラス、つまりサイズと重量によって編成されるようになった競技です。 アトランタ1996大会では「ヨット」の呼称で開催され、シドニー2000大会から現在の「セーリング」が競技名となります。
大海原のレースを制するカギは、自然との共闘、クルーがひとつになったとき、船に命が宿るセーリング競技です。
【ルール】
種目
ウィンドサーフィン(男子/女子)
カイト(男子/女子)
一人乗りディンギー(男子/女子)
スキフ(男子/女子)
混合2人乗りディンギー
混合マルチハル
セーリングは、海面で実施され風の力だけで船を動かします。 自然環境によって大きく試合展開が左右される競技の一つです。 レースは、海面に設置されたマークと呼ばれるブイを決められた回数、決められた順序で回りながら、フィニッシュラインまでの着順を競い合います。
刻々と変化するコンディションを熟知するには、アスリートの優れたスキルと経験の両方が必要です。 オリンピックの競技では、国際セーリング連盟であるワールドセーリングのルールが適用されます。 競技はフリートレースで構成されており、2隻のボートが同じバラエティに富んだコースを走りる形式です。
東京大会では、ウィンドサーフィン、混合ナクラ17フォイル、49ers、470など10種目が行われています。 多様なセーリング分野は絶えず変化しており、競技に参加できるボートはますます小型で軽量になるように設計されており、セーラーの運動能力と技術能力の両方に、これまで以上に大きな要求が課せられている競技です。 パリ2024大会では、ウィンドサーファーのiQFoilとカイトボーディングの2種目が初めて実施されます。
種目は使用する艇(ヨット)の種類によって分けられ、どの種目もフィニッシュの順位の高いチームほど低い点数がつく形式です。 このレースを10~12回行い、その合計点数の低い10艇が「メダルレース」と呼ばれる最終レースを戦うことができます。 このメダルレースで最終順位とメダリストが決まります。
大きな三角形を描くコースで、艇は3方向からの風を体験した後、フィニッシュラインに到達し、必ずしもコースに沿って艇をまっすぐに走らせるばかりではありません。 向かい風や横風の場合は、ジグザグに走ることによって風をつかむことにもなります。 また、コースを回るには大胆な方向転換も必要で、いかに無駄なく曲がれるかも腕の見せどころです。 こうしたヨットの操縦を、クルーは自らの体の位置や向きを変えることで艇全体のバランスをコントロールしながら行います。
全員で一斉にスタートする試合方式のダイナミックさも魅力です。 一斉に海面を滑り出し、最初のマークへの一番乗りをめぐって激しくしのぎを削る最初の山場は見逃せません。 最初のマークを越えるとある程度の順位がつき、縦長に伸びた船団がフィニッシュラインに向かって抜きつ抜かれつの戦いを展開します。
環境の変化、他の船との位置関係、自分たちの艇のコンディションなど、刻々と変わるさまざまな条件を計算して臨機応変に戦術を組み立てられる頭脳と、実行に移す技術が必要です。 セーリングは他の艇との戦いだけでなく、波の高さや潮の流れ、風の強さなどの大自然との戦いでもあります。 その自然を味方につけるようなセッティングやテクニックで勝利をつかむ競技です。 強靭な肉体と精神力を持つ選手のダイナミックな戦いに注目しよう。
自然環境との「共闘」が勝利を呼ぶレースのダイナミックさは必見です。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
ロサンゼルス2028大会で実施されるのは、男女共通の4種目(計8種目)と男女混合2種目が予定されています。 これまでの大会で金メダルを最も獲得しているのはイギリスです。 ヨットレース発祥の国として、その実績は他を圧倒しています。 第2のメダル獲得国は、世界最高峰のヨットレース「アメリカズカップ」で最多優勝を誇るアメリカです。 他のメダル常連国にはノルウェー、スペイン、フランスなどヨーロッパ諸国が名を連ねるが、最近ではオーストリアとニュージーランドがヨーロッパ勢に割って入る実力をつけ、注目されています。
女子でメダルを獲得しているのは中国、スペイン、フランス、フィンランドなど様々です。
セーリング最古の種目、1人乗りのフィン級(男子のみ)ではイギリスが6連覇を果たして発祥国の両目を保っています。 古くからの強豪と新興勢力入り乱れるメダル争いは、ロサンゼルス2028大会でも繰り広げられるだろう。
日本は、アトランタ1996大会の女子470級で銀メダル、アテネ2004大会の男子470級で銅メダルを獲得しています。 この種目は乗員2名合わせて約130キログラムが適正体重とされ、小柄な選手が活躍しやすいため日本選手には「ヨンナナマル級」の呼び名で長年親しまれており、今後の成長次第では入賞、メダルに手が届くチームが現れるかもしれません。 ロサンゼルス2028大会に向けては、他の種目でも日本選手にメダルの可能性が見えてきます。 自然環境で行われるこの競技では、「地の利」がより大きく働くことが予想できる競技です。 ロサンゼルス2028大会でも日本選手の活躍に期待したい。
開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
サーフィンは自然状況を見極め、己の最高の波乗り、トリックとの勝負

サーフィンは大自然の海で行われ、波に乗って順位を争う競技です。
試合は慎重に波を選び、技の積極性や難易度、革新性と進歩性など、高度なライディングが求められ、ダイナミックに波を疾走する姿は圧巻!
日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
サーフィンの主な強豪国と地域:
「男子:ブラジル、日本、オーストラリア etc.」
「女子:アメリカ、南アメリカ、日本 etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では欧米、南米、アジア勢との順位争いに世界トップサーファー達が夢みし集う。
己のライディングで最高の波を掴み、トリックを決める国と地域はどこだぁ!
【サーフィンの特徴】
若い世代に関心が高く活気あふれる競技をオリンピックのプログラムに加えたいと、東京2020組織委員会が追加種目として提案し、新たに採用されたのがサーフィンです。
サーフィン競技が行われるのは自然の海で、波の状態は、風の強さや風の向き、潮の干満などによって変わってきます。 同じ波は2つとないため、自然の状況を見極めながら選手が、お互いに高度なライディングテクニックを競うのがサーフィン競技です。
サーフィンはハワイ発祥で、15世紀から一般的になり、ハワイやタヒチに住む古代ポリネシア人によって始められたと言われています。
板を使って波に乗るアート サーフィンを、広めたのはストックホルム1912大会とアントワープ1920大会の水泳でアメリカ代表として金メダルを獲得した、ハワイ出身のデューク カハナモクです。 近代サーフィンの父と呼ばれているカハナモクは、ストックホルム1912大会の金メダルを表彰台の上で受け取りながら、いつの日にかサーフィンがオリンピック競技になってほしいという夢を語り、その種を撒きます。
サーフィンは1950年代に進化し、新しいタイプのボードが一般の人々にとってより身近なものになり、繁栄したスポーツです。 現在、この壮大な自然を基盤としたスポーツには、5大陸で3,500万人以上の愛好家たちによって楽しまれています。
日本に集い、更にパリ2024大会で集う世界のトップサーファーたち、波の上を疾走し、ダイナミックに踊る姿は圧巻です。
【オリンピック競技としての歴史】
1920年代には、ハワイのアスリートでオリンピックのフリースタイルチャンピオンに3度輝いたデューク・カハナモクのような人々が、サーフィンをオリンピックの種目に加わるように働きかけたのが始まりになります。
それから長い年月が経ち、ついに東京2020オリンピックの種目となり、また、パリ2024大会では、タヒチの伝統的なサーフィンスポット「テアフポオ」がサーフィンイベントの会場に選ばれ開催される競技です。
競技としてのサーフィンはサーフボードのサイズや種類によって大きく2つに分けられます。 古くから親しまれたのは、長さ9フィート(約274センチメートル)以上のロングボードで、ボード上を歩くテクニックが中心です。 一方、1970年前後に登場したショートボードは、長さ6フィート(約183センチメートル)前後でボードの先端がとがっています。 こちらは細かいターンがしやすいタイプです。 ショートボードは、それまで平面的な動きだったサーフィンに縦の動きを与え、三次元のダイナミックな技が可能になります。 東京2020大会のサーフィンは、このショートボードで行い、パリ2024大会でも同じ仕様で実施される予定です。
【ルール】
種目
ショートボード(女子/男子)
サーファーは波の上でマニューバーとトリックを披露し、トリックの種類、難易度に基づいて5人の審査員が採点基準に従って1つ1つのライディングを採点して 合計点で競い合います。
採点基準はうまく波に乗れたかどうかをベースに、技の積極性や難易度、革新性と進歩性、主な技が入っているか、バリエーションはどうか、スピード、パワー、演技の流れなどが主な要素です。
オリンピックで選ばれるサーフボードは、ショートボードになります。 ロングボードよりも小さいショートボードは、より速く、より操作性が高いため、華麗なトリックを行うのに理想的なボードです。
オリンピックでは、各ヒート(試合)を4~5選手で競う予選ラウンドを勝ち抜いた選手が本戦ラウンドに進みます。 本戦ラウンドでは2選手が1ヒート(試合)を戦い、勝者が次のラウンドに勝ち進み、敗者はここで敗退する形式です。 1ヒートは通常30分程度で、その日のコンディションによってテクニカルディレクターが決定します。 各選手は時間内に25本までライディングでき、そのうちの点数の高い2本の合計がそのヒート(試合)の結果となる構成です。
海では同じ波は2つとなく、波がどのようにブレークする(崩れる)かも異なるため、波によってどれだけ得点できるかも変わってきます。 選手たちは、より多くの波に乗る、より多く技を披露することよりも、最も質の高い技を仕掛けるためにそれを可能にする波を慎重に選んで乗ることが重要です。
技に決められた点数があるわけではなく、1つのライディングで披露される様々な要素を総合的にジャッジし、得点が加算されます。
例えば、パワーなら様々な種類のカットバック、オフ ザ リップやフローターなどの技、進歩性では様々な種類のエアリアル、スライド、リバースといった技が代表的です。
サーフィンで最高の技と言われるのはチューブ状の波の中に入って乗るバレルだが、これもいくつかのテクニックや完成度によって採点が左右されます。
崩れる直前の波の頂点をピークというが、選手は自分が選んだ波に乗るためにピークにポジションを取ろうとし、同じ波に複数の選手が乗ろうとする場合、ピークに最も近い選手がその波に乗れる「優先権」を持つルールです。
海という大自然と戦う選手たち、ダイナミックな技に感動するだろう。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
東京2020大会でオリンピックデビューとなったサーフィンはパリ2024大会、ロサンゼルス2028でも実施される予定です。 2回目の大会となるパリ2024大会では、どの出場国もメダルを狙ってくるだろう。 サーフィン発展のルーツであるアメリカは長い歴史を誇り、オーストラリアは優れたサーファーを輩出することで知られ、重要な大会では常に上位に入ってくる強豪国です。 最近はブラジルの急成長が目覚ましく、ブラジルではサーフィンはサッカーに次ぐ人気スポーツになっており、「ブラジルアン ストーム」は中南米のサーフィンをけん引しています。 女子では、オーストラリアとアメリカが何十年もトップを独占してきた競技です。
強豪は、やはり発祥の地アメリカ、それともヨーロッパ諸国が力を発揮するか、まずは出場選手に注目が集まります。
日本は、日本サーフィン連盟を中心に、75名の強化指定選手を選出(2019年)し、そのうち次期世界大会で4位以内に入る可能性が高いA指定は男子8名、女子6名(2019年度)と選手層が増えつつあります。 東京大会でも男女とも出場し、特に女子は本番に強く、底力を発揮し銅メダルを獲得した活躍ぶりです。 ロサンゼルス2028大会でも、ニッポン サーフィンの仕上がり具合が気になります。
開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
空手は選ばれし選手達の駆け引きと集中力、己の技と流麗な演武の勝負

子供の心身を育む空手は日本 沖縄を発祥とし、東京2020大会で初披露された競技です。演武にはドラマティックな「形」の仮想演武と、一瞬たりとも目が離せない「組手」が行われ、静と動を感じる格闘技に注目!日本勢や世界各国が激しい勢いで選手強化に取り組む。
世界状況
空手の主な強豪国と地域:
「女子形:スペイン、日本、イタリア、ホンコン チャイナ
男子形:日本、スペイン、アメリカ、トルコ
女子組手 55キログラム級:ブルガリア、ウクライナ、オーストリア、チャイニーズタイペイ
女子組手 61キログラム級:セルビア、中国、トルコ、エジプト
女子組手 +61キログラム級:エジプト、アゼルバイジャン、カザフスタン、中国
男子組手 67キログラム級:フランス、トルコ、カザフスタン、ヨルダン
男子組手 75キログラム級:イタリア、アゼルバイジャン、ウクライナ、ハンガリー
男子組手 +75キログラム級:イラン、イスラエル、サウジアラビア、トルコ、日本 etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。ロサンゼルス2028大会では開催されない順位争いに目には見えない仮想空間が展開される。
時空を超え、己の仮想空間で、華麗な技を繰り出す国と地域はどこだぁ!
【空手の特徴】
空手は流れるような美しい演武、電光石火の攻撃、静と動を感じる格闘技です。 「形」のドラマティックな演武と「組手」の目にも止まらぬ速さの攻撃に注目しよう。 各国の熾烈な代表争い、選び抜かれた選手たちによる激しい戦いが始まります。
空手は琉球王朝時代の沖縄を発祥とする武術、格闘技です。 1920年代に沖縄から日本全国に伝えられ、第二次世界大戦後に世界に広まります。 空手は大きく分けて2種類、「形」と「組手」がある競技です。
【空手の種目には】
形は、仮想の敵に対する攻撃技と防御技を一連の流れとして組み合わせた演武で、2019年1月からルールが改定され、7名の審判による採点で勝敗が決まります。 予選は演武を1人ずつ行い、上位が決勝に進む形式です。 決勝は同じく採点方式だが1対1の対戦形式で行われます。 また、演武する形は世界空手連盟(WKF)が認定している102種類から選択して行う形式です。
組手は、8メートル四方の競技場で2人の選手が1対1で戦います。 白い無地の空手着を着用し、一方の選手は赤帯、もう一方は青帯を締めて行う競技です。 攻撃の際に使える技は「突き」、「蹴り」、「打ち」の3種類になります。 攻撃は相手の決められた部位に対して、良い姿勢で威力のある攻撃を行い、適切にコントロールされた技がポイントとなる仕組みです。 ポイントは、「有効」が中段への突き、上段への突きなどによるもので1ポイント、「技あり」は中段への蹴り、「1本」は上段への蹴り、倒した相手への突きなど が決まったときで3ポイントとなっています。 攻撃部位の「上段」は頭部、顔面、頸部を指し、「中段」は腹部、胸部、脇腹などを示す箇所です。
空手の組手の「1本」は柔道とは異なり、その場で試合が終了するわけではなく、競技時間内に8ポイント差がついたとき、または男子、女子ともに3分の競技時間が終了した際にポイントの多い選手が勝者になります。 この他には、棄権、反則、失格があった場合その相手選手を勝者とする形式です。 同点の場合は先にポイントを獲得(先取)していた選手が勝者となる、というルールがあり、勝敗の決め方はこの4種類になります。 反則は、コントロールせず故意に攻撃部位に当てる「過度の接触」、腕や関節、股間、足の甲など「禁止部位への攻撃」、負傷を装ったり誇張したりすること、繰り返し場外へ出る、自己防衛ができない「無防御」、攻撃せず逃げる、頭部、肘、膝での攻撃などです。
【空手種目の特徴とは】
「形」は
競技としての形は、空手の技の意味を正しく表現することになります。
見どころは、突きや蹴りの力強さやスピード、リズム、バランス、パワーなどであるが、動きがブレないこと、キレと迫力があること、そして技の意味を正しく表した美しい流れがあることも評価のポイントです。
緩と急、強と弱、そして集中が伝わってきます。
仮想とはいえ敵と戦うことを前提とした演武であることから、相手を倒す意気込みが伝わってくるかどうかに注目してみよう。
トップ選手の演武にはドラマがある競技です。
演武である形は、仮想の相手に対する攻撃と防御で構成され、それが一連の流れとして組み立てられています。 一度行った形は同じ試合では二度と使えないため、選手は予選から決勝まで勝ち上がっていくために4種類の形を身につけて臨む必要がある種目です。 しかし、それぞれの選手には得意不得意があると同時に、自分が最も得意とする形を持っています。 その決め手となる形を早い段階で使うか、決勝まで残しておくか、あるいは強い相手と当たる時に使うか、などの駆け引きに注目です。 早く使ってしまっては上位の選手との対戦では使えなくなります。 決勝まで使わずに温存しておこうとすると、それまでに負けてしまう可能性もある種目です。 その選手にとって全力で勝負すべき対戦が、必ずしも決勝ではないことがあります。 形の種類を選択する選手の作戦、駆け引きに注目しよう。
「組手」とは
組手の最大の見どころは、爆発的なエネルギーで繰出される突きや蹴りが相手の目的部位を確実にとらえる、つまり攻撃が決まる瞬間です。
技は目にも止まらぬスピードで繰出されるので、その一瞬を見逃さないようにしましょう。
しかし、組手の魅力はその瞬間だけではなく、攻撃に至るまでの選手同士の駆け引きに注目が集まります。
相手と対峙する際、互いに攻撃されない、あるいは攻撃されても防御できる位置取りを間合いというが、攻撃するには間合いに入って相手に近づかなくてはなりません。 それは自分にとって攻撃できる位置であると同時に、相手から攻撃を受ける位置に入ってしまうことを意味します。 間合いに入った瞬間、一気に試合が動き、矢のような速さで突きや蹴りが繰出され、決まる場合もあれば、防御され逆にカウンターを食らうこともある種目です。 その瞬間を決して見逃さないように、一瞬たりとも目が離せないのが組手になります。 東京2020大会では、男女各3階級、計6階級で行われた競技です。
【未来20XX大会に向けた展望】
世界空手連盟(WKF)の加盟国、地域は194を数えます。 強豪はフランス、スペイン、イタリア、ドイツ、トルコなどのヨーロッパと、イラン、エジプトなどの中東諸国です。 東アジアではベトナム、タイも力をつけています。
空手の発祥国である日本は、数年前まで上位に食い込む選手が少なかったが、数年前からメダル圏内に位置する選手が増えてきた競技です。 組手は、まさに群雄割拠の様相を呈しています。 2016年の世界選手権では20ヵ国以上がメダルを獲得している状況です。
形も多くの国の選手がメダルを狙える位置にいるが、ここ数年、男女とも日本が世界のトップをキープしています。 形も組手同様、多くの国が激しい勢いで選手強化に取り組んでおり、激戦は必至です。
東京2020大会に出場する選手は、形が男女の2種目、組手が男女各3階級、合計8種目に各10人、計80人になります。 2018~2019年の世界ランキングをもとに決定されるのだが、1つの国、地域からは1名しか出場できないため、強豪国の選手にとってはオリンピックに出場すること自体が難しいです。 ランキングを左右する“国際大会”から目が離せません。
地元開催オリンピック大会での日本発祥競技の初披露であるため、日本では金メダル獲得に向けた強化に全力を注ぎ、 世界のトップを走る20歳台半ばの選手に続く若手の選手も育ってきています。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
柔道は己の冷静な一瞬の駆引きと組手争い、気迫の一本が勝負の決め手

柔道は体重別で行われ、哲学的原則で身体と知能、道徳的厳密さを組合せた競技です。試合は漲る気迫と豪快かつ熱い技が繰出され、全ては「一本」のために全身全霊の力を出し尽くす、熾烈な戦いに注目!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
柔道の主な強豪国と地域:
「男子:日本、チャイニーズタイペイ、カザフスタン、フランス、ジョージア、韓国、ブラジル、モンゴル、オーストリア、ベルギー、ドイツ、ハンガリー、ウズベキスタン、ポルトガル、ROC、チェコ共和国 etc.」
「女子:コソボ、日本、モンゴル、ウクライナ、フランス、イギリス、イタリア、カナダ、 スロベニア、オーストリア、ROC、オランダ、ドイツ、ブラジル、キューバ、アゼルバイジャン etc.」
「混合チーム:フランス、日本、イスラエル、ドイツ」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。ロサンゼルス2028大会は欧米や中南米、中東、アジア諸国勢との漲る気迫の順位争いに一瞬足りとも目が離せない。己の柔道を極めた国と地域はどこだぁ!
日本発祥の柔道は1882年に嘉納治五郎博士が最初の学校「道場」を開校し、柔術から派生した武術のスポーツ競技です。 柔道は伝統的なレスリングスポーツで、かなりの肉体的努力を必要とします。
試合は白か青の柔道着を着用した選手が10メートル四方の畳の上で戦い合う方式です。 どちらかの選手が一本を取れば、その時点で試合は終了し勝敗が決まります。 もしも、技が決まり相手を制することができても、“一本”となる全ての要件を満たさないときは“技あり”の判定です。
【オリンピック競技としての歴史】
柔道の創始者である嘉納治五郎は、日本で初めて国際オリンピック委員会の委員に就任し、日本をオリンピック初出場「ストックホルム1912大会」に導き、さらに東京1940大会招致を成功させます。
その東京1940大会は戦争のため開催されなかったが、再び東京1964大会を招致させて、オリンピックデビューを果たし、男子の正式競技として採用された競技です。 その際、日本の全階級金メダル独占を阻止したのは、無差別のオランダになります。 柔道はミュンヘン1972大会からは常設種目となり、オリンピックの柔道に女子の種目が正式採用されたのは、バルセロナ1992大会からで、強豪国の傾向は男子とほぼ同じです。
柔道は20世紀後半にヨーロッパ、特にフランスで発展し、日本国外で広く実践された最初の武道になります。 以来、柔道発祥の地、日本以外では、フランス、ロシア、オランダ、イタリアなどのヨーロッパ勢、韓国、中国、モンゴルなどのアジア勢、そしてキューバ、ブラジルなどの中南米の国、地域が強いです。
東京2020オリンピックでは、柔道が初めてオリンピックで導入されて以来、128ヵ国ものオリンピック委員会が柔道競技に出場するなど、世界中で大きく発展しています。 日本は今大会で圧倒的な強さを見せており、日本の柔道選手は96個のメダルを獲得し、フランスの柔道選手は57個、韓国の柔道選手は46個と大きな成功を収めている競技です。
【柔道の技とは】
柔道の技は100種類存在し“68”の「投技(なげわざ)」と“32”の「固技(かためわざ)」の2種類に分けられます。
「投技」は背負投(せおいなげ)や体落(たいおとし)などの手技(てわざ)、袖釣込腰(そでつりこみごし)や払腰(はらいごし)などの腰技(こしわざ)、大外刈(おおそとがり)や内股(うちまた)などの足技(あしわざ)、そして巴投(ともえなげ)に代表される捨身技(すてみわざ)です。
「固技」は一般に寝技(ねわざ)ともよばれる抑込技(おさえこみわざ)、送襟絞(おくりえりじめ)のような絞技(しめわざ)、腕挫十字固(うでひしぎじゅうじがため)などの関節技(かんせつわざ)があります。
柔道の技は一瞬のうちに繰り出され、勝敗が決する熾烈な戦いです。 試合中は熱い技の応酬と相手の隙をつく冷静な駆け引きで、一瞬足りとも気が抜けない4分間に圧巻されます。 また、ポイントで負けていても終了数秒前に大逆転があり得る大激動試合に期待が高まる競技です。
【柔道の階級とは】
体重別に行われるオリンピックの柔道では、男女とも軽量級(男子73キログラム級以下、女子57キログラム級以下)でアジア人選手が比較的多く活躍しています。 このクラスの特徴は、スピードが速いこと、軽いフットワークで、一瞬のうちに相手の懐に入って投げに入る、全く目が離せないのが、このクラスです。
パワーとスピードを併せ持つ中量級(男子81キログラム級から90キログラム級、女子63キログラム級から70キログラム級)は、男子は日本を始め、オーストリア、オランダ、グルジアなどのヨーロッパ勢が強さを誇っており、女子はフランス、日本、キューバなどがメダル獲得の常連と言われています。
重量級(男子100キログラム級以上、女子78キログラム級以上)は、スピードよりパワーを全面に出した選手が多く勝ってきた競技です。 しかし、最近では、このクラスにも速く動ける選手が増え、重量級といってもただ体重があれば勝てるというわけではなく、かなりの練習量をこなしスタミナをつけた選手にこそ勝つチャンスがあります。 このクラスでは日本とフランスが強いです。
オリンピック柔道の主な階級(男女各7階級)
男子: 60kg級、66kg級、73kg級、81kg級、 90kg級、100kg級、+100kg級
女子: 48kg級、52kg級、57kg級、63kg級、 70kg級、78kg級、+78kg級
混合団体
オリンピックの柔道は体重別で行われ、全ての階級で積極的な戦いに白熱し、更にルール改正でより攻撃的になります。
軽量級クラスの特徴:
①スピードが速いこと
②軽いフットワークで相手の懐に一瞬のうちに入って投げに入る。
中量級クラスの特徴:
①パワーとスピード
②力強いフィジカルと素早く動けるフットワークに圧巻する。
重量級クラスの特徴:
①スピードよりパワー
②速く動けて、練習量を増やしスタミナをつけた選手に勝つチャンスがある。
柔道は哲学的原則で身体的と知的、道徳的厳密さを組み合わせ、柔術が持つ危険な側面の多くを排除した武術です。
東京2020大会から、新種目として「混合団体」が追加され、男女それぞれ3人、合計6人がチームを組んで戦い、ロサンゼルス2028大会も同様に予定されることだろう。 階級は、男子73キログラム級、90キログラム級、+90キログラム級、女子57キログラム級、70キログラム級、+70キログラム級です。 この種目で強いと予想されるのは、日本やフランスのように全階級に強豪選手を擁するチームになります。
【柔道の判定(ルール)とは】
柔道における最高の判定は一本になり、主審が一本を宣告した瞬間に試合は終了し勝負が決する競技です。 全ての柔道選手が狙うのが一本で、非常に難しく選手たちは、そのために死力を尽くす気迫が伝わってきます。
投技の一本は、インパクト(強さ、速さ、背中をつける)がある形で相手を投げた場合に与えられ、豪快に投げて一本が決まる瞬間は見ていてとても美しく気持ちがいいものです。
十分に相手を制して投げた一本のインパクトにおける条件のうち、どれか1つが欠けていた場合は“技あり”になります。 柔道の投技は、技を掛ければ相手が倒れてくれるものではなく、まずは相手の体勢を崩すことが重要です。
そのためにまず、組み手争いから試合が始まり、自分の有利な組み手になれば、相手の体勢を崩し、技に持ち込みやすくなります。 逆に、相手に有利な組み手を取られると自分が不利になるので、組むことを嫌がる選手もいる競技です。
固技は、技の要件が揃った瞬間に主審が「おさえこみ」と宣言し、そこから10秒で“技あり”、20秒で“一本”になります。 選手同士の足が絡まった状態では「おさえこみ」とならないため、逃げる選手は足を絡めようとし、技を掛ける側は足を抜こうと必死です。 重量級では、「おさえこみ」から抜けることが難く、固技のうち絞技や関節技では、技を掛けられた選手がダメージを受けることがあり、「まいった」を宣言することがあります。 この場合は、技を掛けた選手に“一本”が与えられる判定です。
柔道は男女で階級分けされ、どちらの選手も一本を取れずに4分の試合時間が終了した場合は、「技あり」を決めていた方が優勢勝ちになります。 優劣がつかない場合は延長戦に突入です。 なお、消極的行為や柔道の精神に反する行為に対して罰則が科せられることがあります。
全ての選手は“一本”を取るために戦略を考えますが、こだわるあまり相手にチャンスを与えてしまう可能性があり、勝つためにはあえて美しくない戦い方をする選手もいる競技です。 選手たちのすべては一本のために、柔道の勝負は熾烈を極め、みなぎる気迫、一瞬できまる豪快な投げ、そして全ての力を出し尽くす激しい戦い合いから目が離せません。
2016年末、国際柔道連盟(IJF)が行ったルール改正により、試合時間は男子が1分短縮され、男女とも4分間となり、技の判定基準が“一本”、“技あり”だけになります。 固技では技ありまでの時間が15秒から10秒に短縮され、より攻撃的に一本を狙っていく柔道を目指した変更であり、選手にとっては積極的に攻める姿勢が必要となってくるだろう。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
日本柔道選手にとっては、オリンピックで勝つよりもオリンピックに出場することの方が難しいと言われ、それだけ選手層が厚いのが特徴です。 日本はオリンピックの柔道で累計96個のメダルを獲得し、日本の競技別獲得金メダル数では、柔道が最多になります。 これまで日本は「一本を取る柔道」にこだわってきたが、最近では、同じ一本を取るにしても、選手の戦い方が多様化している傾向です。
リオデジャネイロ2016大会では、日本の男子は金メダル2つを含む7階級全てでメダルを獲得し、女子は金メダル1つを含む5階級でメダル獲得しています。 科学的なデータを使用しながら、個々の選手に寄り添って指導をしてきたことが効果を生んだ結果です。
柔道はオリンピックの前半に開催され、日本選手団金メダル第1号をとってチームを勢いづかせることができます。 東京2020大会では、日本柔道は金メダル9個を含む11メダル獲得し、大成功を収めた競技です。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
フェンシングは己の技を駆使した駆引き、一瞬の隙を撃つ刹那の勝負!

フェンシングは欧州発祥とされた剣術で、お互いの有効面を攻防する競技です。試合は照明が落され、瞬きも許されないほど緊迫感に満ち、間合いを詰めた接近戦での華麗な剣さばきに注目!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
フェンシングの主な強豪国と地域:
「男子エペ個人:フランス、ハンガリー、ウクライナ、男子エペ団体:日本、ROC、韓国、男子サーブル個人:ハンガリー、イタリア、韓国、男子サーブル団体:韓国、イタリア、ハンガリー、男子フルーレ個人:香港 チャイナ、イタリア、チェコ、男子フルーレ団体:フランス、ROC、アメリカ etc.」
「女子エペ個人:中国、ルーマニア、エストニア、女子エペ団体:エストニア、韓国、イタリア、女子サーブル個人:ROC、フランス、女子サーブル団体:ROC、フランス、韓国、女子フルーレ個人:アメリカ、ROC、女子フルーレ団体:ROC、フランス、イタリア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。ロサンゼルス2028大会では欧米やアジア諸国とのプライドを賭けた順位争いにアン ギャルドする。己の技とスタイルでフェンシング界の名門に乗り込き、歴史に名を刻む国と地域はどこだぁ!
【フェンシングの特徴】
フェンシングは、2人の選手が向かい合い、片手に持った剣で互いの有効面を攻防する競技です。 種目はフルーレ、エペ、サーブルの3種目があります。 使用する剣の形状や、得点となる有効面、優先権の有無などが種目ごとに異なっており、 ピストと呼ばれる伝導性パネルの上で行われる競技です。
フェンシングの魅力は、両選手が繰り広げる精密な技の応酬と瞬時の駆け引きで、間合いを詰めた接近戦での華麗な剣さばきが見どころになります。 照明が落とされた試合場で繰り広げられる激しい攻防は、瞬きも許されないほどの緊迫感に満ちている試合展開です。
フェンシング競技は、最速の剣士による刹那の勝負、一瞬の隙を狙い撃つ試合展開になります。 精密な技の応酬や瞬時の駆け引き、華麗な剣さばきに注目しよう。
【フェンシングの歴史】
フェンシングの起源は、紀元前1190年頃にさかのぼり、何千年も前から行われてきた剣術です。 その後、軍事練習の一形態であったフェンシングは、フランスやイタリア、ドイツのフェンシングマスターの衝動の下でスポーツになります。 フェンシングは今や世界中で行われており、ヨーロッパだけでなく、アジア、オセアニア、アメリカ、アフリカでも激しい競争が繰り広げられており、国際フェンシング連盟には157の連盟が加盟しているスポーツ競技です。
【オリンピック競技としての歴史】
オリンピックでは、フェンシング競技は第1回アテネ1896大会で男子フルーレ個人と男子サーブル個人が採用されて以来、各大会において欠かすことなく実施されています。 女子種目としてはパリ1924大会から女子フルーレ個人、アトランタ1996大会から女子エペ個人、アテネ2004大会から女子サーブル個人が実施されるようになったフェンシング競技です。 以前は、アトランタ1996大会で女子エペ個人が追加されるまで、フルーレ個人が唯一の女子フェンシング種目でしたが、アテネ2004大会では女子サーブルが初めて追加されます。 東京2020大会では、フルーレ、エペ、サーブルの3種目において、男女とも個人、団体の全12種目が実施され、ロサンゼルス2028大会でも同じく行われる予定になるだろう。
【ルール】
フルーレ、エペ、サーブルの相違点の一つは、得点となるターゲットの範囲、つまり「有効面」になります。 フェンシングでは、片手に剣を持った2人の競技者が向かい合って、体の有効なターゲット領域に攻撃を行う競技です。
使用する剣の種類によってルールが異なり、フルーレは背中を含む胴体(体幹である胴体、肩、首)のみを対象とし、エペはマスクから足まで全身を対象とし、サーブルは頭や両腕を含む上半身が有効面となっています。 判定には電気審判機が用いられ、一方または両方の選手が有効面に突きや斬りを決めた場合、審判機に赤色や緑色のランプが点灯する仕組みです。
そしてフルーレとサーブルには「優先権」というルールがあります。 先に腕を伸ばして剣先を相手に向けたり、先に前進したり、剣を叩いたりした選手が優先権を獲得する形式です。 対戦相手は相手の剣を払ったり、叩き返したりして優先権を奪い返すことができ、すかさず反撃に転じます。
この優先権の奪い合いを魅力とするフルーレ、サーブルに対し、エペには優先権というルールがなく、全身が有効面であり、対戦相手のどこにでも先に突けば得点となる単純明快さが大いなる魅力です。 両者同時に突いた場合は、双方に得点が入ります。
頭の天辺から足の裏までが的であるため、意表をついて足先を突くといった、変化に富む試合が展開される種目です。 さらにフルーレとエペは、剣の先の「突き」だけが得点となるが、サーブルでは「突き」に加えて剣身で触れる「斬り」の動作も得点となります。 フルーレ、エペの精度の高い剣さばきに加え、サーブルの斬る動作を含んだ剣さばきは豪快さが感じられる種目です。
【試合展開】
試合は、男子、女子それぞれ個人戦と団体戦が実施されます。 個人戦トーナメントでは、3分×3セットのうち、15点先取した選手か、または試合終了時により得点を多く取った選手が勝利となる対戦形式です。
団体戦は1チーム3名(+1名の交代選手)による総当たり戦で、3分×9セットのうち、45点先取したチームか、または試合終了時による得点を多く取ったチームが勝利となります。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
フェンシングの原型は、ヨーロッパで発祥し、発達した剣術です。 アン ギャルド(構え)、アレ(始め)などの審判用語をはじめ、公用語としてはフランス語が使われています。
当然ながらヨーロッパの競技人口は多く、特にフランス、イタリアでは伝統と実績を積み重ね、ロシア、ハンガリーといったヨーロッパ諸国も歴史に刻まれる選手を多く輩出している国々です。 しかし、近年、アメリカの選手たちがオリンピックや世界選手権で着実に結果を残しており、リオ2016大会を契機として中南米の活躍も注目されています。 アジア、オセアニアもヨーロッパに次ぐ加盟国を誇り、世界レベルの大会で上位にランクインされる選手が出てきている加盟国です。 追ってアフリカ諸国からの参加も見え始め、ヨーロッパ主流のスポーツからユニバーサリティを重視するスポーツへと進化し始めています。
フェンシングには、高身長を生かして遠い間合いからの攻撃を得意とする選手もいれば、スピードやタイミングを駆使して近い間合いでの戦いを得意とする選手もいる競技です。
伝統的なスタイルを繰り広げる選手や、革新的なスタイルを生み出す選手たちと、東京2020大会では、独特な個性や特性を持ち合わせた選手たちが、フェンシングの新たな境地を織りなし、ロサンゼルス2028大会でも個性的なスタイルを繰り広げ、メダル獲得に世界各国が闘志を燃やすことだろう。 伝統と実績を誇る強国イタリア、フランス、ロシアに、成長著しいアメリカ、中国、韓国が迫る強豪勢力図に各国が食い込む。
日本ではフルーレが主流であるが、ジュニア(17~20歳)やカデ(13~17歳)世代のエペ、サーブルの育成や強化に取り組んだ結果、3種目とも競技レベルが徐々に向上してきています。 2020年の活躍、いわゆる東京世代の選手も実績を残し始めており、新たなスター選手の登場に期待が高まりそうです。
フェンシング開催会場
※東京2020大会関連資料より、参考元:
レスリングは体格の差に関係なく、己の体一つで最強を勝ち取る勝負!

レスリングは人類最古の格闘技と言われ、パワーとスピード、テクニックが激突する競技です。試合は、選手同士が技を掛け合って相手を組み伏せ、両肩をマットに押しつけようと競い合う姿に注目!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
レスリングの主な強豪国と地域:
「男子グレコローマン:キューバ、ジョージア、ROC、トルコ、日本、中国、イラン イスラム共和国、ウクライナ、ドイツ、エジプト、ハンガリー、キルギスタン、アゼルバイジャン、セルビア、アルメニア、ポーランド etc.」
「男子フリースタイル:アメリカ、ジョージア、トルコ、イラン イスラム共和国、ROC、キューバ、イタリア、インド、カザフスタン、日本、アゼルバイジャン、インド、ベラルーシ、ウズベキスタン、サンマリノ etc.」
「女子フリースタイル:日本、キルギスタン、ウクライナ、ブルガリア、中国、アメリカ、アゼルバイジャン、ベラルーシ、モンゴル、ナイジェリア、ドイツ、トルコ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。ロサンゼルス2028大会では欧米や中東、アジア勢との一瞬の隙をついた順位争いに世界中から歓声が沸き起こる。己の体一つで、人類最古の格闘技の歴史に名を刻む国と地域はどこだぁ!
【レスリングの特徴】
レスリングは、最古ではないにしても、最も古いスポーツの一つです。 レスリングの魅力は、何の道具も持たず、衣服をつかむこともせず、体同士がぶつかり合い、技を掛け合うシンプルな競技にあります。 試合中は、パワーとスピード、テクニックが激突し、2人の選手が互いに技を掛け合って相手を組み伏せ、両肩をマットに押しつけようと競い合う展開です。 レスリングは己の体一つで戦う格闘技で、相手をマットに沈めて最強を勝ち取る勝負になります。
【レスリングの歴史】
レスリングは、シュメールの彫刻と低浮き彫りが発見され、紀元前3,000年以前にさかのぼり、力士が描かれており、紀元前708年の古代オリンピックでも行われ、オリンピックの伝統が染み込んだ人類最古の格闘技と言われている競技です。
当時、レスリングは五種競技の重要な種目であり、最後に開催されたため、五種競技の勝者に指定され、オリンピックの中に戴冠した唯一のアスリートと称えられています。 現代のレスリングは、古代のスポーツをベースにしたレスリングスタイルであるグレコローマンスタイルと、より現代的な形式であるフリースタイルレスリングの2つの別々の分野で構成されている競技です。
【オリンピック競技としての歴史】
最初の近代オリンピックは第1回アテネ1896大会から行われて以来、ブルーリボンのオリンピック種目となり、第2回パリ1900大会を除き継続して実施されています。 ロンドン1908大会にはオリンピックの正式種目となった競技です。 フリースタイルレスリングは、数年後のセントルイス1904大会でデビューし、アントワープ1920大会以来、オリンピックのプログラムに採用されている種目になります。
腰から下を攻撃と防御に使うことが禁止されているグレコローマンスタイルと、全身を攻撃と防御に使えるフリースタイルがあり、長い間、男子のみの競技だったが、アテネ2004大会から女子フリースタイルもオリンピック種目として新たに加わった競技です。
体重による階級別で試合が行われるため、体格の差に関係なく活躍できる試合形式になります。 リオデジャネイロ2016大会では男子グレコローマン、男子フリースタイル、女子フリースタイルとも6階級(6種目)で行われ、試合は敗者復活戦のあるトーナメント方式で行われる競技です。 決勝に進んだ選手と直接対戦して負けた選手は敗者復活戦に出場できます。
ROCの選手は、金メダル62個を含む116個のメダルを獲得し、アメリカチームの選手は金メダル57個を含む142個のメダルを獲得している強豪国です。 日本は女子レスリングで最も成功した国であり、金メダル24個のうち15個を獲得しています。
【ルール】
それぞれのレスリングスタイルには独自のルールが設けられている競技です。 グレコローマンスタイルは、競技者は腕と上半身のみを使って攻撃することができます。 フリースタイルレスリングは、競技者も足を使い、腰の上または、下に相手を保持できる、はるかにオープンな競技フォームです。 ただし、目的はどちらのスタイルでも同じになります。
試合は直径9メートルの円形マットの競技エリア上で行われ、3分間×2ピリオドで、間に30秒のインターバルが設けられている試合時間です。 相手を組み伏せて両肩を押さえずに、素手で同時に1秒間マットの上に固定、つけると勝ちとなり、試合は終了します。 これをフォールと呼び、試合中にフォールが確保できない場合は、相手を不利な状況に追い込む(一般的なテイクダウンとリバーサルムーブ)ことによってレギュレーションタイムの終わりに、最も多くのポイントを獲得した方が勝ちです。
グレコローマンは8点差、フリースタイルは10点差がついた場合も、その場で試合終了となりテクニカル フォールとなります。 相手が警告を3つ受けた場合も、その時点で勝ちです。 警告は消極的な姿勢や反則に対して与えられます。 ポイントは技に応じて1点、2点、4点、5点が設定されている配点です。
例えば相手の足が場外に出たら1点、寝技の状態で相手の背後に回り込んで、頭部、両手両足のうち3つをマットにつけると2点、腹這いの相手に後ろから組みついて90度以上回転させると2点、立った状態からの投げ技は4点、寝技の状態からの投げ技は5点などがあります。
【レスリングの試合】
ダイナミックな技が見られるグレコローマン、スピード感あふれる技が魅力のフリースタイルの2種目が実施される予定です。
男子グレコローマン(60、67、77、87、97、130キログラム)、男子フリースタイル(57、65、74、86、97、125キログラム)、女子フリースタイル(50、53、57、62、68、76キログラム)
グレコローマンは、立ち技(スタンド)からスタートし、ここから、いかに攻撃スタイルに持ち込めるかが重要になります。 相手選手が消極的と判定されたときは1点が与えられ、グランドからの攻撃権が与えられる種目です。 グレコローマンスタイルは、上半身で組み合って投げ技などダイナミックな技が多く見られ、本来の格闘技らしい迫力が魅力になります。
フリースタイルはタックルで相手のバランスを崩すことが基本で、スピード感あふれる技の攻防が見どころです。 負けている試合の残り、あと数秒というところで、相手の一瞬の隙をついてタックルに持ち込み鮮やかなフォール勝ちを決めたり、投げ技でテクニカル フォール勝ちになったりすると、観客から歓声と拍手が沸き起こります。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
東京2020大会では、レスリングの出場選手数は男子各スタイル96選手、女子96選手、合わせて288選手と決定し、リオデジャネイロ2016大会の344選手から56選手も少なくなり、出場は「狭き門」です。 1階級16選手での闘いとなり、果たして、ロサンゼルス2028大会での出場選手数は男女合わせて何百名で実施されるのか気になります。
レスリングは、ロシア、アメリカ、日本、トルコなどの国が伝統的に強く、現在男子はロシア、キューバ、ジョージア、アゼルバイジャン、トルコ、イラン イスラム共和国などの選手層が厚いです。
女子は日本の強さが目立っており、リオデジャネイロ2016大会では、女子6階級のうち金メダル4個を日本が獲得し、東京2020大会では男子、金メダル1個、銀メダル1個、銅メダル1個、女子、金メダル4個を獲得し、男女ともメダルラッシュが続く試合展開になります。 ロサンゼルス2028大会では男女ともいくつのメダルが獲得できるか注目が集まる競技です。
日本女子は若手を含め、選手層の厚さは世界一といわれ、男女とも、これから世界のトップレベルに育つ選手の台頭が望まれます。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
ウエイトリフティングは精神統一と驚異の爆発力、己の限界に挑む勝負

ウエイトリフティングはバーベルを持上げ、最高重量の合計を争う競技です。 試合は一瞬に競技人生を懸けた選手達の集中力とスピード、気合の全てを最高状態に仕上げ、驚異のパワーを発揮し記録に挑む姿に注目! 日本勢は限界に挑む。開催国アメリカ勢は。
世界状況
ウエイトリフティングの主な強豪国と地域:
「男子:ウズベキスタン、アルメニア、ラトビア、ジョージア、イラン・イスラム共和国、シリア・アラブ共和国、中国、インドネシア、カザフスタン、コロンビア、イタリア、ベネズエラ、ドミニカ共和国、カタール etc.」
「女子:中国、インド、インドネシア、フィリピン、カザフスタン、チャイニーズタイペイ、トルクメニスタン、カナダ、イタリア、エクアドル、アメリカ、メキシコ、ドミニカ共和国、イギリス etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。
ロサンゼルス2028大会では一瞬の勝負の順位争いに全身が力む。
己を超えたウエイトリフティングができる国と地域はどこだぁ!
【ウエイトリフティングの特徴】
ウエイトリフティングは、両手でバーベルを握り、一気に頭上まで持ち上げて立ち上がる「スナッチ」とプラットファーム(床)からいったん鎖骨の位置までバーベルを持ち上げ(クリーン)、次の動作で頭上に押し上げる(ジャーク)「クリーン&ジャーク」の2種類があります。 これらを、それぞれ3回ずつ行い、それぞれの最高重量の合計を競うのが、ウエイトリフティングです。 バーベルにかかる重圧、自らの限界に挑む者だけが栄冠を勝ち取れる競技になります。
ウエイトリフティングは、スポーツとして何千年も前から行われ、目的も変わっていません。 ウエイトリフティングの原型は、古代エジプトとギリシャまで、さかのぼり、競技者は重い石を持ち上げる力比べのコンテストで、古代より世界の多くの地域で行われてきたスポーツです。 その後、ウエイトリフティングは、19世紀に国際的なスポーツとして再登場します。
【オリンピック競技としての歴史】
オリンピックでの歴史も古く、近代史上初めて開催された、第1回アテネ1896大会で採用され、実施された競技です。 ただし、アテネ1896大会、セントルイス1904大会ではウエイトリフティングは、現在と異なるテクニックで実施され、両手で持ち上げる種目のほか、片手のみで持ち上げる種目があり、体重別の階級がありません。
その後、ウエイトリフティングは、1900年、1908年、1912年の数回のオリンピック種目から除外されましたが、アントワープ1920大会で再導入され、体重別の階級が設定され、モントリオール1976大会から現在のスナッチとクリーン&ジャックの2種目に整理されます。
20世紀初頭、ヨーロッパ諸国、特にドイツ、オーストリア、フランスが重量挙げを支配しています。 1950年代以降、ソ連の選手が表彰台の頂点に立ち、1990年代には中国、トルコ、ギリシャ、イランが主導権を握った競技です。 中国は、女子ウエイトリフティングがオリンピックの正式種目として導入されて以来、圧倒的な強さを誇っています。 女子はシドニー2000大会で初めて登場した競技です。
一瞬、一瞬に競技人生をかける選手たちの精神と肉体の融合が生み出す驚異のパワーは、目が離せません。 一見シンプルに見えるウエイトリフティングだが、肉体的にも、精神的にも非常に過酷な競技になります。 まず、自分で体重の2倍以上にもなるバーベルを、一瞬で床から頭上まで持ち上げるという行為を想像してみてほしいです。 体中の筋肉を、ただ総動員するだけでは、到底無理だと見当がつくだろう。 そこに必要なのは、全身に行き渡る集中力と精神統一、そしてスピード、気合、これらが全て最高の状態で組み合わさったときに一瞬の爆発力が生まれます。 選手たちは日々、鍛錬を積み重ねながら、記録を伸ばすべく努力をしている競技です。 競技の進め方にも、実は細かいルールがあります。
【試合ルール】
女子部門
49キログラム、59キログラム、71キログラム、81キログラム、81キログラム超
男子部門
61キログラム、73キログラム、89キログラム、102キログラム、102キログラム超
オリンピックのウエイトリフティングプログラムは、時代とともに大きく進化した競技です。 モントリオール1976大会以降、リフティングには「スナッチ」と「クリーン&ジャーク」の2つのリフティング技術になります。
スナッチでは、バーを床から頭の上に一気に持ち上げ、対照的に、クリーン&ジャークは、2段階の動作で、バーを、まず肩まで上げ、その後、頭の上に押し上げる種目です。 これらの過酷な動作は、並外れた体力と鉄壁の精神的決意が必要になります。
まず、選手は名前が呼ばれてから基本的に1分以内に試技を行います。 連続で試技を行う場合でも与えられるのは2分間です。 短時間のうちに心と体の状態を整える必要があるが、少しでも焦ってしまえば呼吸が合わずに失敗します。 たとえ時間ぎりぎりになっても落ち着きを払い、自分にとって最高のタイミングでバーベルに挑むことで好記録が生まれる競技です。 また、バーベルを持ち上げる時に両足の足裏以外、例えばお尻がプラットフォームに、少しでも触れてしまえば、失敗の試技として判定されます。
バーベルを持ち上げる間に肘の曲げ伸ばしがあってはならず、左右の腕の伸び方に不均衡が無いようにします。 持ち上げている間、バーベルをうまくコントロールできずにプラットフォームの外に足を踏み出すことがあれば失敗です。 バーベルを持ち上げた後、両足を結ぶ線と胴体とバーが平行になった状態でレフリーが合図をするまで静止していなければならず、合図より前にバーベルを降ろしてしまえば失敗として判定されます。 前半のスナッチで3回とも失敗した場合は失格となり、クリーン&ジャックに進むことができない競技です。 重いバーベルを頭上に差し上げ、顔を紅潮させて静止する選手たちの姿は1ミリの乱れもなく美しく、そして求める記録を出した時、喜びを全身から放ち、笑顔を弾けさせる選手たちの姿がまた、観客の感動を呼びます。
現在、競技者は両方のリフトを3回実行し、各リフトの最高結果を合計して総合スコアを決定する競技です。 合計スコアが最も高い競技者が優勝として宣言されます。 パリ2024大会では、男女それぞれ5段階で競い合う競技です。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
リオデジャネイロ2016大会での実施階級は男子8階級、女子7階級です。 国際ウエイトリフティング連盟は2018年11月1日より男女ともに全く新しい10階級ずつを適用するべくルールを変更し、それらの中から東京2020大会では男女ともに7階級ずつ実施されてきたが、ロサンゼルス2028大会では5階級で実施される予定になります。 オリンピックの歴代国別メダル獲得数では、ロシアと中国が他国を大きく引き離す数を誇っている競技です。 中国は21世紀に入ってからが特に強く、男子69キログラム級ではアテネ2004大会からリオデジャネイロ2016大会まで4連覇を果たしています。 女子は中国の強さが男子よりも顕著で、リオデジャネイロ2016大会では7階級中3階級を制している競技です。 その他の国では、アメリカが20世紀前半までは存在感を見せていたものの、近年での金メダルはシドニー2000大会の女子48キログラム級のみになります。 しかし、これは女子ウエイトリフティング史上初のメダルとして歴史に刻まれている結果です。 イランや北朝鮮などのアジア勢や、ヨーロッパ諸国の選手たちが活躍する競技でもあります。 東欧、中欧、アジア勢のメダル争いを崩せる新たな勢力は出現するのか楽しみになるだろう。
日本選手がオリンピックのメダル争いに常時食い込む時代が、再びやってきている。
ウエイトリフティング会場
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
テコンドーは世界屈指の格闘技で、己の繰出す蹴り技と緊迫した攻防戦

テコンドーは韓国発祥で200超の国と地域、競技人口8,000万人に達する競技です。試合は華麗でダイナミックな蹴り技の応酬や手技、神速かつアクロバティックな動きが魅力!テコンドーは連覇が難しく、日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
テコンドーの主な強豪国と地域:
「男子:イタリア、チュニジア、ROC、韓国、ウズベキスタン、イギリス、トルコ、中国、ヨルダン、エジプト、クロアチア、マケドニア、キューバ、女子:タイ、スペイン、イスラエル、セルビア、アメリカ、ROC、チャイニーズタイペイ、トルコ、クロアチア、イギリス、エジプト、コートジボワール、韓国、フランス etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。ロサンゼルス2028大会では世界各国との切迫した順位争いに電光石火の技が飛び散る。己の技で、テコンドー界の歴史に名を刻む国と地域はどこだぁ!
テコンドーは華麗な蹴り技の応酬で、緊迫した攻防が連続する格闘技です。 蹴り技が見もので、回し蹴り、横蹴りなど多彩な足技が特徴の競技になります。 テコンドー発祥の地、韓国をも脅かす、ヨーロッパ勢や西アジアの強豪国が再びメダル獲得できるか注目です。
【テコンドーの特徴】
テコンドーは「蹴る、殴る方法」という意味で、韓国発祥の武術になります。 そのルーツは韓国の三国時代(紀元前50年頃)にさかのぼり、テッキョン(足手)として知られる武術が展開された競技です。
約2,000年の間、朝鮮半島では様々な武術が研鑚されてきた歴史があります。 そうした中、20世紀初頭テコンドーは韓国内で実践的に広く普及する武術となり、やがて韓国の国技として国際的に普及が進められた競技です。 その後、国際的に展開し、1973年に世界テコンドー(WT)が設立されます。 同年、ソウルで第1回世界選手権が開催され、現在、テコンドーは200を超える国と地域に推定8,000万人に達する競技人口を誇る人気のスポーツです。 5つの大陸連合(アフリカ、アジア、ヨーロッパ、バンアメリカ、オセアニア)のもと、世界で最も人気のあるスポーツの一つとなっています。
【オリンピック競技としての歴史】
テコンドーの初オリンピック出場は母国で、ソウル1988大会とバルセロナ1992大会で、デモンストレーション種目として登場し、実施されたが、アトランタ1996大会では不在になった競技です。 しかし、その4年後、テコンドーはシドニー2000大会でオリンピック正式競技として採用されて以来、 毎大会で実施され、男女ともに種目が開催されるフルメダル種目として復活した競技になります。
【テコンドーの魅力とは】
テコンドーの最大の魅力は、なんといっても華麗でダイナミックな蹴り技とパンチの応酬です。 前蹴り、横蹴り、回し蹴り、後ろ回し蹴りなど、蹴りの技の種類は実に多彩で、素人目には何が起こったのかわからないようなスピードで、さまざまな角度、方向からの蹴り技が次々と繰り出されます。 時には飛んだり宙を回ったり、アクロバティックな動きは、観る者を魅了させてくれる試合展開です。 かかと落としや回し蹴りなどの豪快な大技が決まると、会場から大歓声が沸き起こります。 ロンドン2012大会からは技術の有効性や打撃の強さを公正に判定するために、電子センサーが付いたプロテクターやヘッドギア、ソックスなどを使用るPSS(Protector and Sconng System)が導入された競技です。 足技に象徴されるテコンドーだが、手技も存在しています。 顔面へのパンチは禁止されているため、手による攻撃は胴プロテクターへの攻撃のみです。 テコンドーは顔や胴に防具をつけており、直接当てて攻める「フルコンタクト」で、思い切り力を込めて当たり合うため、迫力があり、観戦者もエキサイトしてくる競技になります。
【試合ルール】
テコンドーの目的は、選手が相手を蹴ったり殴ったりしながら、自分自身が打たれないようにすることです。 試合は八角形のフィールドで、それぞれ2分間の3ラウンドで行われます。
ポイント制とは
選手が使用するテクニックの難易度に応じてポイントが与えられる競技です。 例えば、頭への蹴りはパンチや胴体への蹴りよりも高いスコアを獲得することができ、スピニングキックにも追加ポイントが与えられます。 ポイントを積み重ねて勝ちが決まることが多いので、どんな技が何ポイントなのか知っておくと良いでしょう。
基本的にプロテクターに攻撃が当たることでポイントとなります。 頭部への蹴りは3点、回転が加わると5点です。 また、胴部への蹴りは2点、回転が加わると4点となり、胴部へのパンチは1点となります。 倒れた後、審判により8カウントまでにファイティングポーズをとれないとKOになるが、ほとんどの試合はポイント差で勝敗が決まる競技です。 また、逃げてばかりで消極的な態度など、減点となる反則も存在し、減点になった場合は、相手選手に1点与えられます。 10回反則をもらうと試合は、その時点で終了となり、仮に相手よりポイントが上回っていたとしても、相手選手の勝利となるルールです。 さまざまな過失に対してアスリートに罰則が科せられる場合もあります。
これらの知識も知っておくと、試合をより面白く見ることができるテコンドーです。 さらに、新しい技術的な取り組みとして、東京2020大会ではビデオ判定として4Dリプレイシステムによる映像判定が導入されます。 コートの周りを360度囲うように多くのカメラを設置することで、あらゆる角度から選手の迫力満点のアクロバティックな技を見ることが可能です。 また、最先端の技術により開発された素材を用いた新ユニフォームも披露され、ロサンゼルス2028大会でもこれらの新たな技術が使われる可能性があります。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
テコンドーの競技は、韓国の国技ということで、やはり韓国が伝統的に強い、というのはひと昔前の話です。 現在、多くの国がテコンドーでトップに立ち、例えば、ロンドン2012大会では、8つの異なる国の選手がそれぞれ金メダルを獲得しています。
2000年にはベトナム、2008年にはアフガニスタン、2012年にはガボン、リオデジャネイロ2016大会は最も幅広い国々へメダルを提供したスポーツのひとつです。 同年にはヨルダンとコートジボワールに史上初のオリンピック金メダルが授与されています。 テコンドーで初めてオリンピックのメダルを獲得した国や、イランやコートジボワールに史上初の女性オリンピックメダリストが誕生し、歴史に名を刻んだ国もある競技です。
一方で、男子では2大会連続で金メダルを獲得した選手はまだおらず、2大会連続メダル獲得というケースも珍しく、それほど、続けて勝つことが難しい競技になります。
ロサンゼルス2028大会へチャレンジすることになる、リオデジャネイロ2016大会や東京2020大会、パリ2024大会のメダリストが、再び表彰台に上がれるか注目です。 ロサンゼルス2028大会では、男女ともに様々な国や地域がメダル争いに絡んでくるだろう。 国際色豊かな試合が観戦できそうな競技です。
日本ではテコンドーの歴史は浅く、東京2020大会の経験を盾に有望選手や若手選手に期待がかかります。 ロサンゼルス2028大会出場枠を獲得し、再びチャレンジすることができるか注目です。
子供も夢中になる野球は複雑なルールや戦略、選手同士の駆引きの勝負
子供達を魅了し続ける野球は世界から選ばれし強豪チーム同士で熱戦が繰広げられる競技です。試合は監督の采配やピッチャーとバッターの対決、キャッチャーや野手の強肩など華麗かつ迫力あるスーパープレーが魅力!日本チームは侍ジャパンで金メダル獲得に挑む。
参考元:https://tokyo2020.org/jp/games/sport/olympic/baseball-softball/復活!ソフトボールは独特のルールと投打の駆け引き、手に汗握る対決
ソフトボールは子供達も含め幅広い世代で楽しまれる球技です。試合はコンパクトなフィールドで行われ、打球が遠くまで飛ばず、スピーディーでスリリングな展開に注目。日本チームは選手強化を図り伝統的な守備力と剛速球、俊足と好打、監督の采配に期待する。
参考元:https://tokyo2020.org/jp/games/sport/olympic/baseball-softball/射撃は精密な技術に宿る強靭な精神力と集中力、己のメンタルとの勝負

射撃は銃器を用いて標的を撃ち、精度の高さを競い合う競技です。 試合は新たな種目も加わり、極限の緊張感が漂う中、手に汗握るエキサイティングな展開で、標的に命中した時の迫力や臨場感、爽快感が魅力! 日本勢は有力選手で挑む。開催国アメリカ勢は。
世界状況
射撃の主な強豪国と地域:
「女子:ROC、ブルガリア、中国、スイス、韓国、アメリカ、イタリア、スロバキア、サンマリノ etc.」
「混合:中国、ROC、ウクライナ、アメリカ、スペイン、サンマリノ etc.」
「男子:イラン・イスラム共和国、セルビア、中国、アメリカ、フランス、キューバ、ROC、デンマーク、クウェート、チェコ共和国、イギリス etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。
ロサンゼルス2028大会では極限のプレッシャーに撃ち勝つ順位争いに呼吸をするのを忘れる。
己の精度、精密さを駆使し、確実に標的を撃ち抜く、極限射撃を魅せる国と地域はどこだぁ!
【射撃の特徴】
射撃は、銃器を用いて標的を撃ち、精度の高さを競う競技です。 射撃は、固定された標的を撃つ「ライフル射撃」と、空中に放出された動く標的を撃ち壊していく「クレー射撃」があります。 射撃は、精密な技術に宿る強靭な精神力、極限のプレッシャーに撃ち勝つことが求められる競技です。
射撃は、動きの少ない静的な競技で、体力より重要となるのがメンタルの強さで、集中力をどれだけ高め維持できるかが勝敗を決めるカギとなります。 ライバルと戦うというより、各選手が自分自身と戦うスポーツです。 ライフル射撃は同心円が等間隔で描かれた標的の中心を狙って撃ち、中心に近いほど高い得点になります。
射撃は、ライフル銃を使う種目と、ピストルを使う種目があり、それぞれに標的までの距離、使う銃の種類などにより、種目が分かれている競技です。 銃の種類は、50メートル ライフル、10メートル エアライフル、25メートル ピストル、10メートル エアピストルの4種類があり、距離は50メートル、25メートル、10メートルの3種類になります。 撃つ時の姿勢は立位がほとんどであるが、片方の足を膝立て、膝の上に銃を置いて構える「膝射(しっしゃ)」、伏せて銃を構える「伏射(ふくしゃ)」、立った姿勢で銃を構える「立射(りっしゃ)」、の3種類を組み合わせた種目です。 一方、空中に飛び出したクレーといわれる皿状の標的を散弾銃で撃つのがクレー射撃になります。 1つの装置から遠くにクレーが飛び去る「トラップ」と、左右の装置からクレーが放出される「スキート」の2種目です。
東京2020大会では、10メートル エアライフルと10メートル エアピストル、クレー トラップに男女混合種目が加わります。 パリ2024大会では、10メートル エアライフル(女子 男子 混合団体)、50メートル ライフル3姿勢(女子 男子)、10メートル エアピストル (女子 男子 混合団体)、25メートル ラピッドファイアピストル(男子)、25メートル ピストル(女子)、トラップ (女子 男子)、スキート(女子 男子 混合団体) が実施される予定です。
【オリンピック競技としての歴史】
射撃は、最初の近代大会以来、オリンピック競技であり、ヨーロッパでは何百年も前から行われており、ドイツのクラブの中には、500年以上の歴史を持つクラブもあります。 射撃は、英国圏で最近人気が高まり、特に1871年に米国で全米ライフル協会(NRA)が結成され、現在、射撃は世界中で人気のあるスポーツであり、オリンピックでは毎回100ヵ国以上の選手が射撃競技に参加している競技です。 オリンピックでは第1回アテネ1896大会からの正式競技で、セントルイス1904大会、アムステルダム1928大会を除き、すべての夏季オリンピックで射撃競技が実施されています。 大会の開催回数は、1896年の5大会から現在は15大会に増え、オリンピックで獲得したメダルは米国が圧倒的に多く、次いで中国とロシアが続き、イタリアは、リオデジャネイロ2016大会で金メダル3個、銀メダル2個を獲得している強豪国です。
【ルール】
オリンピックの射撃競技は、ライフル、ピストル、ショットガンの3種目になります。 ライフルとピストルは、射撃場で行われ、射手は10メートル、25メートル、50メートルの距離にあるターゲットを狙う種目です。 また、肘立ち(マークスマンが片肘をつき、もう片方の膝に肘を乗せる)、うつ伏せ、立位の3つの姿勢があり、一部のイベントには、すべてのポジションが含まれます。
ターゲットをできるだけ正確に、できるだけ中心(ブルズアイ)に近づけるために、マークスマンはリラクゼーションテクニックを使用して心拍を下げることが必要です。 ショットガンイベントは、屋外で行われるため、原則的に異なります。 マークスマンは、さまざまな角度や方向から発射された飛行中のターゲットを撃つことが求められ、集中力、判断力、鋭い反射神経が要求される競技です。
【射撃の代表的な種目の見どころ】
射撃は、迫力と爽快感が魅力になり、見どころは選手のメンタルの強さです。 射撃の魅力は、撃つ前の張りつめた緊張感と、標的に命中した時の迫力、そして爽快感になります。 ライフル射撃で標的の中心に当たった時の心地よさは観客にもストレートに伝わるだろう。 決勝では1発ごとに点数が表示され、着弾がわずかに中心からずれただけで順位が劇的に変わるところも面白いです。 クレー射撃で見事にクレーを粉砕したとき、スカッとした達成感が感じられます。 射撃は観客にとっても手に汗握るエキサイティングなスポーツです。
「代表的な種目の見どころを紹介しよう。」
50メートル ライフル3姿勢は、膝射、伏射、立射の3姿勢で、それぞれ決められた弾数を撃ちます。 ファイナル進出者を決める本戦競技の制限時間は男女共通で2時間45分、ファイナル進出者は更に1時間に及ぶファイナル競技を経てメダルを争い、試合終了後には2キロも痩せるともいわれる過酷な種目です。 集中力を長時間保つことが要求され、体力も必要で、どれだけ緊張感を維持できるか各選手の心身の強靭さに注目が集まります。
10メートル エア ライフルは空気銃を用いて10メートル先の標的を立射で射撃する種目です。 10点圏は直径0.5ミリの点で、最も中心に近い着弾は10.9点と記録されます。 小数点単位で記録されるので、いかに安定的に中心を撃ち続けられるかが勝敗を決する最もテクニックな種目です。
10メートル エア ピストルは圧縮空気で弾を発射する単発ピストルが使用されます。 片手で狙う標的の10点圏は直径11.5ミリです。 銃を保持する手と引鉄を引く手が同じであり、いかに静かに引鉄を引くことができるかが勝負を決定する要素となります。
25メートル ラピッドファイアピストルは、8秒、6秒、4秒という短い時間に立った姿勢で次々と連射していく種目です。 8秒間の制限時間で5発を5つの標的に連続して撃つ「8秒射」を2シリーズ、「6秒射」を2シリーズ、「4秒射」を2シリーズ、合計6シリーズを1ステージとして、2ステージを2日間に分けて行われます。 短時間で集中力を高める必要があるため、観る者にまで緊張感が伝わってくる種目です。
25メートル ピストル個人は、立った状態で25メートル先の標的を片手で撃つ女子のみの種目で、5分間に5発という「精密射撃」と、3秒間に1発という「速射射撃」の2つの合計60発撃ちます。 じっくり構えて撃つ精密射撃と即座に撃つ速射射撃は、選手によって得意不得意があり、どれだけ得意な射撃でリードし、不得意射撃で失点を抑えるかが見どころとなります。
クレー射撃は、標的が動くので、瞬時の判断力と鋭い反射神経、精密な動作が要求される種目です。 トラップは、横一線に配置された5か所の射台を順に移動しながら、ランダムに放出され、逃げるクレーを撃っていく種目で、1枚のクレーに対し、2発撃つことができます。
スキートはトラップより複雑で、半円形に配置された1番から7番と中心の8番の合計8か所の射台を使い、様々な方向からクレーを狙う種目です。 クレーは左右に配置された2つのハウスの一方か、両方から射出され、1枚だけの場合や2枚同時になることもあります。 クレーは全部で25枚です。 トラップとは異なり、1枚のクレーに対し1発しか撃つことができません。
射場の地形や風向きにより変化する進路を予測することは難しく、当たるかどうか観客も固唾を飲んで見守ることになります。 この発射までの緊張感、そして命中したときの快感と興奮を選手とともに味わうことができるのが、クレー射撃観戦の醍醐味です。 射撃は、機会があれば一度、会場に行って観戦してみたいもので、発射音や火薬臭は独特で、迫力や臨場感が直に伝わってきます。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
射撃を得意とする国は数多く、特にヨーロッパでは伝統的に盛んなスポーツで、強豪国が多い地域です。 ただ、過去最も多くのメダルを獲得しているのは、アメリカで、近年では中国や韓国が台頭しています。
リオデジャネイロ2016大会で、一番成績が良かった国はイタリアです。 次に活躍したのはドイツの金メダル3個、銀メダル1個、さらに中国の金メダル1個、銀メダル2個、銅メダル4個になります。 複数のメダル獲得国は、他にアメリカ、韓国、ベトナム、ニュージーランド、ギリシャ、ロシア、フランス、クウェートです。
ロンドン2012大会では韓国が、金メダル3個、銀メダル2個と最も健闘し、アメリカも3個の金メダリストを輩出しています。
東京2020大会は、数多い国々が活躍しており、ロサンゼルス2028大会では、どの国が活躍するのか予測をするのは難しいです。 しかし、種目によっては突出した選手がいます。 ロサンゼルス2028大会では、突出した世界の強豪選手たちがロサンゼルス2028大会でもメダルを獲得するか?それとも新たな勢力図になるか、楽しみです。
日本は、射撃で金メダルを獲得した選手がいる競技で、現在、日本は若手の射撃選手の育成に力を入れていて、10代の選手も育ってきています。 だが、射撃は必ずしも若さが有利とはいえない競技なので、リオデジャネイロ2016大会、東京2020大会に出場した選手はやはり有力な候補です。
射撃会場
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
近代五種は強靭な精神力と体力、多彩な技術を駆使した己の限界に挑戦

近代五種は1日に異質な5種類の競技を行い、万能性を競い合うキング オブ スポーツです。 試合は種目に合わせ、頭や体を素早く切り替える高い戦略性と、強い精神力で身体をコントロールする姿に圧巻! 日本勢は3名の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
近代五種競技の主な強豪国と地域:
「イギリス、リトアニア、ハンガリー、エジプト、韓国 etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では過酷な1日の順位争いに目まぐるしさを覚える。
己に打ち克ち、最高に身体をコントロールできる国と地域はどこだぁ!
【近代五種の特徴】
近代五種は、競技ごとに身体を切り替える、多彩な技術と高い戦略性が求められるスポーツです。 1人選手が1日の間に、フェンシング、水泳、馬術、レーザーラン(射撃、ラン)という、それぞれに全く異質な5種類の競技に挑戦します。 近代五種は、万能性を競う「キング オブ スポーツ」とも呼ばれる複合競技です。
五種競技とは、ランニング、ジャンプ、やり投げ、円盤投げ、レスリングで構成され、古代オリンピックで行われていたペンタスロン(五種競技)の後続です。 近代オリンピックを提唱したピエール ド クーベルタン男爵が「近代オリンピックにふさわしい五種競技を」考案したもので、自ら「スポーツの華」と称したと言われています。 彼は、「完全な」アスリートの長所をテストする同様の競技を提案しましたが、より近代的な分野を含んだ内容です。
ヨーロッパでは王族、貴族のスポーツとも呼ばれて人気がある半面、さまざまな競技施設、競技用具を要することから競技人口が伸び悩んでいたが、 1848年に国際近代五種連合(UIPM)の設立やさまざまな取り組みにより、加盟国が近年では120ヵ国を超えるなど地域的に広がりを見せています。
【オリンピック競技としての歴史】
オリンピックの正式競技となったのはストックホルム1912大会からであり、ヘルシンキ1952大会からバルセロナ1992大会までは個人競技の他、団体競技も実施されていた競技です。 シドニー2000大会からは女子種目が加わります。
当初は1日に1種目、計5日間にわたって競技が行われたが、アトランタ1996大会から1日で、すべての種目を行うようになった競技です。
この種目は長い間、ヨーロッパ諸国、特にハンガリーとスウェーデンが支配しており、ストックホルム1912大会とロサンゼルス1932大会の間に獲得した15個のメダルのうち13個をハンガリーとスウェーデンが獲得しています。
秀でた体力と強い精神力を持ち、自らをコントロールできた選手のみが栄冠に輝く競技です。 1日1種目、計5日間にわたって行われていたころは、「王族、貴族のスポーツ」とも言われるような優雅さもあったが、5種類を1日で行うようになると一転、心身ともに限界まで追い込まれる、まさに万能性が問われる競技となります。
【ルール】
近代五種は、5つのスポーツを組み合わせた4つの種目で構成される競技です。
種目:個人(女子、男子)
相手の全身に対して突きを繰り出す「エベ」で戦います。 すべての選手が、1分間1本勝負で総当たり戦を行い、勝率によって得点が得られるトーナメントです。 静かな対峙から相手の意図を察知し、駆け引きの中での一瞬のスキをついて剣で攻撃するが、目にも止まらぬ、その攻撃は最新テクノロジーによってしか判定できないほどの速さをもちます。 短時間に次々と試合を行うため、選手は1試合ごとの瞬発力の他、途切れない集中力と自己の迷いを断ち切る勇気が必要です。
水中という体に大きな抵抗がかかる環境で、全身の骨格及び筋肉を効率よく動かし続けて200メートルを泳ぎ切る速さを競います。 フェンシングで最も強く求められるのが瞬発力ならば、水泳で必要とされるのは水の抵抗を回避しつつ効率よく推進力を得る技術に裏付けされたパワーと持久力です。 200メートルを泳ぐのに要したタイムによって得点が得られます。
フェンシングランキングラウンドの結果に基づく下位選手から順に30秒1本勝負でスピード感あふれる試合進行が行われるトーナメント方式です。 ランキングラウンドとボーナスラウンドの合計点がフェンシングの得点となります。
貸与された馬を操り、制限時間内に競技アリーナに設置された様々な色や形の障害物を飛越しながらコースを周る種目です。 単体競技としての馬術は、長年共に練習し息を合わせた自らの馬に乗って競技を行うが、近代五種においては初めて対面する馬と短時間(20分前)で信頼関係を築きながら障害と対峙することが求められます。 そのため、この種目では、馬との繊細なアプローチによるコミュニケーションを図り、確固たる信念と粘り強さや柔軟さ、焦りを表に出さず冷静さを保つ精神力なども必要です。 この種目のみ、得点は減点方式で計算されます。
これまでの3種目の得点を1点=1秒にタイム換算し、時間差を設けて上位の選手からスタートする種目です。 射撃とランニングを交互に4回行い、着順を競い合います。 射撃はレーザーピストルを使い、10メートル離れた場所から直径約6センチメートルの標的にレーザーを5回命中させるのだが、5回命中するまでは50秒の制限時間の間、撃ち続ける必要があります。 ランニングは800メートルのコースを走行する種目です。 長い距離を走った直後、瞬時に全身の動きを静止させて息を整え、精密な射撃動作を行う難しさを想像してみよう。 動から静、静から動への状態変化の激しさを思えば、この種目がいかに自身の身体的、精神的コントロール能力を要求されているかがわかります。 静と動の切り替えの難しさと毎回の射撃での順位の入れ替わりが見どころです。 このレーザーランでフィニッシュした着順が競技全体の最終順位となります。
近代五種は2つのセクションに分かれる競技です。 まず、フェンシング、乗馬、水泳の種目での順位に応じてポイントを獲得し、レーザーラン種目のスタート位置を決定します。 次に、レーザーラン中、アスリートはリーダーとのポイント数に応じた遅延でスタートし、レーザーランで最初にフィニッシュラインを通過した選手が金メダルを獲得する競技です。
近代五種競技は、種目が多岐にわたるため、選手を精神的、肉体的に限界まで追い込み、非常に多様なスキルを必要とする非常に厳しいスポーツになります。 それぞれに固有の技術と理論を必要とされる個々の種目をマスターするだけでなく、競技の全体像を常に頭で描き、自分の体力を計算しながら、種目が変わるごとに求められる状態に体を切り替えていくことが重要です。 体力に加えて強い精神力で自分の身体をコントロールできた選手のみが栄冠を手にすることができます。 まさに「キング オブ スポーツ」であり、全スポーツの頂点を目指す競技が、この近代五種です。 長時間におよぶ競技だが、観客は最後までその順位を確信することはできません。 なぜなら、挑戦する種目が多種にわたる上、ハイレベルな5種目の能力の中に、更に得意種目を持つ選手同士の戦いが繰り広げられ、順位が最後まで入れ替わり続けるからです。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
オリンピックでの金メダル獲得上位には西欧、東欧諸国が名を連ねています。 リオデジャネイロ2016大会までで、最もメダルを獲得しているのはハンガリーで、それにスウェーデン、ロシア、ポーランド、イギリスなどが続く競技です。 近代五種競技におけるヨーロッパ勢の強さは他の競技にも類を見ません。
近年ではメダリストにカザフスタン、オーストラリア、メキシコ、中国などの選手が名を連ねるようになり、少しずつ競技地域が広がってきていることが伺える競技です。 また、近年は新興国もメダルを狙える位置にきており、韓国などが、この競技の重点的強化に取り組み、世界ランキング上位に選手を送り込むようになっています。 ヨーロッパを頂点にメダル獲得国の変遷が競技地域の拡大を示す中、ヨーロッパ内の勢力図も時代によって変化をみせている競技です。
男子では、オリンピック正式競技となってからの数大会はスウェーデン勢が、ほぼ全てのメダルをさらったが、シドニー2000大会からの5大会でロシアの選手が金メダル4つ、チェコの選手が金メダル1つと東欧勢が金メダルを独占中になります。
東京2020大会では、イギリス、リトアニア、ハンガリー、エジプト、韓国がメダルを獲得し、パリ2024大会では、ロシアを筆頭とする東欧勢にライバル心を燃やすイギリス、フランス、イタリア等の西欧勢の巻き返しにも期待が集まる競技です。
女子では、イギリスが金メダル、銅メダルを獲得したシドニー2000大会を含め、4大会で表彰台に立ち続けてきたが、リオデジャネイロ2016大会で初めて全てのメダルを他国に譲ります。
世界ランキング上位はヨーロッパ勢が中心だが、オリンピックのメダリストには近年ブラジルやオーストラリアの選手が顔を見せ、彩りを加えている競技です。 こうした新興勢力がヨーロッパ勢に、どこまで迫ることができるか注目が集まります。
日本はローマ1960大会からバルセロナ1992大会までは毎大会出場していたが、アトランタ1996大会以降選手を送り出すことができなくなっています。 しかし北京2008大会に日本選手として16年ぶりに出場を果たすと、続くロンドン2012大会では男子1名、女子2名が、リオデジャネイロ2016大会でも男子2名、女子1名が出場し、2018ワールドカップファイナル大会の女子個人において6位に入賞するなど、メダル獲得を狙える位置に来ているのが現状です。
その背景には、最近までは競技の内容や用具の性質から自衛隊や警察出身の選手がほとんどであったが、一般の人々が使用のしやすい用具にルールが改正されるなど、一般の人々の間で競技人口が広がりつつあることが挙げられます。 また、日本近代五種協会も、水泳、レーザーランからなる「近代三種」を積極的に推進するなど、一般の人々への普及に努めており、選手層の拡大によって今後オリンピックでの活躍が期待されている競技です。
近代五種競技会場
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
競泳は己の限界を凌ぐ闘い、技術と加速力、戦術で世界新記録に挑戦!

競泳は新たに3種目も加わり合計35種、決った距離と泳法でタイムを争う競技です。 試合はタイムが拮抗する世界最高峰の舞台!水抵抗を極限まで減らし、限界を越え続ける美麗な泳ぎとスピード、迫力が魅力。 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
競泳の主な強豪国と地域:
「50メートル 自由形(男子/女子)女子:オーストラリア、スウェーデン、デンマーク
男子:アメリカ、フランス、ブラジル etc.」
「100メートル 自由形(男子/女子)女子:オーストラリア、ホンコン・チャイナ
男子:アメリカ、オーストラリア、ROC etc.」
「200メートル 自由形(男子/女子)女子:オーストラリア、ホンコン・チャイナ、カナダ
男子:イギリス、ブラジル etc.」
「400メートル 自由形(男子/女子)女子:オーストラリア、アメリカ、中国
男子:チュニジア、オーストラリア、アメリカ etc.」
「800メートル 自由形(男子/女子)女子:アメリカ、オーストラリア、イタリア
男子:アメリカ、イタリア、ウクライナ etc.」
「1500メートル 自由形(男子/女子)女子:アメリカ、ドイツ
男子:アメリカ、ウクライナ、ドイツ etc.」
「100メートル 背泳ぎ(男子/女子)女子:オーストラリア、カナダ、アメリカ
男子:ROC、アメリカ etc.」
「200メートル 背泳ぎ(男子/女子)女子:オーストラリア、カナダ
男子:ROC、アメリカ、イギリス etc.」
「100メートル 平泳ぎ(男子/女子)女子:アメリカ、南アフリカ
男子:イギリス、オランダ、イタリア etc.」
「200メートル 平泳ぎ(男子/女子)女子:南アフリカ、アメリカ
男子:オーストラリア、オランダ、フィンランド etc.」
「100メートル バタフライ(男子/女子)女子:カナダ、中国、オーストラリア
男子:アメリカ、ハンガリー、スイス etc.」
「200メートル バタフライ(男子/女子)女子:中国、アメリカ
男子:ハンガリー、イタリア etc.」
「200メートル 個人メドレー(男子/女子)女子:アメリカ、日本
男子:中国、イギリス、スイス etc.」
「400メートル 個人メドレー(男子/女子)女子:日本、アメリカ
男子:アメリカ、オーストラリア etc.」
「4×100メートル フリーリレー(男子/女子)女子:オーストラリア、カナダ、アメリカ
男子:アメリカ、イタリア、オーストラリア etc.」
「4×200メートル 自由形リレー(男子/女子)女子:中国、アメリカ、オーストラリア
男子:イギリス、ROC、オーストラリア etc.」
「4×100メートル メドレーリレー(男子/女子/混合)女子:オーストラリア、アメリカ、カナダ
混合:イギリス、中国、オーストラリア 男子:アメリカ、イギリス、イタリア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国と地域です。
ロサンゼルス2028大会では欧米、オセアニア、南米、アフリカ、アジア勢との順位争いに水しぶきが目に刺さる。
己の泳法で新な世界新記録を打ち出す国と地域はどこだぁ!
【競泳の特徴】
競泳は一定の距離を決められた泳法(自由形、背泳ぎ、バタフライ、平泳ぎ)で泳いでタイムを争う競技です。 リオデジャネイロ2016大会では、個人種目とリレー種目を合わせ、男女で32種目がプールで行われています。 東京2020大会では、800メートル自由形(男子)、1500メートル自由形(女子)、4×100メートルメドレーリレー(混合)の3種目が新たに加わり、種目数は35です。 それぞれの泳法はもちろん、スタートの飛び込みから水中動作、ターンに至る一連の加速、水の抵抗を極力受けないためのテクニックも重要になります。 4泳法のうち自由形は、どのような泳法で泳いでもルールとしては問題ないが、現在は最も速いクロールで全員が泳ぐ種目です。 プール以外では、オープンウォータースイミングとも呼ばれ、北京2008大会から正式種目に採用された10メートルマラソンスイミングだけが、海や川、湖など、プール以外で行われています。
水泳の歴史は先史時代にまでさかのぼりますが、競技スポーツになったのは、19世紀になってからです。 英国水泳協会は1800年初頭に誕生し、最初の大会を開催し始めます。 ほとんどの水泳選手は平泳ぎ、または平泳ぎの一種を使用していましたが、その後、より多様なストロークが競技に追加され、現在はオリンピックで採用されている競技です。
最も速いクロールで争われる自由形は、世界の男子トップ選手であれば、50メートルを約21秒で泳ぎ切るという、圧倒的なスピードと迫力が魅力な種目になります。 背泳ぎは仰向けの体勢で、しなやかに腕を使い、水面を滑るようにして進んでいく種目です。 バタフライは、蝶が飛ぶような美しさとダイナミックなフォームで魅せる種目になります。 4泳法のうちで唯一、水をかいた腕を水中で前へ戻す平泳ぎは、水の抵抗との戦いをいかに制するかがポイントです。
タイムが拮抗する世界最高峰の舞台で戦う選手たちは、泳力、体力の向上に加え、キックのタイミング、腕の向きなどを微妙にチェックし、細かい技術を磨き上げています。 さらに、どのようにペースを配分するかという戦術も注目のポイントです。 例えば、予選では前半から飛ばして圧倒的なタイムで決勝に進んだ選手が、決勝ではあえて前半はペースを抑えて余力を残しておき、後半にスパートをかけるなどの作戦も、見どころの一つとなります。
水泳の競泳は、水の抵抗を極限まで減らす技術と加速のパワー、 泳ぎの美しさと迫力が見ものです。 限界を超え続ける最速スイマー達、0.01秒の極限の闘いに挑み続けています。
【オリンピックとしての歴史】
水泳は、現代のオリンピックで長年行われている種目です。 最初のオリンピックレースは自然環境の中で行われましたが、1908年のロンドン大会以降、競技はプールで行われるようになり、国際自然連盟(FINA)が創設されます。 1896年のアテネ大会では自由形種目が唯一実施され、1904年のセントルイスオリンピックでは平泳ぎと背泳ぎ、52年後の1956年のメルボルン大会では背泳ぎが加わった競技です。 女子水泳は1912年に2種目でオリンピック種目に加わったが、現在、女子と男子の水泳競技は同じになります。 オリンピックの水泳は、250個以上の金メダルを獲得した米国を代表する選手が大半を占めている競技です。
【ルール】
種目
50メートル 自由形(男子/女子)
100メートル 自由形(男子/女子)
200メートル 自由形(男子/女子)
400メートル 自由形(男子/女子)
800メートル 自由形(男子/女子)
1500メートル 自由形(男子/女子)
100メートル 背泳ぎ(男子/女子)
200メートル 背泳ぎ(男子/女子)
100メートル 平泳ぎ(男子/女子)
200メートル 平泳ぎ(男子/女子)
100メートル バタフライ(男子/女子)
200メートル バタフライ(男子/女子)
200メートル 個人メドレー(男子/女子)
400メートル 個人メドレー(男子/女子)
4×100メートル フリーリレー(男子/女子)
4×200メートル 自由形リレー(男子/女子)
4×100メートル メドレーリレー(男子/女子/混合)
オリンピックでは、水泳は長さ50メートルのプールで行われます。 オリンピックの競泳は、個人戦、リレー種目ともに、平泳ぎ、バタフライ、背泳ぎ、自由形の4種目で、常にクロールが用いられる競技です。 5番目のレースである混合メドレーは、4つのストロークすべてを用い、選手は4ストロークを交互に行います。 距離もさまざまで、50メートルから1500メートルまでのレースに必要なスキルは異なり、爆発力、持久力、強さ、テクニックなどすべて、選手にとって不可欠な資質です。
1人で4泳法を泳ぐ個人メドレーには、高い総合力が求められます。 選手によって得意種目が異なるため、泳法が変わるたびに順位の変動が見られることもあり抜きつ抜かれつのスリリングなレース展開は見応え十分です。 個人メドレーは、バタフライ~背泳ぎ~平泳ぎ~自由形の順番で泳ぎます。
リレー種目では、前の泳者がタッチする瞬間と、次の泳者の足がスタート台から離れるまでの「引き継ぎ」の時間をどう縮めるかが重要です。 メンバーの合計タイムが上位であっても引き継ぎ次第では順位を落とすことがあり、また、引き継ぎ時にフライングをしてチームが失格することもあります。
メドレーリレーは、個人メドレーとは異なり、背泳ぎ~平泳ぎ~バタフライ~自由形の順で泳ぐ種目です。 各泳法のトップ選手らでチームが組まれ、オールスター対抗戦のような華やかな盛り上がりを見せてくれます。
新種目の4×100メートルメドレーリレー(混合)は、男女2人ずつの4人でチームを組むが、どの泳法を男女どちらが泳ぐかは、チームが自由に決められる種目です。 男子と女子が同時に泳ぐこともあり、大きな順位変動や逆転があり得るエキサイティングな試合展開になります。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
競泳の技術革新は今日でも進んでおり、オリンピックではロンドン2012大会、リオデジャネイロ2016大会ともに決勝で世界記録が7回更新されてきた競技です。 象徴的なのは100メートル平泳ぎで、北京2008大会で、初めて58秒台に突入している種目になります。
体を伸ばし水の抵抗を極限まで減らす美しいストリームラインや、息継ぎの後の頭の位置を低くする動作などで効率を追い求めるとともに、ストローク(水をかく動作)数の少ない泳ぎが世界の主流となりつつあった種目です。 それを大きく変えます。 テンポが速くパワフルな泳ぎ、言い換えればストローク数が多くキックが力強い泳ぎで驚異的なスピードを実現させ、リオデジャネイロ2016大会で57秒13の世界新記録を樹立した種目です。
自由形や背泳ぎ、バタフライにおいても、大会ごとに新しいテクニックが生み出されており、技術力の進化が競泳の記録の進歩を促しています。
近年ではスペシャリストよりも多種目で活躍する選手が増え、マルチに活躍する選手、そしてスペシャリストとの二分化は、これから先の水泳界に大きな変革を起こしていくことになるだろう。 マルチスイマーとスペクトルの二分化が世界記録更新に拍車をかけてくる時代です。
日本はリオデジャネイロ2016大会 400メートル個人メドレー(男子)で日本選手団第1号となる金メダルに輝き、さらに52年ぶりとなる4×200メートルリレー(男子)での銅メダル獲得にも貢献しています。 かつて日本にはスペシャリストが多かったが、近年では多種目で活躍する選手が登場する競技です。 小学校の頃から4つの泳法を指導されることが背景にあります。 また、1964年東京大会以降あまり日本が得意としてこなかった自由形にも、強い選手が育ち、選手層の厚みも増しつつあり、競泳での日本のメダルはますます増えることだろう。
開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
飛込は己の高難易度の演技と美しく入水できるか、一瞬の美の逆転勝負

飛込は反発力と瞬発力を活用した「3メートル飛板飛込」と「10メートル高飛込」の2種目の演技が行われる競技です。 試合はダイナミックさと美しさが求められ、2秒弱で勝負が決るスリリングな展開に注目。 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
ダイビングの主な強豪国と地域:
「男子10メートル高飛込:中国、イギリス etc.」
「男子3メートル飛板飛込:中国、イギリス etc.」
「男子シンクロナイズド10メートル高飛込:イギリス、中国、ROC etc.」
「男子シンクロナイズド3メートル飛板飛込:中国、アメリカ、ドイツ etc.」
「女子10メートル高飛込:中国、オーストラリア etc.」
「女子3メートル飛板飛込:中国、アメリカ etc.」
「女子シンクロナイズド10メートル高飛込:中国、アメリカ、メキシコ etc.」
「女子シンクロナイズド3メートル飛板飛込:中国、カナダ、ドイツ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会ではアジア、欧米、オセアニア、南米勢との順位争いに息を呑む。
己の演技で華麗に入水できる国と地域はどこだぁ!
【ダイビング(飛込)の特徴】
飛込は3メートルのジュラルミン製でできた飛板を使い、反発力を利用して演技を行う「飛板飛込」と、10メートル高さの台から飛び込む「高飛込」の2種類が行われます。 演技は、踏切の方向と宙返りの方向、演技に捻りを加えたもの、逆立ちからスタートするものがある競技です。 採点は、回転の型(伸型、蝦型(えびがた)、抱型)の3種類を組み合わせた演技の美しさや入水時の水しぶきの少なさなどを見ます。 これに加え、シンクロナイズドダイビングは、2人でどれだけ演技が同期(シンクロ)しているかも採点される種目です。
ダイナミックな回転から、一点の乱れもない入水、2秒の演技が起こす大逆転劇は、まばたきすら許されない展開が見どころになります。
飛込は19世紀にスウェーデンとドイツで最初に人気を博し、アクロバットとスタイルを競うために、体操選手が水中で演技することに触発されたのがきっかけです。 19世紀の終わり頃、スウェーデンのダイバーがイギリスに渡ってデモンストレーションを行い、1901年にアマチュアダイビング協会が設立されます。
【オリンピックとしての歴史】
飛込はオリンピック競技に、いち早く取り入れられ、1904年のセントルイス大会でデビューを果たした競技です。 1904年にダイビングがオリンピック種目になったとき、アメリカが主流でし、1912年に初めて女子種目が実施され、2000年のシドニーオリンピックでは同期種目が追加されます。
現在、中国は欧米の強豪国を追い越しており、東京2020大会では金メダル7個を含む24個のメダルのうち12個を中国選手が獲得した強豪国です。
【ルール】
種目
3メートル飛板飛込(女子/男子)
10メートル高飛込(女子/男子)
シンクロナイズド3メートル飛板飛込(女子/男子)
シンクロナイズド10メートル高飛込(女子/男子)
飛込の魅力は、演技がスタートして2秒弱で勝負が決まる「一瞬の美」にあります。 5種類の踏切の方法と、前後の回転の方向に加えた捻りに、回転時の身体の形を組み合わせて演技を行い、その美しさとダイナミックさが採点される競技です。 入水時の水しぶきをどれだけ抑えられるかも採点基準のひとつで、採点は10点満点からの減点法で行われます。 入水は見た目にも分かりやすく、オリンピックの決勝で戦う世界のトップ選手たちは、ほとんど水しぶきを上げない仕上がりです。 特に、入水したかと思えば、全くしぶきが上がらず、ぼこぼこと泡が水面に見えるだけの「リップ クリーン エントリー」と呼ばれる入水は美しく、最も得点が高くなります。
以前は、3メートル飛板飛込では踏切から入水までの回転が、1回転半から2回転半が基本です。 近年では、飛板をしならせてその反発力を使って高く飛び上がることにより、3回転半から4回転半も回転するダイナミックな演技がメインになっています。 近年の世界トップクラスの選手をみると力を発揮し始めているのは、背が高く手足の長い選手です。 特に男子は手足が長いと空中での回転が大きくなり、演技がダイナミックかつ美しく見えます。
高飛込では台の反発力を得られないため、飛び上がることよりも、いかに入水までに素早く小さく回転することができるかがポイントです。 そのため、高飛込の上位には、背が低く瞬発力の高い選手が多く、飛板飛込、高飛込ともに男子は6回、女子は5回演技を行い、その合計得点を競い合います。 最後の演技の直前までリードを許していたとしても、最後の演技で逆転することもできる種目です。 1試合の順位変動が激しい種目になります。 事実、北京2008大会の高飛込では、5本目まで地元中国の選手がリードしていたが、最後の6本目でオーストラリアの選手が逆転してオリンピック史にのこる劇的な優勝を飾ります。 演技は一瞬で決まるのに対し、勝負は最後の最後まで分からない、こうしたスリリングな魅力が、飛込には詰まっている競技です。 一瞬に凝縮された美 逆転劇も起こりやすい手に汗握る試合展開に観客からも大歓声が上がります。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
セントルイス1904大会以降、アメリカが圧倒的な強さを誇っていたが、女子はロサンゼルス1984大会から、男子はバルセロナ1992大会から中国選手が台頭しはじめ、北京2008大会においては全8種目中7種目を中国が制するなど、強さを見せつけ始めた強豪国です。 中国は2回転半~3回転半が主流だった時代に、4回転半という難しい飛込を行い、さらに入水もリップ クリーン エントリーまではいかないまでも、ほとんどしぶきがあがらない「ノースプラシュ」の演技をしています。 しかし、近年ではイタリア、イギリス、オーストラリアに加え、アメリカも力を取り戻しているため、東京2020大会では混戦になった競技です。
欧米勢が復活しつつある大きな理由は、長身の選手が難度の高い4回転半を飛べるようになったことにあります。 捻りの数も1回が2回になり、そして3回行う選手も出てきており、やはり手足の長い選手が大きな身体を素早く回転させ、そしてノースプラッシュの入水をする様は美しいです。 事実、リオデジャネイロ2016大会では、男子3メートル シンクロナイズドダイビングの優勝チームはイギリスで、2位にはアメリカが入り、中国は3位と勢力図に変化が訪れ始めています。
また、演技の難易率が高くなければなるほど入水が難しくなっていくため、今まで以上に入水が勝敗を分ける重要なポイントになっていくことだろう。 より高く、より速く、より多くの回転し、より美しく入水することが求められていく飛込です。 ロサンゼルス2028大会に向けて、演技が大きく変わっていくに違いなく、それに伴い、勢力図が大きく変動する可能性もあります。
男女ともに中国優位か、牙城を崩すのはどの国、地域か注目です。
日本はベルリン1936大会の4位入賞が、オリンピックにおける日本の飛込の最高順位で、リオデジャネイロ2016大会では、高飛込で8位入賞を果たしています。 難易度の高い種目で、いかに美しい入水を決められるかが日本の課題となっている競技です。 また、シンクロナイズドダイビングは、一つの国、地域から複数の選手が出場できる他の飛込種目とは異なり、出場は各国、地域で1組だけになります。 日本が出場権を得ることができれば、メダル獲得の可能性が出てくる競技です。
【開催地】
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
マラソンスイミングは自然環境を己の経験と読解力で攻略し勝負に挑む

マラソンスイミングは水泳の耐久レースとも呼ばれる競技です。 試合は心技体が揃った選手たちの戦略や経験に加え、体力と頭脳、スピード、自然環境の読解力、駆引き、自分を磨き上げ戦い抜く強い心に注目。 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
マラソン水泳の主な強豪国と地域:
「男子10キロメートル:ドイツ、ハンガリー、イタリア etc.」
「女子10キロメートル:ブラジル、オランダ、オーストラリア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では欧米、南米、オセアニア勢との順位争いに野鳥たちも驚く。
己の鍛え上げた折れない心で、世界新記録を打ち出せる国と地域はどこだぁ!
【マラソンスイミングの特徴】
マラソンスイミングは、海や川、湖といったなかで安全に配慮された場所を使い、男女ともに10キロメートルを泳ぐ競技です。 その名のとおり、水泳のマラソンといえます。 北京2008大会から正式種目に採用された比較的新しい競技です。
基本的には周回コースで、選手たちは途中で給水を行いながらも、約2時間に及ぶ耐久レースを戦い抜きます。 記録も重要ではあるが、天候等の環境によって試合環境が左右されるため、戦略を含めた勝負の比重が高いのが特徴です。 いかに波や潮の流れなどの自然環境を味方につけ、活用していくかも勝負の大きなポイントにもなります。 自分を磨き上げることはもちろん、駆け引き、環境への対応、戦略などの経験が生きるためベテラン選手も多く、抜きつ抜かれつの見応えのある試合展開が魅力です。
【オリンピック競技としての歴史】
近代オリンピックの最初の3大会では、1908年までプールが利用できなかったため、すべての水泳競技は自然の水域で行われています。 マラソンスイミング(OWS)自体は1980年代前後からオーストラリアを中心に行われており、1991年のオーストラリア パースでの世界水泳選手権で正式種目となった競技です。 このときの種目は、男女ともに25キロメートル以上行われ、完走までに5時間を超える競技時間を要しています。 その後、オリンピック競技となる10キロメートルレースが初めて世界大会に取り入られたのは、2001年、日本の福岡で開催された第9回世界水泳選手権(FINA)です。
オリンピックでマラソンスイミングが初めて行われたのは北京2008大会で、10キロメートルが導入され、オリンピック種目に加わった最新の水泳種目になります。 このスポーツの歴史は浅いため、マラソンスイミングで目立つ機会に恵まれた国やアスリートはほとんどいません。 マラソンスイミングだけに専念する選手もいれば、以前は他のフリースタイルプール種目のスペシャリストだった選手もおり、これらの選手は競技性が高いです。 男子10キロメートルで初の金メダルとなった、19歳で白血病と診断されながらもそれを克服し、オリンピックチャンピオンに輝いています。 女子は世界水泳選手権で圧倒的な強さを誇り、数秒差の接戦をものにしている種目です。
【ルール】
種目
10キロメートル水泳(女子/男子)
マラソンスイミングは、海、川、湖などのオープンウォーター環境で行われます。 選手は10キロメートルのコースを完走しなければならず、完走には2時間近くかかり、持久力、体力、頭脳力が試される競技です。 また、適応する能力も重要で、海上では潮の満ち引きや潮流が急激に変化するため、選手はこれを考慮して戦略を立てる必要があります。 したがって、コースとコンディションに適した戦術を使用することが重要です。 最後の3キロメートルで、選手はフィニッシュラインに向かって動き始めますが、その努力をどう管理するかが重要になり、最終的に最終結果に影響を与えます。 マラソンスイミングは駆け引き、環境への対応、戦略を駆使し、2時間もの耐久レースを戦い抜く過酷なレースです。
10キロメートルにも及ぶ耐久レースの中で最も見応えがあるのは、各選手が勝負をかけ始める7キロメートル付近からのスパート勝負になります。 だが、実はそこに至るまでの間、いかに自分の体力を消耗せず、ラストスパートをかけられる力を残すことができるかが勝負を分ける大きなポイントです。 途中に行われるスピードの上げ下げによる揺さぶりに対応できる力、それに伴う集団となったときの位置取りや、海や川の流れがあるなかで、どれだけ効率の良いコース取りができるかも、この種目を制する上での大切な実力になります。 抜きつ抜かれつの展開に加え ラストスパート勝負は見応え十分です。
特にコース取りは環境によって大きく左右されます。 海でいえば、時間によって潮の流れや波の大きさも変わるため、それらを確実に見極めることが必要です。 経験豊富なベテラン選手になると、その潮の流れを利用することもあります。 つまり、指定されたコースの最短距離がベストではなく、試合環境によって他の選手と異なるコース取りをした選手が勝利をもぎ獲る場面も多く見られる展開です。 また、近年ではタッチ差で勝負がつくレースも多く、 体力と頭脳、環境を読み解き、最適解を実行できる技術、そして10キロメートルのレースでも折れない心が求められます。 まさに心技体が揃った選手たちが、世界一を懸けて争う種目なのが、このマラソンスイミングです。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
マラソンスイミングがオリンピック競技となった北京2008大会当時は、まだマラソンスイミングに特化した選手が強かった試合展開です。 しかし、オリンピックの正式競技になって以来は、勢力図が変わり始め、競泳競技の長距離選手たちが徐々に参戦するようになります。 結果、競泳とマラソンスイミングの両方を主戦場とする選手が登場し始めた競技です。 いわゆるデュアルスイマーで、このデュアルスイマー誕生の背景にはロンドン2012大会の会場となったハイドパーク内のサーペンタイン湖は流れのない静水面だったことから競泳競技でも代表となれるほどのスピードが生かしやすかったこともあります。
なお、北京2008大会の会場もロンドン2012大会と同じく公園内の湖を利用して行われた競技です。 ただし、ロンドン2012大会以降からはマラソンスイミングのスピード化が顕著に表れるようになります。 戦略、経験に加えてスピードも重要視されるようになり、現在では多くの選手がデュアルスイマーとしてオリンピックを始め、世界大会で活躍するようになった種目です。
その影響か、近年では10キロメートルにも及ぶ長距離ながら、コンマ数秒差のレースも多くなります。 代表的なのは、リオデジャネイロ2016大会の男子10キロメートルです。 オリンピック競技になって、初の海でのレースとなった今大会は、ラスト100メートルから13人にも及ぶ選手がフィニッシュになだれ込み、身体ひとつ抜け出していた選手を他の選手が猛烈に追い込み、ほぼ同時にフィニッシュしています。 同じタイムと表示されたが、写真判定にもつれ込み、頭の位置が前に出ていたが、タッチのタイミングを合わせた選手が勝利し、まさに最後の最後まで目が離せないレースです。
海や河川といった多くの外的要素がある会場ですら、高いスピードを出せる泳力が求められ始められています。
この競技で、競泳でも力を伸ばしているヨーロッパ勢が勢力を伸ばしているのは必然かもしれません。 ロサンゼルス2028大会では、スピードレース化が進むマラソンスイミングで、どんなレース展開になるのか楽しみです。 10キロメートルとは思えない接戦、スピードレース化がさらに進む可能性が高く2時間、目が離せない試合になることは確かだろう。
日本人初のオリンピック選手が誕生したのは、ロンドン2012大会です。 今も、このふたりが日本のトツプを牽引しているが、現在は若手も成長しており、この競技で最も大切な経験を積み始めています。 単純な泳力がそのまま結果に反映されないマラソンスイミングだからこそのチャンスやラスト3キロメートルを切ったところから始まる、ラストスパート勝負に入るまで、先頭集団をキープし続けることがメダル獲得への道となるだろう。
【開催地】
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
アーティスティック水泳は己の民族性や同調性、緻密かつ優美さの勝負

アーティスティックスイミングは民族性に富んだ華麗かつ特殊な水着、演技構成で行う競技です。 試合は音楽に合せ、水中で様々な動きや演技を披露し、完成度や同調性、さらに芸術性や表現力に注目。 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
アーティスティックスイミングの主な強豪国と地域:
「チーム:ROC、中国、ウクライナ etc.」
「デュエット:ROC、中国、ウクライナ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では欧米、アジア勢との順位争いに美学を覚える。
己の演技で世界中を魅了させることができる国と地域はどこだぁ!
【アーティスティックスイミングの特徴】
アーティスティックスイミングは、音楽に合わせてプールの中でさまざまな動き、演技を行い、技の完成度や同調性、演技構成、さらには芸術性や表現力を競い合います。 オリンピックでは女子のみで実施されるアーティスティックスイミングです。(パリ2024大会 男子団体あり)
2分20~50秒の曲に、決まった5つの動きを入れるテクニカルルーテインと、3~4分の曲の中で自由に演技するフリールーティンが行われます。
美しい装飾を施した特殊な水着を着け、水にぬれても落ちないメイクを施し、水が鼻に入らないようにノーズクリップを着用(しなくてもよい)し、水の中で舞う選手たち、同調性、難易度、技術、そして演技構成などが採点され、順位が決まる競技です。
ダイナミックかつ繊細な舞、一糸乱れぬマーメイド達の競演が観客を虜にします。
アーティスティックスイミングは、水上アクロバットと音楽を組み合わせて発展した競技です。 最初の競技会は男性向けに開催されましたが、アーティスティックスイミングは後に女性との関連が強くなります。 20世紀初頭に米国で多くのデモンストレーションが行われた後、この種目は人気が高まり、最初の大会が開催された歴史です。
【オリンピックとしての歴史】
アーティスティックスイミングは、1984年のロサンゼルスオリンピックでオリンピック種目になります。 パリ2024大会では、男子選手がオリンピック史上初めて団体戦に出場することが認められる競技です。 アメリカとカナダは当初、オリンピックのアーティスティックスイミングで圧倒的な強さを発揮し、合計17個のメダル(金メダル8個を含む)を獲得しています。 2000年のシドニー大会以来、ロシアオリンピック委員会は12大会連続で金メダルを獲得し、国内オリンピック委員会のトップとなった強豪国です。
【ルール】
種目
フリー デュエット
テクニカルデュエット
フィナーレのデュエット
フリー チーム
テクニカル チーム
アーティスティックスイミングがオリンピックで正式種目として採用されたのは、ロサンゼルス1984大会からで、その30年あまりの歴史のなかで、幾度となく競技規則やルールの変更が行われています。 当時はソロ(1人)とデュエット(2人)の2種目が行われていたが、アトランタ1996大会では、チーム(8人)のみが行われた競技です。 その後、シドニー2000大会でデュエットが復活し、それ以降はデュエットとチームの2種目が行われています。
プールは水深3メートル、20メートル×25メートル以上という決まりがあり、採点は1組5人の審判員が3組で行う形式です。 審査員団は、アスリートの演技やシンクロ、難易度、音楽や振り付けの使い方などを採点します。
オリンピックでは、デュエットと8人の選手チームによる2種目の構成です。 各イベントには、フリールーティンとテクニカルルーティンの2つのパフォーマンスが含まれています。
テクニカルルーティンでは、1組が完遂度を採点し、もう1組は構成、音楽の使い方、同調性、難易度、プレゼンテーションを採点し、3組目はエレメンツ(5つの決まった動き)を採点する形式です。 主に規定の技の完遂度が高く、うまく同調しているかどうかが採点基準となります。
フリールーティンでは、1組が完遂度、同調性、難易度を採点し、もう1組は構成、音楽の解釈、プレゼンテーションを採点し、3組目は難易度を採点する形式です。 演技時間は長く構成は自由だが、そこには高い表現力と芸術性が必要となり、ある意味テクニカルルーティンよりも難しくなります。
選手は、特定の動きをしたり、上半身を水中で回転させたりするために、水から出て推進する力が必要です。 したがって、この種目には、アスリート側の優れた柔軟性、パワー、細部への注意、および調整が求められます。
テクニカルルーティンもフリールーティンも、それぞれの国、地域が思い思いのデザインの水着を身につけ、民族性に富んだ構成、音楽で演技をするため、チームごとに個性的な美しいさがあるのが特徴です。 チームによって異なる美しい個性と次々に繰り出される新しい技に注目しよう。
選手たちは手で水をかき体の位置を保ったり推進力を得たりするスカーリングという技術と、それを脚で行うエッグビーターキック(巻き足)などの技術を駆使することによって、身体を水面から大きく出す演技を行います。
その瞬間の力はかなり強く、腰まで水面に出すこともできるくらいです。 また、水中で逆さまになって下半身だけを水面から出す演技も行います。 脚技もアーティスティックスイミングでは非常に重要な技術です。 顔が水中に沈んでいる時間が長く、もちろんその間は呼吸を行うことはできないため、息を止めた状態で、ときには30秒以上の脚技を繰り出す選手もいます。 だが、技が激しいだけでは演技が雑に見えてしまい、減点対象になることもあり、激しさのなかに、丁寧さや細やかな同調性が伴っていないと高得点を得ることが難しくなった競技です。 リフトのダイナミックさのみならず、指先、つま先まで意識を行き渡らせた繊細な演技と同調性こそが、今後のアーティスティックスイミングにおける重要な要素になっていくことだろう。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
アーティスティックスイミングの起源は、1800年代後半にイギリスで行われていたスタントスイミングと呼ばれるもので、主に男性が中心の競技です。 その後、ドイツのアーティスティックスイミングと組み合わせた競技が1900年代初頭から行われ、これがアーティスティックスイミングの基礎になったといわれています。
オリンピック競技として最初に行われたのはロサンゼルス1984大会、その頃は、まだそれほど激しい演技は少なく、しなやかさと艶やかさを前面に押し出した演技構成が多かった競技です。
ところが、シドニー2000大会あたりから多種多様なリフトが行われるようになります。 さらに1、2人の選手を持ち上げて高さをアピールするリフトに、ジャンプが加わるようになり、そこから捻りを加えたり、空中でさまざまな演技を行ったりするように変化し現在ではジャンパーというポジションが確立されるほどになった演技です。
リフトはデュエットでも行われるようになり、こちらもダイナミックなジャンプが多く取り入れられるようになっています。 これらの技は、アーティスティックスイミングの大きな見どころといえるだろう。 リフトのダイナミックさに加え緻密な演技と同調性を兼ね備えた繊細さが勝負の決め手です。
演技の細かい部分にも、少しずつ変化が起こっています。 指先、つま先はピンと伸ばした美しさが重視されていたが、近年ではわざと足首を背屈させ、回転する際に少し変化をもたらすことも多くなっている演技スタイルです。 手で水面を叩いたり、円を描くようにしてなぞったりするときに生じる水しぶきすらもコントロールすることで、演技の幅を大きく広げています。
演技構成の変化は、アーティスティックスイミングにおける勢力図にも変化をもたらしているのが現状です。
オリンピックに正式採用された当時は、アメリカやカナダが強かったが、長身で手足の長い選手をそろえるロシアやスペイン、フランス、さらにはウクライナといったヨーロッパ諸国が力をつけ始めています。 さらにアジアの活躍もめざましく、最近では日本に加えて中国も強豪国の仲間入りを果たしている競技です。
日本はアーティスティックスイミングが初めて行われたロサンゼルス1984大会以来メダルを獲り続け、北京2008大会のチームでメダルを逃し、ロンドン2012大会ではデュエット、チームともにメダルなしに終わています。 だが、元来得意としていた同調性を追求し、日本の伝統文化を表現した曲や演技構成で、リオデジャネイロ2016大会ではデュエットもチームも銅メダルを奪還し、 ロサンゼルス2028大会では出場枠を獲得してさらなる活躍に挑む。
【開催地】
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
水球は己たちの鍛え上げた体と緻密な戦略や戦術、ルール変更との勝負

水球は水中の格闘技と称され、プール中で、激しくぶつかり合う唯一の球技種目です。 試合は揚力や浮力、泳力を活かしスピーディな攻撃や華麗なパスワーク、豪快なシュートなど多彩なプレーが魅力! 日本チームの活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
水球の主な強豪国と地域:
「男子:セルビア、ギリシャ、ハンガリー etc.」
「女子:アメリカ、スペイン、ハンガリー etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では欧米との順位争いに子供たちもプールでドッチボールを始める。
己たちの磨き上げた戦術と戦略が世界に通用する国と地域はどこだぁ!
【水球の特徴】
水球は水深2メートル以上のプール内につくられた縦30メートル×横20メートルのコートで、2チームがボールをゴールに投げ入れ合って得点を競う水中の球技です。 ゴールキーパーを含めた1チーム7人の選手たちは、試合中一度も底に脚をつけずにプレーします。 攻撃開始から30秒以内にシュートまで持ち込まなければならないというルールがあり、それを過ぎると攻撃権は相手に移るルールです。 試合時間は4ピリオド制(1ピリオドは8分間)、プールで行われる唯一の球技種目になります。
鋼の肉体がぶつかり合う水中の格闘技です。 水球は激しいゲームの中で各国の緻密な戦略が光る競技になります。
水球は当初、19世紀半ば(1860年代)のイギリスの川や湖で「ボールを決められた水上のポイントまで運び合うゲーム」として始まり、そのあまりの荒々しく非常に危険なスポーツであり、危険を防ぐためにルールが制定され、スポーツとしての水球が確立したとされている競技です。
1870年、ロンドン水泳協会は、屋内プールで使用するスポーツの一連のルールを開発し、スコットランドで発展した後のルールは、「ラグビーの変種」とは対照的に、フットボールのプレースタイルを強調した仕様になります。
また、水球は19世紀(1888年)にアメリカに紹介され、アメリカンフットボールのスポーツに似たラグビースタイルのプレーが水中で使用されてきた起源を持つ競技です。 しかし、世界の他の地域ではスコットランドのルールが採用され、それが今日の水球の基礎となります。 最初の国際試合は1890年にイングランド対スコットランドの間で行われた競技です。
【オリンピック競技としての歴史】
水球は、1900年にラグビーと同時に競技種目として加わり、1908年からは国同士の大会として、近代オリンピックで最も古いチームスポーツの一つにあります。 オリンピックでは、男子はパリ1900大会から、女子は100年後のシドニー2000大会に導入されてから行われている種目です。
欧州各国の国内オリンピック委員会は、1908年以来、すべての大会で金メダルを獲得しており、長年にわたって男子水球の支配的な力を発揮しています。 ハンガリーは16個のメダル(うち金メダル9個)で男子のメダルランキングでトップです。 オリンピックの女子水球は、まだ始まったばかりだが、アメリカはロンドン2012、リオ2016、東京2020で金メダルを獲得し、3連覇を達成しています。
【ルール】
種目
水球大会(女子/男子)
水球は7人の選手からなる2つのチームが、20×10メートルから30×20メートルの間で異なる大きさのプールで対決する競技です。 (FINA公認の試合では、男子は30×20メートル、女子は25×20メートルのプールが必要) 試合は8分間のクォーターを4回行います。
水球は鍛え上げられた大きな体が、プール内を縦横無尽に行き交い、激しくぶつかり合う競技です。 審判から見えにくい水中では、相手をつかみ、蹴り上げるといったプレーが少なくなく、ボールを持っていない選手に対してこれを行うとファウルになるが、ボールを持っている選手に対しては、荒々しいコンタクトが許されています。 この激しさから「水中の格闘技」と称され、さらにスピーディーなゲーム性を兼ね備えたスポーツでもあり、ゴール前を固めるゾーンディフェンスや、素早いカウンターアタックなど多彩な戦術も魅力の一つです。
ゴールキーパー以外の選手は、ボールを片手で扱うことが定められています。 1チーム7人であることや手を使ってボールをゴールに投げ入れること、選手交代の回数が自由であることから、ルールはハンドボールに似ているともいわれる競技です。 ゴール前、選手たちが軽々とボールを扱い、華麗なパスワークでディフェンスのフォーメーションを崩す場面などは、目を見張るものがあります。
ポゼッションは30秒間続き、その時間内にチームがゴールを攻撃しない場合、ポゼッションは相手に渡されるルールです。
水球はファウルが多いことも特徴の一つで、それが得点を左右する重要なポイントにもなります。 ファウルは、オーディナリーファウルとパーソナルファウルの2種類があり、前者は軽微な反則と見なされ攻撃権は移らないルールです。 一方、パーソナルファウルをした選手は自軍ゴール横にある「退水ゾーン」で20秒間の待機が命じられます。 その場合は相手チームよりも1人少ない状態でのディフェンスを強いられるため、失点につながりやすい状態です。 選手はプールの底に足をつけず、身体を水中で垂直に維持しながらプレーします。 それを可能にするのが、巻き足と手の平の動作で生まれる「揚力」です。 相手のディフェンスを超えてシュートを打つときは、体をコントロールし、浮力をつくる「スカーリング技術」を合わせることで、瞬間的に上半身を思い切り高く水上に持ち上げます。 片手でボールをつかだ状態でジャンプし、全身の力を利用して打つシュートは、男子では時速70キロメートル程度、女子は時速50キロメートルを超えるスピードです。 この豪快なシーンも、水球の大きな見どころのひとつになります。
水中でありながらスピード感あふれる展開や激しい肉体のぶつかり合いは迫力満点です。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
イギリスを発祥の地とし、ヨーロッパを中心に普及が進んだこともあり、男子はヨーロッパの各国、地域がオリンピックのメダルの多くを獲得しています。 なかでも国内にプロリーグを有するハンガリーは、シドニー2000大会から北京2008大会までの3連覇を含め、金メダル数は合計9個を数える強豪国です。 ロンドン2012大会ではクロアチアが、リオデジャネイロ2016大会ではセルビアが金メダルを獲得するなど、国内で絶大な人気を集める旧ユーゴスラビア圏の国々の実力が拮抗しています。 金3個、銀2個、銅3個の実績を持つイタリアもメダル常連国です。
一方女子は、シドニー2000大会から正式種目となったこともあり、自国開催で強化に力を入れたオーストラリアがその大会で優勝しています。 オリンピックデベロップメントプログラムを導入し、選手発掘と強化を継続的に進めているアメリカが、ロンドン2012大会、リオデジャネイロ2016大会で連覇を達成している強豪国です。 この2ヵ国以外では、北京2008大会でオランダが、アテネ2004大会でイタリアが、金メダルを獲得しています。
男女とも強豪国に共通しているのは、大きな体格、長い手足を利用した戦術、戦略です。 攻撃時間の30秒をしっくり有効に使い、センターポジションの選手にボールを集めてゴールを奪う攻撃パターンが主流になります。 素早いパス回しからディフェンスの隙を突いて、ロングシュートを豪快に打ち込むこともある試合展開です。
水球をさらに世界的に発展させていくためには、泳力を生かしたスピーディーな攻撃が得意な国や「パスラインディフェンス」というカウンターアタックのような戦術を実現する日本など、新たな勢力の台頭が持たれています。 国際水球連盟ではワールドリーグを開催して、さまざまなレベルの国が戦える機会を増やし、コーチやレフェリーの強化を国際的に図っていくなど、新たな動きを開始している競技です。 従来の激しい格闘技的な要素を残しつつも、競技としての新たな魅力の可能性も押し広げていくために、より展開が早くなることを狙い、コートの長さや攻撃の時間を短縮するルール変更も予定されています。 水球の戦術、戦略が今後どのように変わっていくかに注目です。
パワープレーからスピードプレーへとルール変更が勢力図の変化をもたらすか期待が高まります。
日本はリオデジャネイロ2016大会で、32年ぶりのオリンピック出場を果たした男子の日本代表です。 その原動力となったのは、相手にパスをさせない守備で、ボールを奪ってカウンター攻撃をしかける「パスラインディフェンス」という作戦にあります。 リオデジャネイロ2016大会では未勝利に終わったが、強豪国の高さとパワーに対抗して、スピードと持久力で勝負する日本独自の戦い方を強化し、自国開催のオリンピックで強豪相手に勝利するべく準備を進めているチームです。
東京2020大会で初出場初優勝を目指す女子は、24時間使用可能の練習プールを拠点とし、強化合宿を増やすことで底上げを図っています。 男女ともに海外でプレーする選手も増え、新たな日本の水球の歴史をつくることに意欲を燃やしているチームです。
東京2020大会では、力を発揮することができず、ロサンゼルス2028大会では自国開催の経験を活かし活躍に期待がかかります。
【開催地】
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
スポーツクライミングは知力と判断力、己の体一つで限界を超える戦い

スポーツクライミングは指先に渾身の力を込め、高い壁を登る競技です。 試合は2種目、各選手は素手とクライミングシューズのみで挑み、身体・精神的能力と空間把握能力、柔軟性、高度なテクニックに注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
スポーツクライミングの主な強豪国と地域:
「女子複合:スロベニア、日本 etc.」
「男子複合:スペイン、アメリカ、オーストリア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では、欧米、オセアニア、アジア勢との順位争いに野生本能が目覚める。
己の燃え上がる情熱で、世界最高峰に高くそり立つ壁を制覇できる国と地域はどこだぁ!
【スポーツクライミングの特徴】
小さい頃、野山の崖を競争しながらかけ登った経験がある方も多いのではないだろうか。 スポーツクライミングは、その競技性を極限まで高めたスポーツで、選手は垂直にそり立つ壁をカラフルなホールドを使って道具を持たずに自身の体一つで登る競技です。
スポーツクライミングは、過去20年間で絶大な人気を博した現代的な種目になります。 クライマーの39%が18歳以下で、屋外と屋内のより都会的な形式の両方で練習される、若い混合スポーツです。 世界約150ヵ国に2,500万人以上の登山家がいます。
高くそり立つ壁に、自身の体ひとつで挑む選手たち、指先に込めた力で、限界を超えていく試合展開です。
【スポーツクライミングの歴史】
1985年、イタリアのトリノ近郊のバルドネッキアにクライマーたちが集まり、一定の時間内にクライミングを行う初の組織的なリードコンペティション「SportRoccia」が開催されます。 その1年後、フランスのリヨン近郊のヴォー・アン・ヴェランで、人工クライミングウォールを使った最初の競技会が開催されたのが始まりです。
【オリンピック競技としての歴史】
スポーツクライミングは、2018年のブエノスアイレスユースオリンピックでオリンピックの舞台に第一歩を踏み出します。 このイベントはあまり宣伝されていませんでしたが、一般の人々はこのエキサイティングなスポーツのスペクタクルとサスペンスに感銘を受けた競技です。 ユース大会で人気を博したスポーツクライミングは、東京2020大会で初披露され、新たな競技としてオリンピック種目に加わります。 これらのイベントの独創性と、この分野の視覚的、美的、刺激的な性質により、都市や自然など、非常に多様な環境で開催できる若者にとって非常に人気があり、 広く実践されているスポーツです。
東京2020大会では、各選手が3種目すべてに出場し、3種目の合計結果が最終スコアに反映され、最も低いスコアのクライマーが、スポーツクライミング史上初のオリンピック金メダルを獲得しています。
スポーツクライミングは、ブレイキン、サーフィン、スケートボードと並ぶパリ2024大会の新4競技の1つでもあり、ロサンゼルス2028オリンピックの種目にも採用されます。
【リマインド東京2020大会仕様】
東京2020大会で実施された種目は、同じ条件で設置された高さ12メートルの壁を2人の選手が同時に登り速さを競う「スピード」、高さ4メートルの壁を制限時間内にいくつ登れるかを競う「ボルダリング」、制限時間内に高さ12メートル以上の壁の、どの地点まで登れるかを競う「リード」の3つです。
オリンピックでは、各選手がこの3種目を行い、各種目の順位の掛け算で順位が決まります。 どの選手も得手不得手があるため、2種目終了時点では最終順位の予測ができない競技です。
種目によって安全確保のためのロープなどの器具は装着するが、登るために道具の使用は許されず、選手とクライミングシューズのみで壁に挑みます。 身体能力とテクニック、そして攻略するための読みが必要です。 何よりも知力や判断力がないと勝利を手にすることができないスポーツになります。
【ルール(※パリ2024大会仕様一部変更あり)】
実施種目
ボルダー&リード複合(女子/男子)
スピード(女子/男子)
オリンピックのスポーツクライミングは、ボルダー、スピード、リードの3種目です。 パリ2024大会では、スポーツクライミングの2種目が、それぞれのオリンピックチャンピオンを決めます。 1つはボルダーとリードの複合競技で、もう1つはスピード種目のみの競技です。 異なる3種目の魅力と高度なテクニックに脱帽する試合展開は見逃せません。
「ボルダリング」
ボルダーでは、選手はロープを使わずに高さ4.5メートルの壁を、限られた時間で、できるだけ少ない回数で登ります。 高さ4.5メートル程度の壁に極限まで難しく設定されたコースを4分の制限時間内にいくつ登れるかを競い合う種目です。 選手は事前に練習ができない中でルートを考えながら登り、トップ(最上部)のホールドを両手で保持することができれば、その課題(コース)はクリア(完登)になります。 選手はロープ無しで臨み、途中で落下しても再度トライできる試合です。 ボルダリングの壁は、指先しか、かからない小さなものから、両手でも抱えきれないホールドが設定されており、次のホールドには左右のどちらかの足をかけるか、 そのとき手はどこをつかむか、制限時間内に自分の能力を考えながら登らなければ攻略できません。 また、途中から手前に倒れこむオーバーハングになっていることが多いため、頭と体の柔軟性も必要です。 頭脳と手足を上手に使いながら驚くような姿勢で、一つ一つ課題をクリアしていく選手を思わず応援したくなります。
「リード」
リード種目では、選手は事前にルートを見ずに、高さ15メートルを超える壁を6分間でできるだけ高く登ることが求まられる種目です。 この大会のルートは、大会期間中、ますます複雑で難易度が高くなり、すべてのアスリートの身体的および精神的能力が要求されます。 6分の制限時間内に高さ15メートル以上の壁の、どの地点まで登れるかを競い合う試合です。 選手は安全のために、ロープをクイックドロー(ロープを引っ掛ける器具)に掛けながら登り、トップのクイックドローにロープを掛ければ「完登」となります。 途中で落ちた場合はそこが記録となり、再トライはできないルールです。 完登した選手、あるいは同じ高さまで登った選手が複数いる場合は、タイムのよい選手が上位となります。 多くの選手は一手でも上に到達するよう渾身の力を込めて壁を登る試合展開です。 ダイナミックなクライミングが見どころとなります。 ボルダリングとリードについては、他の選手のクライミングを見ることは見た選手にとって大きなプラスになるため、自分が登る前は、他の選手のクライミング を見ることができない「オンサイト方式」を採用している種目です。 競技前の選手は隔離されていて、競技開始直前に全員に数分に限りルートを見る時間が与えられます。
「スピード」
スピードは、精度と爆発性を兼ね備えた1対1のエリミネーションラウンドで、時間との戦いを繰り広げる壮大なレースです。 最高のアスリートは、高さ15メートル、傾斜5度の壁を、男子は6秒未満、女子は7秒未満で登ります。 世界共通のスピードルートで設定された、高さ15メートル、95度に前傾した2つの壁が用意されており、安全確保のためのロープを装着した2人の選手がタイムを競い合う種目です。 2人の瞬発力がぶつかり合う試合が展開されます。 フライングは一発で失格です。 優勝タイムは男子では5~6秒、女子で7~8秒、あまりの速さに驚きます。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
国ごとに異なる得意種目 種目ごとに、どの選手に有利か注目です。 伝統的に強いのは、フランス、イタリア、ドイツ、オーストラリア、スロベニアなど険しい岩壁を擁するヨーロッパ アルプス山脈周辺の国々だが、近年はアジアや北米も力をつけてきています。 ただし、これまではスピード、ボルダリング、リードで、それぞれ別に競技が行われてきたため、パリ2024大会で実施される2種目で競う経験をしてきた選手は少なく、オリンピック2カ国目の採用の競技ということもあり、勝利の行方は、極めて予測が難しいだろう。
日本がトップクラスなのは、身体能力だけでなく知力や空間把握能力も問われるボルダリングです。 ロサンゼルス2028大会では20歳代など若い世代に注目で女子はボルダリング界をリードする有力選手たちに注目が集まります。 持久力を必要とするリードも日本の得意種目です。 ロサンゼルス2028大会は2種目で競い、スピードを含め活躍できる選手の登場に期待しましょう。
スポーツクライミング開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
スケートボードは都市環境コースを、己のパフォーマンスで魅せる戦い

スケートボードはアメリカが発祥とされ若者に人気の競技です。 試合は駆け上がるスリルの中、独創的なトリックを披露し、技の難易度や高さ、スピード、オリジナリティ、完成度が求められ、技の成功に注目! 日本勢の活躍に期待する。開催国アメリカ勢は。
世界状況
スケートボードの主な強豪国と地域:
「女子ストリート:日本、ブラジル、 女子パーク:日本、イギリス etc.」
「男子ストリート:日本、ブラジル、アメリカ、男子パーク:オーストラリア、ブラジル、アメリカ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国々です。
ロサンゼルス2028大会では、欧米、オセアニア、アジア勢との順位争いにストリートカルチャーの音楽が響き渡る。
己の滑りで、見事にパフォーマンスを決める国と地域はどこだぁ!
【スケートボードの特徴】
スケートボードは、サーフカルチャーが始まった1950年代にアメリカで発展した若くて壮大なスポーツです。 スケートボードは、前後に車輪がついた板に乗り、トリック(ジャンプ、空中動作、回転などの技)を行い、その技の難易度や高さ、スピードなどを評価する採点競技になります。 独創的トリックと駆け上がるスリル、観客のボルテージは最高潮へ達する競技です。
【スケートボードの歴史】
スケートボードの起源は諸説あるが、1940年代にアメリカ西海岸で木の板に鉄の車輪をつけて滑った遊びが始まりとされており、1950年代に入って木製の板にゴム製の車輪がついた(ローラーサーフィン)という商品が開発され、これが現在のスケートボードの原型になったといわれています。
その後、1980年代のアンダーグラウンドなオルタナティブカルチャーの一部となり、自由、反逆、スリルを求めるという価値観と密接に関連し始めたスポーツです。
このスポーツは発展を続け、特に若者に人気の比較的新しいスポーツで、1980~1990年代にかけて世界に広まり、1990年代後半からは、グラフィックや音楽、ファッションをともなったストリート・カルチャーの中心的位置を占めるようになります。 21世紀初頭には、より広く普及し、若者の間で大ヒットしたスポーツです。
【オリンピック競技として歴史】
2021年の東京2020大会でオリンピックデビューを果たしたスケートボードは、パリ2024大会でも再びプログラムに採用され、フランスの首都パリ中心部にある有名なコンコルド広場で開催されます。
オリンピックで行われる種目は2つ、町の中を滑るようなコースで技を競う「ストリート」と、複雑な形のコースで技を競う「パーク」です。 それぞれ、男女別に行われます。
【ルール】
実施種目:
ストリート(女子/男子)
パーク(女子/男子)
世界最高峰のスケートボーダーたちがパリ2024オリンピックで対決し、パークとストリートという最も人気があり、壮観な2種目で競い合います。 アスリートは、難易度、スピード、動きの範囲の基準を満たして、最も印象的なトリックを行う必要がある競技です。 大会は予選と決勝の2ラウンドで行われ、繰り出されるトリックの数々、フェスティバルのような雰囲気を楽しみましょう。
「ストリート」
街にあるような階段や手すり、縁石やベンチ、壁や坂道などを模した直線的なセクション(構造物)を設置した「ストリートライク」なコースで行われます。 選手は1人ずつ競技を行い、セクションを使いながら、さまざまなトリック(技)披露し、45秒間のランニングを2回、5つのトリックをこなすことで、ボードをどのようにコントロールするかが判断される種目です。 そのトリックの難易度や高さ、スピード、オリジナリティ、完成度、そして全体の流れを見て審査員が総合的に判断し採点されます。
縁石を模したレッジや、手すりを模したハンドレールでは、デッキ(板)を直接レールやレッジに当てて得る「スライド」、デッキとウィール(車輪)をつなぐ金属部分のトラックを当てて滑る「グラインド」がよく行われる種目です。 レールやレッジに飛び乗る際には、選手が手を使うことなくボードとともにジャンプする「オーリー」というトリックを活用します。 これは、なかなか難しいテクニックなのだが、選手たちはごく普通に、これを繰り出す種目です。 ここでは、都市環境をイメージしたレールやレッジへの乗り方や滑り方、レールやレッジ上を滑る距離にも注目しよう。
スケートボードやサーフィンのように横向きに乗る競技には「スタンス」と呼ばれる選手の向きがあり、進行方向に対して左足が前になるスタンスを「レギュラースタンス」、右足が前になるスタンスを「グーフィースタンス」と呼びます。 これは右利き、左利きのように個々それぞれ違い、本来のスタンスを「メインスタンス」、逆のスタンスを「スイッチスタンス」と呼ぶ乗り方です。
同じトリックでもメインスタンスで行う場合とスイッチスタンスで行う場合の評価は違い、もちろん難易度も格段に上がります。 デッキを回転させるフリップもよく行われるが、選手自身が回りながらデッキも回し、手を使わずに再び足に戻すというハイレベルなトリックも見れる試合展開です。 まるで足にデッキがマグネットで吸いつけられているように見えるトリックになります。 デッキの回し方も、水平、縦、横とまさに三次元、見ている者の意表を突くテクニックを成功させることこそ、スケートボード最大の見どころです。
「パーク」
大きな皿や深いお椀をいくつも組み合わせたような、複雑な形をした窪地状の変化に富んだコースで行われるパーク競技になります。 アスリートはそれらを使用してスピードを上げ、空中でトリックを行う種目です。 スケートボーダーは、ジャンプ中に行うトリックの高さとスピード、および表面全体とすべての障害物を使用する能力によって判断されます。 45秒間のランを3回行い、3回のうち3回を最終ラウンドのスコアとしてカウントされるルールです。
直線的なセクションが中心のストリートに対して、パークはアール(湾曲)がついた曲線的な形状で、その窪地の底から曲面を昇ると傾斜は急になり、上部は垂直もしくは垂直に近くなります。 ここを一気に駆け上がり、空中へ飛び出す美しいエア、トリックが、パークでは中心となる試合展開です。
キッカー(ジャンプ台)で空中に飛び出すと、トリックのバリエーションも増えます。 空中でデッキを手でつかむグラブも、どこをつかむか、どちらの手でつかむか、そのときの姿勢をどうするか、などによって難易度が異なる種目です。 飛びながらデッキを手でつかむグラブや、デッキを回転させたり、選手自身が回転したり、それらの組み合わせや、回転方向や回転位置によって難易度と独創性を上げていきます。 また、上部のリップ(縁)を使ったスライド系のトリックも行われ、いずれにしても、まるで浮遊しているかのようなパフォーマンスで、多くの複雑なトリックを行い、いかにスリリングな、かっこよさを披露できるかがパークの見どころです。 パフォーマンスの大きさやスピードにも注目が集まります。
スケートボードでは、コース取りや順番、種類はすべて自由です。 同じトリックでも、スピードがあるのとないのでは流れのシャープさが異なります。 スピードも重要な要素であるが難易度や独創性を加味して総合的に評価される競技です。 採点は、トリックの難易度や完成度、オリジナリティ、スピードに加えて、全体の流れやダイナミックさ、安定感、浮遊感なども考慮して総合的に評価され、数値化されます。 スケートボードは、軽快なBGMが流れる開放的なムードで行われ、「すごい!」「かっこいい!」と思われるトリックの数々や高さ、スピードに圧倒されながら、フェスティバルのような雰囲気が楽しめる競技です。
【ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望】
強豪は、やはり発祥の地アメリカで、まずは出場選手に注目が集まります。 ストリート、パークともに、そして男女ともに発祥地のアメリカの強さが他を圧倒しているが、近年、スペインやフランス、ドイツ、スウェーデン、チェコなどを中心としたヨーロッパ、さらにブラジル、オーストラリアも力をつけている競技です。 ただ、選手の年齢層が低く、10歳代後半から20歳代が中心であるため、若くて実力のある選手が次々と登場しています。 初めて東京2020オリンピックに採用されたこともあり、再びロサンゼルス2028大会へ挑んでくるか、世界の選手の動向から目が離せない競技です。 まず出場メンバーに注目が集まります。
日本は10代の選手を中心に世界との差を着実に縮めている競技で、東京2020大会の経験を活かして更なる世界への舞台にチャレンジしていくだろう。 有力選手の活躍に期待する。
スケートボード 開催地
※東京2020大会組織委員会 公式サイトより
新規検討競技
ファイナルセレモニー
ロサンゼルス2028 オリンピック 参加国リスト
計XX競技&種目が実施され、参加人数12,000人以上、計207カ国と地域が参加予定です。
公式スタッフ&ボランティア、観客人数延べ10万人~100万人想定!
最新の進捗情報が入り次第、更新を予定しています。
Powered by Solar Energyで製作しています。2025/3/9
パラリンピック 8月15日から27日 13日間
パラリンピック競技の参考内容です。(パリ2024大会まで)
22競技プラス「クライミングとサーフィン」が追加を検討中
- パラアーチェリー Ver.
- パラ陸上競技
- パラ水泳 Ver.
- パラ卓球 Ver.
- ボッチャ Ver.
- シッティングバレーボール Ver.
- ゴールボール Ver.
- ブラインドフットボール(5人制サッカー)Ver.
- パラバトミントン Ver.
- パラボート Ver.
- パラカヌー Ver.
- パラサイクリング(自転車)トラック Ver.
- パラライディング(馬場馬術)Ver.
- パラパワーリフティング(重量挙げ)Ver.
- パラ柔道 Ver.
- パラテコンドー Ver.
- パラ射撃 Ver.
- パラトライアスロン Ver.
- 車いすバスケットボール Ver.
- 車いすラグビー Ver.
- 車いすテニス Ver.
- 車いすフェンシング Ver.
アーチェリーは肢体を巧みに使い工夫と個性で的を狙う、己との勝負!

パラアーチェリーはパラリンピック原点の歴史を持つ競技です。試合は弓と矢、補助用具、残存機能を巧みに使ったハイレベルな競技と選手に応じた多彩多様なスタイルに注目。日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラアーチェリーの主な強豪国と地域:
「アメリカ、中国、インド、イラン、チェコ、トルコ、イタリア、イギリス、チリ、RPC etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダルを獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会は欧米や中東、アジア諸国勢との的を狙った順位争いに天使の矢が的を得る。 己に打ち克ち、巧みに的を捉え、強豪国の列強を揺るがす国はどこだぁ!
パラアーチェリーの特徴:
パラリンピックのアーチェリーは50メートル、または70メートル先にある的を狙い得点を競い合う、肢体不自由の選手を対象としたアーチェリー競技です。 試合はオリンピックとほぼ同じルールで行われるが、ディサビリティーズの内容や程度に応じて補助用具の使用が認められています。
ディサビリティーズ者を対象にしたアーチェリーが行われるようになったのは1940年代からで、1948年にストーク マンデビル病院で車いすのアーチェリー大会が開催されたのが始まりです。 この大会はのちに「パラリンピックの原点」と言われるようになります。 パラリンピックとしてのアーチェリーは、第1回ローマ1960大会で正式競技として採用され、以来、継続して実施されている競技です。 かつては、選手はディサビリティーズの程度によって、W1(四肢にディサビリティーズがあり、車いすを使用)、W2(下半身のディサビリティーズにより車いすを使用)、ST(平衡機能ディサビリティーズがあり立つか、いすに座って競技)の3クラスに分類されています。 現在のパラリンピックは、W2とSTはオープンクラスとして統合され実施されているクラスです。
クラスと種目別:
競技種目は3部門に大別され、弓の形が異なる「リカーブオープン」と「コンパウンドオープン」、そして、W1クラス限定の「W1」が設けられています。 リカーブオープンとコンパウンドオープンはいずれもW2とSTクラスを含み、それぞれの弓を使って競技を行うのに対して、W1部門ではリカーブ、コンパウンドどちらの弓を使うかは選手の自由です。 全部門で男女別の個人戦と、男女各1名による混合(ミックス)戦が行われます。
的までの距離と的のサイズは部門ごとに異なり、リカーブオープンでは、70メートル先にある直径122センチメートルの的で、10点を中心に外側に向かって点数が低くなり1点まで得点帯がある的を使用した競技です。
コンパウンドオープンでは、50メートル先にある直径48センチメートルの的で、10点を中心に外側に向かって点数が低くなり5点の得点帯までの「6リング」と呼ばれる的を使用します。
W1部門では、50メートル先にある直径80センチメートルの的で、10点を中心に外側に向かって得点が低くなり1点の得点帯まである的を使用した競技です。 実施種目は男女別の個人戦と混合(ミックス)戦の全9種目で、ランキングラウンドという予選を行い、その順位によって決勝トーナメントの対戦相手が決まります。 決勝トーナメントは1対1の対戦で勝敗が決まる形式です。
ルールと得点方法:
使用できる2種目の弓のうち「リカーブ」は、オリンピックでも使われる一般的なタイプで、もう一つの「コンパウンド」は、上下の両先端に滑車がついたタイプで、その滑車の動きによってリカーブとは異なる力で弦を引き、矢を射(う)つことができる弓になります。
パラリンピックはオリンピックでは見ることのできない、コンパウンドを使用したアーチェリー競技が見られるのも魅力の一つです。
かつて選手はディサビリティーズの程度によって3つのクラス(W1、W2、ST)に分類され、ディサビリティーズに応じて補助用具の使用やアシスタントをつけることもできます。 車いすに座ったまま弓を引いたり、口で弦を引いたり、それぞれに工夫しながら、個性あふれるさまざまなスタイルで矢を放つのが見どころです。
予選ラウンドでは選手は72本の矢を射ち、合計得点によりランキングが決まり、トーナメントに進みます。 試合形式は、部門によって異なり、リカーブ部門の個人戦は5セットマッチで行われ、ヒットごとに勝者2、引き分け1、敗者0のポイントが加算され、合計6ポイント以上先取すると勝ちです。 ミックス戦は4セットマッチで行われ、個人戦と同様にポイントが加算され、ペアの合計で5ポイント以上先取すると勝ちとなります。
コンパウンドとW1部門の個人戦は1エンドにつき3射(30点満点)射ち、5エンドの合計得点(150点満点)の高い選手が勝ちとなる形式です。 ミックス戦は、1エンドにつき4射(1人2本40点満点)射ち、4エンドの合計得点(160点満点)の高いチームが勝ちです。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
パラリンピックのアーチェリーはイギリスや中国が強豪国として知られ、それをアメリカやイラン、韓国などが追っています。 選手層の厚さを誇る中国やオーストラリアなど新たな国の台頭も見られ、世界記録が更新された種目もあり、ロサンゼルス2028大会に向け競技の広がりや競技力のさらなる向上に期待が高まるところです。
日本勢は第2回パラリンピックである東京1964大会に初出場以来、各大会へ選手を送り、これまで多数のメダルを獲得しています。 ロサンゼルス2028大会に向け、強化選手や育成選手などを合宿や海外遠征で強化を図り、さらなる躍進を狙う。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
トラック Ver.
トラックは己の競技能力を最大に引出し、過酷な環境の中で限界に挑む

パラ陸上トラックは参加人数が最も多く、公平にレースが行えるようにクラス分けが工夫され、試合は1秒でも速く駆抜けるために競技レベルや記録も急速に向上し、世界新記録の誕生に注目。日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラ陸上競技 トラックの主な強豪国と地域:
男子「ギリシャ、フランス、中国、ノルウェー、アメリカ、RPC、アイルランド、アルジェリア、コロンビア、イギリス、クウェート、チュニジア、オーストラリア、アラブ首長国連邦、ウクライナ、アルゼンチン、インドネシア、ブラジル、ポーランド、ベルギー、フィンランド、メキシコ、タイ、カナダ、サウジアラビア、ドイツ、コスタリカ、南アフリカ、スペイン、ナミビア、モロッコ、ベネズエラ、ニュージーランド、オランダ、スイス、イタリア、ブルガリア、ウガンダ etc.」
女子「ベネズエラ、中国、キューバ、ウクライナ、スペイン、アゼルバイジャン、アメリカ、イギリス、オーストラリア、RPC、ニュージーランド、コロンビア、ドイツ、フィンランド、イタリア、オランダ、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、フランス、ポーランド、南アフリカ、スイス、メキシコ、ケニア、エチオピア、チュニジア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会 パラ陸上競技 トラックで金 銀 銅メダルを獲得した諸国です。
ロサンゼルス2028大会は欧米やアフリカ、アジア諸国勢とのクラスごとに繰り広げられる順位争いに神々が微笑む。
年々増える選手や参加国、向上する競技力、人間の可能性を求め切磋琢磨で練習を繰り返して身につけた走りをレースで発揮するパラ陸上競技 トラックの新星が現れる国はどこだぁ!
パラ陸上競技 トラック種目の特徴
パラリンピックの陸上競技は第1回ローマ1960大会から正式競技として実施されています。 幅広いディサビリティーズ(disabilities)を対象とすることで夏季大会の競技の中で参加人数は最も多いのが特徴です。
パラリンピックの大きな特徴はクラス分けと呼ばれるシステムで、対象となるディサビリティーズが知的ディサビリティーズや麻痺、四肢の欠損など多岐にわたるため、極力条件を揃え公平にレースが行えるようにし、各選手のクラスは専門の資格を持つ判定員が医学的、運動機能的な側面から審査して決めています。
出場選手をディサビリティーズの種類や程度、運動能力などに応じてクラス分けし、レースはクラスごと、あるいは隣り合うクラスを合わせた統合クラス(コンバインド)で実施される仕組みです。
トラック競技は短距離から中、長距離、リレー種目(4×100メートル)などが実施されてきたが、実施種目やクラスは参加選手数に応じて大会ごとに検討され、固定されていません。
パラリンピックの陸上競技ルールとは
競技ルールはオリンピックと同じルールを基本に、ディサビリティーズの内容や種目の特性などに応じて一部のルールが変更されます。 選手たちはディサビリティーズを補いながら、コンマ1秒を削るべく己の限界と向き合いながら挑戦できる環境の下、実施される大会です。 例えば、視覚ディサビリティーズクラスではT11(全盲など)の選手全員とT12(弱視)の一部の選手(伴走者と走るか単独走か選べる)は目の代わりとなり、視覚から得られる情報を補う伴走者(ガイドランナー)とロープを握り並んで走ることができます。 ガイドランナーは選手の安全を第一に、コース状況やタイム、周囲の様子などを言葉で伝え、フィニッシュラインへと導く役割です。 ただし、選手を先導したり、フィニッシュラインを選手より先に越したりすると失格になります。
肢体不自由のクラスで四肢に欠損がある選手は、左右バランスを取ることを目的に競技用の義肢を使用することが可能です。 特に義足は近年、素材や形状などの研究、開発が進んでおり、ルールの範囲内で選手は自身のディサビリティーズに合わせて調整もできます。 だが、義足は想像以上に固く反発力を競技力に活かすには、選手自身に義足を十分に合せて馴染ませ反発力を受けとめられる筋力や技量が必要です。 同じモデルの義足を使っていても、記録に差が見られるのはこうした点にも要因があります。
車いすクラスはレーサーと呼ばれる高速走行用に開発された競技用車いすを使用し、ルールの範囲内で自身のディサビリティーズや体格に合わせて各パーツをカスタマイズすることが可能です。 選手は3つの車輪を腕力など上半身の力だけで操作することが求められます。 軽量性などレーサーの性能は年々向上しているが、座席の高さや車輪を駆動させるための部品のサイズなどは自分仕様にするプロセスが必要です。 自身の力を最も効率よく車輪に伝えられるように様々なパーツをミリ単位で微調節し、トライアンドエラーを繰り返しながら最適なポジションやセッティングを探ることも記録向上に欠かせない地道なプロセスになります。
陸上競技のクラスとは
パラリンピック陸上競技のクラスはアルファベット「T」または「F」と2桁の数字を組み合わせて表記しています。 「T」はトラック競技/跳躍競技/マラソン、「F」は投てき競技です。 数字は10の位がディサビリティーズの種類を表し、1の位の数字が小さいほどディサビリティーズの程度が重いことを表しています。
パラリンピック陸上競技の主なクラス紹介
T/F11、T/F12、T/F13は視覚ディサビリティーズがある選手のクラス。
T/F20は知的ディサビリティーズがある選手のクラス。
T/F30は脳性まひ、または脳損傷に起因する協調運動障害(アテトーゼ、運動失調および/または筋緊張)がある選手のクラス。
F31、T/F32、T/F33、T/F34は車いす、または投てきフレームを使用し、T/F35、T/F36、T/F37、T/F38は立位で競技を行う。
T/F40、T/F41は低身長症の選手のクラス。
T/F42、T/F43、T/F44は下肢欠損、脚長差、下肢の筋力低下、下肢の他動間接可動域制限がある選手が立位で競技を行う。
T/F45、T/F46、T/F47は上肢欠損、上肢の筋力低下、上肢の他動間接可動域制限がある選手が立位で競技を行う。
T/F51、T/F52、T/F53、T/F54、T/F55、T/F56、T/F57は頸髄損傷、脊髄損傷、切断、機能障害などにより筋力低下、可動域制限下肢欠損、脚長差がある選手が車いす、または投てきフレームを使用して競技を行う。
T/F61、T/F62、T/F63、T/F64は下肢欠損の選手が義足を使用して立位で競技を行う。
オリンピックに比べ実施される種目数は少ないが、クラス別に競技する1種目の決勝レースの数が多いのが特徴です。(実施されないクラスも含む)
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは
義肢やコーラーとひとつになり、己の能力を引き出した選手たちが駆け抜ける戦いになります。 パラリンピック陸上 トラック競技では近年は中国が圧倒的な強さを誇り、1人で複数の距離に挑む選手もいます。 視覚ディサビリティーズクラスのトラック種目では、T11の選手全員とT12の一部の選手は伴走者(ガイドランナー)と並んで走るため、1選手につき2レーンが与えられます。 ガイドランナーの力量も問われる種目であり、短距離では選手とともに磨き上げ、スタートからフィニッシュまでピタリと同調した走りも見どころです。 知的ディサビリティーズクラスはディサビリティーズの程度によるクラス分けはなくT20のみだが、選手によりディサビリティーズの特性が異なるのが特徴になります。 近年、記録の伸びが顕著なクラスの一つです。
走ることはスポーツの基本であり、どのクラスも新しい選手の参加が増えてきています。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
フィールド Ver.
フィールドは己の競技能力と独自スタイルを最大に引出して限界に挑む

パラ陸上フィールドは公平に競い合えるようにクラス分けが工夫され、試合は練習方法や競技レベル、記録が伸びるなか、自己ベストを目指す選手のパフォーマンスや世界新記録の誕生に注目。日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラ陸上競技 フィールドの主な強豪国と地域:
男子「アメリカ、インド、イギリス、ポーランド、中国、フランス、イラン、キューバ、アゼルバイジャン、スペイン、マレーシア、ギリシャ、オーストラリア、RPC、ニュージーランド、ウクライナ、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、南アフリカ、ドイツ、デンマーク、イタリア、ウズベキスタン、オマーン、モロッコ、アルジェリア、チュニジア、クロアチア、ヨルダン、カタール、イラク、ポルトガル、カナダ、チェコ、ブルガリア、クウェート、パキスタン、ラトビア、スリランカ、セルビア、スロバキア etc.」
女子「ブラジル、ウズベキスタン、ウクライナ、スペイン、アルジェリア、ポーランド、RPC、クロアチア、中国、アメリカ、ハンガリー、イギリス、ニュージーランド、エクアドル、オーストラリア、イタリア、スイス、オランダ、フランス、ウズベキスタン、メキシコ、エクアドル、モロッコ、チェコ、チュニジア、ナイジェリア、コロンビア、アルゼンチン、チリ、ラトビア、ベラルーシ、ドイツ、フィンランド、イラン etc.」
上記の強豪国は東京2020大会 パラ陸上競技 フィールドで金 銀 銅メダルを獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会は欧米やアフリカ、アジア諸国勢とのクラスごとに繰り広げられる順位争いに神々が微笑む。年々増える選手や参加国、向上する競技力、人間の可能性を求め切磋琢磨で練習を繰り返して身につけたパフォーマンスを発揮するパラ陸上競技 フィールドの新星が現れる国はどこだぁ!
パラ陸上競技 フィールドの特徴
パラリンピックの陸上競技は第1回ローマ1960大会から正式競技として実施されています。 幅広いディサビリティーズ(disabilities)を対象とすることで夏季大会の競技の中で参加人数は多いのが特徴です。
パラリンピックの大きな特徴はクラス分けと呼ばれるシステムで、対象となるディサビリティーズが知的ディサビリティーズや麻痺、四肢の欠損など多岐にわたるため、極力条件を揃え公平にレースが行えるようにし、各選手のクラスは専門の資格を持つ判定員が医学的、運動機能的な側面から審査して決めています。 出場選手をディサビリティーズの種類や程度、運動能力などに応じてクラス分けし、試合はクラスごと、あるいは隣り合うクラスを合わせた統合クラス(コンバインド)で実施される仕組みです。
フィールド競技は跳躍と投てきが行われ、跳躍競技には走高跳や走幅跳、三段跳があり、投てき競技には砲丸投、やり投、円盤投に加え、パラリンピック独自の種目、こん棒投が実施される予定になります。
パラリンピックの陸上競技 フィールドのルールとは
競技ルールはオリンピックと同じルールを基本に、ディサビリティーズのクラスに応じて一部のルールが変更され、ディサビリティーズを補いながら、1センチメートルでも、より高く、より遠くへと、自己の限界に挑む戦いです。
跳躍は、車いすクラスを除いた全てのディサビリティーズクラスが対象となるが、実施種目とクラスは大会ごとに異なります。 ディサビリティーズクラスはアルファベットの「T」とディサビリティーズの種類と程度を表す2桁の数字で表され、用具やアシスタントとのコンビネーションは勝利への重要な押さえどころです。
投てきは全てのディサビリティーズクラスが対象となり、アルファベットの「F」とディサビリティーズの種類と程度を示す2桁の数字で表されます。 視覚ディサビリティーズクラスではF11、12クラスの選手はアシスタントを伴えるが、エスコート役とコーラー役を兼務することが条件です。 跳躍競技同様、投てきサークルに選手を導き、手拍子や声かけで投げる方向を知らせます。
視覚ディサビリティーズ(T11/12)の選手は目からの情報を補うアシスタントと競技することが認められているクラスです。 選手を助走開始点に導き、助走の方向付けをするエスコートと競技中に助走の方向や踏切地点などを手拍子や声で伝えるコーラーを伴うことができます。 T11クラスは2つの役割を2人で担当しても1人で兼務することも可能です。 競技に支障がなくルールの範囲内なら、声かけの方法やコーラーが立つ位置などは自由で、走幅跳では、踏切板ではなく少し幅の広い踏切エリアが設けられているのも特徴になります。
T11(全盲など)の選手のみ、見え方の違いによる公平性を保つためアイマスク着用が義務付けられ、暗闇の中でコーラーの発する音声だけが頼りです。 選手は声のする方へ、助走路をできるだけ真っ直ぐに思い切り走り、「ここ」と信じる位置で踏み切り、空中へ跳び出します。 暗闇の中での恐怖に打ち克つ勇気を得るには、日々の練習でお互いの信頼関係を築き高めるプロセスが重要です。 手をたたき続ける、歩数を数えるなど、それぞれの方法を見比べるのも関心が高まります。
切断/機能ディサビリティーズクラスでは左右のバランスをとるため、競技用の義足や義手を使用する選手も多いが、実はトラック競技と異なり、跳躍競技では義足の着用義務はなく、ホッピング(片足跳び)も認められているクラスです。 選手は自身の力を最大限に発揮できる競技方法を探り、より高みを目指しています。
投てきは車いすクラスの選手も対象で、投てき台と呼ばれる道具を用いて試合が実施される競技です。 投てきは脚やお尻が浮かないように体をベルトなどで固定することで安定した投てきが可能になります。 つまり、助走などはできず、座ったまま上半身の力だけで投げることになり、選手はルールの範囲内でカスタマイズした自分専用の台を使うことも可能です。
投てき競技にはパラリンピック独自のこん棒投という種目もあります。 車いすクラスの中でもディサビリティーズが重度であり、手にもディサビリティーズのある選手を対象としてボウリングのピンに似た、長さ約40センチメートル、重さ397グラムのこん棒を投げて距離を競い合う種目です。 投げ方に制限はなく、後ろ向きに投げることも認められています。 また、知的ディサビリティーズクラスは程度によるクラス分けがなく、TまたはF20の1クラスのみだが、個々の選手でディサビリティーズの特性が大きく異なるのが特徴です。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは
パラリンピックの陸上競技 フィールドはディサビリティーズクラスごとに工夫された用具やアシスタントとのチームワークなどを活用して、選手がどうパフォーマンスするかに注目が集まります。 近年、世界各地で盛り上がるパラリンピックの陸上競技 フィールドはトレーニング方法の向上や用具の性能などの進化により、パフォーマンスのレベルや記録が大会ごとに急速に伸び、オリンピックに迫る勢いです。 フィールド競技はトラック競技に負けず劣らず、多くの種目で記録更新が続き、また1人で複数種目の世界王者となる選手が多いのも特徴になります。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
マラソン Ver.
マラソンは己の競技能力を最大に引出し、強い情熱で限界に挑むドラマ

パラ陸上マラソンは公平にレースが行えるようにクラス分けが工夫され、試合は過酷な条件の中で気象や路面状況を見極め、ガイドやレーサーと力を合せ強靭な精神力で駆抜ける選手達に称賛。日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラ陸上競技 マラソンの主な強豪国と地域:
男子「モロッコ、オーストラリア、中国、ブラジル、スイス、アメリカ etc.」
女子「RPC、南アフリカ、オーストラリア、スイス、オランダ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会 パラ陸上競技 マラソンで金 銀 銅メダルを獲得した諸国です。
ロサンゼルス2028大会は欧米やアフリカ、アジア諸国勢とのクラスごとに繰り広げられる順位争いに真夏のパリが微笑む。
年々増える選手や参加国、向上する競技力、人間の可能性を求め切磋琢磨で練習を繰り返して身につけた走りで真夏のパリを制する国はどこだぁ!
パラ陸上競技 マラソンの特徴
パラリンピックの陸上競技は第1回ローマ1960大会から正式競技として実施されています。 幅広いディサビリティーズ(disabilities)を対象とすることで夏季大会の競技の中で参加人数は多いのが特徴です。
パラリンピックの大きな特徴はクラス分けと呼ばれるシステムで、対象となるディサビリティーズが知的ディサビリティーズや麻痺、四肢の欠損など 多岐にわたるため、極力条件を揃え公平にレースが行えるようにし、各選手のクラスは専門の資格を持つ判定員が医学的、運動機能的な側面から審査して決めています。 出場選手をディサビリティーズの種類や程度、運動能力などに応じてクラス分けし、試合はクラスごと、あるいは隣り合うクラスを合わせた統合クラス(コンバインド)で実施される仕組みです。
マラソン競技で実施されるクラスは参加者数などを考慮しながら、大会ごとに検討されます。
パラリンピックの陸上競技 マラソンのルールとは
ロード競技であるマラソンのディサビリティーズクラスの表示はアルファベットの「T」と種類と程度を表す2桁の数字(T11など)の表記です。 競技ルールはオリンピックと同じルールを基本にし、視覚ディサビリティーズクラスは必要に応じて伴走者(ガイドランナー)と走ったり、車いすクラスの選手は競技用の車いす(レーサー)を使用したりすることが認められています。 体の一部ともいえる伴走者や用具との一体感もパフォーマンスを左右する重要な要素です。 他の種目同様、マラソンにおいても複数のクラスが実施されるため、順位はクラスごとに決められています。
T12の選手は単独走か、目の代わりとなり安全に導く伴走者(ガイドランナー)を選択することが可能です。 そのため、レースには単独走の選手と伴走者とのペアの選手が混在します。 ペアで走る選手は伴走者とロープを握り並んで走るので、フォームを合わせるなどコンビネーションを磨くことが大切です。 選手より先に伴走者がフィニッシュラインを越すと失格となるなど、伴走者はあくまでも選手のパフォーマンスをリードではなく、サポートする存在でなければなりません。 現行のルールでは2人の伴走者が認められており、コース上の決められた地点で交代できます。 選手は、コースの凸凹や起伏、曲がり角など、緊張感をもちながら走ることが大切です。
車いすのクラス(T54)は、少なくとも3つの車輪があり、高速走行用に開発された競技用車いす(レーサー)を腕だけで駆動させて42.195キロメートルを走り抜きます。 レーサーの素材や性能は年々進化しているが、それを活かすには選手自身が筋力や技量を磨いたり、個々のディサビリティーズに合わせて ルールの範囲内でレーザーをカスタマイズしたりするなど、使いこなすための努力が必要です。
マラソンは気象条件も大きな要素で、気温や湿度が高い場合は完走率も低くなります。 参加人数の関係で集団でなく単独で走ることもあり、過酷な条件の中で1人でペースを守り、レースをつくる精神的な強さも必要です。 一般道路もコースとなることから、路面状況や坂道などの起伏や曲がり角の数などがタイムに与える影響も大きく、注意が必要になります。 例えば、石畳のように細かな起伏が続く路面は、視覚ディサビリティーズの選手は、つまずきや転倒、車いすの選手はレーサーのパンクなどの危険性も高く、急な曲がり角などでは転倒する車いすの選手も少なくありません。
ロサンゼルス2028大会に向けた展望
視覚ディサビリティーズクラス(T12男子/女子)や車いすクラス(T54男子/女子)は近年、ヨーロッパ勢やアジア勢の活躍が見られ、南米やアメリカ、アフリカ勢も力を発揮しています。 車いすクラス(T54男子/女子)は疾走する速さを腕力だけで生み出し、平均時速30~50キロメートルに達することもあるスピード感はレーサーならではの魅力です。 風の抵抗を避けるため、自転車レースのように縦一列に並び集団で疾走するのも車いすレースの特徴の一つで、ペース維持のため先頭が交代する駆け引きやラストスパート合戦で勝負が決まることも多いので目が離せません。 欧米勢を中心に有力選手が多く、王座を守れるのか、それとも新星が現れるのかが注目です。 両クラスとも他の種目から参戦し、世界新記録など新たな王冠を手にしています。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
水泳は全身を駆使し試行錯誤を繰返し、磨上げた己の泳ぎで最速に挑む
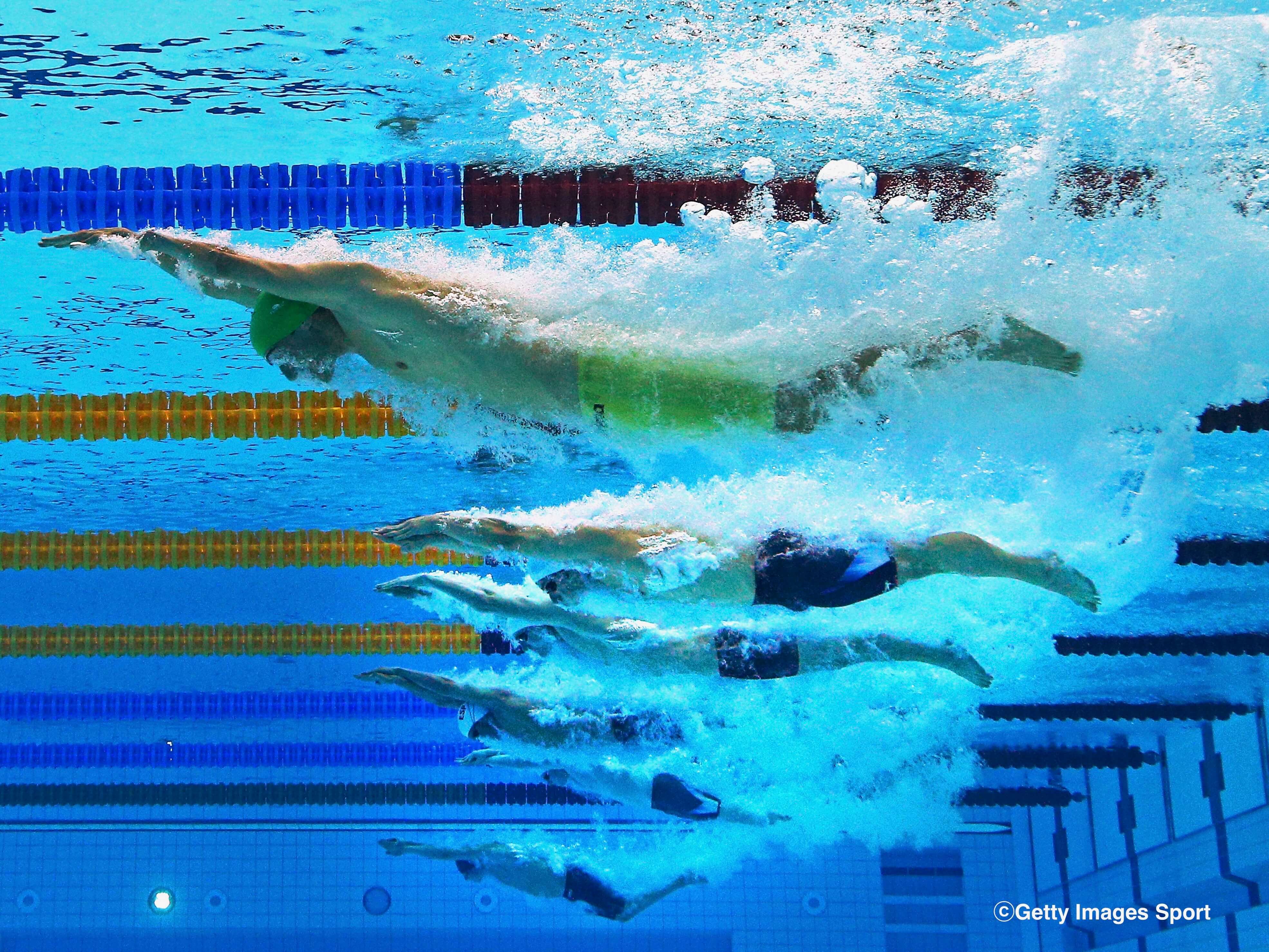
パラ水泳は出場選手の多い競技で、試合は多種多様のスタート方法と個性豊かなフォームで水の抵抗を限りなく低減させ、推進力を最大限に発揮させる独自のスタイルに注目!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラ水泳の主な強豪国と地域:
「メキシコ、中国、ウクライナ、イスラエル、イタリア、コロンビア、ROC、アメリカ、オーストラリア、ブラジル、リトアニア、ベラルーシ、ギリシャ、アゼルバイジャン、イギリス、チリ、スペイン、フランス、オランダ、チェコ、アルゼンチン、クロアチア、カナダ、キプロス、ニュージーランド、スイス、ハンガリー、ポーランド、シンガポール、トルコ、ドイツ、アイルランド、ウズベキスタン etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した諸国です。 ロサンゼルス2028大会は欧米やアジア勢との熱い闘魂と泳ぐ情熱の順位争いに水しぶきが舞い散る。残存能力である身体能力や競技能力、強靭なメンタルを最後の最後まで発揮できる国はどこだぁ!
パラ水泳の特徴:
パラ水泳は第一回パラリンピックローマ1960大会から実施されています。 試合は、できるだけ条件を揃え公平に競い合えるように選手のディサビリティーズの種類や程度、運動機能などを考慮し、クラス分けされている競技です。 各国の代表である選手たちは、それぞれのディサビリティーズに応じて全身を駆使して独自に工夫して作り出したスイムスタイルで泳ぎます。 磨き上げた個性豊かなフォームは「残されたものを最大限に活かす」というパラリンピック精神を強く感じさせられる体現です。
パラリンピックは適格なディサビリティーズたちが、参加できる大会で14のクラスに分けられています。 なお、パラ水泳では泳法を表すアルファベットと競技クラスを表す数字を組み合わせた表記です。 パラ水泳は日常的に車いすを使う選手から多様なディサビリティーズを対象としています。 選手はディサビリティーズ クラス別に競技するが、たとえば同じクラスでも、それぞれの身体の状態は千差万別です。 そのため、選手は試行錯誤を繰り返し、自分の身体に最も合う泳ぎ方を見つけ、練習をくり返すことで泳ぎを磨き上げていきます。
ディサビリティーズの選手たちは「速く泳ぐ技術」を習得するのが難しいです。 競技の勝敗は「誰よりも速く泳ぐこと」で決まり、そのために水の抵抗を少なく推進力を最大にし、まっすぐ最短コースでゴールを目指します。
例えば、下半身にディサビリティーズがある選手は上半身の筋力などの動きで補い、腕や脚に欠損や変形がある選手は、できる限り水の抵抗の少ない理想の形(ストリームライン)に仕上げ、上下左右のバランスをとりながら泳げるよう身体の使い方を工夫することが必要です。
また、視覚のディサビリティーズ クラスの選手の中には、自分の位置を目で確認することが難しい選手もいます。 そのため、まっすぐ泳げずにタイムロスすることも少なくないです。 日々の練習を繰り返し、バランスの良いフォームを身につけたり、左右どちらかのコースロープに身体を触れさせて位置を確認したりするなど、自分なりの泳法を体得していきます。 個性あふれる泳ぎ方を見比べて、それぞれの工夫を知ることも大切です。
プールの壁を目で確認できない選手もいるので、ターンやゴールのときに壁にぶつかってケガをしないよう安全のため、コーチなどがプールの上から選手に合図を送ります。 特にS11(全盲)クラスの選手には合図を送ることが義務付けられている競技です。 合図は選手の頭や身体に棒でタッチ(タッピング)して行い、合図を送る人を「タッパー」、合図を送る棒を「タッピングバー」と呼びます。 選手はタッパーのおかげで、恐怖心を取り除き、思い切って泳ぐことができるのです。 なお、タッピングバーに関するルールは設けられておらず、日本製の弾力性ある釣竿を改良した手作りタッピングバーは完成度の高さから海外チームからお問い合わせがあるぐらい重要なアイテムになります。
競技ルール
オリンピックの競泳に、ほぼ準ずるがディサビリティーズに合わせて一部変更されています。 特にスタート方法は多種多様で、自由形や平泳ぎ、バタフライは飛び込み台からスタートすることが基本だが、ディサビリティーズによって台からの飛び込みが難しい場合は水中からスタートすることも可能です。 水中スタートや背泳ぎはスタート台に設置されたスターティンググリップを握り水中からのスタートを基本とするが、握力の関係や切断などのディサビリティーズによりグリップを握ることが難しい場合は、ベルトなどの補助具を使用したり、ひもやタオルを口にくわえたりしてスタート体勢を取ることも認められています。 ゴールも同様で、両手タッチが原則の平泳ぎやバタフライであっても、ディサビリティーズによっては上半身の一部でのゴールタッチが認められているのです。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは
パラ水泳は陸上競技に次いで出場選手の多い競技で、選手の年齢の幅が広く、何大会にもわたって活躍したり、1大会で複数のメダルを手にしたりするスター選手も少なくありません。 競技レベルが向上していくとともに、今後ますます記録の更新、技術の進化は続いていきます。 日本選手団は世界で存在感を放っており、ベテラン勢のメダリストたちと切磋琢磨しながら若手選手たちの活躍が大いに期待がもてる競技です。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
卓球は粘り強いメンタルと集中力、多様な戦略を駆使した己との勝負!

パラ卓球は特有のルールが適用される競技です。試合は多彩なプレースタイルや正確なラケットワーク、ラリーの応酬、高いパフォーマンスなど最強の座を狙う熱き戦いに注目。日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラ卓球の主な強豪国と地域:
「韓国、イギリス、フランス、ポーランド、中国、ドイツ、アメリカ、トルコ、デンマーク、タイ、ウクライナ、ベルギー、オーストラリア、RPC、インドネシア、モンテネグロ、ハンガリー、スロバキア、チェコ、スペイン、ナイジェリア、ブラジル、インド、ヨルダン、オランダ、ノルウェー、台湾、香港、クロアチア、イタリア、セルビア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会はアジア諸国勢、欧米、南米、中東、アフリカとの大陸を跨いだ順位争いに荒波が打ち寄せる。♪最高の波に乗れる新たなスター誕生で勝利を掴み取れる国はどこだぁ!
パラ卓球の特徴:
卓球は愛好家も多く世界的に普及し、第1回のローマ1960大会から継続して実施されている競技の一つです。 オリンピックで卓球が正式競技になったのはソウル1988大会で、パラリンピックの卓球が先に始まっています。
パラリンピックの卓球が対象とするディサビリティーズは幅広く、肢体不自由と知的ディサビリティーズの2つに大別され、肢体不自由クラスは車いすと立位の2クラスです。 試合はそれぞれのディサビリティーズの程度に応じて、さらに11クラスに分かれて競い合います。
ルール:
卓球台やラケット、ボールといった用具を含め、試合の進め方、得点の入り方といった基本的なルールはオリンピックの卓球とほぼ同じです。 ただし、ディサビリティーズのクラスによってはサービスやトスなどにクラス特有のルールが適用されます。
試合は男女別に、1対1で戦うシングルスと2~3人でチームを組んで戦う団体があり、それぞれクラス別に競技が実施される対戦方法です。 試合は1ゲーム11点先取の5ゲーム制で行われ、3ゲームを先取した方が勝ちとなります。 ディサビリティーズに応じた多彩なプレースタイルや粘り強いラリーの応酬、多様な戦略など見どころが多い試合展開です。 ディサビリティーズのない選手も参加する大会でも上位入賞を果たす選手もいます。
肢体不自由クラスは車いすと立位に分かれ、さらにディサビリティーズの程度や運動機能などから重い順に、車いすはクラス1~5まで、立位はクラス6~10に細かく分かれて競い合う競技です。 知的ディサビリティーズはクラス11の1クラスのみ実施され、ディサビリティーズのクラスによって、クラス特有のルールが適用されます。
クラス特有のルール適用としてはサービスのトスです。 例えば、オリンピックでは、サービスは開いた手の平にボールを乗せてから、卓球台よりほぼ垂直方向に16センチ以上、トスしなければならないが、パラリンピックでは、ディサビリティーズの特性によって正規のトスが難しい場合は、ひじ先に乗せてトスしたり、ラケットに乗せてからトスしたりする工夫も認められています。
特に車いすクラス(シングルス、団体ダブルス)では、サービスを出した際、ボールが相手コートに触れた後にネット方向に戻った場合や相手コート上で止まった場合は、やり直し(レット)です。 さらに、シングルスの場合には、サービスしたボールが相手コートのエンドラインを正しく通過せずにサイドラインを割った場合も、やり直し(レット)となります。 なお、車いすに関しても特別な規定が定められ、ラリー開始時からラリーの間、少なくとも2つの大きな車輪と1つの小さな車輪が付いていなくてはなりません。 また、座位の高い方が有利なため、車いすのクッション(2つまで許可)は、その高さ(全体)は最大15センチと決められています。
見どころ:
選手はディサビリティーズに応じ、車いすや義足、杖などの補助具を使ったり、ラケットを口でくわえたりするなど、さまざまなプレースタイルで競技を行うことが可能です。 それぞれのスタイルで、コースを正確につくラケットワークや高い集中力で繰り広げられるラリーの応酬、時速100キロメートルを超えるスマッシュや、高速サービスをものともせずに打ち返すレシーブなど、高いパフォーマンスが見どころになります。
車いすクラスは車いすを操作するチェアワークに加え、低い位置でのプレーとなるため、立位の卓球よりも速いラリーや、ネット際に短く落とすボールなどの技が披露されるハイレベルな試合展開のテクニックにも注目です。
知的ディサビリティーズのクラスはオリンピックと同じルールで行われます。 相手との駆け引きやメンタルの強さを日常の練習を通じて体で覚え、それを如何に試合で発揮できるかが重要なカギです。 卓球は陸上、水泳と並んで知的ディサビリティーズのクラスが数多い、パラリンピック競技種目の一つでもあります。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
パラリンピック競技の中で卓球は出場選手が多く、近年は陸上、水泳に続いて第3位の参加人口です。 出場権を得るには大陸別選手権大会での優勝、または国際大会を転戦してポイントを稼ぎ、世界ランキング上位に入ることが必要となります。 近年、圧倒的な強さを誇るのは卓球王国の中国です。
ディサビリティーズクラスによっては、一般の大会にも出場し、活躍する選手も少なくありません。 絶対王者、中国の牙城を揺るがす国の登場や若手選手の台頭などロサンゼルス2028大会は注目が集まります。
日本勢はこれまで多数の選手が出場し、入賞者やメダリストも出てきているなか、更なる可能性を求め強化を図りベテラン勢や若手選手で、さらなる高みを目指す。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
ボッチャは己を磨き、正確なショットと緻密な戦略を駆使する頭脳戦!

ボッチャはパラリンピック特有の球技です。試合は個人所有のボールを使い、お互い赤か青の6球を投げ、転がし、足で蹴るなど、攻め手を予想しながら一発逆転の大技に注目!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
ボッチャの主な強豪国と地域:
「タイ、中国、ポルトガル、ブラジル、RPC、韓国、イギリス、スロバキア、アルゼンチン、マレーシア、チェコ、ギリシャ、オーストラリア、香港 etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会はアジア諸国勢、欧米、南米との新たなショットの順位争いに拳を握りしめる。♪神がかりのショットでジャックボールに好まれ、勝利を掴み取れる国はどこだぁ!
ボッチャの特徴:
ボッチャは、イタリア語で「ボール」を意味し、脳原性疾患による四肢麻痺など、比較的重いディサビリティーズのある人のために考案されたパラリンピック特有の球技です。 最初にジャックボールと呼ばれる白いボールを投げ、続いて赤と青の各6個のボールを投げたり、転がしたりして、目標となるジャックボールにいかに多くのボールを近づけるかを競い合います。 ルールの類似性から、「地上のカーリング」とも呼ばれるが、的となるジャックボールの位置が毎回変わり、また途中で弾いたりして動かすこともできる点が特徴です。 将棋やオセロのように戦略性も高く、一発逆転もあり最後まで目が離せない競技になります。
古代ギリシャの球投げを起源とし、6世紀のイタリアで競技としての原型が考案され、20世紀に入って重いディサビリティーズのある人も参加できるように整備され普及した球技です。 重度脳性麻痺者、もしくは同程度の四肢の重度機能ディサビリティーズを対象とし、ニューヨーク1984大会から競技となり、現在、団体戦(チーム戦、ペア戦)3種目、個人戦4種目の合計7種目が実施されています。
クラス分けと競技種目:
男女の区別なく、ディサビリティーズの内容や程度などにより4クラス(BC1~4)に分けられ、1対1の個人戦、2対2のペア戦、3対3のチーム戦で競い合う球技です。 さまざまなディサビリティーズの選手に対応するため、クラスによってルールがアレンジされており、例えば、ボールを手で投げることが難しい選手は足で蹴ったり、競技アシスタントのサポートを受けたり、滑り台に似た勾配具(ランプ)を使って転がしたりすることが認められています。
試合はバトミントンコート大(12.5メートル×6メートル)の平面のコートを使い、2人(または2チーム)で対戦し、それぞれ赤か青の6個のボールを投げ合う競技です。 持ち手のボールを転がす、足で蹴るなど各選手ができる方法で白いジャックボールに近づけ、6個ずつの試技を終えた時点で、ジャックボールに最も近い色の選手(チーム)が勝ちとなります。 さらに、ジャックボールを円の中心とし、ジャックボールに最も近い敗れた側のボールとを結んだ半径内にある勝利側の球の数1個につき1点が得点として加算されるルールです。 6個ずつの試技を「1エンド」として、個人、ペアは4エンド、チームは6エンドで1試合とし、エンドごとの得点の総計で勝利選手(チーム)が決まります。
ルール:
試合に用いられるボールは選手個人が所有する「マイボール」です。 規定の範囲内(重量275グラム プラスマイナス12グラム、周長270ミリメートル プラスマイナス8ミリメートル、転がり具合がテストに合格)で、好みの硬さを組み合わせ使い分けます。 ただし、大会前には必ず競技備品検査が行われ、検査に適することができなかったボールは試合に使用することができません。
ボールは主に皮革製または合皮製で、表面はつまめるほど柔らかく、弾まず転がりにくい仕様です、 表面の縫い目によってボール軌道が変わることもあり、一つひとつ癖を見極める力も必要になります。 ボールを確実に積み上げたり、寄せたりするため、空気を抜いたり、クリームを塗って柔らかさを調整したり、どの場面で、どの素材のボールを使うかといった戦術にも注目するとより、臨場感が味わえるゲームです。
BC3クラスは手足にディサビリティーズがあり、ランプと呼ばれる滑り台のような勾配具を使います。 ランプには形の規定はなく、試合状況に応じて部品を継ぎ足して高さや長さを調整することも可能です。 ただし、全体のサイズは1メートル×2.5メートル以内でなければなりません。 手でボールを押し出せない選手は頭部や口に補助具(リリーサー)を装着して投球します。
また、BC1クラス、BC3クラス、脚蹴りで競技をするBC4クラスの選手については1人につき1人のアシスタントが競技をサポートすることが可能です。 ただし、その役割はクラスごとに規定が設けられています。 例えば、BC3クラスは選手の指示を受けてランプの高さや位置、コースを調整したり、ボールを丸めたり、選手がプッシュする位置にボールを置くなどの役割を担うことはできますが、競技中、コートを見ることは禁止です。
ボッチャの戦略は無数で、日々新たな戦法が生まれています。 球種は大きく分けて3種類、目標に近づける「アプローチ」、他の球に当てて飛ばす「ヒット」、他のボールを押して近づける「プッシュ」です。 各球種の得点はアプローチ1得点、ヒットは相手のボールを弾くので逆転にもつながり、プッシュは当てながら自身のボールを残すので、2得点も可能になります。 投球は力の加減がポイントで、初めに最終的な得点方法をイメージし、1投球ごとに積み上げて競技を進めていくやり方です。 ディサビリティーズによっては3種類の投げ分けが難しい選手もいるが、それぞれが得意球を磨き上げ勝利を目指していきます。
見どころ:
ミスショットだと思ったら、実は戦略上の重要な一手である可能性もあり、最後までストーリーが読めない展開が見どころです。 選手のイメージを想像し、次の攻め手を予想しながら観戦すると面白さが増し、双方の戦略を探り合う楽しさが味わえます。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
パラリンピックへの出場は世界各地で開かれる国際ボッチャ競技連盟(BISFed)公式のオープン大会でランキングポイントを重ねたり、パラリンピック前年の各地域別選手権で優勝することなどが主な条件です。 ボッチャはヨーロッパ諸国勢が強かったが、近年ではアジア勢が力をつけ、現在は最強国タイの牙城、中国、香港(ドラゴン)や韓国(ホワイトタイガー)が猛威をふるっています。
日本は冷静で正確なショットを持ち味に、漲る闘志とパワー溢れる若手選手たちも含め、ベテラン勢の「火ノ玉JAPAN」が虎視眈々とメダル獲得を狙う。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
パラバレーボールは鍛上げた上半身と巧みな頭脳プレーの激しい地上戦

パラバレーボールは臀部を床に付けて競技し、試合は攻守ともに幅広い技術やコミュニケーション能力、工夫、戦略が求められ、ラリーの応酬やスピーディーでパワフルな試合展開に注目!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
シッティングバレーボールの主な強豪国と地域:
「イラン、RPC、ボスニアヘルツェゴビナ、アメリカ、中国、ブラジル etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会は中東や欧米、南米、アジア諸国勢との狭いコート上のネット際の順位争いにお尻が持ち上がる。最後まで腕の力などでお尻を滑らせてコート内を移動し勝利を掴み取れるチームはどこだぁ!
シッティングバレーボールの特徴:
シッティングバレーボールはディサビリティーズのある選手を対象とし、お尻(臀部)を床につけた状態で競技するバレーボールです。 シッティングバレーボールは1956年、リハビリを目的にオランダで考案され、世界に広まったスポーツになります。 パラリンピックでは男子がアーネム1980大会から、女子はアテネ2004大会から正式競技となった球技です。
オリンピックのバレーボールと同様に、1チーム6人でネットを挟んで対戦し、試合は5セットマッチで、1セットは25点先取(第5セットは15点)のラリーポイント制で行われます。 ただし、座位でプレーできるようにオリンピックよりも小さいコートや低いネットなどを使用し、一部のルールが変更されている球技です。
ルール:
シッティングバレーボールはVS1とVS2の2つのクラスが設けられ、ディサビリティーズの程度はVS2がVS1よりも軽度で、VS2の選手は12名の全体リストに2名、コートの中の6名のレギュラーメンバーの中には1名入ることができます。 最も重要なルールは、プレー中に臀部が床から離れると、「リフティング」というファウルになる点です。 選手はお尻を床に付けたまま、腕の力などでお尻を滑らせるようにしてコート内を移動することが求められています。 また、相手のサーブを直接ブロックやアタックなどで返球できる点もオリンピックとは異なるところです。
シッティングバレーボールコートはオリンピックのバレーボールで使用されるコート(長さ18メートル×幅9メートル)より狭い、長さ10メートル×幅6メートルの長方形のコートで、センターラインからエンドに向かって2メートルの位置にアタックラインが引かれています。 ネットの高さは男子が1メートル15センチ、女子が1メートル5センチで、オリンピックのネット(男子は2メートル43センチ、女子2メートル24センチ)よりも1メートル以上低く設定されている仕様です。
見どころ:
攻撃も守備も、シッティングバレーボールならではの工夫や戦略が必要であり見どころも多く、例えば、攻撃では相手のブロックを交わすため、クイックなどのコンビネーションプレーやフェイントなども多用されます。 相手ブロックを翻弄する巧みな頭脳プレーにも注目です。 また、シッティングバレーボールは速くパワフルなサーブを武器にするチームも多く、サーブブロックが認められているので、より速く、コースを読まれないようなサーブの技術も重要なポイントになります。
守備では臀部を床につけたまま移動しなければならないため、選手の守備範囲は通常より狭く、オリンピック同様、守備を専門とするリベロも導入されているが、チーム一丸となった守備が必要です。 レシーブしたボールをいつもセッターに返せるとは限らないので、チームの誰もがトスを上げることができ、また、誰もがスパイクを打てることが要求されます。 選手全員に幅広い技術が求められるのも、シッティングバレーボールの特徴です。
オリンピックのバレーボールよりコートが狭く、ネットも低いということは、より近い地点からスパイクやサーブが放たれるということになります。 そのため、守備側はすばやく反応する必要があり、スピーディーでパワフルなボールの応酬は見どころの一つです。 スピーディーな試合展開やラリーの応酬など、見どころの多いチーム球技になります。
シッティングバレーボールはジャンプができないので、スパイクやブロックは身長の高い選手が一般的には有利です。 小柄な選手が攻撃する場合は、フェイントやブロックアウト(ブロックされたボールが外に弾かれアウトになること)を担うなど、テクニックとアイデアを使った戦略が求められます。 前衛の選手は、相手チームのサーブを直接ブロックしたりアタックしたりできるが、ブロックをするとき、選手はコートから臀部を持ち上げることはできません。
コートを打ち分けたり、高さを工夫したりするなど、バリエーション豊かなサーブも見どころの一つです。 シッティングバレーボールは、スパイクやブロック、サーブなどのプレー中、臀部が床から離れると反則となるが、レシーブの時に短時間であれば臀部が床から離れることが許されています。 しかし、立ち上がったり、歩いたりすることは禁止です。
ロサンゼルス2028大会に向けた展望:
世界各国から予選などで選ばれた男女各8チームが出場できる大会で、それぞれ4チームずつの総当たり戦による予選リーグが行われます。 その結果により順位決定トーナメントに進む、ネット際の激しい地上戦です。
男子はパラリンピック出場9大会中、7大会で金メダルを獲得している強豪国イランを中心に、女子は中国を倒して頂点に君臨するアメリカが強く、ロサンゼルス2028大会では男女とも、どこの国が優勝を果たすのか注目が集まります。
日本チームは東京2020大会で培った経験を、さらに磨き上げ強化を図り、屈辱を奪還すべく出場枠獲得に挑む。 攻撃、守備ともに頭脳プレーの連続で一瞬のコミュニケーションが勝敗を決する!
※東京2020大会関連資料より、参考元:
ゴールボールは静寂の格闘技、全神経を集中させ緻密な戦略の頭脳戦!

ゴールボールはアイシェードを着用し、可聴ボールを投げ合い得点を競うチーム球技です。試合は凄腕の攻撃や力強い守備など様々な工夫を駆使した鋭敏な技と多彩な球種の駆け引き!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
ゴールボールの主な強豪国と地域:
「ブラジル、中国、リトアニア、アメリカ、ベルギー、ウクライナ、トルコ、ドイツ、アルジェリア、イスラエル、ROC etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得や入賞した諸国です。ロサンゼルス2028大会は南米や欧州、アジア諸国勢との静寂の中の順位争いに審判の「Quiet Please!(お静かに)」コールが響き渡る。静寂の中の熱き頭脳戦、強化次第ではどこの国にも上位に名を連ねられるチャンス、果たして勝ち残れる国と地域はどこだぁ!
ゴールボールの特徴:
ゴールボールは、視覚ディサビリティーズを対象にしたパラリンピック特有のチーム球技です。ゴールボールは、視覚ディサビリティーズのために特別に設計されたチームスポーツであり、視力を失ったアスリート向けに開発されます。コート上の選手は3名で全盲から弱視(B1~B3クラス)の選手まで出場できるが、公平に競技を行うため、ディサビリティーズの程度に関わらず「アイシェード」と呼ばれる目隠しを装着した全盲状態でプレーし、試合時間は前 後半各12分の計24分間です。
ゴールボールは、バレーボールと同じサイズのコート(長さ18メートル×幅9メートル)を使い、1チーム3名の2チームで対戦し、ベンチコーチ3名、コート上3名からなるチームで構成されます。試合は、攻撃チームが鈴の入った可聴ボールを転がし、対戦相手が守っている反対側のゴールに向かって床に沿って高速で転がし、相手のゴールに入れて得点を競い合う競技です。攻撃と防御を交互に行いながら、可聴ボールを投げ合い得点を競うチームスポーツで、選手は相手の強力な攻撃をブロックするため、全身を鍛える必要があります。守備側は3名で協力しながら、全身でボールをブロックしゴール(幅9メートル×高さ1.3メートル)を守りますが、ネットは床の幅全体に広がっており、特に防御が困難です。
攻撃側はスピードボールやバウンドボールを活用し、相手側のディフェンスしづらいコースを狙ったり、できるだけ音を消してボールの出所が分からないように投球するなど頭脳戦の駆け引きが見どころになります。
守備側はボールの中の鈴の音や相手選手の足音やボールがバウンドした位置により、ボールが転がってくるコースを瞬時に察知し、全身を横たえ守備の壁をつくってボールを止める勇気あるプレイーが見どころです。ブラインドサッカーと同じように、選手は音を頼りにプレイするので、観客はプレー中に沈黙を保つ必要があり、静かに見守ることが求められます。
ゴールボールは激しいスポーツであり、各試合は前 後半12分ハーフで、延長戦(前 後半各3分)になった場合は「ゴールデンゴール方式※」で勝敗を決めるルールです。注釈:“ゴールデンゴール方式”とは決められた時間の中で一方のチームが得点した場合、試合を打ち切り、得点を入れたチームが勝利となる。
ルール:
1チーム最大6名で構成し、コート上3人対3人で対戦します。ボールはバスケットボールとほぼ同じ大きさ(直径25センチメートル)だが、重さは約2倍(1.25キログラム)とずっしりと重く、あまり弾まない可聴ボールです。ボールの中に鈴が入っていて転がると音が鳴るので、選手は耳を澄ましてボールの位置を知ることができます。味方同士のコミュニケーション(ボールの位置や投球したコース等の共有)や、相手側の足音、気配なども重要な情報源になるので試合中はご静粛にお願いします。
コートは自陣ゴールラインから3メートルごとに3つのエリアに分けられ、ゴールラインから3メートルのエリアを「オリエンテーション エリア」、オリエンテーション エリアの前方3メートルのエリアを「ランディング エリア」、ランディング エリアからセンターラインまでのエリアを「ニュートラル エリア」と大きく3分割されています。
投球する時は必ずチームエリアと呼ばれているオリエンテーション エリアとランディング エリアの6メートルのエリア内でボールをバウンドさせなければならないルールです。もしも、チームエリア内にファーストバウンドしなかった場合は「ハイボール」、更にセンターラインを挟んだニュートラル エリア内でセカンドバウンドしなかった場合は「ロングボール」という反則(ペナルティ)になります。
「10(テン)セカンズ」は、守備側選手が最初にボールに触れた時点から10秒以内にセンターラインを越えるように投げ返さねばならないというルールです。できるだけ素早く、確実にキャッチして攻撃に移るなど時間の管理も欠かせなく、反則を犯すと、相手チームの「ペナルティスロー」となります。反則した側は9メートルのゴールを1人で守り、ペナルティスローを受けなければならなく、攻撃側にとって得点の大きなチャンスであり、大きな勝負どころです。
見どころ:
ゴールボールは「静寂の中の格闘技」とも呼ばれ、パワフルなボールの投げ合いやそのパワーに負けない力強いディフェンス、選手の鋭敏な感覚に根差したハイレベルのテクニックに加え、選手側とベンチ側が繰り出す緻密な戦略も欠かせなく奥深い競技と言えます。攻撃側の目的は、「いかにボールのコースを察知されずに、相手ディフェンスの隙間を狙いゴール(得点)できるか」です。
そのため、ボールをキャッチして、すぐに投げ返す「速攻」やボールをキャッチした地点から足音を立てないように移動して投げる「移動攻撃」、キャッチしてから味方に「パス」するなど、さまざまな工夫でボールの出所を消して戦うプレイは一目を引き付けます。投球も緩急をつけ、バウンドさせたり相手のディフェンスの壁を乗り越えさせたりと多彩な球種での駆け引きの勝負です。
一方、守備側は幅9メートルのゴールを味方3名で連携して守ることが求められ、全身を横たえ、両手足をしっかり伸ばすことが基本的なスタイルになります。スピードのあるボールやバウンドボールなどは、一度止めてもボールが弾んで体を乗り越えてゴールに入ってしまうこともあり、きっちり止める筋力や正しい守備姿勢と何よりもボールに向かっていく強い意志が必要です。他の選手が後方に回り込んでカバーするチームプレイも試合展開の醍醐味になります。
「選手の目の代わりになる」という意味ではベンチワークも重要で、相手チームの攻撃や守備のパターンをいち早く把握、分析して、味方選手に相手のプレイがイメージできるように伝え、戦略を考えるポジションです。プレイ中にベンチから選手に声をかけることは反則(ペナルティー)だが、オフィシャルブレイクやタイムアウト、選手交代をうまく活用し選手に戦略や情報を伝えることができます。そのため、タイムアウト明け直後のプレイでスコアが動くことも多く、目が離せない場面です。選手たちのエキサイティングなパフォーマンスは、試合を見守る観客側にとって魅力的なシーンの一つになります。
注目ポイントは音を消した移動攻撃や味方の声を頼りにパスするなど、多彩な攻撃の展開です。それに対し、試合は静寂の中で行われ、選手は相手選手の足音などのかすかな音を頼りにボールの出所を読み、体全体を使ってゴールを守ります。審判が「Quiet Please!(お静かに)」のコールを出したら、選手に声援を送りたい気持ちを抑えて静かに見守りましょう。必ず、携帯電話はマナーモードに設定するのもお忘れなく。
また、プレー「再開後」にも注目です。両チームとも一歩も譲らない攻防が続き、得点もなかなか入らず、もどかしい時間帯が続く場面もあります。それは選手自身で相手を見て、状況を打開することが難しい上、プレー中にコートの外から声をかけることも禁止されているからです。だが、「得点率の高い局面」に入る状況があります。コーチが直接、選手に作戦を伝えられるタイムアウトや選手交代の直後は試合が動きやすくなるポイントです。条件は両チームとも同じで、ゲーム再開後の数プレーは特にまばたきなどに注意しながら観戦すると面白さが倍増します。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
ゴールボールは静寂の中の熱き攻防戦!選手3人で心をひとつに、全神経を集中させる静寂の戦いです。静寂の中の、緻密な攻防に見応えあり、拮抗する各チームの実力、強化次第ではどこの国にもチャンスがあります。
男女とも欧米諸国が強かった競技だが、アジア勢が徐々に力をつけ、中国、韓国、日本などが割って入り込んでいる状況です。現在は南米やヨーロッパ、北米、アジア勢の実力は拮抗で、身体能力が高いアフリカ勢の台頭も気になります。
世代交代に取り組むチームもあるが、世界のゴールボール界では熾烈な戦いが繰り広げられ、強化次第ではどこの国にも上位に名を連ねられるチャンスです。果たしてどこの国、地域が表彰台に上がるのか、目が離せません。
日本勢は定評ある堅守と多彩な攻撃力を持ち味に強化合宿や海外遠征で、更なる経験を積み上げ、チーム底力を発揮させて出場枠獲得を目指す。新生オリオン、再起動なるか!コミュニケーション力アップ!!合うんの呼吸!!!を組み合わせたスーパーミラクルボール(炎球)がゴールを貫く。闘魂投球ボールだぁ~♪
※東京2020大会関連資料より、参考元:
5人制サッカーは感覚を駆使し困難や課題、逆境を乗越える己との試練

5人制サッカーはアイシェードを着用しプレーする競技で、試合中は静寂が求められ、足先の感覚を駆使したドリブルや守備を巧みに抜いていく華麗で迫力あるプレーに圧巻!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
ブラインドフットボール(5人制サッカー)の主な強豪国と地域:
「ブラジル、アルゼンチン、モロッコ、中国、スペイン、タイ、フランスetc.」
上記の強豪国は東京2020大会で5人制サッカー男子の出場諸国です。
ロサンゼルス2028大会は南米や欧州、アジア諸国勢との感覚を駆使した順位争いに世界中の観客がどよめく♪
ボールコントロールやスピードなど並外れた空間認識でスーパープレーを魅せるチームはどこだぁ!
5人制サッカーの特徴:
5人制サッカーはブラインドサッカーとしても知られ、可聴ボールでプレーされる視覚ディサビリティーズのある選手(B1クラス男子、全盲)を対象とするサッカーです。 1チームは4人のフィールドプレーヤーとゴールキーパーで構成されています。 ゴールキーパーは晴眼(視覚ディサビリティーズの無い選手)、または弱視の選手が務め、守備時にチームメイトに手がかりを与えることができる重要なポジションです。
フィールドプレーヤー4人はアイマスクを着用し、転がると音が鳴る可聴ボールをドリブルやパスでゴールまで運ぶ競技になります。 ボールが両サイドを割らないように、サイドラインに壁を設置してある競技場です。
チームにはFPの目の代わりとなる「ガイド」と呼ばれるメンバーがいて、敵陣のゴール裏に立ち、味方にゴールまでの距離や角度などの情報を声や音で伝える役割を担います。 また、晴眼者や弱視者が務める「ゴールキーパー」、サイドフェンスを越えたベンチに立つ「監督」の声を聞きながらプレーするスタイルです。
フィールドプレーヤーは視覚ディサビリティーズのある選手で完全盲目に分類され、非常に低い視力および光知覚がないことを意味します。 しかし、公正なプレーを確保するために、すべての外野手はアイシェードの着用が必要です。 フィールドプレーヤーは個々の見え方による有利不利をなくすため、アイマスク(目隠し)着用の義務があり、視覚を遮断した状態でプレーします。
可聴ボールは鉛が仕込まれた特製のボールで、転がると「シャカシャカ」と音が鳴る仕様です。 選手はボールの音やガイドの声などを頼りにプレーするが、想像以上に激しく、スピーディーなプレーでのボールコントロールに驚かされます。
プレーヤーは完全に音の感覚に依存しているため、周囲の音声に耳を傾ける選手を妨げないよう、観客はプレー中、沈黙を保つように求められる競技です。 ただし、得点が決まったときは大きな歓声で称えましょう。 このようなメリハリある観戦スタイルも、5人制サッカーの醍醐味です。
5人制サッカーはボールの軌跡を感じる音、仲間との声の絆でゴールを目指す。
華麗で迫力あるプレーと緊張感 仲間とのコミュニケーションや信頼感が勝敗のカギ!
ルール:
5人制サッカーは国際ブラインドスポーツ連盟(IBSA)が統括し、ルールは国際サッカー連盟(FIFA)のフットサルをもとに、視覚ディサビリティーズのある選手がプレーできるよう一部がアレンジされています。
例えば、ピッチは40メートル×20メートルのフットサルコートを使うが、サイドライン上には選手やボールが飛び出さないよう、高さ1メートルほどのフェンスを立てられている競技場です。 フェンスはまた、選手が触って自分の位置を知る目安にしたり、ボールを意図的に蹴ってバウンドさせ、その跳ね返りを利用してパスしたりする目的でも使われています。
人間は外界からの情報の約80パーセントを視覚から得ているとされるが、視覚を遮断した状態でプレーするFPのために情報を補う工夫もさまざまです。 例えば、ボールを持った相手に向かっていくときは衝突を避けるため、守備側が「ボイ」と声をかえるルールがあり、違反するとファウルになります。
サッカー選手が対戦相手に向かって移動したり、タックルをしたり、ボールを探したりするときは「ボイ」などの言葉を発しますが、ゴールが決まると、誰もが好きなだけ騒ぐことが可能です。
また、フィールドプレーヤーに情報を与える役割は味方チームの3名が担い、敵陣のゴール裏から「8メートル、45度、シュート」のように、ゴールの位置などを伝えるガイド、主に守備に関する情報を与えるゴールキーパー、そして、監督(コーチ)がサイドフェンスの外からピッチ中盤の選手に指示を出します。 それぞれ声をかけられる範囲が決まっており、範囲外の選手に声をかけるとファウルになるルールです。
試合中にファウルを犯すと、相手チームにペナルティキック(PK)が与えられます。 5人制サッカーでは2種類のPKがあり、1つ目は、ペナルティエリア内でファウルがあった場合の「PK」で、ゴールから6メートルの位置にキッカーが立ち、ゴールキーパーと1対1でシュートを行うものです。 もう1つ目は、「第2PK」と呼ばれるPKで、前半と後半それぞれで、チームの累積ファウル数6つ目から相手チームに与えられ、キックは1つ目の「PK」よりも遠い、8メートルの位置から行います。
ルールの改正に関する内容:
ルールの一部が改正され、主な改正点の1つはゴールのサイズです。 従来のフットサルサイズ(幅3メートル×高さ2メートル)からフィールドホッケーサイズ(幅3.66メートル×高さ2.14メートル)に拡大されます。 得点の可能性が高まる分、失点の危険性も高まった変更点です。
もう1つは試合時間の変更で、従来はサッカーと同じ、時計を止めずに試合を進行させるランニングタイムによる前 後半25分ハーフだったが、新しいルールではプレーが続いている間のみ試合時間を計測するプレイングタイムによる20分ハーフに変更されます。
この方式では、ボールアウトやファウルなどで計時が止まるので、実質的には試合時間の延長になる可能性があります。 これらのルール変更は戦術にも影響し、体力も問われ、今後、各国の戦い方にどんな影響が見られるか注目です。
見どころ:
5人制サッカーの見どころはアイマスクを着けた選手が視覚以外の感覚を駆使してプレーする点です。 まるで見えているかのようなスーパープレーが見られます。 試合中の選手たちは仲間の声や音を頼りにピッチ上の自分の位置を把握し、自分や周囲の動きをイメージしながらプレーする妙技です。 ボールの音からは位置だけでなく、転がり方やスピードなども把握し、チームメートとの声かけによるコミュニケーションも重要なカギとなります。 また、足先の感覚を駆使したドリブルは華麗で、相手の気遣いや仲間の声を頼りに守備の隙間を見つけ、巧みに抜いていく動きは圧巻です。 力強いシュートや連携プレーも驚きだが、GKと駆け引きは想像を絶し、思わず、感嘆の声を上げてしまいそうになるが、そこはぐっとこらえましょう。 なぜなら、選手はGKが弾いたボールの音や切り替えし後の仲間の指示に耳を澄ましているからです。 試合は想像以上に目まぐるしく展開し、最後まで気を抜けない緊張感がピッチを覆います。 試合中は胸の中で声援を送りましょう。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
世界的なサッカーの人気もあり、5人制サッカーの普及 強化も各国で進んでいます。 アテネ2004で初めてパラリンピックに出場して以来、すべての大会で開催され、プレーヤーはそのスピードと並外れた空間認識で世界中の観客やテレビ視聴者を驚かせてきた競技です。 絶対王者ブラジルの牙城を崩す強豪国は、果たしてどこの国が上位に名を連ねるのか注目になります。
アジア勢の著しい躍進の中、日本勢は近年にプレーされるようになり知名度も徐々に広まり、国内リーグ戦なども行われ普及 強化が進められている5人制サッカーです。 若手も成長を見せ選手層も厚みを増しているなか、国内合宿や海外遠征を重ね調整力と経験で勝利を目指す。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
バトミントンは己の強靭な上半身や予測力を活かした緻密な戦略の勝負

パラバトミントンは世界中に広がりを魅せる競技です。試合は俊敏な動きや技、強烈なショット、ラリーの応酬、各選手のプレースタイルやスピーディーで迫力ある試合展開に注目!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラバトミントンの主な強豪国と地域:
「中国、韓国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、タイ、イギリス、フランス etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会はアジア諸国勢や欧州勢との熾烈な順位争いに世界中が熱狂する♪ パラリンピック二代目チャンピオンを巡る熱い戦いを制覇する国や地域はどこだぁ!
パラバトミントンの特徴:
バトミントンは東京2020大会からパラリンピックの正式競技となり、身体ディサビリティーズが対象です。 さまざまなディサビリティーズの選手ができるだけ公平に競えるよう、ディサビリティーズの内容や程度で6つのクラス(車いす2クラス、立位クラス4クラス)に分かれて競い合います。
バトミントンの国際的な競技会が開かれるようになったのは1990年代からで、1998年には第1回世界選手権がオランダで開催された競技です。 2011年から世界バトミントン連盟(BWF)が統括するようになり、2015年にイギリスのストーク マンデビルで開かれた第10回大会には35ヵ国から230選手以上が参加します。 競技人口も増え、競技規模も5大陸で60ヵ国以上へとさらなる広がりを見せている競技です。
ルール:
ルールはオリンピックのバトミントンとほぼ同じだが、クラスによって一部アレンジされています。 例えば、シングルスのコートの大きさは車いす2クラスと立位1クラスのみ通常のコートの半分を使うが、ネットの高さは全クラス共通です。 また、車いすクラスに限り、ネット周辺の一定範囲に落ちたシャトルはアウトとなるなど、クラスに応じて工夫されています。
試合は全種目とも21点3ゲーム制で、2ゲーム先取のラリーポイント方式で行われ、スピードやパワーが魅力の立位クラス、テクニックや駆け引きが重要な車いすクラスなど見どころもさまざまです。 種目は男女シングルスとダブルス、混合ダブルスが実施されます。
クラスと種目別の特徴:
車いすクラスは体幹機能の有無などによりディサビリティーズの重い方からWH1とWH2の2クラスに分かれ、両クラスともシングルスではコートの半面を使い、ネット近くに設けられたサービスラインとネットとの間に落ちたシャトルはアウトです。 狭いエリアでの俊敏な動きに注目が集まります。
また、シャトルを打つ瞬間に胴体の一部が車いすと接していなければならないというルールがあるため、豪快なスマッシュは少ないが、厳しいコースをついたり、前後に揺さぶったりと、テクニックで戦略的な攻撃が見どころです。 構造的に真横への移動ができない車いすを、片手にラケットを持ちながら巧みに操作してシャトルを追う躍動感や、シャトル落下点を予測する能力、ラリーの応酬などにも注目が集まります。
立位のカテゴリーは4クラスあり、SL3とSL4はともに下肢ディサビリティーズのあるクラスです。 左右のバランスがとりづらい状態からの軽快なステップワークや、豪快なスマッシュなどに迫力があります。
SH6は遺伝子疾患などによる低身長クラスです。 高い運動能力が魅せるシャープな動きや、素早く繰り出されるジャンピングスマッシュなどが見どころになります。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
バトミントンの選手は、BWF公認の国際大会を転戦し、成績に応じたポイントをもとに算出された国際ランキングで競い合う競技です。 競技人口は世界的に広がりを見せているが、特にバトミントン人気の高い、アジア勢やヨーロッパ勢が多数を占めています。 競技レベル的にはマレーシアやインドネシア、タイなどが世界ランキング上位に名を連ねる強豪国です。 例えば、男子車いすクラスでは特に韓国勢が強さを見せ、また、国際大会への出場が少なく国際ランキング的には目立たないが、世界選手権で上位に食い込んでくる中国勢のパフォーマンスもハイレベルになります。
バトミントンは各クラスとも選手層が多彩で見どころも多く、屈辱奪還に向け、金メダルを狙った白熱した戦いに注目です。
日本勢はバトミントン人気が高く、パラリンピックの正式競技入りもあり、年々競技人口を増やしています。 世界ランキング上位に食い込む選手たちを始め、世界での存在感を増やしながら国内での代表争いも熾烈さを極めるなか、切磋琢磨でさらなるレベルアップを図り 世界の頂点を目指す。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
ボートは己の力強いオール捌きや自然の読解力、戦術を駆使する勝負!

パラボートは6つの直線コースで競い合う水上最速のレースです。試合はスタートの合図で同時にボートを漕ぎ出し、フィニッシュラインを通過した僅差で勝敗が決するレース展開に注目。日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラボートの主な強豪国と地域:
「ウクライナ、オーストラリア、ブラジル、ノルウェー、イスラエル、フランス、イギリス、オランダ、中国、アメリカ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダルを獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会は欧米や南米、オセアニア、アジア諸国勢との水上の順位争いに荒波が打ち寄せる。 自然環境を読み解き、パワー漲るトルクと最速のスピードが打ち出せるオール捌きを魅せる国はどこだぁ!
ローイング(ボート)の特徴:
ローイング(ボート)は競技用のボートに乗り、ブイで仕切られた6つの直線コースで競い合う競技です。 スタートの合図で同時にボートを漕ぎ出し、ボートの先端がフィニッシュラインを通過した順に順位がつけられます。 距離はリオデジャネイロ2016大会までは、1,000メートルだったが、2017年にオリンピックと同じ2,000メートルに変更され、実施されている水上レースです。
種目はボートの種類別に、シングルスカル(1人乗り)、ダブルスカル(2人乗り)、舵手付きフォア(5人乗り4人漕ぎ)の3種目で、それぞれ対象となるディサビリティーズが規定されています。 ルールはオリンピックとほぼ同じだが、シングルスカルとダブルスカルは下肢にディサビリティーズのある選手が対象なので、一般のボートとは異なりシートが固定されており、基本的に腕など上半身のみで漕ぐスタイルです。
クラス分け:
肢体ディサビリティーズ、視覚ディサビリティーズによって、以下のクラスに分けられています。
PR1は、体幹機能が無いまたは最小で、腕および、または肩のみでオールを漕ぐ選手クラスです。 座位バランスが悪く、支えるため艇内のシートに座ってベルトで固定し、シングルスカル(男子/女子)で行われます。
PR2は、体幹、腕、肩の機能を使ってオールを漕ぐが、下肢の機能または可動性が低いため、ボートを推進させるためのスライディングシートを使うことができない選手のクラスです。 ダブルスカル(混合)で行われます。
PR3は、下肢、体幹、腕、肩に残存機能があり、スライディングシートを使うことができる選手のクラスです。 視覚ディサビリティーズがある選手も該当し、視覚ディサビリティーズ選手の漕手は2名まで、舵手付きフォア(混合)で行われます。
種目別:
ボートがパラリンピックの正式競技となったのは北京2008大会からで、比較的歴史の浅い競技です。 パラリンピックでの実施は、シングルスカル(1人乗り)、ダブルスカル(2人乗り)、舵手付きフォア(4人乗り)の3種目になります。 シングルスカルは男女別で行われ、ダブルスカルは男女のペア、舵手付きフォアの漕手は男女2名ずつのチームで構成される種目です。
シングルスカルは下肢にディサビリティーズがあり、体幹が使えない選手が対象となるため、バランスがとりやすいようボートの両脇に補助用の浮きがついています。 シートは固定されて動かず、また、背もたれもあり身体をベルトで固定し、オールは左右1本ずつ持ち、両手で漕ぐスタイルです。
ダブルスカルもシートは固定されているが、背もたれはなく体幹を使って漕ぐことができます。 オールはシングルスカル同様、各選手が左右1本ずつ持ち、両手で漕ぐので、2人のタイミングを合わせる難しさがある種目です。
舵手付きフォアは男女2名ずつの漕手に加え、舵取り役のコックスも同乗し、5人で一組となります。 オリンピックで使うボートと同様にシートはスライディング式で、膝の曲げ伸ばしも使うことができ、1人1本のオールを両手で持ち、左右交互に座って漕ぐスタイルです。 身体ディサビリティーズと視覚ディサビリティーズという異なる組み合わせでのチーム戦もボート競技の面白いところになります。 舵手付きフォアは4選手の呼吸や漕ぐスピード、タイミングなどをそろえることが重要です。 コックスが多くの役割を担い、号令をかけて漕手の動きを合わせたり、ボートが波や風の影響でまっすぐ進まない場合に舵を切って進路をコントロールします。 コックスは健常者が務めてもよく、漕手の乗る位置などはチーム戦略に合わせて自由に設定可能です。
見どころ:
シングルスカルは個人技や身体能力の競い合いが魅力で、ダブルスカルと舵手付きフォアは、さらにコンビネーションもポイントで、息の合ったチームワークも見どころになります。
上半身での力強いオールさばき、波や風の動きを読み、水上最速を狙う戦いやフィニッシュラインを目指して一直線に水上を滑り、僅差で勝敗が決する目が離せないレース展開に注目です。 2,000メートルに伸びたレースの距離、勢力図にどんな影響を及ぼすのか、注目が集まります。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
パラリンピックのボート競技は、国際ボート連盟(FISA)が統括しており、世界選手権やワールドカップ、各国内大会などでは健常者の大会にパラリンピックの ボート競技が組み込まれ実施されているのが現状です。 2017年のルール変更によってレースの距離が1,000メートルから2,000メートルに延長され、オリンピックと同じになり、ロサンゼルス2028大会でも2,000メートルコースで行われるだろう。
1,000メートルは陸上競技の短距離走に匹敵するイメージであるのに対し、2,000メートルは中長距離走に匹敵するだけに、強度だけでなく、駆け引きなど戦術もより一層必要となります。 また、距離は2倍だが、身体への負担は2倍以上かかることが想定されるレースです。
上半身だけでボートを漕ぐ選手にどんな影響を及ぼすのか未知数の部分も大きく、今後、トレーニングデータの蓄積や生理学的研究、分析などが待たれます。
パラリンピックのボートはメンバー構成が変わりやすいので、世界ランキング制度はなく、パラリンピックの出場権は大会での順位で、その都度決められている競技です。 まず、パラリンピック前年に行われる世界選手権の上位国(人数は大会ごとにFISAが決定)に与えられ、続いて、翌年(パラリンピック開催年)の世界最終予選の上位国に与えられ、さらに大陸バランスなどが検討され、FISAが「推薦枠」を与えます。 また、過去のパラリンピックでは、「開催国枠」が設定されたことがある競技です。
世界情勢としてはオリンピックのボート強豪国が、パラリンピックでも強い傾向にあります。 強豪国、欧米、オセアニア、南米勢に、アジア王者の中国が絡む。
ボートは他競技からの転向者や複数競技に挑む選手も比較的多く、わずか3年で世界の頂点に立つことも可能です。 リオデジャネイロ2016大会以降、大きな変化となる距離の延長がどのような影響を及ぼすのか、選手構成によるチームワーク強化など、ロサンゼルス2028大会に向けて世界情勢に変動はあるのか、目が離せません。
日本は過去の大会で推薦枠での出場や東京2020大会での開催国枠、自力での出場枠獲得など潜在的な競技人口は100名ほどだが、うち競技志向者は約30名で、強化選手となるとかなり絞られるため、選手強化と並行し、競技の普及や選手発掘も精力的に進められています。 ロサンゼルス2028大会への日本選手の出場枠獲得で活躍が期待されている競技です。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
カヌーは己の鍛え上げた上肢と艇との一体化、パドルリング技術の勝負

パラカヌーは2種類の艇を使い、水上の速さを競うレースです。 試合は磨き上げた上半身やバランス感覚、高度な技を駆使し、いかに効率よく力強く、驚異のパドル捌きのレース展開に注目。日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラカヌーの主な強豪国と地域:
「ハンガリー、ブラジル、フランス、オーストラリア、ウクライナ、イタリア、RPC、イギリス、アメリカ、ポルトガル、ドイツ、チリ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダルを獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会は欧米や南米、オセアニア、アジア諸国勢との水上の順位争いに小鳥たちも競い合う♪ 自然環境を読み解き、パワー漲るトルクと最速のスピードが打ち出せるパドル捌きを魅せる国はどこだぁ!
パラカヌーの特徴:
パラカヌーはリオデジャネイロ2016大会からパラリンピックの正式競技となり、ボートとは異なり、選手は進行方向に向かって座って競い合う競技です。 1艇に1人が乗り、8艇が一斉にスタートし、パドル(櫂)を使って漕ぎ進み、タイムを競い合います。 パラリンピック競技となっているのは障害物のない直線コースで着順を競う個人200メートルスプリントです。 リオデジャネイロ2016大会ではカヤック種目が行われ、東京2020大会では、ヴァー種目(VL)が新たに追加され、カヤック(KL)とヴァー(VL)は、艇とパドル(櫂)の形状が異なり、漕法も異なっています。 カヌーのスプリント種目はパドル(櫂)を使ってカヌーを漕ぎ、シンプルに速さを競う水上での短距離競争です。
クラス分け:
対象となるのは下半身や体幹にディサビリティーズのある選手で、公平な競技を行うため選手はディサビリティーズの程度や運動機能によって3つのクラスに分けられています。 クラスは重いほうから順に、L1クラス(体幹の機能がなく胴体を動かすことが困難なため、肩と腕の機能だけで漕ぐ選手)、L2クラス(下肢で踏ん張ることが困難だが、胴体と腕を使って漕ぐことができる選手)、L3クラス(脚、胴体、腕を使い、踏ん張ることや腰を使う動作によって艇を操作できる選手)です。 カヤック部門はKL1、KL2、KL3、ヴァー部門はVL1、VL2、VL3と表されます。
種目別:
パラカヌー競技は上半身の力を推進力とし、水面を滑るように進み、いかに効率よく力強く、そして安定してパドルを回転させられるかという、パドリングの技術が勝利の大きなポイントです。 パラカヌーについては、とりわけカヌーと体のフィッティングが重要で、使用される艇はカヤックとヴァーの2種類で、競技はそれぞれの部門に分かれて行われます。
・カヤック
艇は長さ5メートル20センチ、最小幅が50センチ、最小重量12キログラムの直進性に優れた形状のものを使用し、オリンピックで使用される艇と同じような形状です。
パドルは長さ2メートルほどで、水をとらえるブレードが両側についているタイプで、1本のパドルを持った選手が艇の左右を交互に漕ぎながら前進していきます。
・ヴァー
東京2020大会からの新種目で艇はカヤックよりも長く、7メートル30センチ以内、最小重量13キログラム(浮き具を含む)です。
長いほど推進力があり、本体の左右どちらか片方に、バランスをとるためのアウトリガー(浮き具)が付いています。
アウトリガーの付いたカヌーは、太平洋の島々で古くから用いられたものだが競技としては新しいです。
これが付くとカヌーは安定します。
ヴァーで使用するパドルはカヤックとは異なり、片側にだけブレードが付いているものを使い、左右どちらか片方のみを漕いで進み、艇を直進させるためには高度な技術が必要です。
選手は自身のディサビリティーズに応じて、ルールの範囲内でカヌーの座席(シート)部分やコックピット内部の改造をすることが認められています。 例えば、体幹バランスをとることが困難な選手にとっては座席の改造が大きなポイントです。 素材や形状などを自身のディサビリティーズや体型に合わせて工夫し、座席と体を固定するためにベルトを取り付けるなどして姿勢を維持し、艇と一体化して漕げるようそれぞれ工夫しています。
見どころ:
カヌーの選手の多くは「水の上は究極のバリアフリー」と言い、段差も坂道もなく風を切って進める、それがカヌーの魅力です。 車いすからカヌーに乗り込むと、体幹や下肢の機能にディサビリティーズを感じさせない鍛え抜いたバランス感覚と高度な技術で、爽快に水の上を漕ぎ進める姿に魅了されます。
また、ポリネシアの言葉で小舟を意味するヴァーでは、オリンピックのカヌー競技にはない、パラカヌーだけのアウトリガー付きのカヌーレースを観戦することができる競技です。
鍛え抜かれた上半身の筋肉とフィッティングを駆使してバランスを保ちカヌーと一体化、爽快に風を切って水面を進む、カヌーと一体化したバドリングのテクニックが見どころになります。 なめらかなパドルさばきでスプリント勝負に注目です。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
2009年のカヌー スプリント世界選手権で、初めてパラカヌーのレースが公開競技として行われ、2010年に第1回世界選手権大会が開かれ、パラリンピックにはリオデジャネイロ2016大会から正式競技としてカヤック部門が採用されています。
強豪国として知られるのはイギリスやブラジル、オーストラリアなどで、パラリンピックの正式競技への採用が決まって以降、他競技から転向してくる選手も多く、競技性やレベルも向上している競技です。
東京2020大会で初めて実施されたヴァー部門、パリ2024大会でも新たなスター選手の誕生に期待が集まります。
日本はパラカヌーが初めて採用されたリオデジャネイロ2016大会に出場し、8位入賞を果たし、東京2020大会では7位入賞の結果です。 これまで競技人口が少なかったパラカヌーだが、東京2020大会を目指す選手で男女とも少しずつ増えており、ロサンゼルス2028大会への選手の強化が進められています。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
トラックは車両と一体化し、残存機能を最大限に発揮した己との勝負!

パラサイクリング トラックは屋内の自転車専用競技場で行われる種目です。試合は乗車、走行技術を磨き上げ、限界ギリギリまで挑戦する選手たちの迫力あるパフォーマンスに注目。日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラサイクリング(自転車)トラックの主な強豪国と地域:
「中国、フランス、イギリス、スペイン、スロバキア、RPC、カナダ、オーストラリア、ルーマニア、コロンビア、ウクライナ、オランダ、ポーランド、ベルギー、ドイツ、アメリカ、アイルランド etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会は欧米、オセアニア、アジア諸国勢との限界ギリギリの順位争いに突破口の光が差し込む♪ 己を信じ、限界を打ち破り、さらなるターボチャージャーのトップスピードで走り切れる国はどこだぁ!
パラサイクリング トラックの特徴:
パラサイクリングと呼ばれる自転車競技がパラリンピック正式競技に加わったのは、ニューヨーク ストックマンデビル1984大会から、トラック競技がアトランタ1996大会からです。 自転車競技にはトラックとロードがあり、それぞれ複数の種目が行われます。
トラックはオリンピックと同様にすり鉢状の傾斜がついた自転車専用競技場「ベロドローム」が舞台です。 オリンピックやパラリンピックをはじめとする大きな世界大会は1周250メートルのベロドロームで開かれ、屋内を走るため、風など天候の影響が少なく、トップ選手は時速60キロメートルを超えるスピードで駆け抜けます。
パラリンピックの自転車は、参加する選手のディサビリティーズにより、使用する自転車が異なる点が最大の特徴です。 選手自身のポテンシャルを最大限に発揮するために自転車の乗車技術、走行技術を磨き上げます。
種目とクラス別:
トラックは、一般的な競技用2輪自転車を使用するCクラス、2人乗りのタンデム自転車を使用するBクラスに大別され、「タイムトライアル」、「パーシュート」、「チームスプリント」が実施される種目です。
Cクラスは、四肢の切断や欠損、または筋力低下、可動域制限、運動失調、アテトーゼなど、運動機能にディサビリティーズがある選手のクラスで、できるだけ公平に競い合えるようにするため、ディサビリティーズの程度によってさらに細かくC1、C2、C3、C4、C5に分けられます。 個人種目は男女別、チーム種目「チームスプリント」は男女ミックスで競い合う形式です。
トラック種目のうち、Cクラスは切断やまひなど四肢のディサビリティーズを対象とし、ディサビリティーズの程度の重いほうからC1~C5の5つに区分されます。 使用する2輪自転車は競技用を使用するが、安全性の確保を目的に、選手のディサビリティーズの特性に合わせた最小限の改造も認められている仕様です。 例えば、上肢ディサビリティーズの選手はハンドルの形を変えることができたり、ひざ下切断の選手は義足をペダルに固定できます。
Bクラスは視覚ディサビリティーズを対象とするが、他の競技のように見え方の程度に応じたクラス分けはなく、ひとつのクラスで競い合う形式です。 2人乗りのタンデム自転車は、前方にパイロットと呼ばれる晴眼の選手が乗ってハンドル操作やコース取り、レース状況に応じた判断を行い、後方に視覚ディサビリティーズの選手が乗ります。 両者のペダルは連動しているため、ピッタリとリズムを合わせて漕げば、2人の力を合わせた最大限のパフォーマンスが発揮できるクラスです。 コーナーでの体重移動や息の合ったスピード緩急、ペダリングなど、2人の高いコンビネーションが欠かせません。 日ごろの練習の積み重ねが重要になります。
見どころ:
トラック種目は、残存機能をフル活用して限界ギリギリまでスピードを出す選手たちの迫力あるパフォーマンスが見どころです。 己の限界に挑戦する選手たちの姿に引き込まれるように観客もヒートアップします。 観客席と選手との距離感も近く、会場全体が一体となって盛り上がることができるのもトラック種目観戦の楽しみです。 傾斜のある屋内走路でスピード感のある短距離の勝負は会場が一体になり、限界に挑む選手たちの姿に手に汗握る!
3つの種目別の特徴:
「タイムトライアル」はそれぞれが最大限のスピードで走り、コンマ一秒を競い、計測したタイムで順位が決まります。 Bクラスは時速60キロメートルを超えるスピードで、迫力が味わえ、激しいバトルに見るものも手に汗握ること間違いないです。 Bクラス男女及び男子Cクラスは1キロメートル、女子のCクラスは500メートルを走ります。
「チームスプリント」は男女混合の1チーム3人で構成し、空気抵抗による減速を避けるため縦列になりながら1人が一周ずつ先頭を走り、周回ごとに1人ずつ隊列から離脱していき、3周目を走った選手のタイムで優劣を競い合う種目です。 公平さを保つため、性別、クラスごとに点数が決められ、3人の組み合わせは定められた上限のポイントを超えてはなりません。 各国のチームワークも見どころです。
個人追い抜きとも呼ばれる「パーシュート」は、予選の計測タイム上位4組が決勝に当たり、順位決定戦に進みます。 予選1位と2位が金メダルを競い、同じく3位と4位の選手で銅メダルをかけて対戦する形式です。 ホームストレッチ、バックストレッチからそれぞれが同時にスタートして先にフィニッシュするか、対戦相手を追い抜いた選手が勝者となります。 男子Bクラス、男子C4~C5は4キロメートル、それ以外のクラスは3キロメートルで競い合う種目です。
なお、Bクラスは、視覚ディサビリティーズの選手に競技パートナーが不可欠だが、そのパイロットを健常のトップ選手が務めることも珍しくありません。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
圧倒的な強さを発揮しているイギリスをはじめ、オーストラリアや中国が発揮するトラック種目で、近年、オリンピックとパラリンピックチームの強化体制の統合が進んでいることで各国のトレーニング環境が整い、競技レベルも上がっています。 また、東京2020大会の個人戦でも力を発揮するフランス勢のさらなる追い込みに注目が集まりそうです。 アジア地域では中国がトラック競技で抜群の存在感を放っており、警戒すべき存在であることに変わりありません。
ロサンゼルス2028大会では出場国ともに、果たしていくつのメダルを獲得できるのか、輝き続けるスター選手などに注目です。 団体種目のチームスプリントは、リオ016大会で世界記録を打ち立て、東京2020大会で優勝したイギリスを中国やスペインらが引きずり下ろせるか。 強豪国、欧米とオセアニア、中国、健常との垣根がなくなり、より一層ハイレベルな争いに観客も熱狂!
日本勢はパラリンピック連盟(JPCF)の強化指定選手や同育成選手を中心に競技力強化が行われており、男女ともに若手の育成も進められています。 ロサンゼルス2028大会での活躍が見込まれる選手も現れるかも、乞うご期待。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
ロード Ver.
ロードは自然環境を見極め、メンタルと独走力を駆使した己との勝負!

パラサイクリング ロードは起伏ある屋外の長距離コースで戦う種目です。試合は多彩なバイクコントロールやペース配分、ポジション確保、ライバルを牽制し駆引きする走りに注目。日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラサイクリング(自転車)ロードの主な強豪国と地域:
「イギリス、フランス、ウクライナ、オランダ、イタリア、スペイン、RPC、スイス、オーストリア、中国、ベルギー、コロンビア、アメリカ、ドイツ、オーストラリア、スロバキア、南アフリカ、アイルランド、スウェーデン、ポーランド etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会は欧米、オセアニア、アフリカ、アジア諸国勢とのコンマ数秒の順位争いに各国が熱狂する♪ 大自然のなか、コース状況を読み解き、華麗に疾走遂げる国はどこだぁ!
パラサイクリング ロードの特徴:
オリンピックでは第1回のアテネ大会から正式競技として実施されている自転車競技だが、パラリンピックで採用されたのはニューヨーク ストークマンデビル1984大会から、以来継続して実施されています。 パラリンピックの自転車は、屋外の道を走る「ロード」と屋内の自転車専用走路を使用する「トラック」に大別され競技です。
屋外でレースを行うロードは、風や雨、暑さなど刻々と変化する自然の中で行われます。 屋外の長距離コースで競い合うため、スタミナを考慮したペース配分、ポジションの確保、ライバルを牽制して仕掛けるポイントなども勝敗を分けるカギです。
クラス分けや使用する機材の違いはあるが、UCI(国際自転車連合)の規制に沿ってオリンピックとほぼ同じルールで行われています。
ロードでは、自転車ごとに異なるバイクコントロールテクニックを駆使し、選手によって得意不得意が明確に分かれるため大きな勝負所となる上り、繊細なスピードコントロールとコーナーワークが必要とされる下りといったコースの特徴をどう攻略できるかがポイントです。
ロードでは「ロードレース」、「タイムトライアル」、「チームリレー」の3種目があり、選手はディサビリティーズの種類や程度、そして使用する自転車により4つのクラスに分かれてメダルを競い合います。 メダル数が多い、ロードは総計34個の金メダルを争う競技です。
クラス:
トラックにはなく、ロードのみ実施されるクラスもあります。
Tクラスは、重度のまひなどで、ペダルを漕ぐ脚力はあるものの、一般的な2輪の競技自転車には乗ることが難しい選手を対象とし、ディサビリティーズの程度によってT1~T2に区分されるクラスです。 このクラスの選手は体幹の機能強度低下、平衡感覚の欠如、筋緊張、運動失調、アテトーゼなどによりバランスを取ることが難しいため、安定性の高い2輪自転車「トライシクル」を使用します。 運動機能に制限があるなか、ペダルに力を伝えるテクニックはもちろんのこと、車幅のあるトライシクルで失速せずにコーナーを曲がる技術の習得も欠かせません。
もうひとつのHクラスは、切断や脊髄損傷によるまひなどで、主に下肢に重度のディサビリティーズのある選手が対象です。 ディサビリティーズの程度の重いほうからH1~H5の5つに細分され、手で漕ぐタイプのハンドルサイクルを使います。 一般的にH1~H4の選手は仰向けの状態で自転車に乗り、腹筋や背筋の筋力が安定しているH5の選手は上体を起こし前かがみに乗り込むスタイルです。
トラック同様に、2輪自転車を使用するCクラス(切断、まひなどの四肢ディサビリティーズ)と、視覚ディサビリティーズの選手が後方に乗る2人乗りタンデム自転車のBクラスも実施されます。
3つの種目:
一斉スタートで順位を競う「ロード」種目は男女別に行われ、クラスそれぞれに設定された長い距離を走る種目です。 先頭の選手が空気抵抗を受けるため、できるだけ他の選手の後ろで体力を温存しながらレース中に駆け引きを行い、勝負所で一気に仕掛けます。 ラストの直線で激しく競い合った末、わずかな差で勝者が決まることもあるレース展開です。
「タイムトライアル」は1周8キロメートルのコースを男女やクラスごとに定められた周回を走り、個々の完走タイムで順位を決めます。 選手は時間差で一人ずつスタートし、全員がゴールした後に順位が決まるため、自らを追い込む強いメンタルと独走力も必要です。
基本的には先着もしくは計測タイムが最も早い選手が勝ちだが、パラリンピックでは複数のクラスを統合して競技を行うことがあり、その場合、実際に計測したタイムにクラス間のディサビリティーズの程度を補正した係数をかけた「計算タイム」で順位を算出します。
「チームリレー」は1チーム男女混合の3名で編成され、一周2.7キロメートルのコースを各3周計9周する勝負です。 実施されるのはHクラスで、次の走者へリレーする際はタッチではなく、前の走者がラインを通過したら次の走者はスタートできます。
見どころ:
自然の影響やコース状況を読み、長距離のコースを走破する姿に圧巻です。 ロードの舞台は起伏のある屋外のコース、ディサビリティーズに応じて駆使する駆け引き、ポジション争いの末、コンマ一秒の争いを制する選手に注目が集まります。 プロ、二刀流、個性豊かな選手たち、圧倒的な存在感を放つスター選手のパフォーマンスに注目です。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
勢力図は自転車文化の盛んな欧米が上位を占め、とくにイギリス、フランス、オランダ、ドイツが強豪です。
Cクラスでは、上記の他にもスペイン、ベルギー、オーストラリア、アメリカなど各国がひしめいています。 アジア地域では、トラックで強さを誇る中国がロードでも力を発揮しているのが現状です。
Bクラスは、オランダ、フランス、イギリス、アイルランド、スウェーデンが金メダルを狙っています。
Hクラスのチームリレーでは、イタリアが強さを誇っているがフランス、アメリカなど頂点をにらむ各チームの動向からも目が離せません。
メダルを量産してきた欧米のベテランが牙城を守るのか、それとも列強を脅かす新勢力が現れるのか、楽しみです。
日本は自転車の盛んな強豪国の実力者に割って入り、メダリストを生んできたチーム、さらなる活躍に乞うご期待!
※東京2020大会関連資料より、参考元:
馬術は人馬との信頼関係や技の正確性、同調性、己の華麗な演技の勝負

パラ馬術は芸術的で、技の正確さや演技の美しさを競い合う競技です。試合は馬場を駆抜ける人馬一体の華麗な演技やチームワーク、競技スタイル、補装馬具、音楽との一連の動きに注目!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラライディング(馬場馬術)の主な強豪国と地域:
「アメリカ、ラトビア、イタリア、イギリス、オーストリア、デンマーク、オランダ、ブラジル、ベルギー、ノルウェー、スウェーデン、ドイツ etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会は欧米やアフリカ、アジア諸国とのダイナミックかつ華麗な順位争いに気品漂う風が流れ込む♪練習で培った人馬との信頼関係で芸術の都を華麗に演技できる国はどこだぁ!
パラリンピックの馬術の特徴:
乗馬の芸術は古代ギリシャで始まり、その後、ルネサンス期に復活し、1952年のヘルシンキ大会では、女性が初めて馬場馬術に参加し、1964年には、女性がすべての馬術種目に参加できるようになり、オリンピックで唯一の完全に混合で行われる種目です。 最初の大会は1970年代に開催されます。 欧米で人気のあるスポーツである馬場馬術は、パラリンピックではアトランタ1996大会から正式競技として採用された競技です。
馬場馬術の競技対象は肢体不十分の選手と視覚ディサビリティーズの選手で、男女が対等な条件で、ディサビリティーズの内容や程度に応じてグレードⅠからⅤまで5つのクラスに分かれて競います。 オリンピックの馬術とは異なり、パラリンピックでは技の正確さや演技の美しさを競う馬場馬術(ドレッサージュ)種目のみが行われる競技です。
種目は、個人課目と、選手3名で構成される団体課目(音楽付き)があります。 また、個人課目の結果が上位の選手のみが出場できる「馬のバレエ」とも呼ばれ、選手が考えたオリジナルな動きのパターンを組み合せた音楽に合わせて乗りこなす自由演技課目(音楽付き)の3つです。 勝負は5名の審判の拠点によって決められ、歩様やステップの正確性、乗り手と馬の一体感などが評価の対象となります。 人馬一体の華麗な演技を競う馬場馬術です。
クラス分け:
パラリンピックではオリンピックと同様に男女混合での採点演技で行われるが、ディサビリティーズの内容や程度により、5つのクラスに分かれて競い合います。 クラスごとに求められる技術レベルが異なり、ディサビリティーズを補うための馬具の使用や改造なども認められている競技です。
リオデジャネイロ2016大会までは、クラスはディサビリティーズが重い方から順に5つだったが、2017年からグレードⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴに変更され、東京2020大会も新しいクラス分けで実施され、パリ2024大会も同様のクラス分けで実施されることだろう。
グレードⅠは、全四肢および体幹に重度のディサビリティーズがある選手のクラスです。 グレードⅡは、上肢のディサビリティーズは最小だが体幹に重度のディサビリティーズがある、または体幹、腕、足に中度のディサビリティーズがある選手のクラスになります。 グレードⅢは、体幹のディサビリティーズは最小またはディサビリティーズが無いが、両下肢に重度のディサビリティーズがある、または両上肢、両下肢および体幹に中度のディサビリティーズがある選手のクラスです。 グレードⅣは、両上肢欠損または両上肢に重度のディサビリティーズがある、全四肢に中度のディサビリティーズがある、または低身長の選手のクラスになります。 重度の視覚ディサビリティーズがある、または盲目(B1クラス)の選手も該当の対象です。 グレードⅤは、可動域または筋力に軽度のディサビリティーズがある、片下肢欠損、または軽度の両下肢欠損の選手、視覚ディサビリティーズ(B2クラス)がある選手のクラスになります。
採点内容とルール:
馬場は、グレードⅣとⅤはオリンピックと同じ20メートル×60メートルのサイズで、グレードⅠからⅢは少し小さい20メートル×40メートルの馬場を使う競技です。 選手は、この馬場内で決められたコースを移動しながら、図形などを描き、馬を操る技術レベルを審査されます。 最も基本的な技術は「常歩(なみあし)」、対角線上の肢が交互に2拍子のリズムで動く「競歩(はやあし)」、スピードのある「駈歩(かけあし)」、さらに高度な、 前肢と後肢が異なる軌跡を描く「ニ蹄跡運動(にていせきうんどう)」です。 グレードⅠは常歩、グレードⅡは常歩と速歩など、クラスによって求められる技術レベルが異なります。
馬場の周囲にアルファベットなどのマークが記され、例えば「B → E → Kの順に常歩で」といった指示に従って馬をコントロールし、馬場を囲むように5人の審判員が座っており、動きの正確さ、馬の頭の位置など項目ごとに採点シートに点をつけていく方法です。 順位は各審判員の採点を満点で割ったパーセンテージで決まります。
視覚ディサビリティーズの選手はグレードⅣやⅤにクラス分けされるが、「コーラー」がマークの位置を声で知らせ競技をサポートし、コーラーは最大13人までつけられるルールです。 高次脳機能のディサビリティーズなどで記憶ディサビリティーズがある選手は、「コマンダー」が馬場外からコースを逐次伝えることができます。 こうしたアシスタントとのチームワークも見どころです。
選手はヘルメットやジャケットの着用が義務付けられています。 まひや切断のため下半身の支えがない状態でも、選手はバランスよく鞍に乗って騎乗するので、ディサビリティーズは見えにくいが、ブーツの中は義足の場合もある競技スタイルです。 選手のディサビリティーズや症状は一人一人違うので、ディサビリティーズに応じて改造した特殊な馬具の使用が認められています。 例えば、鞍や手綱、鐙など人と馬をつなぐ道具は選手の身体状況に合わせ、安全第一の工夫が認められている仕様です。 鞍には補助ベルトや背あてを付けたり、手のディサビリティーズで手綱を握れない選手は手綱の先に輪(ループ)をつけたり、口でくわえたり、足の指で握ったりする選手もいます。 下半身まひの選手は馬の制御のため、1~2本の鞭を使用することが可能で、道具の改造や使用も演技の出来ばえを左右する重要なプロセスです。 これらは注目すべきポイントの一つになります。
馬術においては、素質が高く美しい馬との出会いが大切だが、さらに乗り手との相性の良さも重要です。 言葉を交わすことはできないが、一緒に同じ時間を過ごしてコミュニケーションをとり、馬の性格や能力を理解し、尊重することで演技を創りあげていきます。 人と馬との信頼関係を築き、呼吸と気持ちを合わせ、同調性を高めることが欠かせません。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
パラリンピック出場には、既定の国際大会を転戦し、出場条件となるパーセンテージを得る必要があります。 リオデジャネイロ2016大会以降は、「選手のみの出場資格」から「選手と馬のコンビネーションでの出場資格」に要件が変更され、選手が同じ馬を各地の競技場に輸送する必要があり、日本などの島国にとってはクリアすべき課題が増えているのが現状です。
歴史的に馬術の人気が高いヨーロッパ地域の国が強く、特に圧倒的強さを見せるイギリスは馬術大国として知られ、個人課目で多数のメダリストを輩出しており、団体戦でも連覇を続けています。 特に、オランダやドイツなども上位に食い込む他、近年は欧州勢優位を脅かす、南アフリカやシンガポール、アメリカなども力をつけている諸国です。 ロサンゼルス2028大会は開催国であるフランスを始め、ヨーロッパの牙城を他の国が崩せるかに注目が集まります。
互いを信じて、心をひとつに、馬場を駆ける人馬一体の息づかいに耳を澄ませ、思うままに馬を操り、見事な演技を引き出す国や地域の台頭が魅力的です。
日本はリオデジャネイロ2016大会や東京2020大会で培った経験やパラ馬術に転向してきた選手など強化指定選手も増え、厚みを増した陣容で躍進を目指す。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
パワーリフティングは上半身の三頭筋と精神力を駆使した己との勝負!

パワーリフティングはバーベルを押し上げ重量を競い合う人気競技です。試合は体重別で実施され、独特の緊張感と多くの観客中、鍛え上げた筋肉と集中力を発揮させる試技の成功に注目!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラパワーリフティング(重量挙げ)の主な強豪国と地域:
「ヨルダン、ベトナム、アゼルバイジャン、カザフスタン、フランス、ギリシャ、中国、エジプト、エルサルバドル、イラン、アルジェリア、マレーシア、イギリス、コロンビア、モンゴル、イラク、インドネシア、ベネズエラ、ナイジェリア、ポーランド、ウクライナ、トルコ、メキシコ、ウズベキスタン、ブラジル、RPC etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会は欧州や南米、アフリカ、中東、アジア諸国勢とのパワー漲る順位争いに成功を示すランプが点灯する♪世界110ヵ国以上に普及するパワーリフティングの新記録を更に持ち上げる国はどこだぁ!
パワーリフティングの特徴:
パワーリフティングは重りのついたバーベルを押し上げ、その重量を競う競技の総称です。 そのうちパラリンピックでは、台上に仰向けに横たわった状態からバーベルを押し上げるベンチプレス競技が行われます。 下肢または腰にディサビリティーズがあり、立位でウエイトリフティング競技を行うことができない選手が参加し、腕や肩、胸など上半身の筋力だけが武器です。 上半身だけで、自身の体重の約3倍以上の重量を持ち上げる選手もいます。
東京1964大会からパラリンピックの正式競技となったが、当時はウエイトリフティングという名称で行われ、さらに脊髄損傷の男子選手のみ出場が認められた競技です。 ソウル1988大会からパワーリフティングという名称に変更され、脳性まひやポリオ、下肢欠損など対象とするディサビリティーズも拡大されています。 シドニー2000大会からは女子の部も実施されるようになり、近年競技選手は110ヵ国以上に広がっている競技です。
実施階級:
パリ2024大会も東京2020大会と同様に男女各10階級が実施される予定になっています。 試技は一人1回ずつ順番に行い、3回の試技で最も重いバーベルを挙上した選手が勝者となる試合形式です。 また、ディサビリティーズの内容や程度によるクラス分けはなく、試合は体重別で行われます。 男女各10階級に分かれるが、下肢の一部を切断している選手は切断の範囲に応じて選手自身の体重に一定の重さを加算した重量で分類する構成です。
ルール:
選手がパラリンピック専用のベンチプレス台に仰向けに横たわった状態で試合が開始されます。 台は長さ2.1メートルで最大幅は61センチメートル、上半身部分の幅30センチメートル、高さは床から48センチメートルから50センチメートルまでの規定です。
一般のベンチプレス競技では足を床に着けた状態で行うが、パラリンピックでは足も台に乗せた状態で行われるので、足でふんばることができません。 バランスを保つため、足をストラップ(布製のベルト)で固定することもあります。 足を床につけない状態での競技が、いかに難しいか想像してみましょう。
選手はラックから外したバーベルを腕が完全に伸びた状態で支え、審判の指示でバーベルを胸の位置で一旦止めて、肘を真っ直ぐに伸ばしながら元の位置まで一気に押し上げる方式です。 左右どちらに傾いたりせず、正しい姿勢でバーベルを上げたまま静止し、主審が「ラック」と合図したらバーベルをラックに戻します。 試技は3人の審判によって判定され、白いランプが2個以上点灯すれば成功です。 逆に、赤いランプが2個以上点灯すれば不成功を意味します。 鍛え上げられた筋肉と一瞬の集中力が試される会場は独特の緊張感に包まれ、成功を示すランプが点灯すると、大歓声が響き渡る瞬間です。
選手はこの試技を3回行うことができます。 申告した重量の少ない選手から1回ずつローテーションし、3回目の試技を終えた時点で最も重い重量を持ち上げた選手が勝ちです。
見どころ:
厳しいトレーニングによって見事に鍛え上げられた上半身、特に胸や肩、腕の三頭筋などの発達も見どころになります。 パラリンピックの中でも多くの観客を集める人気競技の一つです。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
競技の世界的な普及もあり、中東諸国やアジア、アフリカなど強豪国も幅広く、競技歴の長いベテラン選手も少なくありません。 世界的な競技普及と記録はどこまで伸び続けるのか、期待が高まります。 試技の成功が会場の息詰まる緊張感や緊迫感、静寂から大歓声に変わる瞬間です。
日本選手はアトランタ1996大会から出場しており、過去に入賞選手も輩出し、2016年に京都府に新設された常設の練習拠点で定期的に合宿を開いたり、 海外からトップコーチを招いての練習会を行うなど、メダル獲得を目指し強化が進められ、ロサンゼルス2028大会での躍進に期待する。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
柔道は身体能力と全神経を最大限に発揮し、己の技で一瞬の勝機に挑む

パラ柔道はクラス分けがなく階級制で行われる競技です。試合は全力での激しい技の応酬で瞬発力や集中力、持久力が求められ、微妙な持ち手争い、全ては一本のために繰出される戦略に注目。日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラ柔道の主な強豪国と地域:
「アゼルバイジャン、カザフスタン、トルコ、ルーマニア、ウズベキスタン、スペイン、カザフスタン、ウクライナ、リトアニア、メキシコ、韓国、イラン、イギリス、フランス、アメリカ、RPC、ジョージア、アルジェリア、カナダ、ブラジル、中国、イタリア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会は欧米、南米、中東、アフリカ、アジア諸国勢との5大陸、7つの海を跨いだ順位争いに黄金のメダルが眠っている。「はじめ」の合図で素早く一本を決める国はどこだぁ!
柔道の特徴:
パラリンピックの柔道は視覚ディサビリティーズ者だけで行われ、パラリンピックの柔道の程度に応じたクラス分けはなく、オリンピックと同様に男女別、体重別の階級制で行われる競技です。 アイマスクなどは使わず、全盲や弱視など見え方の異なる選手同士でも、そのまま対戦します。
柔道は、男子がソウル1988大会から、女子はアテネ2004大会から、それぞれパラリンピックの正式競技となり、選手の視覚ディサビリティーズの程度は全盲(B1)~弱視(B3)まで区分された3クラスのみです。
ルール:
ルールはオリンピックとほぼ同じだが、大きく違う点は試合の始め方です。 両選手がお互いの襟や袖を決められた位置でつかみ、組み合った状態から「はじめ」とするルールが設けられています。 ここがオリンピックの柔道と異なる大きなポイントです。
最初の組み方には手の位置などに細かい規定があり、一度組み合ったら、主審が「はじめ」を宣言するまでそのまま待つ、動けば「指導」が与えられます。 ただし、全盲の選手は、試合の最中に場外に出てしまった時に、場内中央へと戻る際の移動の介助が必要なこともあり、主審が全盲であることを認識しやすいように、柔道衣(白、青とも)の両袖外側に直径7センチメートルの赤い円形のマークを縫い付けなければならないルールです。
組み手争いの時間がないため、試合開始から技の掛け合いになり、全力での激しい技の応酬により、選手の体力の消耗は激しく、集中力と持久力が必要になります。
また、試合の途中で両手が離れた場合は、「待て」がかかり、選手は組んだ状態に戻され、故意に不注意の場合には場外指導が与えられるが、オリンピックに比べて緩やかに適用されているルールです。 主審は選手が場外に近づいたら、畳の中央付近から「場外、場外」と声を出すことで選手に正しい方向を知らせます。 もし場外に出た場合は、中央に戻って組み直しです。
コーチは試合中、コーチ席から選手に指示を与えることが認められているのも、オリンピックの柔道とは違う点になります。 選手の目の代わりとなり、視覚からの情報を補うようなコーチングを行ってもよく、特に残り時間についての情報などは選手にとって重要です。
見どころ:
試合は開始早々に「一本」で勝負が決することもあれば、終了間際の形勢逆転もあり、接近戦での技の応酬は壮絶で4分間の試合は最後まで目が離せない魅力があります。 組み手争いがないため、試合開始直後から一本狙いの大技が繰り出されることが多く、迫力のある試合が繰り広げられる展開です。 最初に組み合った状態から自分の得意な組み方に移行しながら技につなげていこうとする、微妙な持ち手争いも見どころの一つになります。 視覚からの情報を得にくい中で、相手の微かな動きや力の入れ具合、息遣いなどから出方を察知し、攻めを封じながらいかに相手を崩し、自分の技を出すタイミングを探る戦いです。 神経を研ぎ澄ませ、集中力を高め続ける気力のスタミナも問われます。
オリンピックのパワー柔道の潮流は、パラリンピックの柔道にも同様に見られ、選手は技をかけられた不利な体勢から、一気に巻き返す展開も見どころです。 技の幅を広げるため、ブラジル発祥で寝技を主体とする「ブラジリアン柔道」や、ロシア発祥で投げや関節技で一本を狙う「サンボ」などを練習に取り入れる選手も増えています。
残り2秒でも組み合ってから始まるため、大逆転勝利もあり得るのはパラリンピックの柔道ならではの見どころです。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
日本発祥の柔道は欧米にも普及や浸透し人気も高く、パラリンピック柔道のルールは、2016年末に国際柔道連盟(IJF)が行ったルール改正により、一部変更されています。 例えば、試合時間は男子が1分短縮されて男女とも4分間となり、技の判定基準が一本、技ありのみです。 ルール改正で、より攻撃的に「一本」を狙う柔道を目指した変更となっており、選手はさらなる瞬発力やパワーをつけ、これまで以上に試合開始直後から積極的に攻める戦略も必要になります。
パラリンピックの柔道は強い国が多く、各国がメダル獲得を狙っている競技です。 激動の最中、ウズベキスタンは専用の練習施設の設立や育成プログラムの導入など、パラリンピック競技全体に対する国の厚い支援もあり、強化につながっています。
日本勢は男女とも、大会に連続出場するなか、毎大会1個以上のメダルを獲得し、今後さらなる活躍に期待が持てるように強化を図る所存です。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
テコンドーは相手の特性を見極めた戦略や有効な蹴り技、己との勝負!

パラテコンドーは蹴り技が特徴の格闘技です。試合はキョルギ(組手)のみ実施され、至近距離で対峙し、華麗で力強くスピード感ある足技や強烈な蹴り技の応酬、鉄壁のガードの大迫力!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラテコンドーの主な強豪国と地域:
「ブラジル、エジプト、RPC、トルコ、メキシコ、イラン、アルゼンチン、韓国、クロアチア、アメリカ、ペルー、タイ、デンマーク、イギリス、中国、ウズベキスタン、オーストラリア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会は欧米や南米、中東、アジア諸国とのスピード感ある足技の順位争いに目の色が変わる♪試合時間内に己の有効な足技が数多く決まる国はどこだぁ!
パラテコンドーの特徴:
テコンドーは東京2020大会からパラリンピックの正式競技となった2競技のうちの一つです。 パラリンピックのテコンドーは比較的新しい競技の一つで、2005年から始まり、2009年に最初の世界選手権大会が行われます。 蹴り技を特徴とする格闘技で、基本的なルールはオリンピックとほぼ同じです。 パラテコンドーは、知的ディサビリティーズ、神経ディサビリティーズ、視覚ディサビリティーズのある選手が行うプムセ(型)と、おもに上肢ディサビリティーズの選手によるキョルギ(組手)があり、パラリンピックではキョルギ(組手)が行われます。
キョルギはディサビリティーズの程度により、重いほうから順にK41からK44まで4つのスポーツクラスに分けられるが、パラリンピックではK43(両上肢の肘関節より先にディサビリティーズがある選手のクラス)とK44(上肢または下肢の片方にディサビリティーズがある選手のクラス)の2つのスポーツが統合され、男女、別に体重階級制(各3階級)で競い合う競技です。
ルール:
試合は八角形のコートで行われ、有効な攻撃に対してポイント(2~4点)が与えられ、試合時間内により多くの得点をとったほうが勝ちです。 3ラウンド終了時点で同点の場合は延長戦が行われます。
パラリンピック特有のルールとして、胴部への足技だけが有効な攻撃であり、頭部への蹴りは反則です。 相手と至近距離で対峙し、繰り出される蹴りの応酬は迫力満点で、力強さとスピード感が見どころになります。
使用するコート(八角形)や試合時間(2分×3ラウンド、インターバル1分)、安全対策を考慮したヘッドギア、電子防具、マウスピース、ハンドグローブといった装具もオリンピックと同様です。
華麗な足技の迫力やスピード感が魅力だが、パラリンピックのテコンドーは頭部への蹴りは禁止で、胴体への3種類の蹴り技だけが有効となります。 ポイントにおいては、有効な蹴りは1回2点で、180度の回転が加わった後ろ蹴りは3点、後ろ蹴りから軸足を入れ替えて計360度の回転蹴りは4点です。 360度の回転蹴りが4点技となったのは2017年からで、回転蹴りを回転度数によって点数を分けるというのはオリンピックにはないパラリンピックならではのルールになります。 豪快で華麗なこの技を習得すれば、一発逆転の可能性も高まる大技です。
見どころ:
ダイナミックな蹴り技は見応えがあるが、相手の蹴りを上肢でガードして止める防御力も重要になります。 ただし、選手それぞれ上肢ディサビリティーズの状態が異なるので、体の使い方にも個性や工夫が見られる試合展開です。 選手は自身の特性とともに、対戦する相手の特性をも見極め、どう守り、どう攻めるか戦略を立てて戦います。
技の特効性の判定は選手が胴部に装着した電子防具で行われ、正しい位置に正しい強さで蹴りが入るとポイントが加算される仕組みです。 しっかり蹴らないと得点にならないため、相手のガードをかいくぐり、強烈な蹴りを決めることが必要になります。
競技はディサビリティーズの程度に応じて重いほうから順にK41からK44まで4つのクラスに分けられ、男女それぞれ体重別に3階級で競い合う構成です。 1階級内の体重差が大きく、例えば、男子75キログラム級は61キログラムから75キログラムまでと14キログラムの幅があり、それだけ体格差も大きくなります。 一般に大柄の選手のほうが長い足を活かした攻めで有利だが、戦術やガードも含めた体の動き方により小柄な選手が勝利を収めることもあり得る競技です。 体格差だけでは測れない勝利の行方にも注目が集まります。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
世界的な競技人口は少ないパラテコンドーだが、東京2020大会での正式採用が決まり、徐々に普及が広がり、競技レベルも向上しているのが現状です。 そんな中、競技人口も多く強豪国の筆頭はロシアで、続いてトルコ、イラン、アゼルバイジャンなど続きます。
また、フランスやモンゴルなどは競技人口は少ないが精鋭を擁している国です。 パラリンピックのデビュー戦となる東京2020大会では、クラスはK43とK44クラスが統合された1クラスのみの実施で、男女3階級ずつ計6個の金メダルが競われ、ロサンゼルス2028大会ではどのようなクラス分けで実施されるか期待が高まります。
ロサンゼルス2028大会は2度目のパラリンピック採用で、アジア勢とヨーロッパ勢が競いながら頂点を狙うも、多彩な国と地域の有力選手が出場枠を狙ってくるだろう。 豪快な蹴り技や鉄壁のガード、選手の個性に合わせた攻守に観客の声援も上がる試合展開です。
日本は東京2020大会で、急ピッチで普及が進められ、競技人口を増やし女子選手の発掘や強化合宿を行い、地域の道場や大学で健常者と練習を続けて強化を図っています。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
射撃は究極の高精度と正確性、精神力と集中力を駆使した己との勝負!

パラ射撃は遠方にある円状の的を撃ち、正確性を求む競技です。試合は射撃場により自然環境を読み、何事にも動じない感情の制御や撃発の微妙な技術、プレッシャーに打ち勝つ姿に注目。日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラ射撃の主な強豪国と地域:
「中国、ウクライナ、韓国、アラブ首長国連邦、セルビア、インド、ドイツ、イラン、トルコ、ハンガリー、スウェーデン、スロベニア、イタリア、スロバキア、スペイン、ポーランド、RPC etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会は欧米や中東、アジア諸国との緊迫した順位争いに額と手に汗が噴き出る♪実力拮抗する出場選手たち、ライバルとの僅差を撃ち抜ける国はどこだぁ!
パラ射撃の特徴:
パラ射撃は、肢体不自由の選手を対象に実施され、ライフルやピストルで遠方に固定された円状の的を撃ち、その正確性を競い合う競技です。 撃ち抜いた位置によって点数が与えられ、制限時間内に規定の弾数の射撃を連続して行い、合計得点によって勝敗が決まります。
パラリンピックでは、選手のディサビリティーズの程度、ならびに上肢(手または腕)で銃を保持できるかどうかを基準として、SH1ピストル、SH1ライフル(上肢で銃を保持できる)、SH2ライフル(上肢で銃を保持できず、支持スタンドを使用する)の3つに分けられたクラスです。
クラス分け:
ピストルは片手で保持するため、SH1ピストルのみで、切断または脊髄損傷により、片方の上肢および、または両下肢にディサビリティーズがある選手が通常、競技規則に沿って立位で行います。(座位で競技する選手もいる)。
ライフルは両手で保持するため、保持できるかどうかにより2つのクラスに分けられ、SH1ライフルは、切断または対まひにより下肢にディサビリティーズがある選手のクラスです。 通常、立位で行います。(座位で競技する選手もいる)
SH2ライフルは、上肢にディサビリティーズがある選手のクラスです。 ライフルの全重量を保持することができないため、支持スタンドを使用します。 上肢切断または上肢の筋力、可動性に影響を及ぼす先天性のディサビリティーズがある選手や四肢まひ等、上肢、下肢両方にディサビリティーズがある選手も含まれ、大半の選手は座位で行うスタイルです。
種目:
競技種目は銃の種類や的までの距離、撃つ姿勢などを組み合わせた、さまざまな種目があり、それぞれ男女別、男女混合などで競い合います。 近年は選手の技術や銃の性能の向上により、満点連発のハイレベルの戦いも増えており、究極の精度と精神力、集中力などが求められる過酷な競技です。
種目は銃の種類や的までの距離、射撃姿勢などの組み合わせによって分けられ、それぞれの条件に従って的を狙います。 合計得点の多い選手が勝ちとなり、種目にもよるが、競技時間は約1時間から3時間に及ぶこともある闘いです。 また、射撃場によっては、天候など自然の影響を受けることもあり、勝つためには、風の強さや向き、陽光などを読むことも必要になります。 近年は1発のミスが勝敗を分けるほど競技レベルも上がっており、ライバルは自分自身、究極のプレッシャーに打ち勝つ、集中力を保ち続け、練習通りのパフォーマンスを発揮できるかが問われる競技です。
パラリンピックで使用する銃は5種類で、種目によりそれぞれ的までの距離が規定されています。 ライフル種目はエアライフル(10メートル)とライフル(50メートル)の2種類、ピストル種目はエアピストル(10メートル)、スポーツピストル(25メートル)、フリーピストル(50メートル)の3種目です。 エアライフルとエアピストルは圧縮した空気の圧力で弾を撃ち出す仕組みになっています。
ルールとスタイル:
的には10個の同心円が書かれていて、10メートルエアライフル標的の中心の円は直径わずか0.5ミリで、これが10点圏です。 円の外側に行くにつれて等分に9~1点と得点が低くなり、的を外した場合は0点となります。 ライフル種目は電子計測によってさらに10分割されており、10点圏の中心に命中すると最高得点の10.9点の満点が与えられ、0.1点を争う僅差の勝負も少なくないです。
射撃姿勢には「立射(りっしゃ)」、「膝射(しっしゃ)」、「伏射(ふくしゃ)」の3種類あるが、パラリンピックでは車いすの選手など下肢にディサビリティーズのある選手も参加するため、ルールが緩和されています。 例えば、「立射」は立って銃を構えるため安定せず、最も厳しいとされるが、立位のほか、車いすや射撃用いすに座って射撃することが可能です。 「伏射」は伏せて銃を構えるため、最も安定した姿勢になります。 車いすなどを使う選手は台に両肘をつき、引き金を引かないほうの腕にスリング(負革)を巻き、銃を引き寄せて安定性を高めて行えるスタイルです。 「膝射」は片膝を立て、その上に腕を置いて構える姿勢だが、車いすや射撃用いすに座って射撃する場合は引き金を引かない方の肘を膝の代わりとなるスタンドに置いて撃つことができます。 「伏射」の次に安定する姿勢だが、単独での種目はなく、3姿勢混合種目で使われる方法です。
見どころ:
究極の正確性を競う射撃競技においては、定めた照準をぶらさないよう、さまざまな「制御」を行わなくてはなりません。 例えば、呼吸や心臓の鼓動も照準のブレを呼び、パフォーマンスに影響するので、呼吸のリズムと撃発のタイミングを合わせる微妙な技術が必要になります。 また、集中力を保つため、何事にも動じない感情の制御もポイントです。 それぞれに合った射撃のルーティンをつくり、常に正確に再現できる安定性も見どころの一つになります。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
パラリンピックの射撃は、トロント1976大会から正式競技となり、2016年に名称がIPC射撃(IPC Sheeting)から、パラ射撃(Sheeting Para Sport)、に変更された競技です。
東京2020大会では、リオデジャネイロ2016大会より1種目増やした全13種目が実施され、新たに加わったのは、男女混合の50メートル ライフル伏射SH2になります。 これまで、SH2クラスの種目はエアライフル10メートル立射と同伏射の2種目のみだったため、SH2クラスの選手にとっては出場枠の拡大となるため、競技人口の増加も期待されるクラスです。
近年は、参加国、地域の数が40以上にのぼるが、特に活躍が目立つのは男女とも中国勢で、また、韓国やウクライナなども強さを見せています。 ロサンゼルス2028大会で新たなチャンピオンやスターの誕生に期待が集まる競技です。
日本はシドニー2000大会で出場して以来、連続して数名ずつが出場を果たし入賞者も出ており、東京2020大会にはより多くの選手を送り強化が進められている。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
トライアスロンは自然を見極め、補助と連携し切換の時短や己との勝負

パラトライアスロンは1人で3つの過酷な種目を連続して行う競技です。試合は男女別、クラス別に行われ、距離はオリンピックの半分、計25.75キロメートルで強靭的なレース展開に注目。日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
パラトライアスロンの主な強豪国と地域:
「オランダ、オーストリア、イタリア、フランス、スペイン、ドイツ、イギリス、カナダ、アメリカ、オーストラリア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダルを獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会は欧米やオセアニア、アジア諸国勢との拮抗する順位争いに各国の旗が振られる♪ 自然状況を見極め、創意工夫で過酷なレース展開を制する国はどこだぁ!
パラ トライアスロンの特徴:
パラ トライアスロンは1人で3つの種目(スイム、バイク、ラン)を連続して行い、その合計タイムで競い合う競技です。 パラリンピックでは、リオデジャネイロ2016大会から正式競技となります。 レースの距離はオリンピックのちょうど半分となる「スプリント ディスタンス」で、スイム(750メートル)、バイク(20キロメートル)、ラン(5キロメートル)の計25.75キロメートルです。 レースは男女別、クラス別に行われ、ディサビリティーズの内容や程度により6クラスに分かれ、クラスごとに競技方法が一部異なります。
クラス分け:
座位(PTWC)は、バイクはハンドサイクルを使い、ランでは競技用車いすを使うクラスです。 立位クラス(PTS2~5)はバイク、ランではディサビリティーズに応じて義足など補助具が使用でき、バイクの改造なども認められています。 視覚ディサビリティーズ(PTVI)は、競技全体を通して同性のガイド1名と競技を行うクラスです。
リオデジャネイロ2016大会で初めて採用されたトライアスロンは、男女各5クラスあるうちの3クラスずつが実施された競技です。 その後、ディサビリティーズの内容や程度の違いによる競技力の差をより公平化するクラス分けの基準が再検討され、5クラスから9クラスに細分化されます。 東京2020大会は新たな9クラス制のもと、男女各4クラスが実施された競技です。 パリ2024大会もおそらく、9クラス制で実施されることだろう。
PTS(立位)クラスは機能的ディサビリティーズの程度に応じて3クラスから4クラスに細分化されています。
また、PTWC(座位)とPTVI(視覚ディサビリティーズ)は、それぞれPTWC1(重度)とPTWC2(軽度)、PTVI1(IBSAのクラス分類によるB1、全盲)と PTVI2(IBSAのクラス分類によるB2、弱視)、PTVI3(IBSAのクラス分類によるB3、弱視)というサブクラスが設定されているクラスです。
より公平に競えるよう時差スタートか、もしくは一斉スタートの場合はより軽度のクラスの実走タイムに、規定の補正時間を加算します。 一例を挙げると、PTWC男子の補正時間は3分に規定されており、例えば、時差スタートの場合はPTWC1選手のスタート後、3分後にPTWC2選手がスタートし、一斉スタートの場合はH2選手の実走タイムに一律3分が加算されたのち、H1の選手と合わせて順位が決定することになる形式です。
トライアスロンは国際トライアスロン連合(ITU)が統括し、ITUのルールに則って行われるが、さまざまなディサビリティーズの選手が安全に公平に競技ができるよう、ディサビリティーズの内容や程度に応じてそれぞれルールの一部がアレンジされています。
スイム、バイク、ランそれぞれの見どころ:
スイムは、PTWCクラスの選手はニーブレイスの使用が認められており、PTSクラスでは補助具などの使用は認められていません。 PTVIの選手は同性のガイドが横を泳いでサポートして行うクラスです。 また、スタートはどのクラスも飛び込まず、あらかじめ水中に入った状態で行います。
バイクは、クラスごとに使用する自転車が異なり、PTWCはリカンベット型(仰向けに横たわるタイプ)のハンドサイクル(手でクランクを漕いで進む)を使い、PTVIはタンデム(2人乗り)自転車を使い、ガイドが前、選手が後ろに座り、協力して漕ぐスタイルです。 PTSクラスはロードバイクを使うが、ディサビリティーズに合わせた改造も認められています。 例えば、ペダルを義足で踏みやすい形にする、腕のディサビリティーズに合わせて片手でブレーキやギアチェンジを可能にする、ハンドルの位置などを調整するなどです。
ランでは、PTWCは競技用車いすを使い、PTSは義足や杖など必要な補装具を装着し、PTVIはガイドとロープでつながって走ります。
もうひとつ、「第4の種目」とも呼ばれ、次の種目へと移るトランジションも重要なポイントです。 スイムからバイクへ、バイクからランへと種目を移行する過程の「トランジション」はその時間もタイムに加算されるので、「第4の種目」とも言われています。 パラリンピックのトライアスロンでは、ディサビリティーズのクラスごとに使用機材が異なり、着脱する補助具もさまざまなので、個人差も出やすい競技です。 選手はディサビリティーズによってウエットスーツを脱いだり、シューズを履き替えたりすることが難しい場合もあります。 合計タイムに大きく影響するので、いかにトランジションの時間を短縮するかが工夫のしどころです。 ウエアや義足などの補助具を脱着しやすいよう改良するなど、「モノ」の開発 工夫も欠かせません。 選手を「モノ」で支える職人の技術と情熱を感じることができます。
さらに、ディサビリティーズのある選手たちをサポートする、「ヒト」にも注目です。 まず、視覚にディサビリティーズのあるPTVIの選手を支える「ガイド」は、選手の目の代わりとなり安全にフィニッシュまで導く役割を担います。 選手と同性で、全パートを一人でサポートしなければならないため、トライアスリートとしての高い競技力と、さまざまな状況に応じた的確な判断力などが求められるポジションです。
また、PIWCの選手とコンビを組む「ハンドラー」は、トランジションエリアでウエアの着脱や競技機材への乗り換えなどをサポートします。 「ガイド」も「ハンドラー」も選手とともに戦う重要なパートナーです。 日頃から練習をともにし、チームワークを磨くことが求められます。 選手をサポートする「ガイド」「ハンドラー」たち、人と人とが深い信頼関係を築き、メダルを目指して限界に挑む姿は感動的です。
また、クラスによっては、「ハンドラー」や「ガイド」のサポートを受けるので、チームワークも不可欠で、そんな様子が見られ、選手を間近で応援できるトランジションエリアも、おすすめの観戦ポイントになります。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
オリンピックと同様に国際トライアスロン連合がトライアスロン部門も統括していることもあり、多くの大会がトライアスロンと併催されています。 強化が共に行われている国も見られ、トライアスロン人気の高い欧米諸国での普及が進んでおり、強豪国である、イギリス、アメリカなどの選手がトライアスロンでも強さを見せる競技です。
リオデジャネイロ2016大会では男女合わせて6クラスが実施され、それぞれ初代チャンピオンが決定します。 しかしリオデジャネイロ2016大会以降、新しいクラス分け制が導入され、今後の勢力図にどう影響するかが注目される競技です。 特に3クラスから4クラスに細分された立位クラスは、選手の実力が拮抗し、より白熱したレースが期待されます。
他競技から転向してきた選手も少なくなく、それぞれ得意種目をもつ選手も多いのも特徴です。 先行型、後半追い上げ型などレーススタイルもさまざまで、順位の入れ替わりも激しく、最後まで目が離せないのも魅力の一つになります。
2023年5月13日に開催された「ワールドトライアスロンパラシリーズ」では、アメリカ、オーストラリア、フランス、ドイツ、日本勢が闘志を燃やし情熱で柵む展開です。
3つの過酷な種目を乗り切った選手たち、3度目の大舞台で、さらなる進化に期待、新クラス分けの影響はあるか? ゴールの向こう側に見える宝物を目指し、各国の代表たちが熱い戦いを魅せます。
ロサンゼルス2028大会では、強豪国、欧米勢を凌ぐアジア勢の活躍に中国が絡みつくか、注目です。
日本はリオデジャネイロ2016大会に4選手が出場し、東京2020大会でも大いに活躍を魅せるなか、他競技からの転向組みも増え、選手層の厚みも徐々に増すなか、競技力の強化や使用機材の改良など、日本チームとしての底上げをさらに図り、さらなる躍進を目指しメダル獲得に情熱を燃やす。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
車いすバスケは高い身体能力と緻密な戦略、チームワークが勝敗のカギ

車いすバスケは世界的に人気があり普及度も高い競技です。試合は巧みなチェアワークや正確性と精度あるシュート、独特の戦術で魅せる華麗なプレーに注目!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
車いすバスケットボールの主な強豪国と地域:
「アメリカ、イギリス、オランダ、中国etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した国です。
ロサンゼルス2028大会は欧米やアジア勢との激しい攻防の順位争いに会場が熱気を帯びる。
スピーディなパスワークで美しい放物線を描く花形競技の車いすバスケでシュートが決まる国はどこだぁ!
車いすバスケットボールの特徴:
車いすバスケットボールは、下肢部にディサビリティーズのある選手たちを対象にした競技です。 車いすは回転性や敏捷性の高い競技用の仕様で、ボールの大きさやコートのサイズ、ゴールの高さや出場人数など基本的なルールはオリンピックとほぼ同じになります。 美しい放物線を描くシュートの正確性や車いすで走るスピード感、勢いあまって転倒もある選手同士の激しいぶつかり合いなど、多彩な魅力が人気なところです。
大きな特徴はクラス分けで選手はディサビリティーズの程度や身体能力によって、重いほうから順に1.0点から4.5点まで0.5点刻みで8クラスに分けられ、 コート上の5選手の合計点を14.0点以内で構成するというルールになっています。 そのため、幅広い選手の起用が必要で、緻密な戦略に基づいた役割分担によるチームワークも見どころです。
巧みな車いす操作(チェアスキル)は見逃せない注目ポイントで、車いすにはブレーキがなく、ダッシュ、ストップ、ターンなど、選手はすべて自身の手で行います。 シュートは微妙なボールタッチが欠かせないため、ほとんどの選手は素手で車いすを操作し、体幹や腰を使って体の一部のように車いすを操る選手もいて、その身体能力の高さには驚きです。
競技ルール:
車いすバスケットボールは、ディサビリティーズのスポーツの中でも世界的に人気と普及度が高い競技の一つと言われています。 オリンピックとの大きなルールの違いは、ダブルドリブルがない、トラベリングの代わりにボールを持って車いすを手で漕ぐ (プッシュ)ことは連続2回までになっているところです。
なお、車いすバスケはそれぞれ1.0点から4.5点までの持ち点を与えられた選手を14.0点以内で組み合わせるというルールにより、 ディサビリティーズの重い選手(1.0~2.5点/ローポインター)から軽い選手(3.0~4.5点/ハイポインター)までバランスよく起用することが求められています。
車いすバスケットボールの主なプレー:
ハイポインターは主に攻撃面での活躍が期待され、スピーディーな車いす操作でディフェンスの壁をすり抜け、シュートを決めるポジションです。 一方、ローポインターは攻守の要で、相手の動きを予測したディフェンスで相手選手をブロックし 味方のハイポインターを助けるポジションになります。 観戦の際、ローポインターのアウトサイドシュートや重要な守備的役割にも注目です。
また、車いすバスケットボールでよく見られるプレーの一つに「スクリーンプレー」があります。 このプレーは相手ディフェンスにスクリーン(壁)をかけてブロックし、味方のシュートを助けるというバスケットボールの基本戦術です。 競技用の車いすは幅が広く、スクリーン(壁)を回避するための方向転換にはスペースが必要になるため、とても効果的なプレーになります。
応用編では「ピック&ロール」と呼ばれる戦術があり、相手にスクリーンをかけること(ピック)で生まれたスペースにすばやく移動(ロール)してパスを受け、シュートを決めるコンビネーションプレーです。
その他にバックコートで相手にスクリーンをかけて動きを封じ、守備への参加を遅らせる「バックピック」も多用されています。 アウトナンバーでゴールに向かう味方のシュートチャンスをアシストする重要なプレーです。 他にもローポインターが相手ハイポインターを止める動きなど、車いすバスケの独特な戦術にも注目すると臨場感が伝わります。
車いすバスケはシュートの精度も重要で、最近ではスリーポイントシュートの決定率も上がっており、 勝敗のカギを握る重要な要素の一つです。 競技用車いすに座ったまま、ジャンプや下半身の反動も使わずシュートする選手たちの鍛え抜かれた腕力は一つの武器です。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
車いすバスケットボールは第一回パラリンピックのローマ1960大会から正式競技として実施され、競技の魅力などから急速に世界に広まり、現在は100か国以上で実施されている人気競技の一つになります。
世界情勢ではバスケットボール人気とともに欧米勢が圧倒的な強さを見せ、女子も欧米勢が優勢です。 ドイツやスペイン、イタリアなどのリーグは海外からプロ契約で参戦する選手も多く、アメリカでは大学リーグが存在し世界のトッププレーヤーが集まり切磋琢磨しながら技を磨き上げています。
日本チームは男女とも俊敏性を活かした「トランジションバスケ」の強化を図り、確実な成果を上げるべく日々の鍛錬に励む。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
車いすラグビーは緻密な戦略と時間管理、チームワークが勝敗のカギ!

ラグビーは車いす競技で唯一、タックルが認められた男女混合の競技です。試合は華麗なチェアワークや素早いボール捌き、迫力あるスピーディーな展開が魅力!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
車いすラグビーの主な強豪国と地域:
「イギリス、アメリカ、カナダ、フランス、デンマーク、ニュージーランド、オーストラリアetc.」
上記の強豪国は東京2020大会に参加された国です。ロサンゼルス2028大会は欧米やオセアニア勢との激しいぶつかりあいの順位争いにホイッスルが鳴り響く。大音響が響き渡る車いすラグビーでチーム一丸となり優勝のトライを決める国はどこだぁ!
車いすラグビーの特徴:
車いすラグビーは車いす競技の中で唯一、タックルが認められている男女混合の競技です。 激しいぶつかりあいと緻密な戦術が醍醐味で、バスケットボールと同じ広さのコートで、競技用の車いすに乗った選手が4対4で対戦します。 車いすバスケに代わるもので、ディサビリティーズを持つプレーヤーが平等に参加できることを目的にし、ラグビーやバスケ、ハンドボールの要素を組み合わせた競技です。 そのため、車いすラグビーで使用するボールは楕円形ではなく、丸いボールを使ってプレーします。 専用の丸いボールを運び、車いすの前後4輪のうち、2輪がトライラインを通過するとトライとなる競技です。 主に四肢にディサビリティーズのある選手を対象とし、選手ごとに、ディサビリティーズの程度の重い方から順に0.5点から3.5点まで0.5点刻みで「持ち点」が与えられます。 1チームの持ち点の合計は8点以内で構成しなければならず、それぞれの持ち点で攻撃と守備の役割分担を明確したチームの戦術が見どころです。
歴史:
1970年代にカナダで最初に車いすラグビーが開発され、シドニー2000でパラリンピックデビューを果たします。 車いすラグビーは騒がしい接触、頻繁にパンクするタイヤ、更に激しさのあまり転倒さえもある非常に攻撃的なスポーツのため「マーダーボール」とも呼ばれる競技です。
ルール:
車いすラグビーの大きな特徴は持ち点で、選手はディサビリティーズの程度に応じ、重いほうから順に0.5点から3.5点まで0.5点刻みで7クラスに分類されます。 1チームは12名で、コート上の4選手の持ち点の合計を8点以内でチーム構成しなければならないルールです。 実は、車いすラグビー男女混合の競技で、女子選手が出場するときは1人につき0.5点の追加点が与えられます。 もしも、女子2名を含む場合、チームの持ち点合計は9.0点で構成することが可能です。(最大4名10点まで)
持ち点制のルールにより、ディサビリティーズが軽く運動能力の高い選手(ハイポインター)だけでなく、重い選手(ローポインター)にも出場チャンスが与えられています。 ハイポインターは機敏に動き、主に攻撃的な役割を担当し、ローポインターは防御的な役割を担い、相手ディフェンスを車いすで止めてハイポインターのために進路をつくるなど、チーム一丸でトライを取りにいく競技です。
競技用車いすは2種類あり、役割分担がある程度分かるようになっています。 攻撃型は相手の守備をかいくぐり、狭いスペースでも機敏に動けるように凸凹がなく、主にハイポインターが使用する車いすです。 防御型は前部に長いバンパーが突き出しており、相手の車いすにぶつけたり引っ掛けたりして相手の動きを止めるために使用し、主にローポインターが使用する車いすになります。 ハイポインターが華麗な車いす操作(チェアーワーク)で得点を重ねる影で、ローポインターの献身的な動きが重要です。 また、ハイポインターの動きをローポインターが果敢なタックルで阻止するシーンも必見になります。
試合は28つの15分間のクォーターに分割され、両端にセンターサークルとトライラインを設けたバレーボールコートを改造してプレーします。 ゲームは相手のトライラインを越えてボールを運び、相手が反対側で同じことをすることを阻止することです。 車いすラグビーのルールはプレーヤーは少なくとも10回ドリブルするか、40秒ごとにボールを通過する必要があります。 なお、フォワードパスは許可され、膝の上にボールを投げたり、転がしたり、ドリブルしたり、運んだりして相手のボールに向かって進むことが可能です。
ラグビーといっても前方へのパスは認められ、足で蹴る以外はボールを投げたり手で打つことでパスをしたり、膝の上にボールを載せたりして巧みに運んでいくことができます。 ただし、膝に載せて運ぶときは10秒に1度、ドリブルをするか、パスをしなければなりません。
1試合は8分間のピリオドを4回繰り返す(未定※要確認)、バスケットボールのようなプレイのタイム制限があります。 また、攻撃側が40秒以内にゴールしないと相手にボールの所有権が移る40秒ルールや、ボールを持ってから12秒以内にセンターラインを越えなければならない12秒ルールなどが設けられた競技です。 スピーディーなボール展開が必要であり、時間管理も勝敗の重要な要素になります。
タイムアウトもベンチ側から2回、コートの選手から4回までコールが可能です。 ピンチのときに戦況打開のきっかけにすることもでき、どのタイミングでコールするかもチーム戦略の一つになります。 試合終了まぎわの行き詰まる局面で、一つのタイムアウトが逆転のきっかけになることもある試合展開です。
見どころは:
車いす競技のなかで唯一、ルールとして認められている、タックルで大音響が響き渡り、勢い余って車いすが転倒するなど迫力満点で、タイヤのパンクは頻繁におきます。 ただし、車いすの後方からぶつかるなど危険なタックルは反則です。 ボール以外に、相手の身体や車いすに触れたり押さえつけたりすることも禁止で、ファウルを犯した選手は1分間、または相手がトライを決めるまでペナルティーボックスに入らなければなりません。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
車いすラグビーは手と脚にディサビリティーズがある、比較的重度なディサビリティーズの人にもできるスポーツとして1970年代にカナダで考案され、各地に広まった競技です。 パラリンピックにはアトランタ1996大会で公開競技となり、シドニー2000大会から正式競技となっています。 日本チームは細かな改善点を割り出し、切磋琢磨で精度を極め出場枠の獲得を目指す。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
テニスはチェアワークと技、敏捷性や緻密な戦略を駆使した己との勝負

車いすテニスは世界的に知名度も高い競技です。試合はラリー展開の先読みと予測で、素早く打点を入れる確実なボールコントロール、多彩なショットやロブショット、スマッシュなどに注目。日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
車いすテニスの主な強豪国と地域:
「オランダ、イギリス、フランス、オーストラリア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会は欧米やオセアニア、アジア勢との実力拮抗の順位争いに熾烈さを極める。世界最高峰の躍動感あふれるチェアワークを駆使した最高の一打を打ち放つ国はどこだぁ!
車いすテニスの特徴:
パラリンピックのテニスは車いすに乗ってプレーするスタイルで、2バウンドまでの返球が認められている以外はテニスと同じルールで行われます。 なお、コートの広さやネットの高さ、用具なども同じですが、ボールの2バウンド目はコート内外どちらでもよいルールです。
テニスは相手のボールを追いかける俊敏さが必要だが、車いすテニスは片手にラケットを持ちながら車いすを操作し、コート内を動き回ることが求められます。 車いすテニスは、テニスのテクニックに加え、車いすの操作(チェアワーク)にも高い技術が必要です。
車いすテニスは1970年代にアメリカで生まれ、パラリンピックではバルセロナ1992大会から正式競技となります。 国際テニス連盟(ITF)が車いす部門も統括し、世界4大大会(グランドスラム)でも車いすテニスの部が実施され、 近年はプロ選手も多数生まれ世界を転戦するなど、国際的な知名度も高く人気競技の一つです。
クラス分け:
試合カテゴリーは男女シングルス、ダブルスに加え、三肢まひ以上の重度ディサビリティーズがある選手を対象とした、男女混合の「クアード」があり、それぞれシングルスとダブルスがあります。 クアードの選手はディサビリティーズの程度により、電動車いすの使用やラケットと手をテーピングで固定するなどが認められているクラスです。 なお、パラリンピックは3セットマッチで行われ、2セット先取したほうが勝ちとなります。
見どころ:
車いすテニスは2バウンド以内での返球が認められている以外、ルールはテニスとほぼ同じなので観戦しやすく、車いすを巧みに操作しながら繰り出される多彩なストロークは豪快です。 相手からの返球が到達する地点にすばやく移動した上で、コースを正確につくボールコントロールや迫力あるスマッシュは観客を魅了させます。 ボールを打つ時は車いすの座席から臀部を浮かせることはルールで禁止されているので、相手選手の頭上を越す絶妙なロブショットなども見応えあるシーンの一つです。
観客を魅了する驚きのプレーに欠かせないのは、「チェアワーク」と呼ばれる車いす操作の巧みさにあります。 テニスは左右に機敏に動くサイドステップが多用されるなか、車いすは構造上、真横への動きはできなく、車いすをすばやく回転させ、回り込むように移動させることが必要です。 足を地面につけて車いすを操作したり、ブレーキをかけたりすることは禁止されています。
選手がプレーしやすく、巧みなチェアワークを実現するために、テニス用の車いすはさまざまな工夫が施されている仕様です。 例えば、背もたれなど競技に不要なパーツは極力そぎ落して軽量化を図ったり、タイヤを大きくハの字型に傾けて回転性を高めたりしています。 また、前、または後方への転倒を防止するため、前後2つずつ補助車輪も取り付けられ、さらに、選手は自身の体格やディサビリティーズに合わせ、ルールの範囲内でカスタマイズすることが可能です。
相手からの返球に対応し、素早く的確な打点に入るために、選手は相手の体勢やラケットの向きなどからボールのコースをある程度予測してプレーしています。 ときには、予め自分のショットをコントロールして、相手が打ち返せるコースを制限し、最終的に自分の得意なショットにつなげられるように戦略を立てる試合展開です。 ラリーの展開で先を読み、正確にコースをつくテクニックも見逃せません。
また、体温調節が効かず汗をかけない場合は首を冷やしたり、手の握力が少ない場合はラケットと自分の手をテーピングで固定したり、ボールはスローだが、グリップチェンジができないからこその頭脳的なプレーも随所に見られます。 観客が選手の個性を把握しやすいのが特徴で、クアード選手ならではのショットやコース、試合展開を”読む”観戦は、まるで詰将棋のような楽しさです。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
近年、車いすテニスの普及や人気の高まりとともに、競技人口も増え、ジュニア層を対象にした強化なども進んでいます。 競技レベルも上がり、実力拮抗でラリーが続き、長時間にわたる熱戦も増えている競技です。
パラリンピックへの出場は世界ランキングが重要な要素で、選手は世界ランキングを得るためにランキングポイントを獲得できるツアー大会を転戦し、ポイントを積み重ねることが求められます。 ランキングは週に一度、ITFによって更新されるが、年間を通してコンスタントに試合に出ていないと、ランキングは自然に降下してしまう仕組みです。 近年は実力が拮抗しており、ランキングの入れ替わりも激しく、目が離せません。
4年に1度のパラリンピックのメダリストも、若手の台頭などあり、大会ごとに変化が見られます。
ツアー大会では他国の選手と組む選手も少なくないが、パラリンピックでは母国の選手と組んで戦うので、普段あまり見られないペアが力を合わせ、チームワークよく戦う姿も、パラリンピック車いすテニス ダブルスの楽しみの一つです。
日本勢は近年、世界での存在感を増やしているなか、ロサンゼルス2028大会は成長を遂げる若手選手たちも含め、選手層の厚みを増し、さらなる活躍が期待されます。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
フェンシングは己の正確な剣術と強靭なメンタル、駆引きの真剣勝負!

車いすフェンシングは上半身の動きだけで戦う過酷な競技です。試合は至近距離で行われ、高い集中力や精神力、俊敏さが求められ、一瞬の隙を突き合う剣の応酬や息詰まる攻防戦に注目!日本勢は。開催国アメリカ勢は。
世界状況
車いすフェンシングの主な強豪国と地域:
「イギリス、RPC、中国、ブラジル、ハンガリー、ウクライナ、ポーランド、ギリシャ、フランス、タイ、イタリア、ジョージア etc.」
上記の強豪国は東京2020大会でメダル獲得した諸国です。ロサンゼルス2028大会は欧州や南米、アジア諸国との鳴り響く金属音の順位争いに騎士道精神が宿る♪世界各地に普及する中、新たな勢力図に塗り替えられる国はどこだぁ!
車いすフェンシングの特徴:
車いすフェンシングは、脊髄損傷や下肢切断による下肢にディサビリティーズのある人を対象とし、「ピストル」と呼ばれる装置に固定した競技用車いすに座り、上半身だけで競技します。 相手を剣で突くとポイントになるなど、ルールは立って行うオリンピックのフェンシングとほぼ同じです。 だが、フットワークが使えず相手との距離が近く、一定なので、剣さばきのテクニックやスピードが重要なポイントになります。 スピーディーな展開の中、息詰まる攻防が続き、一瞬たりとも目が離せません。
クラス分け:
パラリンピックでは、選手は3つのクラスに分けられ、カテゴリーA(Class 3およびClass 4)、カテゴリーB(Class 2)の2つのカテゴリーのいずれかで競い合う競技です。 よりディサビリティーズが重いカテゴリーBのClass 2は、ディサビリティーズがあるが座位バランスは取れ、剣を持つ腕にディサビリティーズがない選手が該当します。 例えば、下半身まひ、または四肢まひがあるが剣を持つ腕にはディサビリティーズがなく、いずれも座位バランスが取れるのが要件です。 Class 3は、下肢の支えなく座位バランスが取れ、剣を持つ腕にディサビリティーズがない選手のクラスになります。 Class 4は、下肢の支えによって座位バランスが取れ、剣を持つ腕にディサビリティーズがない選手のクラスです。
種目別と見どころ:
種目としてはメダルジャケットを着た胴体だけを突く「フルーレ」、上半身の突きを行う「エベ」、上半身の突きに斬る動作が加わった「サーブル」の3つがあります。 東京2020パラリンピックでは、それぞれ男女別に個人戦が行われ、またエベ、フルーレは国別団体戦(3対3)が行われた競技です。 団体戦のチームは3人の中にカテゴリーBの選手を必ず、1名含まなければならないルールとなっています。
車いすフェンシングは剣やマスク、ウエアなどの道具はフェンシングと同じものを使い、相手を突いたかどうかを電気信号によって機械的に判定する電気審判器を使う点も同じです。 ただし、大きな違いはピスト上に固定された車いすに座って行うので、上半身の動きだけで競い合います。 オリンピックのフェンシングのように、足を使って前後に移動するなど全身で戦えないため、相手と至近距離で絶えず突き合う試合展開です。 正確な剣づかいのテクニックはもちろん、高い集中力や強い精神力も必要になります。
試合はまず、2台の車いすの車輪をピスト上の中央線(センターバー)に対して110度の角度で固定することから始め、続いて両選手間の距離を決めていくステップです。 2選手の腕と剣の長さを測り、短いほうの選手に合わせ、こうして1試合ごとに準備を整え、試合開始となります。
競技中は車いすの座面からお尻を離してはいけない、足はフットレストに常に置くなどのルールが設けられ、使用する車いすは選手ごとに体格やディサビリティーズに合わせて規定の範囲内でカスタマイズした競技専用のものを使用する仕様です。 体を固定するベルトや剣を持たない側のアームレストは体のバランスを保ち、安定した剣さばきにも欠かせない重要な役割があります。
試合時間は、個人戦の予選では3分間で5トゥシュ(突き)先取制、決勝トーナメントでは3分間を3セット行い、15トゥシュ先取制です。 また、1チーム3選手で戦う団体戦では1人が3分間5トゥシュ先取制の試合を3セットずつ行い、最高9セット中に45トゥシュ先取か、タイムアップ時点で得点の多いほうが勝ちとなります。 個人戦、団体戦とも、同点の場合は1分間の延長戦がサドンデス方式で行われる試合形式です。
座ったままの競技ながら、かなりの接近戦で目まぐるしい攻防が繰り返され、時には車いすがピストごと傾くほど激しさも見られる過酷な競技になります。 息を弾ませ、汗だくの選手による、まさに真剣勝負が見どころです。
ロサンゼルス2028大会に向けた競技の展望とは:
車いすフェンシングは第1回パラリンピックである、ローマ1960大会から正式競技となっています。 中世ヨーロッパの騎士道として発達したフェンシングから派生した車いす競技で、フェンシング人気の高いヨーロッパ諸国で特に盛んです。 現在はアメリカやアジアなどにも広がり、約40ヵ国、地域で行われています。
パラリンピックへの出場は世界ランキングで決まるが、詳細は大会ごとに見直されている競技です。、 ロンドン2012大会は上位20位までに出場権が与えられたが、リオデジャネイロ2016大会では上位12位まで、同一国から2名までに変更されています。 世界ランキングを上げるには、年に数回開催されるワールドカップを転戦したり、2年に1度の地域選手権や世界選手権に出場したりするなどして、 ランキングポイントを積み重ねることが必要です。
世界の勢力図としては、歴史的にヨーロッパ諸国やロシアで盛んだが、中国や香港も強豪国に名を連ねています。
日本はシドニー2000大会から北京2008大会まで連続出場を果たした日本、東京2020大会では多くの選手を送り日本車いすフェンシング協会(JWFA)は強化策を取り、京都に常設の練習拠点を設け、JWFA強化指定選手らを中心に定期的に合宿を実施し、ワールドカップなど海外転戦の機会を増やし選手強化に取り組む。
※東京2020大会関連資料より、参考元:
懐かしすぎるぜぇ!ロサンゼルス約7~8年暮らした地域だぜぇ~? ついに、LAXから「405」に乗り、10もしくは110に乗り換え「101」に乗る、そこはハリウッドだぜぇ! ついに本場で実写化それとも、映画化かぁ!?メモリアル(記念に残る)ハリウッドからオファーかなぁ!? サンタモニカビーチ沿い、最高だろうなぁ♪それともロングビーチかぁ~?
次回、オーストラリア ブリスベン2032 大会仕様予告♪
夢抱く子供達と文化、エンターテイメント、スポーツは多様な人々の情熱と大自然が持つ力で新世代の世界や未来に力を与える可能性がある。
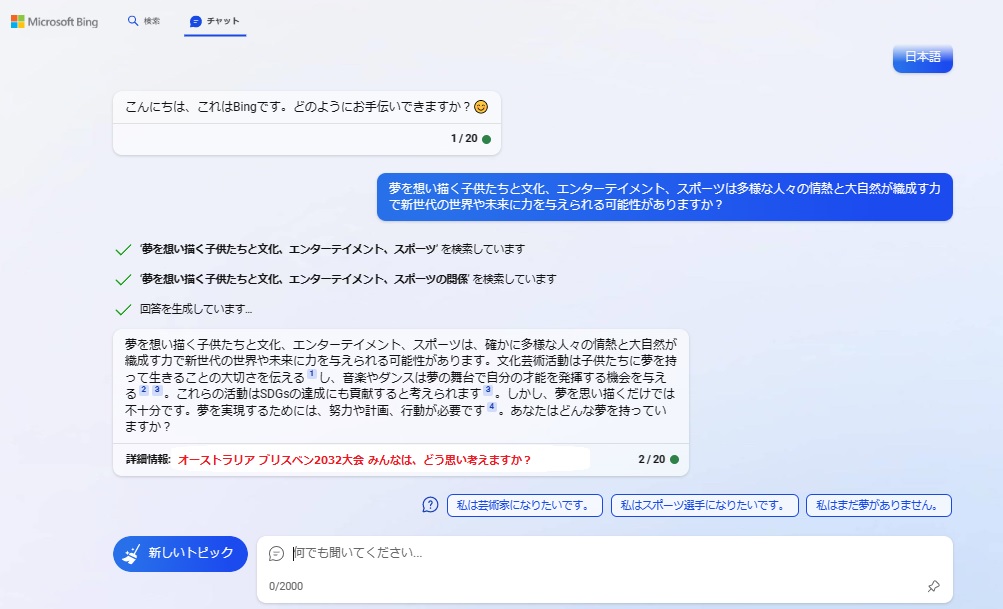
「夢を想い描く子供たちと文化、エンターテイメント、スポーツは多様な人々の情熱と大自然が織成す力で新世代の世界や未来に力を与えられる可能性がある。」です。